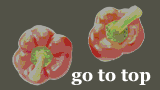Blog
令和8年1月24日 中国12月新築住宅価格
令和8年1月22日 中国12月鉱工業生産
令和8年1月21日 中国10-12月期GDPが減速
令和8年1月20日 ロシア原油収入減少
令和8年1月17日 中国12月貿易統計
令和8年1月15日 世界銀行世界経済見通しを上方修正
令和8年1月14日 中国で鼠人間増殖
令和8年1月13日 米12月雇用統計
令和7年11月12日 中国10月CPI
令和8年1月10日 タイ中銀利下げ
令和8年1月8日 国連安保理緊急会合
令和8年1月7日 ベトナム7-9月期GDP
令和8年1月6日 米国がベネズエラ大統領を拘束
令和8年1月4日 中国12月PMI
令和8年1月3日 2025年を振り返って(5)ロシア
令和7年12月31日 2025年を振り返って(4)ブラジル
令和7年12月30日 2025年を振り返って(3)インド
令和7年12月2日 中国11月PMI
令和7年11月30日 インド7-9月期成長率
令和7年11月27日 日中の政治的対立が先鋭化
令和7年11月26日 COP30終了
令和7年11月25日 G20首脳会議閉幕
令和7年11月24日 米9月雇用統計
令和7年11月21日 中国人民銀行政策金利維持へ
令和7年11月20日 タイ7-9月期GDP減速
令和7年11月19日 中国10月貿易統計
令和7年11月17日 ロシア7-9月期GDP
令和7年11月16日 中国10月鉱工業生産
令和7年11月15日 中国10月新築住宅価格
令和7年11月13日 中国独身の日今年は穏やか
令和7年11月12日 中国10月CPI
令和7年11月11日 インドネシア7-9月期GDP
令和7年11月10日 フィリピン7-9月期GDP
令和7年11月8日 中国とブラジルがCOP30で主導権争い
令和7年11月5日 フィリピン、UAEがTPP参加表明
令和7年11月3日 米中両首脳が会談
令和7年11月2日 APEC首脳会議閉幕
令和7年11月1日 中国10月PMI
令和7年10月30日 アルゼンチン与党選挙大勝
令和7年10月26日 ロシア中銀利下げ
令和7年10月23日 中国7-9月期GDP
令和7年10月22日 中国9月鉱工業生産
令和7年10月21日 日本を目指す中国人が増加
令和7年10月19日 中国9月貿易統計
令和7年10月18日 台湾TSMC業績好調
令和7年10月16日 中国9月CPI
令和7年10月15日 トランプ氏が対中強硬姿勢を後退
令和7年10月14日 中国国慶節で住宅販売が回復
令和7年10月12日 中国国慶節
令和7年10月8日 ベトナム7-9月期GDP
令和7年10月7日 中国のアリババの株価上昇
令和7年10月6日 EV大手BYDの販売台数が減速
令和7年10月4日 中国AI企業に注目集まる
令和7年10月2日 中国国慶節8連休開始
令和7年10月1日 中国9月PMI
令和7年9月30日 ブラジルで前大統領の恩赦求める動き
令和7年9月28日 ロシア成長率予想下方修正
令和7年9月27日 メキシコ中銀利下げ
令和7年9月25日 OECD世界経済見通し上方修正
令和7年9月22日 アルゼンチン4-6月期GDP
令和7年9月21日 ブラジル中銀金利据え置き
令和7年9月20日 インドネシア中銀利下げ
令和7年9月18日 ブラジル・ボルソラノ前大統領有罪
令和7年9月16日 中国8月新築住宅価格
令和7年9月14日 中国8月CPI
令和7年9月13日 トルコ中銀が利下げ
令和7年9月11日 アルゼンチン地方選で与党惨敗
令和7年9月10日 中国8月貿易統計
令和7年9月9日 文京区に中国人が移住
令和7年9月8日 米8月雇用統計
令和7年9月6日 ブラジル4-6月期GDP
令和7年9月3日 トルコ4-6月期GDP加速
令和7年9月2日 中国8月PMI
令和7年9月1日 インド4-6月期成長率
令和7年8月31日 フィリピン中銀利下げ
令和7年8月28日 中国7月貿易統計
令和7年8月27日 中国7月新築住宅価格
令和7年8月26日 中国7月鉱工業生産
令和7年8月24日 メキシコ4-6月期GDP確報値
令和7年8月23日 インドネシア中銀利下げ
令和7年8月20日 タイ4-6月期GDP
令和7年8月19日 パキスタンで大規模洪水
令和7年8月17日 インド国債18年振り格上げ
令和7年8月16日 タイ中銀利下げ
令和7年8月14日 中国7月新車販売
令和7年8月13日 マレーシア4−6月期成長率加速
令和7年8月10日 中国7月CPI
令和7年8月8日 フィリピン4-6月期GDP
令和7年8月7日 インドネシア4-6月期GDP
令和7年8月6日 米インド関税交渉進展せず
令和7年8月4日 米7月雇用統計
令和7年8月3日 メキシコ4-6月期GDP
令和7年8月2日 中国7月PMI
令和7年7月31日 IMF世界経済見通し引き上げ
令和7年7月30日 ロシア中銀利下げ
令和7年7月28日 中国6月貿易統計
令和7年7月27日 アジア開銀アジア成長率見通し下方修正
令和7年7月24日 TSMC決算
令和7年7月23日 中国人民銀行優遇金利据え置き
令和7年7月22日 中国6月新築住宅価格
令和7年7月19日 インドネシア中銀利下げ
令和7年7月17日 中国4-7月期GDP成長率
令和7年7月16日 中国6月鉱工業生産
令和7年7月15日 ブラジルの資産急落
令和7年7月13日 マレーシア中銀利下げ
令和7年7月12日 中国6月CPI
令和7年7月10日 BRCS首脳会議閉幕
令和7年7月6日 BYD売り上げ堅調
令和7年7月5日 米6月雇用統計
令和7年7月3日 新興国株式投資信託年初来リターン
令和7年7月2日 中国6月PMI
令和7年6月30日 メキシコ中銀利下げ
令和7年6月29日 タイ中銀政策金利維持
令和7年6月28日 中国5月新築住宅価格
令和7年6月26日 世界の富裕層が大量に移住
令和7年6月25日 米トランプ大統領イランとイスラエルが停戦と発表
令和7年6月24日 米国がイランの核施設攻撃
令和7年6月23日 フィリピン中銀利下げ
令和7年6月21日 ブラジル中銀利上げ
令和7年6月19日 中国5月貿易統計
令和7年6月18日 中国5月鉱工業生産
令和7年6月16日 イランがイスラエルに報復
令和7年6月15日 中国5月CPI
令和7年6月14日 イスラエルがイランを攻撃
令和7年6月11日 インド中銀利下げ
令和7年6月10日 ブラジル1-3月期GDP
令和7年6月8日 米5月雇用統計
令和7年6月5日 OECDが世界経済見通しを下方修正
令和7年6月4日 トルコ1-3月期GDP
令和7年6月3日 インド1-3月期成長率加速
令和7年6月1日 中国5月PMI
令和7年5月31日 米国が中国人留学生ビザを積極的取り消し
令和7年5月29日 中国4月鉱工業生産
令和7年5月26日 フィリピン1-3月期GDP
令和7年5月25日 マレーシア1−3月期成長率鈍化
令和7年5月24日 インドネシア中銀利下げ
令和7年5月22日 メキシコペソ堅調
令和7年5月21日 タイ1-3月期GDP
令和7年5月20日 中国1月新築住宅価格
令和7年5月19日 ロシア1-3月期GDP
令和7年5月17日 メキシコ中銀利下げ
令和7年5月15日 中国4月CPI
令和7年5月14日 米中が関税引き下げで合意
令和7年5月12日 中国4月貿易統計
令和7年5月10日 印パ両国の衝突が拡大
令和7年5月8日 中国太陽光パネル価格下落
令和7年5月5日 印パ両国が衝突
令和7年5月4日 米4月雇用統計
令和7年5月3日 メキシコ1-3月期GDP加速
令和7年5月1日 中国4月PMI
令和7年4月30日 米中がチキンレース
令和7年4月28日 G20で関税について議論
令和7年4月27日 ロシア中銀金利据え置き
令和7年4月26日 上海モーターショー開幕
令和7年4月24日 IMF世界経済見通し引下げ
令和7年4月22日 ディープシークの衝撃
令和7年4月21日 中国がカンボジアに接近
令和7年4月19日 トルコ中銀利上げ
令和7年4月17日 原油価格が低迷
令和7年4月16日 中国3月貿易統計
令和7年4月14日 中国が米国への関税引き上げ
令和7年4月12日 中国3月CPI
令和7年4月8日 ベトナム1-3月期GDP堅調
令和7年4月7日 中国が報復関税を発表
令和7年4月6日 米3月雇用統計
令和7年4月5日 トランプ大統領が相互関税を発表
令和7年4月3日 中国株と他の新興国株との連動性低下
令和7年4月2日 中国3月PMI
令和7年3月29日 中国ディープシーク創業者が富裕層の一員に
令和7年3月27日 トルコ大統領の「政敵」を逮捕
令和7年3月26日 トルコ中銀利下げ
令和7年3月25日 中国2月新築住宅価格
令和7年3月24日 中国1-2月貿易統計
令和7年3月19日 中国1-2月鉱工業生産
令和7年3月18日 中国2月CPI
令和7年3月16日 中国レアメタル規制強化
令和7年3月15日 インドCPI減速
令和7年3月13日 中国全人代閉幕
令和7年3月10日 グリーンランドへの注目高まる
令和7年3月9日 米2月雇用統計
令和7年3月8日 中国1月新築住宅価格
令和7年3月6日 中国成長率目標据え置きへ
令和7年3月4日 中国2月PMI
令和7年3月3日 トルコ10-12月期GDP+3.0%
令和7年3月2日 インド10-12月期成長率加速
令和7年3月1日 G20機能不全
令和8年1月26日 米がグリーランド領有を主張
おはようございます。米トランプ政権がグリーランド領有を主張しています。
1. 米がグリーランド領有を主張
米トランプ政権がグリーランド領有を主張しています。同政権は中露が北極海での活動を活発化させており、それに対抗する必要があるとしています。只、本当の狙いはレアアースなど地下に眠る区物資源であるとの指摘もあります。
一方、欧州諸国は反発。トランプ大統領が欧州の8カ国に対して10%の関税を課すことを示唆して、それに反発。フランスなどは、グリーンランドに対する軍隊派遣を検討。
2. 米国の地位が低下
中国は南シナ海でのフィリピン船舶への嫌がらせや、台湾への軍事威嚇を強化。世界第1、2の軍事大国がいずれも世界秩序を維持するどころが、不安定化に貢献。
アジア太平洋地域は、長年経済発展は中国、安全保障は米国という図式で発展。その前提が揺らいでいます。経済力も軍事力も中国には遠く及ばない中堅国にとって、中国への脅威が問題となっています。
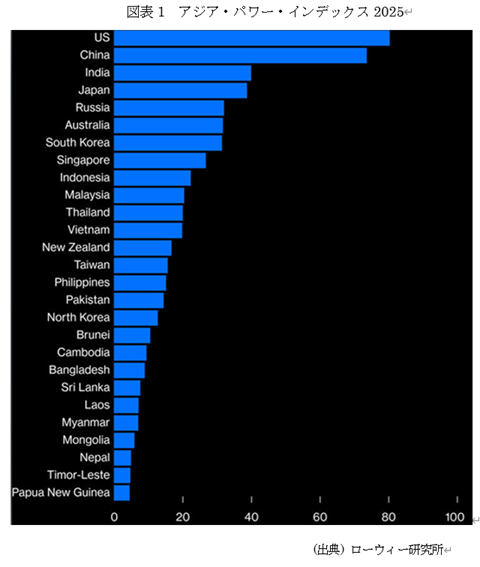
3.Gマイナス1時代到来か
米国が国際政治での指導的立場から後退しG7からG0になった議論も嘗てありました。現在は米国が積極的に国際秩序の崩壊を働きかけるという「Gマイナス1」の世界に突入しつつあります。
今後は、日本、韓国、豪州、インド、NZなどが連携して、中国などに対する脅威に対抗することが求められています。
令和8年1月24日 中国12月新築住宅価格
おはようございます。中国12月新築住宅価格は前月比大幅下落しました。
1. 中国10-12月期GDP+4.5%
中国国家統計局は19日、中国10-12月期GDPが前年同月比+4.5%となり、前期の+4.8%から減速したと発表。12月には小売売上高が3年振りの低い伸び率となり、不動産不況の継続、消費者への政策的梃入れにもかかわらずデフレ圧力が継続したことなどが影響。
一方、生産が加速したにも関わらず、失業率は5.1%と、3箇月連続で横這い。
尤も、2025年の通年成長率は+5%と、政府予想に沿ったものとなり、2024年から横這い。米国への輸出の好調などによる、貿易黒字下支え。関税の圧力、固定資産投資の軟調を相殺。
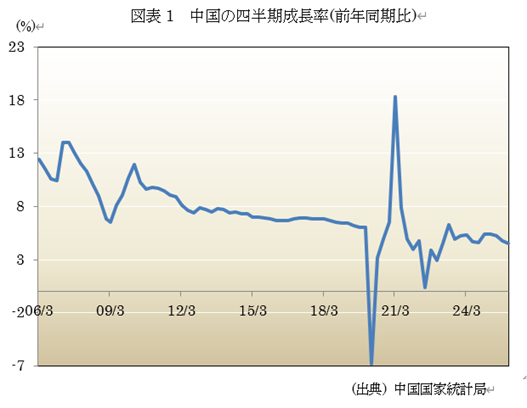
2. 12月新築住宅価格
中国統計局が1月19日発表した統計によると、同国の12月の新築住宅価格は前年同月比+2.7%と、11月の▲2.4%から下落率が拡大。30箇月連続ンで下落。7月以来最大の下落率となり、長引く住宅価格下落に当局が苦労していることを窺わせています。
下落率は加速しており、北京が前年同月比▲4.4%(前月は同▲2.1%)、広州▲4.8%(同▲4.3%)、深セン▲4.4%(同▲3.7%)、重慶▲2.9%(同2.9)など。
モーニングスターの株式アナリストは「不動産セクターの低迷継続は、我々の予想と概ね一致しており、今後2-3年、中国の成長を下押しする要因となる可能性が高い」としました。
70都市のうち、12月に価格が上昇したのは6都市にとどまり、58都市で下落。
又、中古住宅市場も軟調で、1級都市、2級都市、3級都市の中古住宅価格は、いずれも前年比で下落率が拡大。
令和8年1月22日 中国12月鉱工業生産
おはようございます。中国の12月鉱工業生産は加速しました。
1. 中国10-12月期GDP+4.5%
中国国家統計局は19日、中国10-12月期GDPが前年同月比+4.5%となり、前期の+4.8%から減速したと発表。12月には小売売上高が3年振りの低い伸び率となり、不動産不況の継続、消費者への政策的梃入れにもかかわらずデフレ圧力が継続したことなどが影響。
一方、生産が加速したにも関わらず、失業率は5.1%と、3箇月連続で横這い。
尤も、2025年の通年成長率は+5%と、政府予想に沿ったものとなり、2024年から横這い。米国への輸出の好調などによる、貿易黒字下支え。関税の圧力、固定資産投資の軟調を相殺。
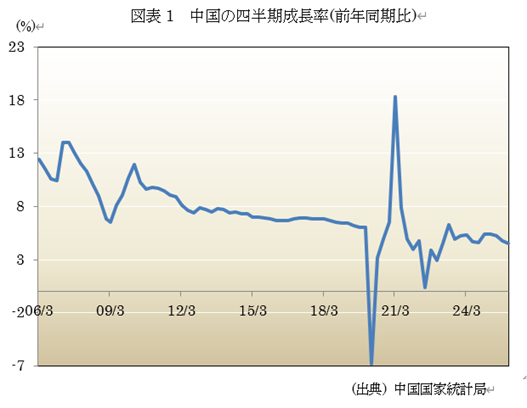
2. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が19日発表した12月の鉱工業生産は、前年同月比+5.2%と、前月の+4.8%から伸び率が加速。市場予想の+5.0%から上振れ。

3.12月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、12月の小売売上高は前年同期比+0.9%と、前月の+1.3%から伸び率が減速。市場予想の+1.2%から下振れ。

4. 1-12月固定資産投は減少
他方、国家統計局による同日発表の1-12月期の固定資産投資は、前年同期比▲3.8%。減少率は1-11月期の▲2.6%から拡大。市場予想は▲3.0%。
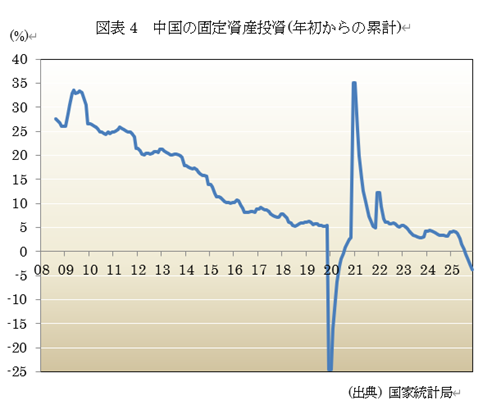
5. 2026年は減速か
同日記者会見に臨んだ康義国家統計局長は「外部環境の変化が一段と厳しくなり、供給が需要を上回る状況が継続」として「積極的且つ効果的なマクロ政策により内需を拡大して、供給面の改善を進める必要がある」としました。
世界銀行と国際通貨基金(IMF)は最近、今年の中国の成長率見通しをそれぞれ、+4.4%、+4.5%としました。米国との貿易摩擦や内需低迷といった要因を乗り越えるには、より踏み込んだ景気刺激策が欠かせないとの分析も出ています。
令和8年1月21日 中国10-12月期GDPが減速
おはようございます。中国の10-12月期GDPは減速しました。
1. 中国10-12月期GDP+4.5%
中国国家統計局は19日、中国10-12月期GDPが前年同月比+4.5%となり、前期の+4.8%から減速したと発表。12月には小売売上高が3年振りの低い伸び率となり、不動産不況の継続、消費者への政策的梃入れにもかかわらずデフレ圧力が継続したことなどが影響。
一方、生産が加速したにも関わらず、失業率は5.1%と、3箇月連続で横這い。
尤も、2025年の通年成長率は+5%と、政府予想に沿ったものとなり、2024年から横這い。米国への輸出の好調などによる、貿易黒字下支え。関税の圧力、固定資産投資の軟調を相殺。
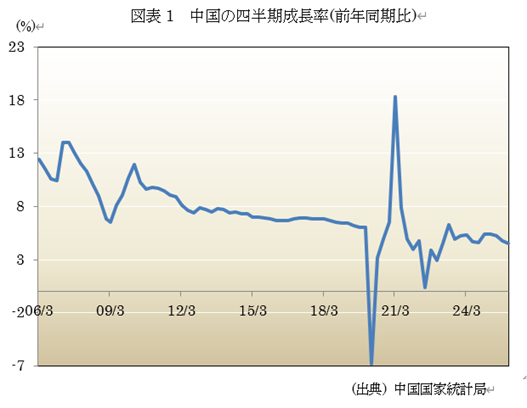
2. 2026年は減速か
同日記者会見に臨んだ康義国家統計局長は「外部環境の変化が一段と厳しくなり、供給が需要を上回る状況が継続」として「積極的且つ効果的なマクロ政策により内需を拡大して、供給面の改善を進める必要がある」としました。
世界銀行と国際通貨基金(IMF)は最近、今年の中国の成長率見通しをそれぞれ、+4.4%、+4.5%としました。米国との貿易摩擦や内需低迷といった服区實成を乗り越えるには、より踏み込んだ景気刺激策が欠かせないとの分析も出ています。
令和8年1月20日 ロシア原油収入減少
おはようございます。ロシアの原油収入減少が減少しています。
1. 7-9月期GDP成長率
ロシア連邦統計局は11月14日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+0.6%になったと発表(速報値)。市場予想通り。前期の+1.1%から減速。継戦能力を左右する戦時経済は、現安の継続により、減速傾向を強めています。
7-9月期には10四半期プラス成長を維持したものの、マイナス成長に陥った23年1-3月期の▲0.3%以来の低い成長率。
経済発展省によると、7−9月期には製造業が+1.1%。前四半期の+3.6%から減速。小売りが+2.1%、建設が+1.2%と、内需が勢いを欠いています。

2. インフレ率減速
国家統計局から11月16日発表された12月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+5.6%と、伸び率は前月から減速(図表2参照)。市場予想の+5.8%から下振れ。
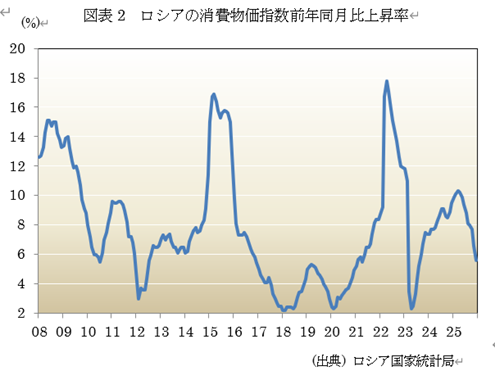
3. 政策金利を引下げ
一方、ロシア中央銀行は10月24日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲0.5%ポイント引き下げ16.5%にすることを決定。引き下げは4会合連続。市場では、政策金利維持を予想していました。
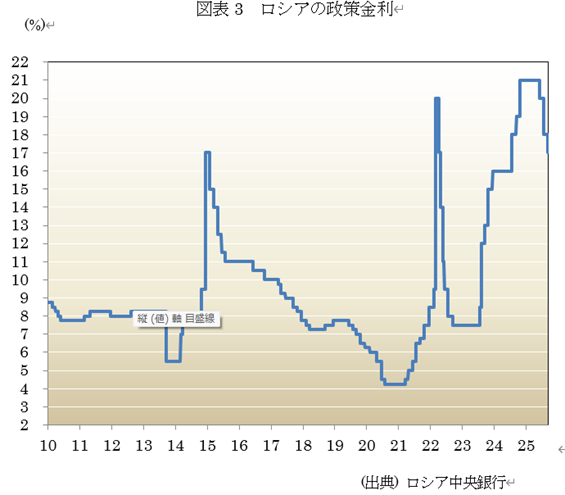
利下げしたものの、中銀は金融環境は、インフレ率上昇懸念により、中期的にはインフレ率上昇懸念により、金融環境は引き続き引き締め気味になるとの予想を維持。
4. 25年のロシア石油・ガス歳入は24%減
ロシア財務省のデータによると、2025年の同国の石油・ス歳入は前年比▲24%と、新型コロナウィルスのパンデミックで落ち込んだ20年以来の低水準。原油価格の下落とルーブル高が影響。
ロシアでは、石油ガス収入が国家歳入の25%を占めています。22年2月のウクライナ振興以降、防衛・安全保障関連の支出が膨らみ、財政を圧迫。
同省によると、25年の石油・ガス歳入は8兆4800億ルーブル(1080億3000万ドル)と、24年の11兆1300億ルーブルから減少。25年の原油価格は前年比▲18%超の下落。20年以来最大の下落。
25年12月の石油・ガス歳入は4478億ルーブルと、前年同月の7902億ルーブルから大幅減少。25年11月の5309億ルーブルを下回りました。
った。
令和8年1月17日 中国12月貿易統計
おはようございます。12月の中国貿易統計で、輸出は増加しました。
1. 12月輸出は増加
中国税関総署が14日発表した12月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+6.6%と、前月の+5.9%から続伸。市場予想の+3.0%から上振れ。
一方、12月輸入は同+6.5と、前月の6.19%から続伸。
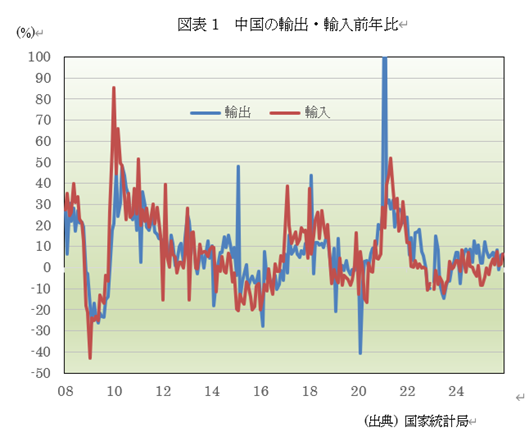
2. 2025年の貿易黒字は1兆ドル突破
一方、2025年には輸出は前年比+5.5%の3兆7118億(約600兆円)。2年連続でプラスを維持。輸入は前年から横這いの2町5829億ドル。輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は1兆1889憶ドル。貿易黒字は初となる1兆ドルをとっぱして、過去最高を更新。
輸出を国・地域別で見ると、最大の輸出先であるASEAN向けは+13.4%。欧州連合(EU)向けが+8.4%、アフリカ向けが+25.8%。日本向けは+3.5%。
令和8年1月15日 世界銀行世界経済見通しを上方修正
おはようございます。世界銀行が世界経済見通しを上方修正しました。
1. 2026年成長率予想+2.6%
世界銀行は13日公表した最新の世界経済見通しで、2026年の世界の実質構内総生産(GDP)成長率予想を+2.6%と、昨年6月公表の前回予測から+0.2%ポイント上方修正。世界経済が想定よりも堅調だと指摘。一方、新興国や途上国の成長を巡る課題を指摘。世界経済の成長持続性に対して警鐘を鳴らしています。
25年GDP伸び率は前回から+0.4%引き上げて+2.7%として、27年は+2.7%になると予想。
関税措置による貿易の混乱にもかかわらず、米国が予想以上の成長を示唆していることが上方修正の約3分の2の要因を占めるとしました。米成長率は25年初めの米国経済の成長を抑制しましたが、26年は減税措置による押上効果や投資が関税措置に伴う投資や消費への影響を和らげるとしました。
2. 米国株は堅調に推移
一方、米国株はここ1年で見ると、堅調に推移。NYダウはトランプ大統領による「関税ショック」の影響などにより、4月7日にはNYダウは37,965.6ドルを付けました、その後、1月13には49,191.9ドルと、順調に上昇。米国および世界経済の拡大を反映。

3. アルファベット時価総額4兆ドル
一方、米IT大手グーグルの親会社「アルファベット」の時価総額が一時4兆ドルを突破。
グーグルとアップルは12日、次世代のSiriなどAI機能の基盤にグーグルの生成AI「ジェミニ」を採用するなど、複数年に亘る提携契約を結んだと発表。
株式市場ではこの提携を好感。アルファベットの株価が上昇。一時4兆ドルと突破。
令和8年1月14日 中国で鼠人間増殖
おはようございます。中国で鼠人間が増殖しています。
1. 1日中ひきこもる若者が増加
中国では1日中、寝室に閉じこもって生活する「鼠(ねずみ)人間」と呼ばれる若者の動画がソーシャル・メディアに投稿されています。こうした若者の増加に危機感を抱いた政府が取り締まりに乗り出しています。
ある若者の動画では、昼過ぎまで眠り続けて、午後になってからも布団から出ず、スマホをいじりながら出前で食事を済ませています。
その後は、ゲームを楽しんだり、ドラマを見たり、合間に家事をしたりしながら、朝方迄ゴロゴロと過ごしています。
従来中国では、都市の地下で暮らす低所得層を指す「鼠族」が問題とされてきました。これは、中国の都市部において、家賃の高い地上の部屋を借りられず、地下室や都市の周辺地域で、集団で暮らす人々を指す言葉でした。これらの人々は経済的な困窮が原因となってこのような暮らしをしているとされてきました。
これに対して「鼠人間」は、消極的な生活を送る若者のこと。一日中自宅にこもり、昼夜逆転の生活を送り、食事はデリバリーで済ませ、スマホやゲームに没頭して人との交流を極力避ける若者と指しています。
2. 若者の失業率
一方、中国の若者の失業率は依然として高水準。中国国家統計局のデータによると、2025年11月の若年(16-24歳、学生を除く)の失業率は16.9%と、10月の17.3%から低下。6月以来の低水準。景気の緩やかな回復により、労働市場が一時的に安定したことをこの改善は示唆。強いサービス業の活動と景気梃入れ政策にも支えられました。
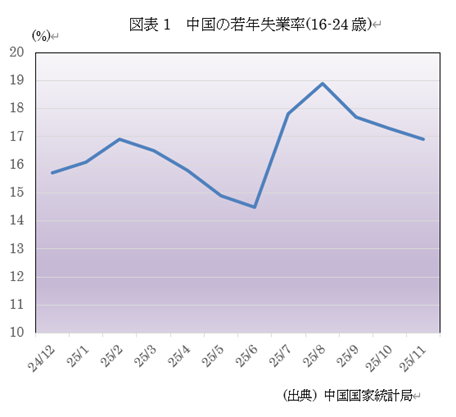
只、構造問題と民間部門の低い信頼感のため、失業率は依然として歴史的高水準にあります。他方、11月の失業率は5.1%と、10月から横這いとなりました。
令和8年1月12日 米10月雇用統計
おはようございます。米国の12月の雇用統計で、雇用者数が+5万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省12月の雇用統計を9日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は12月には前月比+5.0万人。市場予想の+6.0万人から下振れ。特に建設、小売り、製造業での雇用減少が目立ちました。
一方、失業率は4.4%に低下。時間当たり賃金は前年比+3.8%と、伸びは11月の3.6%から加速して、米連邦準備理事会(FRB)が今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で金利を据え置くとの見方を支えました。
11月の雇用者数は+6.4万人から+5.6万人に下方修正されました。又、10月は▲10.5万人から▲17.3万人へと、約5年ぶりの大幅下方修正となりました。
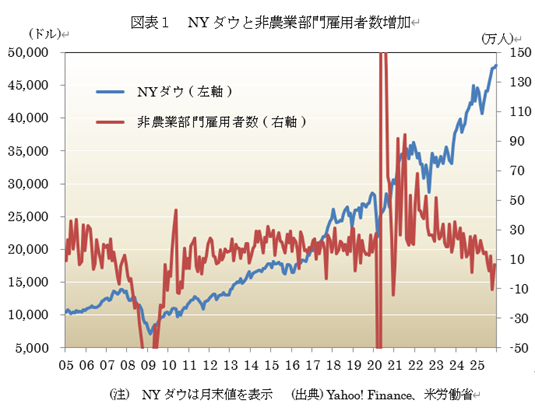
2. FRBは利下げ停止か
一方、米連邦準備理事会(FRB)は30日、12月の連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録を公表。2026年1月以降の金融政策の見通しを巡り、大半の参加者が、インフレ率が想定通り低下すれば、更なる利下げが適切だとの見解を示唆。他方、何人かの参加者が、「しばらくは金利据え置きが妥当」と早期追加利下げには慎重な姿勢を示唆。
又、9日の米金融・債券市場では、金利動向に敏感な2年国債利回りが上昇。12月の雇用統計は、FRBが今月のFOMCで金利を据え置くとの見方を支えました。
野村(NY)の米金利戦略責任者ジョナサン・コーン氏は、12月雇用統計について「雇用の再加速でも大幅な減速でもない、まずまずの内容だった。雇用者数は概ね均衡水準で、1月利下げ観測はほぼ消えた」としました。
令和8年1月11日 中国12月CPI
おはようございます。中国の12月CPIは、前年同月比上昇しました。
1. 12月CPIが上昇
中国国家統計局が9日発表した12月消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+0.8%。市場予想に一致。前月は+0.7%でした。前月比は+0.2%で、市場予想の+0.1%から上振れ。11月には▲0.1%。
CPIは2年10箇月振りの高い伸びとなったものの、通年では16年ぶりの低水準。生産者物価指数(PPI)は下落率が鈍化したものの、引き続き需要の低迷を示唆。市場は、当局が更なる景気刺激策を打ち出すものと予想。
国家統計局の統計管は、12月のCPI上昇率は主に食品価格によるもので、生鮮野菜と牛肉はそれぞれ+18.2%、+6.9%。豚肉価格は12月に前年同月比▲14.6%の下落となったものの、金の宝飾品価格は+68.5%。

食品や変動のがけしい価格を除くコアインフレ率は、前年同月比+1.2%と、11月と同じ。
ゴールドマン・サックスは、金価格を除くコアインフレ率は、前月からわずかにていかしたと推定。
2. PPIはマイナス幅縮小
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、12月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲1.9%と、前月の▲2.2%からマイナス幅が縮小。通年では、▲2.6%。
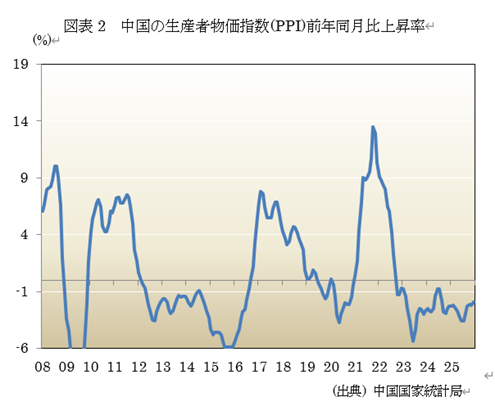
国家統計局の統計管は、PPIの下落幅縮小について、非鉄金属価格の上昇など国際商品価格に加え、主要産業の生産能力を管理する政策が寄与したと分析。
令和8年1月10日 タイ中銀利下げ
おはようございます。タイ中銀は利下げしました。
1. 7-9月期成長率+1.4%に減速v
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は11月17日に、7-9月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.2%になったと発表(図表1参照)。前期の+2.8%から減速。市場予想の+1.6%からはした振れ。
工場の産出の低下、観光業の停滞、米国の関税の高まりに対する懸念などにより、2021年第3四半期以来の低水準。
固定資産投資は前年同期比+1.1%(前期は+5.8%)と急落。政府支出は▲3.9%(同+2.2%)、一方、個人消費は+2.6%と堅調を維持。
外需では、輸出+6.%(同+11.2%)、輸入+4.6%(同+10.9%)と共に減速。只、貿易収支は依然としてGDPには寄与。輸出の鈍化は、新たな米国による関税に起因。
生産面では、産出は農業が+1.9%(同6.4%)、非農業が+1.2%(同+2.5%)と共に鈍化。
政府は2025年成長率予想を従来の+1.8〜2.3%から+2.0%へと下方修正。

2. 消費者物価指数(CPI)上昇率マイナス
タイ商業省は7日、12月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.28 %であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.49%からマイナス幅が縮小。
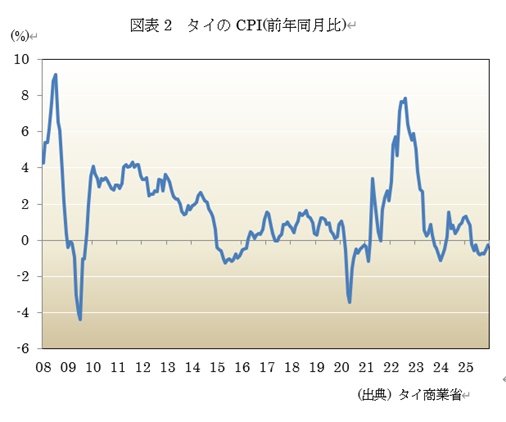
3. 政策金利を引下げ
一方、タイ中央銀行は12月17日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を▲0.25%引き下げ、1.25%にすることを決定。政治の不透明感、タイバーツ高、米国の関税といった課題に直面する中、減速する景気を下支える意図。
決定は全会一致。利下げはほぼ市場の予想通り。利下げは2024年10月以来で、累計で▲1.25%ポイントの利下げ。
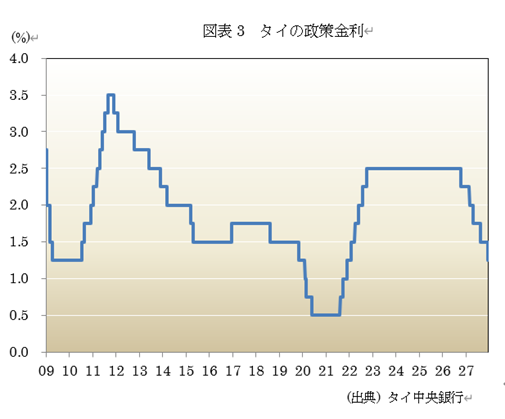
中銀は「金融政策委員会は明らかな景気減速とリスクの高まりを考慮すると、金融政策はより緩和的になりうると評価している」としました。只、政策余地は限定的であるとも認識しているとしました。
26年の成長率は+1.6から+1.5%に引き下げ。27年については+2.3%に回復すると予想するものの、潜在成長率は下回るとしました。
令和8年1月8日 国連安保理緊急会合
おはようございます。米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束しました。国連安保理緊急会合を開催して、加盟国からは批判が相次ぎました。
1. 米国がベネズエラを攻撃
米トランプ大統領は3日、米軍がベネズエラの首都カラカスで軍事作戦を行い、同国のニコラス・マドゥロ大統領とその妻を拘束したと発表。
フロリダの私邸「マール・ア・ラーゴ」での記者会見で、大統領は「適切な政権移行」ができるまでは、今後米国がベネズエラを「運営する」としました。
一方、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領は国営テレビの演説で、マドゥロ氏が同国唯一の大統領であると主張。
2. 国連安保理緊急会合
一方、国連の安全保障理事会は5日、米国のベネズエラ攻撃を受けて緊急会合を開催。米国はベネズエラに対する軍事作戦や同国ノマドゥロ大統領を拘束したことを正当化。米国が介入を示唆する国からは、国際法違反や国連憲章への違反だとする批判の声が相次ぎました。
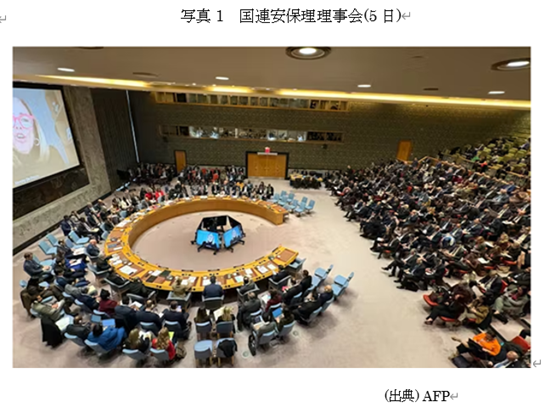
国連のディカル事務次長はグテレス事務総省の声明を読み上げ、「(米国ニヨル)1月3日の軍事行動に関して、国際法が尊重されなかったことを深く懸念している」としました。
米国のウォルツ国連大使は「トランプ米大統領は外交の機会を提供し、緊張緩和を試みた。だが、マドゥロ氏はそれらを拒否した」とし、「マドゥロ氏は単なる起訴された麻薬密売人ではない。彼は非合法な大統領であり、国家元首ではなかった」としました。
ベネズエラのモンカダは「1月3日の出来事は国連憲章に対する米国政府の明白な違反だ」と非難。「国家元首の拉致や主権国家の爆撃が要因されるのであれば、武力こそが国際関係の真の仲介者であうというメッセージを世界に送る」としました。
コロンビアのザラバタ国連大使は「(米国の行動は)ベネズエラの主権や政治的独立、領土保全の明白な侵害であり、武力行使を正当化する根拠は存在しない」と批判。更に「常任次理事国である国が国際法を無視するのであれば、この字理解は何の役割を持つのだろうか」と問いました。
令和8年1月7日 ベトナム7-9月期GDP
おはようございます。米ベトナムの7-9月期GDPは、堅調でした。
1
1. インフレ率は減速
まず、インフレ率を見ておきましょう。ベトナム統計局が1月5日に発表した12月の消費者物価指数(CPI)上昇率は+3.48%、前月の+3.58%から減速(図表1参照)。

2. 10-12月のGDP成長率は+8.46%に加速
一方、ベトナム統計総局は1月5日に、10-12月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+8.46%になったと発表(図表2参照)。7-9期の改定値+8.235%から加速。17四半期連続の増加。2007年第4半期以来の高成長。
広範囲のセクターにわたって見られ、製造・建設業+9.73%、サービス+8.82%、農業+3.7%などが堅調。支出面では、米国が20の関税の課したにもかかわらず貿易は引き続き堅調で、第4四半期には財の輸出、輸入はそれぞれ+19.34%、+19.40%。

一方、最終消費は+7.15%、固定資産投資は+8.92%。
通年では、同国のGDP成長率は+8.02%と、2011年以来の高い成長率。
令和8年1月6日 米国がベネズエラ大統領を拘束
おはようございます。米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束しました。
1. 米国がベネズエラを攻撃
米トランプ大統領は3日、米軍がベネズエラの首都カラカスで軍事作戦を行い、同国のニコラス・マドゥロ大統領とその妻を拘束したと発表。
フロリダの私邸「マール・ア・ラーゴ」での記者会見で、大統領は「適切な政権移行」ができるまでは、今後米国がベネズエラを「運営する」としました。
一方、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領は国営テレビの演説で、マドゥロ氏が同国唯一の大統領であると主張。
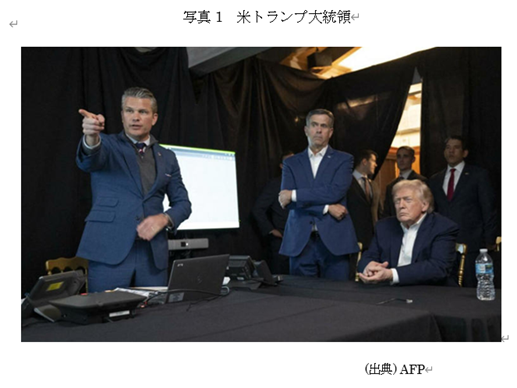
2. ベネズエラが抵抗すれば大きな代償を払うと
一方、トランプ氏は4日、ベネズエラの新しい指導者が米国の協力しなければ、「大きな代償」を払うことになると警告。
ベネズエラの最高裁判所は、米国がニコラウス・マドゥロ大統領を国外に移送したことを受け、デルシー・ロドリゲス副大統領に代行を務めるよう命じました。
トランプ氏は、米誌アトランティックとの電話インタビューで、ロドリゲス氏が「正しいことを行わないならば、非常に大金代償を払うことになるだろう。おそらくマドゥロ氏よりも大きな代償だ」としました。
3. 各国が懸念を表明
ロシアの外務省は声明で「こうした行為を正当化するために利用された口実は根拠がない」とし「現状ではなによりもまず、事態のさらなるエスカレートを防ぎ、対話を通じた大化策を見つける
ことに注力するのが重要だ」としました。
イランの最高指導者であるハメネイ師は、米国によるベネズエラへの攻撃後「重要なのは敵が虚偽の主張で政府や国家に何かを強制しようとしていることに気づいたとき、その敵に対して断固としてたち向かう必要があるということだ」としました。
欧州連合のカラウ外務安全保障上級代表(外相)は、ルビオ米国務訪韓と話したとして、EUがこれまでマドゥロ大統領に正当性が欠けていると主張し、平和的な政権移行を求めてきたとしました。他方、如何なる状況でも、国際法の原則と国連憲章は尊重されなければならないとして、関係国に自制を求めました。
令和8年1月4日 中国12月PMI
おはようございます。12月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 12月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が31日発表した12月の製造業購買担当者指数(PMI)50.1と、前月の49.2
から上昇。景況感の分かれ目となる50を9箇月振りに上回りました。休暇前の受注増加が寄与。市場予想の49.2から上振れ。
キャピタル・エコノミストの中国経済責任者ジュリアン・エベンスプリチャード氏は、「PMIの改善がハードデータで裏付けられると仮定すると、これは持続可能な景気回復の始まりになるというよりは、財政支出の月毎の変動を背景とする一時的な回復にとどまる可能性が高い」としました。「全体としては、不動産不況と産業の過剰生産能力による構造的な逆風が2026年も継続すると予想される」としました。
12月には生産指数が11月の50.0から51.7に上昇し、新規受注指数も49.2から50.8に上昇。サプライヤーの納期も改善して、生産・活動指数は55.5と昨年3月以来の水準に上昇。
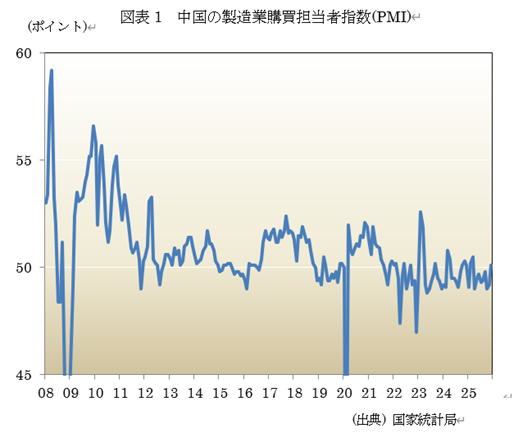
2. 非製造業PMIも上昇
一方、同日に発表した12月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.7と、前月より49.5から上昇。11月には、約3年ぶりに景気判断の節目となる50を下回っていました。
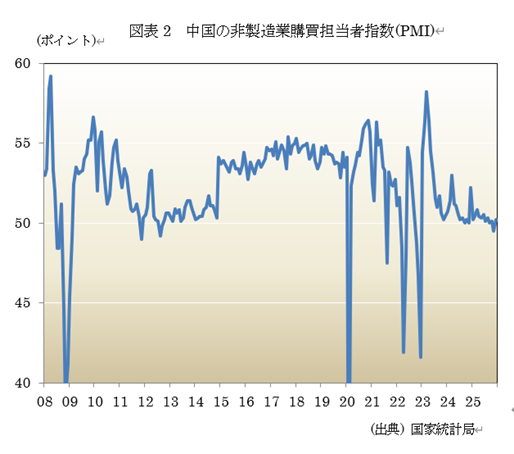
製造業と非製造業を合わせた総合PMIは50.7。11月は49.7。
同日発表された民間調査の製造業PMIも生産と内需の拡大が海外からの受注減少を相殺して、景況拡大・縮小の分かれ目となる50をわずかに上回りました。
令和8年1月3日 2025年を振り返って(5)ロシア
おはようございます。今回はロシアについて。
1. 7-9月期GDP成長率
ロシア連邦統計局は11月14日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+0.6%になったと発表(速報値)。市場予想通り。前期の+1.1%から減速。継戦能力を左右する戦時経済は、現安の継続により、減速傾向を強めています。
7-9月期には10四半期プラス成長を維持したものの、マイナス成長に陥った23年1-3月期の▲0.3%以来の低い成長率。
経済発展省によると、7−9月期には製造業が+1.1%。前四半期の+3.6%から減速。小売りが+2.1%、建設が+1.2%と、内需が勢いを欠いています。

2. インフレ率減速
国家統計局から11月14日発表された10月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.7%と、伸び率は前月の+8.0%から減速(図表2参照)。

3. 政策金利を引下げ
一方、ロシア中央銀行は10月24日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲0.5%ポイント引き下げ16.5%にすることを決定。引き下げは4会合連続。市場では、政策金利維持を予想していました。
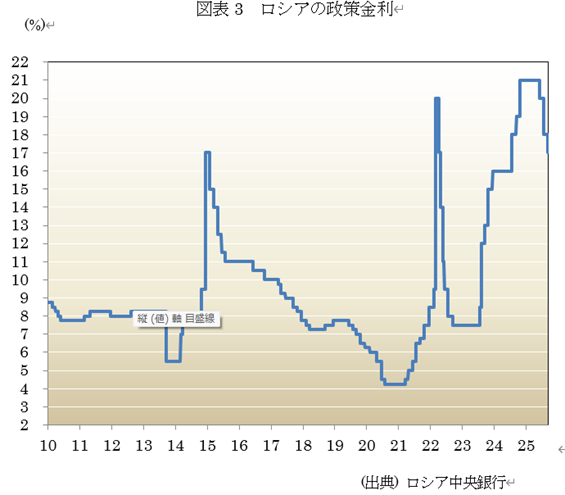
利下げしたものの、中銀は金融環境は、インフレ率上昇懸念により、中期的にはインフレ率上昇懸念により、金融環境は引き続き引き締め気味になるとの予想を維持。
4. 金融政策などについて
同中銀は12月19日に政策金利を+0.5%引き上げて16.0%として、5会合連続の利下げ。インフレは依然として目標を上回るものの、鈍化傾向。金融緩和の動きは進んでいます。
利下げの背景として、戦時経済の長期化による景気減速があります。GDP成長率が鈍化しており、今後も減速傾向を強める可能性があります。プーチン大統領は中銀の独立性を尊重する姿勢を示唆。v
中銀は声明で、経済は緩やかな拡大が継続するものの、分野別のばらつきがあるとしました。内需は消費や財政支出で支えられる一方、ガソリンや生鮮食品価格の上昇によりインフレ期待がやや高まっているとしました。中銀はインフレ率が+4-5%へと低下し、その後は目標に収束すると見込んでいます。
金融市場ではウクライナ戦争の終結期待によりルーブル相場は底堅いものの、不透明感もあります。中銀は為替や原油価格を含む多様な要因を見極め、難しい政策判断を迫られることとなりそうです。
令和7年12月31日 2025年を振り返って(4)ブラジル
おはようございます。22025年を振り返って。今回はブラジルです。
1. 政策金利を維持
ブラジル中央銀行11月5日の金融政策委員会で、政策金利を15.00%に維持することを決定。据え置き3会合連続で、市場の予想通り。
同金融政策委員会は声明で、前回会合と同様に「外部環境では米国の経済政策の影響により、不確実性が高まっている。」と指摘。更に、「国内経済は活動の鈍化が予想通りに進む一方、労働市場は堅調さを維持。インフレ率を目標値に収束させるには、長期的な金融引き締め政策が必要」との見解を示唆。
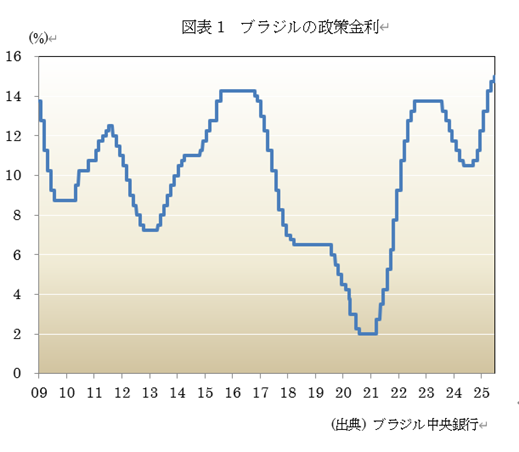
2. インフレ率が減速
一方、ブラジル地理統計院は12月10日に、11月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+4.46%と、前月の同+4.68%から伸び率は減速(図表2参照)。市場予想の+4.49%からやや下振れ。
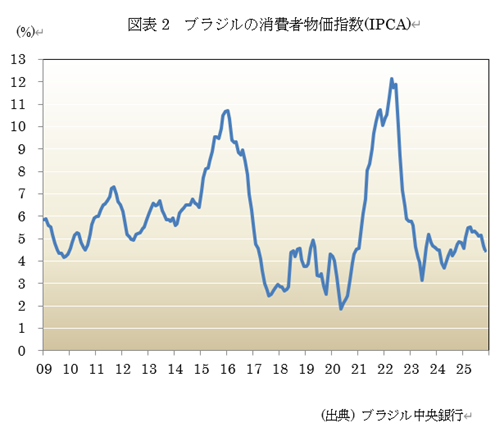
3. 7-9月期GDPは+1.8%に減速
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は12月4日に、7-9月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+1.8%であったと発表(図表3参照)。前期の上方修正された同+2.4%から減速。
中銀は世界の中でも最も高い部類の高金利政策を維持しており、GDPはここ3年で最も低い伸び率となりました。

政府の支出拡大と根強いインフレにより、労働市場は引き続き逼迫。農産物生産は+10.1%に急上昇し、製造業生産は+1.7%。一方、サービス業は+1.3%へと減速。
4. 同国の金融政策の動き
中銀は9-10日開催の定例会合で、政策金利を4会合連続で15.00%に据え置き。景気減速や米国による50%への関税引き上げを背景として、市場では、早期利下げ観測が広がったものの、中銀は9月および11月の会合で追加リア上げの可能性に言及するなど、タカ派姿勢を維持して、市場を牽制。インフレ率が目標上限を超える推移が続いたことが影響する一方、足下では鈍化が確認されています。
声明文では、決定が前回一致であったとしたうえで、インフレ目標の達成や景気安定に関する従来の見解を維持。世界経済の不透明感や地政学的リスクへの警戒を示唆しつつ、国内では景気減速と労働市場の堅調さ、インフレの鈍化傾向を指摘。物価については、上振れ、下振れ双方で高いリスクがあるとして、必要なら再利上げも辞さない考えも示唆。その一方、インフレ見通しは若干下方修正しました。
令和7年12月30日 2025年を振り返って(3)インド
おはようございます。2025年を振り返って、今回はインド。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が12月12日発表した11月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+0.71%(図表1参照)。前月の+0.25%から加速。市場予想の+0.7%にほぼ一致。
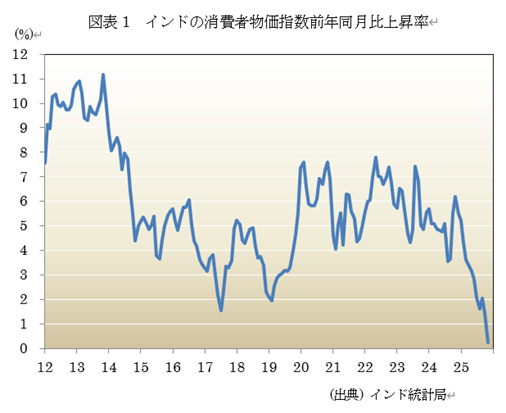
2. 7-9月期成長率+8.2%に加速
続いて、インド統計局が11月29日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+8.2%(図表2参照)。前期の同+7.8%から伸び率が加速。市場予想の+7.4%から上振れ。トランプ大統領による大幅な関税措置で見通しが曇る中でも堅調さを維持。
同国のモディ首相はGDPの数字について「非常に励みになる」とXに投稿。政府の「成長促進政策と改革」の成果を反映していると評価。
エコノミストの多くは当初、インド準備銀行が12月5日に利下げに踏み切ると予想していました。野村ホールディングスのエコノミスト、ソナル・バルマ氏は現在「難しい」判断になるかもしれないとして「高成長と低インフレが同居するインドのゴルディロクス的なマクロ環境はほかに例がない」としました。
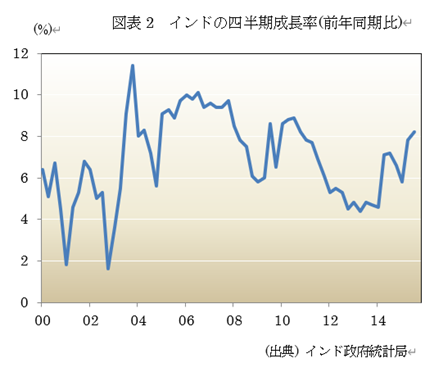
3. 政策金利を引き下げ
他方、インド準備銀行(中央銀行)は12月5日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを▲0.25%ポイント引き下げると決定。引き下げは市場の予想通り。
消費者物価指数(CPI)上昇率が過去最低水準にあり、今後の物価見通しも落ち着いているため、景気を一段と下支える余地が生まれました。
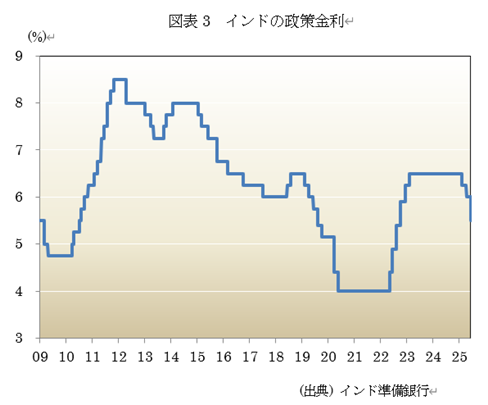
今回の利下げは、6人で構成する金融政策委員会(MPC)の前回一致で決定。政策姿勢は「中立」を維持。今後も利下げ余地があることを示唆。2025年2月以降の利下げ幅は累計▲125ポイント、8月と10月には金利を据え置いていました。
4. その他の動き
12月15日発表された11月輸出額は前年同月比+19.4%となり、前月の▲11.8%から2箇月ぶりに前年を上回る伸びに転じました。中期的な基調も拡大傾向で推移するなど、底入れが継続。奇形製品や電気機械の輸出が堅調。石油製品や化学製品のほか、宝石など幅広い分野で底堅い動き。
国・地域別では50%の関税が課されているにも関らず、米国向けが底堅く推移。EU向けも堅調。中国向けも堅調。
一方、輸入は前年同月比▲1.9%となり、前月の+16.6%から3箇月ぶりに前年を下回る伸びに転じました。国際原油価格を反映して、原油輸入額に下押し圧力がかかったほか、前月にかけて大きく上振れした金の輸入額も下振れすると友井、機械製品関連など幅広い分野で輸入が鈍化。その結果、貿易収支は▲245.30億ドルと、前月の▲416.80億ドルから赤字幅が小。
令和7年12月2日 中国11月PMI
おはようございます。11月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 11月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が30日発表した11月の製造業購買担当者指数(PMI)49.2と、前月の49.0から上昇。景況感の分かれ目となる50を8箇月連続で割り込みました。市場予想は49.2。
11月には生産が停滞し、サブ指数は50.0。新規受注と新規輸出受注のサブ指数はともに10月から改善したものの、いずれも50を下回りました。
ゴールドマン・サックスのエコノミスト、ヤン氏は、11月も製造業の減速が継続し「今年の成長目標は概ね達成可能であると思われる手目、我々は政府が来年第1四半期まで大規模な政策支援を先送りする可能性があるとの見方を維持している」としました。
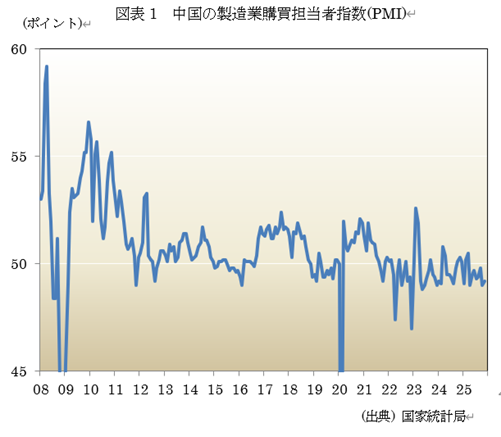
2. 非製造業PMIは低下
一方、同日に発表した11月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは49.5と、前月より50.1から低下。2022年12月以来初めて50を下回りました。
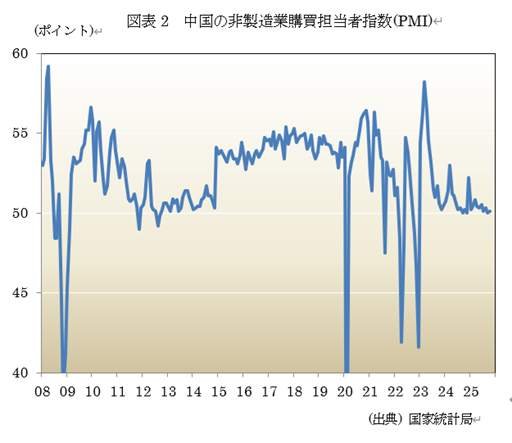
同統計局によると、サービス業は10月の連休による押上効果が薄れ、低水準となりました。統計局のリュー氏は、「不動産と家庭向けサービスの事業活動指数はともに50を割り込み、活動低迷を示唆」としました。
令和7年11月30日 インド7-9月期成長率
おはようございます。イインド4-6月期GDP成長率は、加速しました。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が11月12日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+0.25%(図表1参照)。前月の+1.44%から減速。市場予想の+0.48%から下振れ。
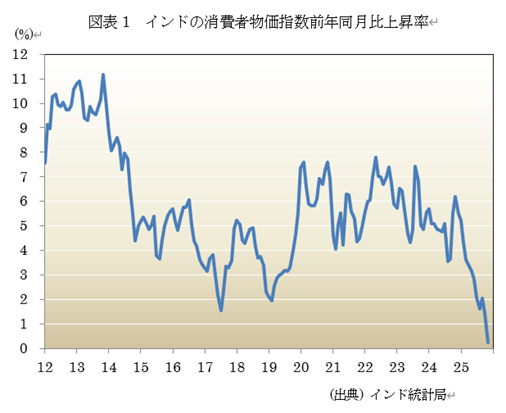
2. 7-9月期成長率+8.2%に加速
続いて、インド統計局が29日に発表した7-9月期成長率は、前年同期比+8.2%(図表2参照)。前期の同+7.8%から伸び率が加速。市場予想の+7.4%から上振れ。トランプ大統領による大幅な関税措置で見通しが曇る中でも堅調さを維持。
同国のモディ首相はGDPの数字について「非常に励みになる」とXに投稿。政府の「成長促進政策と改革」の成果を反映していると評価。
エコノミストの多くは当初、インド準備銀行が12月5日に利下げに踏み切ると予想していました。野村ホールディングスのエコノミスト、ソナル・バルマ氏は現在「難しい」判断になるかもしれないとして「高成長と低インフレが同居するインドのゴルディロクス的なマクロ環境はほかに例がない」としました。
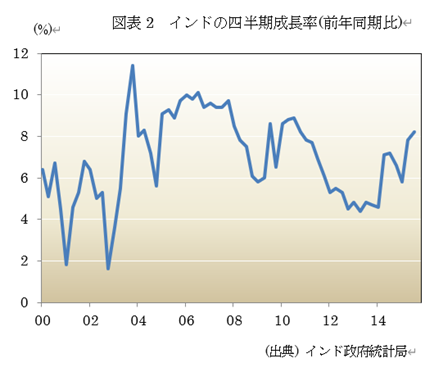
3. 政策金利を維持
他方、インド準備銀行(中央銀行)は10月1日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを5.5%に据え置くことを決定。金融姿勢は「中立」を維持。据え置きは市場の予想通り。
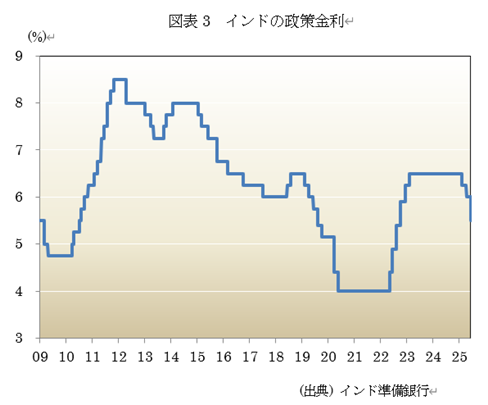
世界経済の不透明感が増す中、早期の利下げの効果と最近の現減税の効果を見極め、また最近のインフレ率の低下も考慮して政策金利維持を表明。年初からの▲1.0%ポイントの累計の金利引き下げにより、政策金利は2022年8月以来低水準を維持。
令和7年11月27日 日中の政治的対立が先鋭化
おはようございます。C高市首相の国会答弁を契機として、日中の政治的対立が先鋭化しています。
1. 台湾有事の質問事前に想定せず
台湾有事を巡る高市早苗首相の発言を機に、悪化の一途をたどる日中関係について、政府内で鎮静化に向けた2つのシナリオが浮上。1つは双方が受け入れ可能な形で発言を事実上撤回する案、もう1つは冷却期間をおいて、両国で落としどころを探る案。政府内では、長期化は避けられないとの判断が強まっています。
問題となった7日の国会答弁は、政府側が事前に準備していたものではなかったとされます。立件民主党の岡田克也元外相が政府側に示した質問主意書は、「総理の外交基本姿勢」などであり、細かな質問事項は書かれていませんでした。
岡田氏から、中国による海上封鎖が発生した場合、という具体的な事態を問われると「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースもあると私は考える」と一歩踏み込んだ答弁を行いました。
猛反発した中国は日本への渡航自粛を国民に呼びかけ、続いて日本海産物の輸入規制を再強化。一方、日本側は薛剣駐大阪総領事が「汚い首は斬ってやる」とソーシャルメディアに投稿したことに抗議し、中国側に適切な対応を求めました。
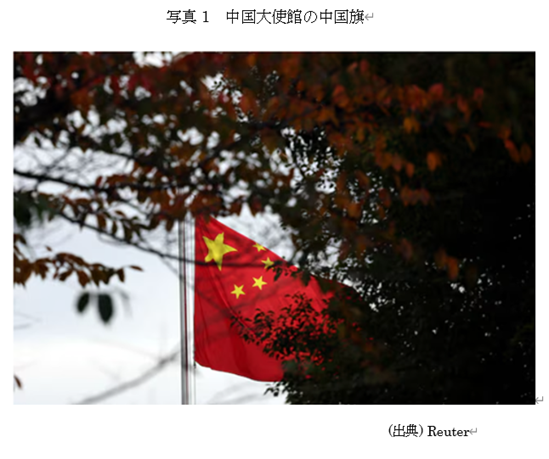
2. 日本に大きな経済的損失
一方、飲む差総合研究所の木内登英エコノミストによると、中国からの渡航樹種区要請による日本の経済的損失は1兆7900との試算になりました。
特に大きいのは、管工業への影響。中国メディアは、北京の旅行会社が日本旅行の新規ツアー客の受付を停止したと伝えました。
日本政府観光局によると、2025年1月から9月迄の中国からの訪日客は約750万人で、国別では最大。
エンタメ業界でも、中国での映画の上映が中止になるなど、影響が出始めています。
令和7年11月26日 COP30終了
おはようございます。COP30が閉幕しました。
1. 成果は乏しく
第30回国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP30)は11月22日、ブラジル議長団が定期王策の課題における進展、国際的な新たな気候実施ルール、そして化石燃料依存からの脱却に向けた議論への道筋を示唆して閉幕。
交渉流量後の記者会見で、議長を務めてアンドレ・コヘア・ド・ラーゴ大使らは、成果を説明。
同大使は、会議が厳しい幾多もの交渉圧力の下で開始され、各分科会の同議長に幅広い裁量の自立性が与えられたことを振り返りました。適応策パッケージは、COPの中でも最も複雑な議題の1つであり、当初は100を超える指標から始まりましたが、最終的に59に整理されたとしました。
「合意が得られたのはわずか10%に過ぎなかった。指標を再編成して、今後も議論を続ける。次は6月ボンでの気候会議で行う」としました。
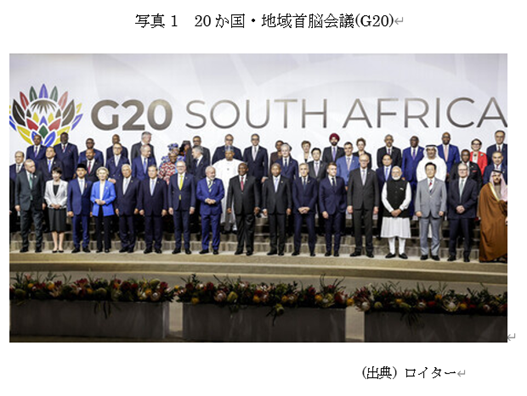
2. 米ニューサム知事が存在感
米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は、ブラジルで開催中のCOP30において、機構変動対策が21世紀最大の経済機会の1つであることを強調。イノベーションと気候変動対策に関する国際協力を加速。
米国は大統領が主要高官を会議に参加させませんでしたが、同知事は、「トランプ大統領による無謀なエネルギー政策は、中国を最優先し、米国を後回しにしており、中国が世界のクリーンエネルギー経済とそれに伴う高賃金の雇用、製造業、経済的繁栄を掌握するのを許している」と批判しました。
令和7年11月25日 G20首脳会議閉幕
おはようございます。G20首脳会議が閉幕しました。
1. G20首脳会議が閉幕
南アフリカのヨハネスブルクで開催されていた20か国・地域首脳会議(G20サミット)は23日、2日間の日程を終えて終了。トランプ米大統領がボイコットして、2008年の発足以来初の首脳宣言が出せない事態が危ぶまれましたが、初日にG20の重要性を確認した「宣言」を米国抜きで採択。来年は米国で開催。
議長国の南アは、新興国・途上国「グローバル・サウス」の立場から「連帯・平等・持続可能性」をテーマに設定。首脳宣言では「世界経済の不確実性と分断」に懸念を表明して、G20が多国間で課題に一致して対処する重要性を訴えました。
南アのラマポーザ大統領は閉幕スピーチで首脳会談宣言の採択は「G20が多国間で課題に対処して、協調行動を促す枠気味としての価値を裏付けた」としました。
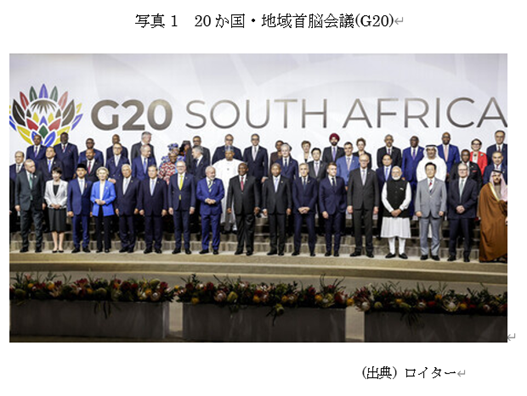
2. アルゼンチンは反発
サミットの議長を務めるラマポーザ大統領南ア大統領は、首脳宣言は「圧倒的な合意があった」としましたが、南ア当局者によると、アルゼンチンは宗さんを採択する直前に交渉から離脱。
アルゼンチンのキルノ外相はサミットで「アルゼンチンは首脳宣言を承認できないが、G20創設以来の協調の精神には引き続きコミットしている」としました。
令和7年11月24日 米9月雇用統計
おはようございます。米国の9月の雇用統計で、雇用者数が+11.9万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想上回る
米労働省が9月の雇用統計を20日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+11.9万人。市場予想の+5万人にから上振れ。失業率は4.4%と、前月の4.3%から上昇。21年以来、約4年ぶりの高水準。8月の雇用者数も大幅に下方修正され、今年2回目のマイナスとなり、労働市場の失速が継続していることを示唆。
失業率の上昇は、労働市場に新たに参入して求職者数の増加を反映。半面、労働省の別のデータによると、11月中旬のレイオフ件数は低水準にとどまっており、労働市場は「雇用も解雇もほぼできない状態」に陥っている模様。
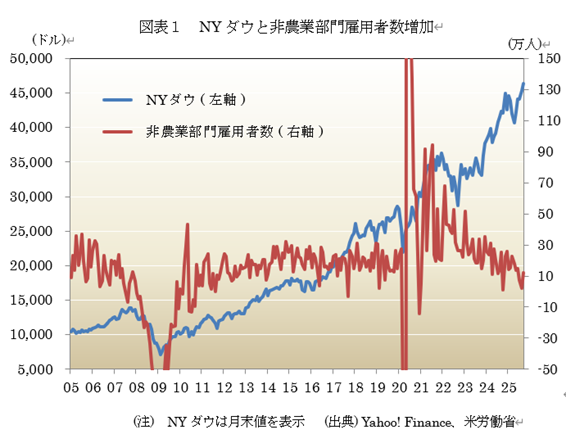
2. 10月雇用統計公表を見送り
一方、米労働省労働統計局(BLS)は19日、10月の雇用統計は公表できないことを示唆。只、同月の非農業部門者数を11月の統計を合わせるとしています。
BLSは「2025年10月の事業所調査データは、11月のデータと共に発表される」と説明。10月の失業率データは予算失効により収集できなかった。家計調査データは過去に遡って収集することはできない」としました。
令和7年11月21日 中国人民銀行政策金利維持へ
おはようございます。中国人民銀行が政策金利維持する見通しとなりました。
1. 金融政策を維持へ
中国人民銀行(中銀)は11日、第3四半期の金融政策を公表。経済が依然としてリスクと課題に直面しており、「適度に緩やか」な金融政策を維持して、流動性を潤沢に保ちながら政策伝達を改善する方針を示唆。
流動性を十分に保ちながら、物価を安定を妥当な水準に維持して、銀行への負債と社会的融資のコストを引き下げるとしています。
同行は経済・金融情勢の変化に応じてカウンター市売りからウクロスシクリカル政策を調整するとともに、海外中銀の金融政策の変化を見極めるとしました。

2. 外的要因には警戒感
さらに、「現在、外的な不安定要素や不確定要因が多く、国際経済・貿易秩序は深刻な課題に直面している」と指摘。
「世界経済の成長モメンタムは不十分で、主要国は異なった経済状況を示唆しており、中国経済は依然として多くのリスクと課題に直面している」としました。
令和7年11月20日 タイ7-9月期GDP減速
おはようございます。タイ4-6月期GDPは減速しました。
1. 7-9月期成長率+1.4%に減速
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は11月17日に、7-9月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+1.2%になったと発表(図表1参照)。前期の+2.8%から減速。市場予想の+1.6%からはした振れ。
工場の産出の低下、観光業の停滞、米国の関税の高まりに対する懸念などにより、2021年第3四半期以来の低水準。
固定資産投資は前年同期比+1.1%(前期は+5.8%)と急落。政府支出は▲3.9%(同+2.2%)、一方、個人消費は+2.6%と堅調を維持。
外需では、輸出+6.%(同+11.2%)、輸入+4.6%(同+10.9%)と共に減速。只、貿易収支は依然としてGDPには寄与。輸出の鈍化は、新たな米国による関税に起因。
生産面では、産出は農業が+1.9%(同6.4%)、非農業が+1.2%(同+2.5%)と共に鈍化。
政府は2025年成長率予想を従来の+1.8〜2.3%から+2.0%へと下方修正。

2. 消費者物価指数(CPI)上昇率マイナス
タイ商業省は5日、11月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.76 %であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.72%からわずかにマイナス幅が拡大。
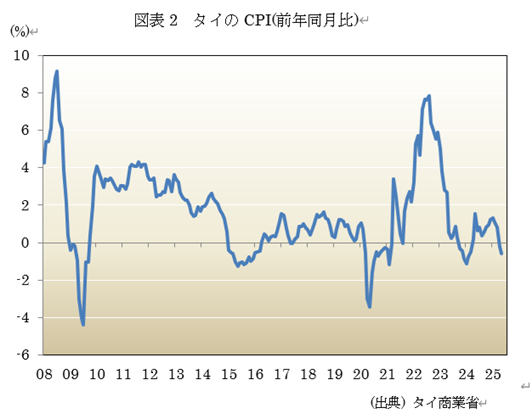
3. 政策金利を維持
一方、タイ中央銀行は10月8日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を1.5%に据え置き。脆弱な景気やバーツ高の中、政策余地を確保する姿勢を示唆。
中銀の金融政策委員会(MPC)はこの日の会合で、1日のルポ金利を1.50%に維持することを5第2で決定。据え置きはほぼ市場の予想通り。
この決定を受けて通貨バーツは上昇。
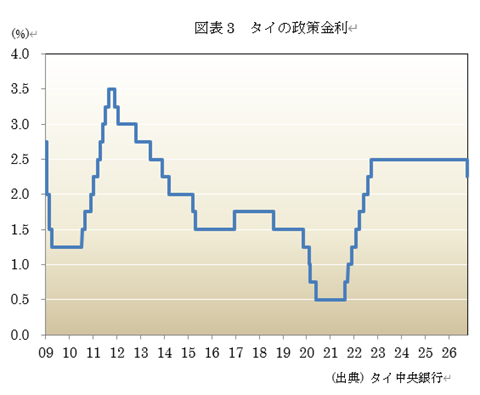
声明では「米国の関税政策は中小企業など一部のセクターで脆弱性を高まる」と指摘。タイ経済は減速に向かうとの見方を示唆。
令和7年11月19日 中国10月貿易統計
おはようございます。10月の中国貿易統計で、輸出は増加しました。
1. 10月輸出は減少
中国税関総署が7日発表した10月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+▲1.1%と、前月の+8.5%からマイナスに転じました。市場予想の+3.0%から下振れ米関税発動を前にした駆け込み輸出の効果が薄れた形。中国の製造業が猶、米国の消費に依存していることを示唆。
減少率は2月以来の大きさ。前年同月は過去2年以上で最速の伸びを規則。高い比較水準が影響。
一方、輸入は+1.0%。市場予想の+3.2%を大幅に下回り、5箇月振りの低水準。9月は+7.4%。
貿易黒字は900億7000万ドルと、前月の904億5000万ドルから縮小。市場予想の956億ドルをしたまわりました。
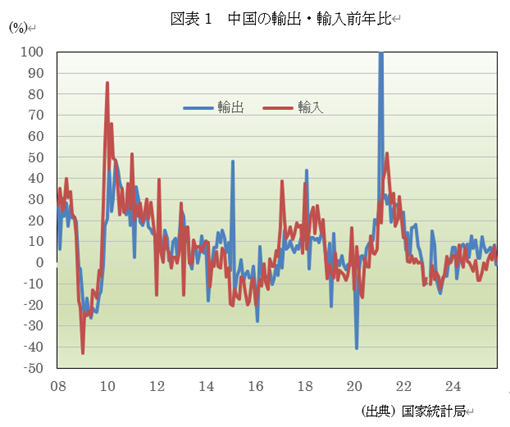
2. 米中がレアアースで協議継続
駐豪のレアアース(希土類)輸出を巡る規制の緩和を巡って、米中な協議を継続。ホワイトハウスはこれまで、貿易戦争の休戦の合意がレアアースの輸出再開に道を開くとしていました。
米国向けのレアアースやその他の重要鉱物の輸出に関して、中国が提供を約束した「一般輸出許可」の条件を11月末までにまとめるよう、両国はそれぞれの交渉チームに指示したと、関係者が述べました。遅延の理由については、明らかにしていません。
令和7年10月17日 ロシア7-9月期GDP
おはようございます。ロシア7-9月期GDPは減速しました。
1. 7-9月期GDP成長率
ロシア連邦統計局は11月14日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+0.6%になったと発表(速報値)。市場予想通り。前期の+1.1%から減速。継戦能力を左右する戦時経済は、現安の継続により、減速傾向を強めています。
7-9月期には10四半期プラス成長を維持したものの、マイナス成長に陥った23年1-3月期の▲0.3%以来の低い成長率。
経済発展省によると、7−9月期には製造業が+1.1%。前四半期の+3.6%から減速。小売りが+2.1%、建設が+1.2%と、内需が勢いを欠いています。

2. インフレ率減速
国家統計局から11月14日発表された10月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+7.7%と、伸び率は前月の+8.0%から減速(図表2参照)。

3. 政策金利を引下げ
一方、ロシア中央銀行は10月24日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲0.5%ポイント引き下げ16.5%にすることを決定。引き下げは4会合連続。市場では、政策金利維持を予想していました。
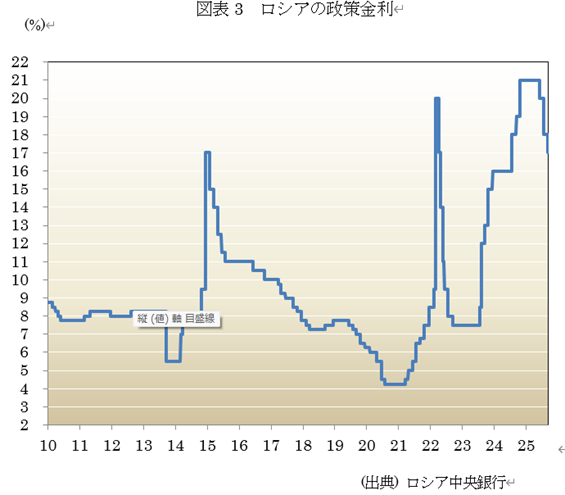
利下げしたものの、中銀は金融環境は、インフレ率上昇懸念により、中期的にはインフレ率上昇懸念により、金融環境は引き続き引き締め気味になるとの予想を維持。
令和7年11月16日 中国10月鉱工業生産
おはようございます。中国10月鉱工業生産は減速しました。
1. 鉱工業生産は減速
中国国家統計局が14日発表した10月の鉱工業生産は、前年同月比+4.9%と、前月の+6.5
%から伸び率が大幅に減速。市場予想の+5.5%から下振れ。

2. 9月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、10月の小売売上高は前年同期比+2.9%と、前月の+3.0%から伸び率が減速。市場予想の+2.8%から上振れ。
HSBCのアジア担当チーフエコノミスト、フレッド・ニューマン氏は、「中国経済はあらゆる方面からの圧力に直面している」としました。「ここ数四半期の成長を支えてきた輸出の力強い圧力に直面」と指摘。「ここ数四半期の成長を支えて来た輸出の力強い押上は、米国の関税が懸念された水準よりも低くなったとしての、来年迄持続するのは困難である。そのため、内需が補うこととなるが、大規模な追加刺激策がなければ、投資と消費の双方における最近の減速を反転させるのは困難だろう」としました。

3. 1-9月固定資産投は減少
他方、国家統計局による同日発表の1-10月期の固定資産投資は、前年同期比▲11.7%。率は1-10月期の▲0.5%から拡大。市場予想は▲0.8%。
資産投資が▲13.%(1-8月期は▲12.9%)と落ち込み、インフラ投資+1.1%(同+2.0%)、製造業+4.0%(同+5.1%)と落ち込みました。
長引く不動産市況に黒点の兆しはなく、10月の新築住宅価格は前月比で大幅な落ち込みとなりました。
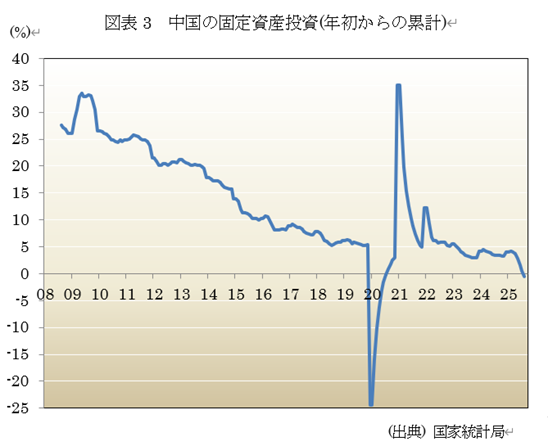
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのシニアエコノミスト、除天辰氏は「投資についてはやや懸念している。中国はより消費主導型のモデルに移行しつつあるが、だからと言って投資がなくなるべきではない」としました。
令和7年11月15日 中国10月新築住宅価格
おはようございます。中国10月新築住宅価格は前月比大幅下落しました。
1. 7-9月期GDPが減速
中国国家統計局が10月20日発表した7-9月期実質GDPは+4.8%。市場予想の+4.6%から上振れ。前期の+5.%から伸び率は鈍化。不動産不況による内需不足が影響。季節調整済み前期伸び率は+1.1%と、4-6月期の+1.0%から加速。同年率では+4.5%程度。生活実感に近い名目GDPは前年同期比+3.7%。前期は同+3.9%。
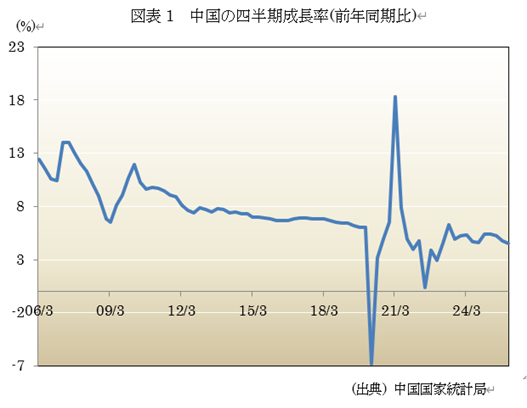
外需では、7-9月期ドル建て輸出は前年同期比+6.6%。貿易摩擦が継続する米国への輸出が減少したものの、欧州連合や東南アジア諸国連合向けなどが伸長。
輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は前年同期比+12%。1-9月期実質GDPは+5.2%。政府は通年の成長目標を「+5%程度」としています。
2. 中国10月新築住宅価格は前月比大幅下落
中国統計局が11月14日発表した統計によると、同国の10月の新築住宅価格は前月比0.5%の大幅下落。昨年10月以来の大幅な落ち込み。危機に見舞われた不動産セクターの需要げ依然として低迷していることを浮き彫りにしました。
9月には▲0.4%の下落となっていました。
10月は、前年比で▲2.2%。下落率は前月と同じ。
令和7年11月13日 中国独身の日今年は穏やか
おはようございます。中国の9月CPIは、前年同月比下落しました。
1. 穏やかな独身の日
中国では11月11日の「独身の日」にちなんだ世界最大規模のインターネット商戦が幕を閉じようとしています。長引く不動産危機や所得不安に伴う消費の低迷により、今年は今一つ盛り上がりに欠けています。
商戦は長期化しており、多くのサイトが10月前半に開始。これまでで最も長い期間となりました。
グローバルファッション・ライフスタイルブランドの中国におけるオンラインストアを管理するカンフー・データのガードナー最高経営責任者は「今回の雰囲気と売上高を表現するには穏やかという言葉がぴったりかもしれない。予想をはるかに超える非常なブランドもある一方、横這いか昨年より微増か微減のブランドもある」としました。
また、値引き率が高いサイトが多く、消費者はどこのサイトの値引き率が高いか、比較しながらの購入が目立っています。

2. 返品も増大
一方、大量の商品が売れるものの、増大する返品が問題となっています。
ネット通販最大手アリババが開始した独身の日のセールは、去年の販売額が約30兆円規模となりました。
今年のセールは先月から始まっていて、過去最長期間となっていますが、大量に商品が購入される一方で、いま問題となっているのが商品の返品です。
配達員によると、1日の返品の数は約100点以上とのこと。返品率は年々増大仕手おり大型サール時には最大で60%にも上るとされています。
令和7年11月12日 中国10月CPI
おはようございます。中国の9月CPIは、前年同月比下落しました。
1. 10月CPIが上昇に転じる
中国国家統計局が9日発表した10月消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+0.2%。市場予想は0.0%。前月は▲0.3%でした。
変動の激しい食品と燃料価格を除いたコアインフレ率は前年比+1.2%と、9月の+1.0%から加速して、1年8月振りの高水準。食品価格は▲2.9%。9月は▲4.4%。

2. PPIはマイナス幅縮小
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、10月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.1%と、前月の▲2.3%からマイナス幅が縮小。市場予想は▲2.2%。PPIは2022年10月以降マイナスが継続。
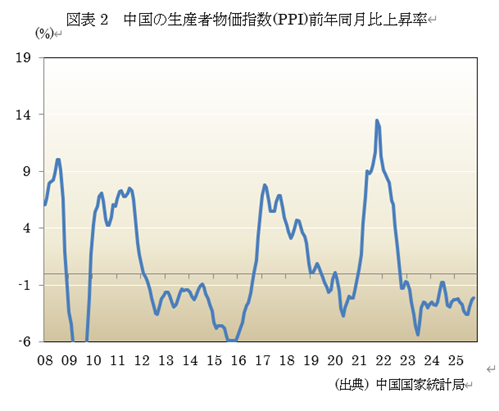
指標は改善したものの、アナリストはデフレ圧力はまだ消えておらず、需要喚起に向けた追加の政策措置が必要になる可能性があると警告。
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのシニアエコノミスト、シュー・ティエンチェン氏は、「需要は依然として弱いが、CPIの回復は供給サイドの政策が効果を上げており、多くの産業で需給バランスが改善していることを示唆している」としました。
令和7年9月20日 インドネシア中銀利下げ
おはようございます。インドネシアの7-9月期GDPは減速しました。
1. 11月CPI上昇率は加速
インドネシア中央統計局は11月3日に、10月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.86%になったと発表(図表1参照)。前月の+2.65%から加速。
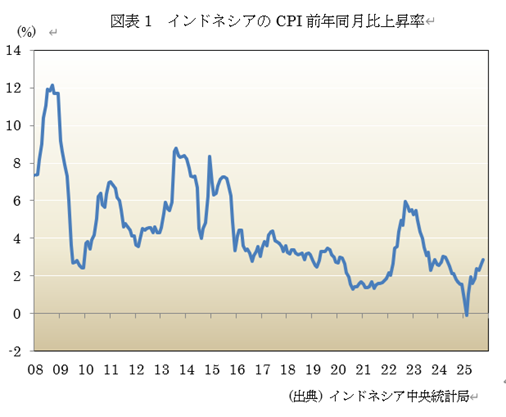
2. 政策金利を据え置き
一方、インドネシア中央銀行は10月22日の理事会で、政策金利であるBIレートを4.75%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想外。
中銀のペリー・ワルジョ総裁は、「インフレ、そして経済成長率支援の観点で言えば、確かに追加利下げの余地は残っている」としました。また、その時期は通貨ルピアの安定と過去の利下げ効果次第で決まるとしました。
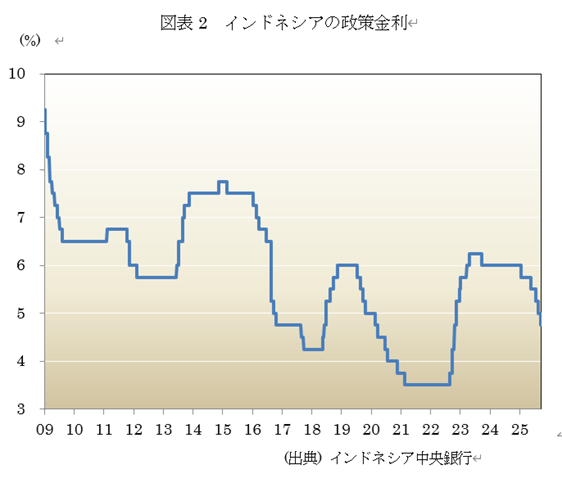
3. 7-9期GDP減速
インドネシア中央統計局(BPS)は8月5日に、同国の4-6月期GDP成長率が、前年同期比+5.04%になったと発表。前期の同+5.12%から減速。市場予想の5.0%から上振れ。
政府は2029年までに+8%成長を達成する目標を掲げており、課題が浮き彫りとなりました。25年の目標は+5.2%、26年は+5.4%。
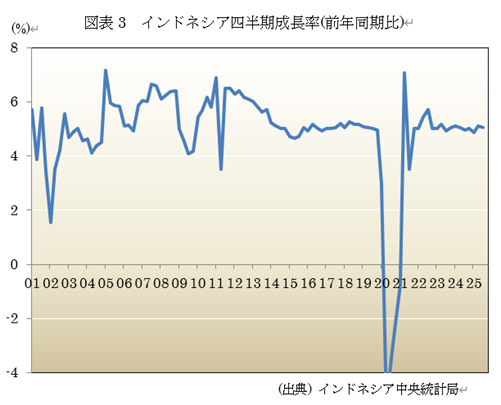
同国では、8月下旬から9月にかけて全国で反政府デモが発生。死者が出ました。
政府は6月に24兆4400億ルピア(役15億ドル)の景気刺激策を打ち出しました。8月には米国が19%の関税を発動しましたが、第3四半期の輸出は毎月増加。
令和7年11月9日 フィリピン7-9月期GDP
おはようございます。フィリピン7-9月期GDPは減速しました。
1. 10月CPI伸び率横ばい
フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は11月5日に、10月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+1.7%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月と同じ。市場予想の+1.8%から下振れ。
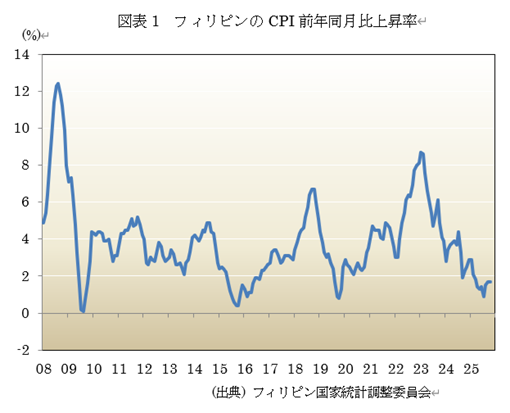
2. 政策金利を引き下げ
一方、フィリピン中央銀行は10月9日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を▲0.25%ポイント引き下げて、4.75%にすると決定(図表2参照、上限を表示)。引き下げは市場の予想外。大半のアナリストは据え置きを予想。利下げは4会合連続。
今回の利下げは、洪水対策予算の支払いを巡る問題を通じて、インフラ関連支出のガバナンスへの懸念が高まったことなどで、国内の経済成長の見通しが世回ったことを受けて実施。
レモロナ中銀総裁は10月に、利下げが2026年まで続く可能性を示唆。政策当局は、世界的な貿易摩擦への備えとして、経済の下支えを図っています。
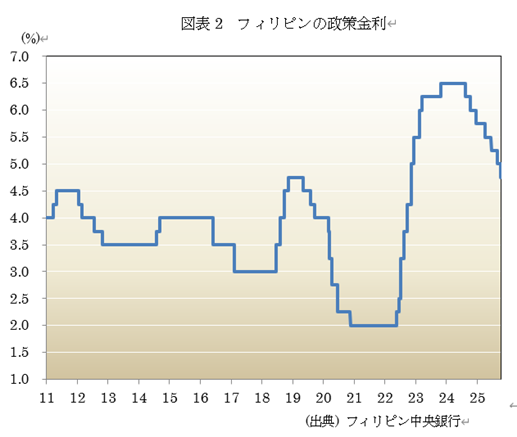
3. 7-9月GDPは伸び率減速
一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は11月7日に、7-9月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+4.0%の伸びになったと発表(図表3参照)。市場予想の+5.2%から下ぶれ。前期の同+5.5%から原則。汚職調査で国協事業を中断したことや、台風などの自然災害が響きました。政府が掲げる年間の成長率目標の達成は厳しくなりました。
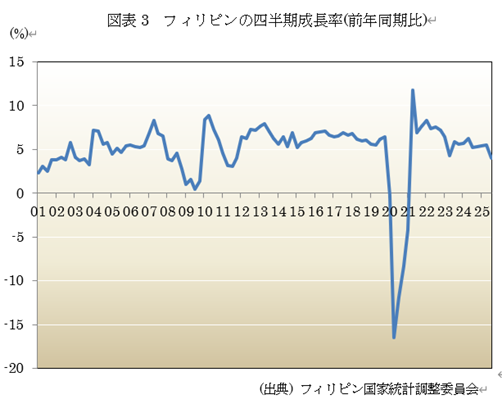
同国は東南アジアの中でも比較的高い成長率を維持してきており、+5%を超える成長率を維持してきました。減速した背景には、公共事業を中心とする設備投資の鈍化があります。
公共投資や民間の設備投資を含む総固定資本形成は、前年同期比▲2.8%。このうち政府による公共投資は▲26.2%と落ち込みました。
マルコス大統領が7月に汚職対策に取り組むと表明して以来、業者が受注しながら未着工の「幽霊事業」が発覚。政府は事業を中断したり、予算を組みかえたりするなどの対応を行いました。
令和7年11月8日 中国とブラジルがCOP30で主導権争い
おはようございます。中国とブラジルがCOP30で主導権争いを演じています。
1. COP30開幕
温暖化対策を話し合う第30回国連気候変動枠組み条約国会議(COP30)が6日に開始。アマゾン川河口のブラジル北部ベレンが舞台。トランプ政権が政府高官派遣を見送り、中国は丁薛祥(ディン・shジェエシアン)副首相、序列6位を送り込み、主導権を狙っています。
二酸化炭素排出量世界2位の米国が好感の出席を見送る一方、同2位の中国は政治局常務員の1人で序列2位の薛祥(ディン・shジェエシアン)副首相を送り込んでいます。6日の首脳夕会談では「中国は約束を守る。経済と社会の全分野でグリーンへの転換を加速する」としました。

2. ブラジルは熱帯雨林基金呼びかけ
一方、COP30開催に先立ち、熱帯雨林の保存を目指す国際基金が6日、議長国ブラジルの主導で立ち上げられました。日本を含む50カ国超が指示を表明。ノルウェーやインドネシア、フランスが拠出を決定。
機器は、各国政府や民間企業から募った資金を運用。熱帯雨林を持つ国に保全状況に応じて配分し、保護活動を促します。ブラジルのルラ大統領が9月に10憶ドル(約1500億円)の拠出を発表して、各国に投資を呼び掛けていました。
令和7年11月5日 フィリピン、UAEがTPP参加表明
おはようございます。フィリピン、UAEがTPP参加表明しました。
1. トランプ関税に対抗
フィリピンとアラブ首長国連邦(UAE)が環太平洋経済連携協定(TPP)への加盟を申請していたことが分かりました。韓国も申請の検討に入りました。トランプ米政権による関税引き上げや米中対立で保護主義が世界に広がる中、日本などのTPP加盟各国は欧州と並び自由貿易を守るとりでになりつつあります。
フィリピンとUAEは事務に書類を提出。日本政府機関者が表明。新規の申請は24年9月のインドネシア依頼、約1年半程度。

2. 中国も加盟申請
一方、2021年9月、TPPに加盟を申請。その数日後にが、台湾も加盟を申請。この申請は、米国に対して揺さぶりのかける狙いを持っており、国際経済をリードする意図があると言えます。
中国が加盟申請することにより、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定を併せて、自由貿易圏の拡大に繋がると期待されています。只、加盟のハードルは高く、特に中国が加盟への地ならしを開始した際には、NZやシンガポールとの話し合いで進展があったとされます。
令和7年11月3日 米中両首脳が会談
おはようございます。A米中両首脳が韓国で会談しました。
1. 米中領首脳1時間半にわたり会談
トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は30日、韓国で会談。約1時間半にわたって、広範な貿易摩擦の鎮静化などについて話し合いました。
会談終了時には両首脳が握手を交わし、韓国・釜山の空軍基地で行われた会談会場から歩み寄る様子が見られました。会談はAPEC首脳会議の合間に行われ、トランプ氏はこの後ワシントンに戻りました。

2. 貿易摩擦は緩和か
一方、トランプ大統領は30日の習近平国家主席との会談後、習氏が合成麻薬ファンタニル対策を講じると約束したとし、対中関税を▲1%引き下げると表明。中国も報復関税を引き下げる予定。
中国商務省によると、中国によるレアアース(希土類)の新たな輸出規制は導入を1年間延期。トランプ氏は同期生を巡って「全て解決した」としました。
令和7年11月2日 APEC首脳会議閉幕
おはようございます。APEC首脳会議が閉幕しました。
1. APEC首脳会議が閉幕
韓国・慶州で開催されていた21か国によるアジア太平洋経済協力会議(APEC)が1日閉幕。米国トランプ政権による高関税政策で世界経済の不透明が深まる中、自由貿易体制の維持・強化に向けた首脳宣言を採択。
2日目の会議には、初日続き高市首相や議長国の韓国の李在明大統領、中国の習近平主席あらが参加。米国は既に帰国したトランプ大統領に代わって、ベッセント財務長官が出席。
李氏は会議の初めに、「AIと人口構造の変化という共通の課題に対する創造的な解決策を、共に模索することを期待する」としました。

2. トランプ氏はAPEC素通り
一方、今回の首脳会談には、トランプ氏の代わりにベッセント財務長官が出席。トランプ氏は日本訪問の後韓国にも行き、慶州にも立ち寄りました。首脳会談の開催地まで行き、習近平国家主席との会談を終えるとすぐに帰国。
トランプ氏の不在をつくように、宙金平氏が存在感を高めることとなりました。WTOを中心とする多角的な貿易体制を維持して、保護主義に対抗する立場を取りました。
中国は2026年にAPECの議長国となります。習氏は首脳会議を来年11月広東省の深センで開催すると表明。ハイテク産業が集積する深センに首脳たちを集めて、新たな貿易体制の主導権を握るつもりであると考えられます。
令和7年11月1日 中国10月PMI
おはようございます。10月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。
1. 9月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が31日発表した10月の製造業購買担当者指数(PMI)49.0と、前月の49.8から低下。市場予想の49.6から下振れ。景気判断の分かれ目となる50を7か月連続で下回りました。内需を押し上げる追加刺激策を求める声が高まるとみられます。
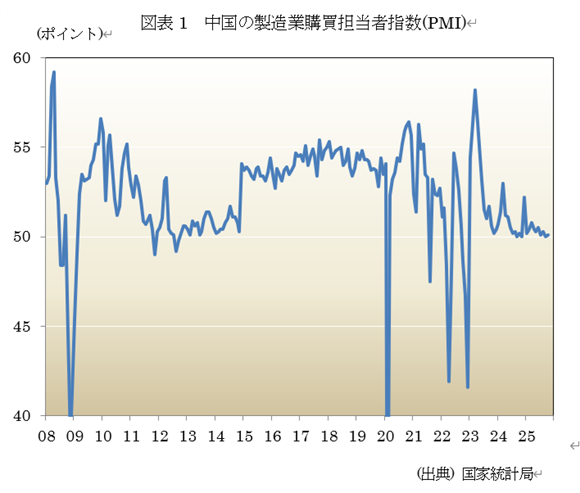
2. 非製造業PMIは低下
一方、同日に発表した10月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.1と、前月より50.0から上昇サービス部門は50.1から50.2に小幅上昇。建設部門は49.3から49.1に低下。
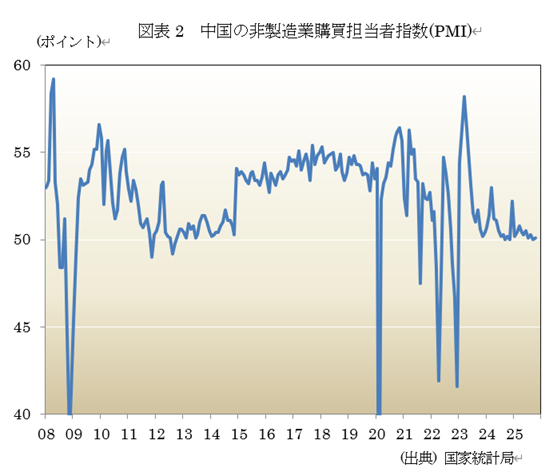
キャピタル・エコノミクスの駐豪エコノミストは「こうした弱さは短期的に反転するかもしれないが、米中貿易合意による輸出増加は小幅にとどまる公算。成長への逆風は続く」としました。
令和7年9月22日 アルゼンチン4-6月期GDP
おはようございます。アルゼンチン与党が中間選挙で大勝しました。
1. 9月CPI上昇率が鈍化
アルゼンチン統計局の10月14日発表によると、9月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+31.8%(図表1参照)。前月の+33.6%から減速。市場予想に一致。
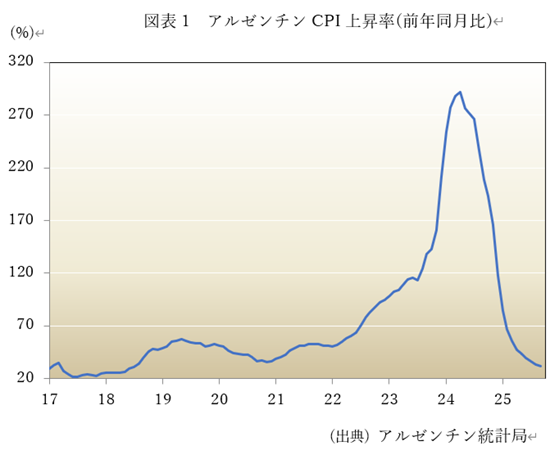
2. 政策金利を引き下げ
アルゼンチンの中央銀行は1月31日、インフレ率の低下を受けて、政策金利を▲3%引き下げて29%にすると発表。これは、ミレイ大統領の2023年12月の就任以来9回目の利下げ。これにより、借入コストは2020年10月以来最低の水準となりました。
2024年12月には、インフレ率は8カ月連続で低下して+117.8%となり、2023年7月以来の水準となり、11月の+166%から鈍化。
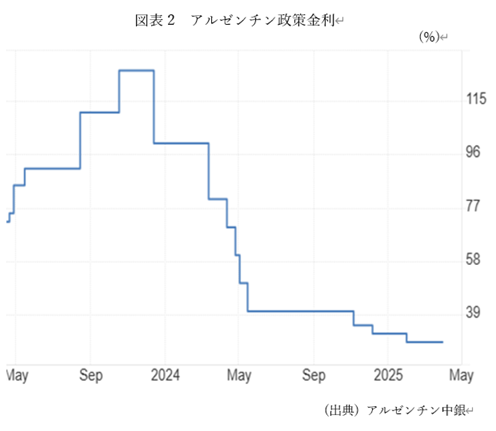
前月比上昇率は+2.7%と、3カ月連続で+3%を下回りました。利下げは、政府の2月1日開始の月次通貨低下率の▲2%から▲1%への圧縮と重なりました。
3. 4-6月期GDP
アルゼンチン統計局の9月10日発表によると、4-6月期のGDP成長率は前年同月比+6.3%。前期の+5.8%から加速。市場予想の+6.5%からは下振れ。
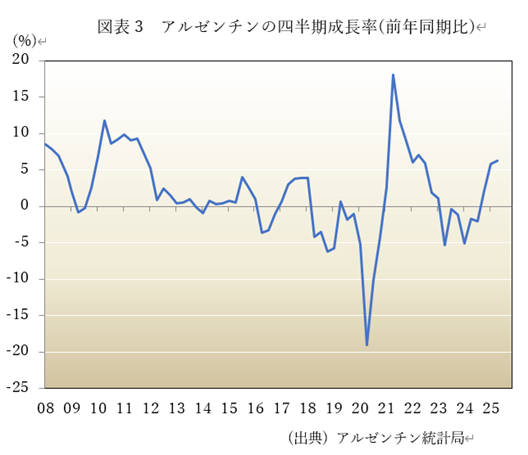
前年同月比では2022年4-6月期以来の高い成長率であり、農業部門(+4.8%、前期は+3.7%)が牽引。製造業が+6.9%(前期は+0.7%)、卸・小売りは+10.3%(同+2.5%)、輸送・通信は+1.4%(同+2%)、金融仲介は+26.7%(同+8.4%)など。好況事業は▲1.1%(同▲1%)。
同国では2023年12月に発足したミレイ政権下で、急進的な緊縮策を進めてきました。国内経済は一時大幅に冷え込んだものの、24年10-12月期には前年同期比でプラス成長に転じていました。
4. アルゼンチン与党選挙大勝
一方、アルゼンチンで26日中間選挙があり、ハビエル・ミレイ大統領率いる「自由の前進」が圧勝。ミレイ政権は発足から2年間、大胆な歳出削減と、自由市場改革を実施。
予想「自由の前進」は得票率約41%を獲得。上院の改選24議席中13議席、下院の同127議席中64議席を獲得。この勝利によって、国家主出のセク減と経済の規制緩和を進める大統領の政策の推進がはるかに容易になります。
未来大統領を支持する米トランプ大統領は、今回の投票に抱き立ち、米国が最近発表した400億ドルの対アルゼンチン支援策について、ミレイ大統領の与党が中間選挙で勝利することが、支援実行の前提であるとしていました。
令和7年10月26日 ロシア中銀利下げ
おはようございます。ロシア中銀が利下げしました。
1. 4-6月期GDP成長率
ロシア連邦統計局は9月12日、4-6月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+1.1%になったと発表(速報値)。市場予想通り。1-3月期の+1.4%から減速。伸び率は9四半期連続でプラス成長。
ロシアの成長率は1996年から2025年で、1999年10-12月期に市場最高の+12.1%となり、2009年4-6月期には史上最低の▲11.2%とつけています。

2. インフレ率減速
国家統計局から10月10日発表された9月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+8.0%と、伸び率は前月の+8.1%から減速(図表2参照)。

3. 政策金利を引下げ
一方、ロシア中央銀行は10月24日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲0.5%ポイント引き下げ16.5%にすることを決定。引き下げは4会合連続。市場では、政策金利維持を予想していました。
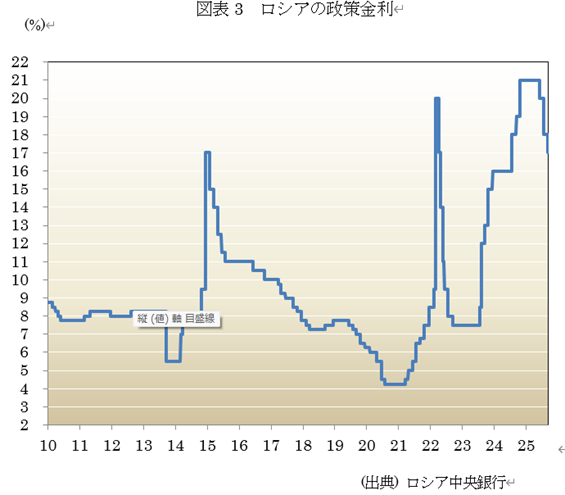
利下げしたものの、中銀は金融環境は、インフレ率上昇懸念により、中期的にはインフレ率上昇懸念により、金融環境は引き続き引き締め気味になるとの予想を維持。
令和7年10月23日 中国7-9月期GDP
おはようございます。中国の7-9月期GDPは減速しました。
1. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が20日発表した9月の鉱工業生産は、前年同月比+6.5%と、前月の+5.2
%から伸び率が加速。市場予想の+5.0%から上振れ。製造業が+7.3%(前月は+5.7%)、鉱業+6.4%(同+5.1%)などが牽引。
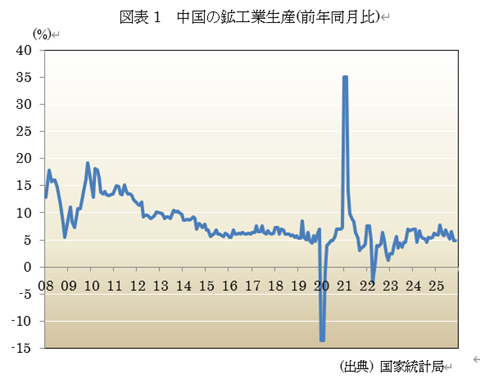
2. 9月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、9月の小売売上高は前年同期比+3.0%と、前月の+3.4%から伸び率が減速。市場予想の▲2.9%から下振れ。

3. 1-9月固定資産投は減少
他方、国家統計局による同日発表の1-9月期の固定資産投資は、前年同期比▲0.5%。伸び率は1-8月期の+0.5%から反転。市場予想の+0.2%から下振れ。資産投資が▲13.%(1-8月期は▲12.9%)と落ち込み、インフラ投資+1.1%(同+2.0%)、製造業+4.0%(同+5.1%)と落ち込みました。
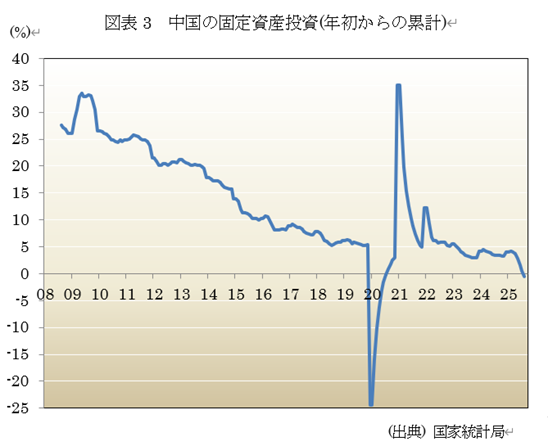
地域別では、東部知己が▲4.5%、中部地域+1.5%、西部地域+1.5%、東北地域▲8.4%)。
企業形態別では、本土上場企業投資が▲0.6%、香港マカオ領特別行政区と台湾地区企業が▲0.3%、外資企業が▲12.6%。
4. 7-9月期GDPが減速
中国国家統計局が同日発表した7-9月期実質GDPは+4.8%。市場予想の+4.6%から上振れ。前期の+5.%から伸び率は鈍化。不動産不況による内需不足が影響。季節調整済み前期伸び率は+1.1%と、4-6月期の+1.0%から加速。同年率では+4.5%程度。生活実感に近い名目GDPは前年同期比+3.7%。前期は同+3.9%。

外需では、7-9月期ドル建て輸出は前年同期比+6.6%。貿易摩擦が継続する米国への輸出が減少したものの、欧州連合や東南アジア諸国連合向けなどが伸長。
輸出から輸入を差し引いた貿易黒字は前年同期比+12%。1-9月期実質GDPは+5.2%。政府は通年の成長目標を「+5%程度」としています。
令和7年10月22日 中国8月鉱工業生産
おはようございます。中国9月鉱工業生産は加速しました。
1. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が20日発表した9月の鉱工業生産は、前年同月比+6.5%と、前月の+5.2
%から伸び率が加速。市場予想の+5.0%から上振れ。製造業が+7.3%(前月は+5.7%)、鉱業+6.4%(同+5.1%)などが牽引。
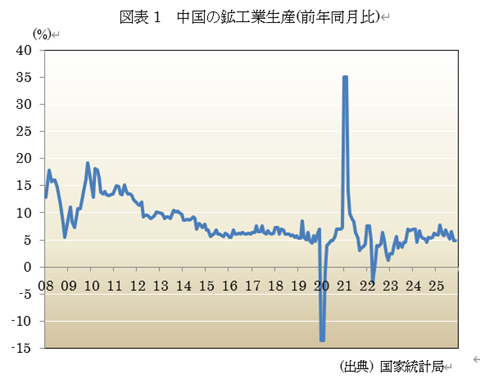
2. 9月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、9月の小売売上高は前年同期比+3.0%と、前月の+3.4%から伸び率が減速。市場予想の▲2.9%から下振れ。

3. 1-9月固定資産投は減少
他方、国家統計局による同日発表の1-9月期の固定資産投資は、前年同期比▲0.5%。伸び率は1-8月期の+0.5%から反転。市場予想の+0.2%から下振れ。資産投資が▲13.%(1-8月期は▲12.9%)と落ち込み、インフラ投資+1.1%(同+2.0%)、製造業+4.0%(同+5.1%)と落ち込みました。
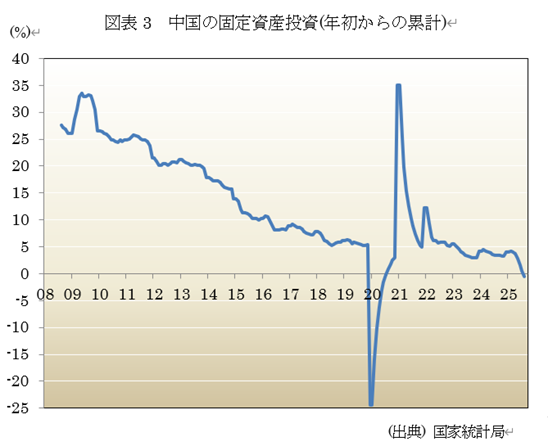
地域別では、東部知己が▲4.5%、中部地域+1.5%、西部地域+1.5%、東北地域▲8.4%)。
企業形態別では、本土上場企業投資が▲0.6%、香港マカオ領特別行政区と台湾地区企業が▲0.3%、外資企業が▲12.6%。
令和7年10月21日 日本を目指す中国人が増加
おはようございます。日本を目指す中国人が増加しています。
1. 中国人の旅行者、移住希望者が増加
日本を目指す中国人がこのところ増加しています。理由としては、まず、距離の近さがあります。北京や上海から東京或いは大阪迄、飛行機で、僅か3-4時間程度で来ることができます。又、文化的にも同じ黄色人種、漢字を使っており、儒教など似た文化圏であるとも言えます。
又、このところの円安の影響があり、物価もとても安くなっています。更に、日本は治安が良く、犯罪の発生率も低く、安全な社会であることも評価されています。
2. 教育のための移住も増加
特に文京区では、教育のために移住を希望する中国人が増加。特に文京区の誠之小学校、千駄木小学校、昭和小学校、窪町小学校への入学を希望する在日中国人が急増。これらは「3S5K」と呼ばれています。
中国人は教育に熱心で、中国国内では猛烈な受験戦争を繰り広げています。来日しても同様で、彼らは熱心な教育を行っているとみられます。

このところ、在日中国人の人口が増加。20224年末には87万3000人、うち東京都には28万6000人となっています。
都内には中国人の観光客も多く、銀座などではどこにいても中国語が聞こえてくるほど。只、文京区における中国人の人気ぶりは、近年かなり目立った現象となっています。
令和7年10月19日 中国9月貿易統計
おはようございます。台9月の中国貿易統計で、輸出は増加しました。
1. 9月輸出は増加
中国税関総署が13日発表した8月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+8.3%と、前月の+4.4%から加速。市場予想の+6.0%から上振れ。3月以来の高い伸び率。
製造業で米国以外への輸出が活発化。輸入も24年4月以来の高い伸び率。只、米国との貿易摩擦再燃により、雇用やデフレが悪化するとの懸念が浮上。
9月の輸入は+7.4%。8月の+1.3%と市場予想の+1.5%を何れも上回りました。只、アナリストは、コモディティの在庫積み上げが背景にあるとしています。
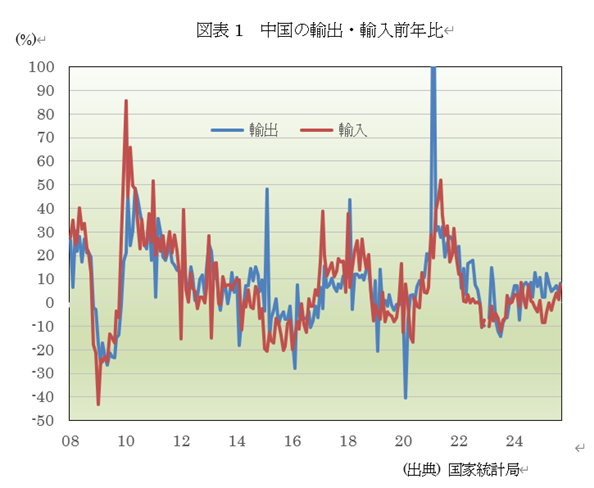
2. G20で中国の輸出規制に批判
一方、20か国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が米ワシントンで16日閉幕。2大経済大国である米国と中国の対立は、実態経済や金融市場を混乱に陥れる可能性があります。レアアースの輸出規制を行った中国に対して批判の目が向けられる一方、高関税政策で押収する米国にも是正を求める動きが見られました。
議長国の南アフリカは、「高い不確実性と複雑な課題に直民し乍らも、強靭性を示した」と、2025年上半期の世界経済を総括。不確実性を齎す要因として、米中の関係悪化を念頭に、「地政学や貿易の緊張、グローバルサプライチェーン(供給網)の混乱」などを挙げました。
令和7年10月18日 台湾TSMC業績好調
おはようございます。台湾TSMCの業績が好調でした。
1. 7-9月期決算が好調
半導体世界最大手の台湾積体製造(TSMC)が16日発表した2025年7-9月期決算では、売上高が前年同期比+30.3%の9899台湾ドル(約4兆9000億円)、純利益が+39.1%の」4523台湾ドル。いずれも四半期として最高。
増収易は7四半期連続。回路幅3-5ナノ(ナノは10億分の1)メートルの先端半導体の販売が好調。大口顧客の米エヌビディア向けなど、人口知能用の半導体が大きく寄与。

2. エヌビディアがオープンAIに出資
一方、半導体大手エヌビディアはオープンAIに最大1000憶ドル(約15兆円)を投資すると発表。この出征は、オープンAIが」次世代のAIモデルと開発するための計算資源を確保することを目指しています。両社は10ギガわっと規模のデータセンターを構築する計画。
これにより、オープンAIはエヌビディアの先端半導体を使用して、より高度なAIモデルと構築することが可能御なります。又、エヌビディアはオープンAIとの提携を通して、半導体の大口供給席を確保して、安定した需要を見込むことが可能となります。
令和7年10月16日 中国9月CPI
おはようございます。中国の9月CPIは、前年同月比下落しました。
1.
9月CPIが下落
中国国家統計局が15日発表した9月消費者物価指数(CPI)は、前年同月比▲0.3%。市場予想は▲0.2%。8月は▲0.4%でした。
PPIも下落しており、デフレ圧力の継続を示唆。長引く不動産市場の低迷や貿易摩擦により、消費者及び企業の信頼感が低下。
中国の輸出の伸び率は9月には回復したものの、米中の緊張の高まりが雇用や一段のデフレへの懸念を増幅させています。政策当局は、株式バブルの発生を警戒。ここまで大規模な景気刺激策を控えてきたものの、物価統計は更なる政策措置の必要性を促していると言えます。
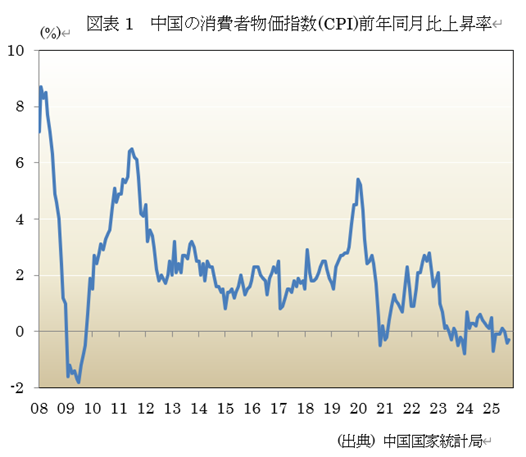
2. PPIはマイナス幅縮小
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、9月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.3%と、前月の▲2.9%からマイナス幅が縮小。市場予想に一致。価格競争を抑制する政府の取り組みなどにより、マイナス幅は8月から縮小して、過去7か月で最も小幅となりました。

キャピタル・エコノミクスの中国エコノミスト、ファン氏は「CPIとPPIは今年、来年ともにデフレ状態が続く」と予想。「当局はデフレをより深刻に受け止めつつあるものの、当局が提案している供給サイドの解決策が需要サイドの大規模な支援なしに成功するとは思えない」としました。
令和7年10月15日 トランプ氏が対中強硬姿勢を後退
おはようございます。トランプ氏が対中強硬姿勢を軟化させました。
1. トランプ氏が対中強硬姿勢を軟化
トランプ大統領は、同盟国敵対国問わず、1対1の取引に拘る姿勢を取ってきました。これは自ら誇るディールの象徴。只、対中国の強硬姿勢がぶれるなど、そのアプローチに陰りが見えます。
中国国務省は8日、レアアースに関する輸出規制を強化する方針を提示。これらの資源は米国のハイテク産業にとって不可欠。只、市場全体には大きな反応はありませんでした。トランプ氏はその後、10日に中国製品に対して大幅な関税引き上げを行うと警告。100%の追加関税を課すとしました。
只、同氏は12日、SNSで「米国は中国を助けたいのであって、傷つけたいのではない」としました。数日前中国に対して100%の関税を表明してから、一転して融和的姿勢を示唆。早くも方針転嫁する姿勢を示しています。
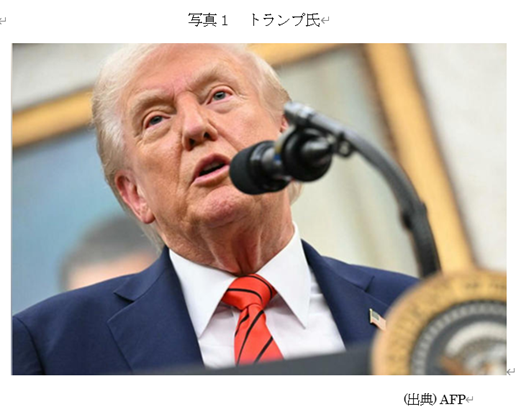
2. NY市場は反発
一方、13日のNY株式市場は反発。前週末比587ドル高で取引を終えました。前週末に強まって米中の貿易摩擦に対する警戒感が一服。主力株を買い戻す動きが強まりました。
トランプ大統領は12日「中国については心配いらない。全てうまくいっている」投稿。トランプ氏の発言を受けて、市場では買戻しの動きが広がりました。
令和7年10月14日 中国国慶節で住宅販売が回復
おはようございます。中国では国慶節により住宅販売が回復しました。
1. 24億人を超える人々が移動
中国政府は建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休で今年、移動した人数場過去最高となる、延べ24億人を超えたと発表。1日あたりの平均移動人数は、昨年比+6.2%。各地の観光客は旅行客で賑わい、中国メディアは消費が堅調であったと報じました。
国家移民権利局は9日、連休中の出入国者は延べ1634万3000人であったと発表。1日辺りの平均出入国者数は昨年比+11.5%。
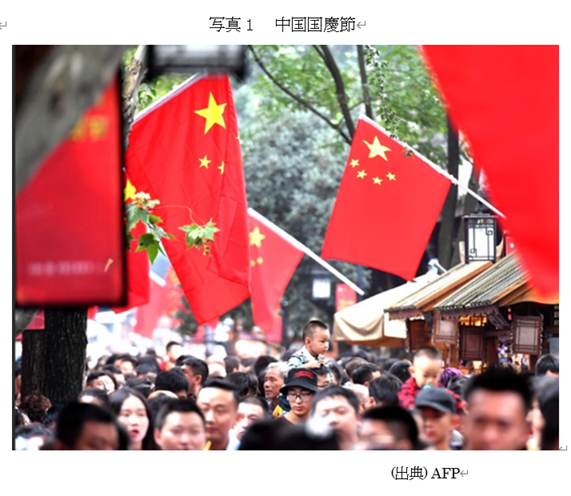
2. 住宅販売が回復
一方、今年の連休中、中国各地で新たな不動産支援策と販売促進イベントが相次いで実施され、住宅市場が活気を取り戻しています。いわゆる「銀十(10月の住宅販売シーズン)」に向けた動きが本格化。
湖北省の武漢市では9月30日、住宅ローンや公積み金に関する新たな制度を導入。2025年10月から翌年6月迄の間、売却中の住宅を保有個数に含めないなど、ローン審査を緩和。更に、中心部以外で初めて住宅を購入する人には融資額の1%(上限2万元、約42万8028円)を補助する制度を設けました。
令和7年10月12日 中国国慶節
おはようございます。中国の国慶節では延べ24億人を超える人々が移動しました。
1. 24億人を超える人々が移動
中国政府は建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休で今年、移動した人数場過去最高となる、延べ24億人を超えたと発表。
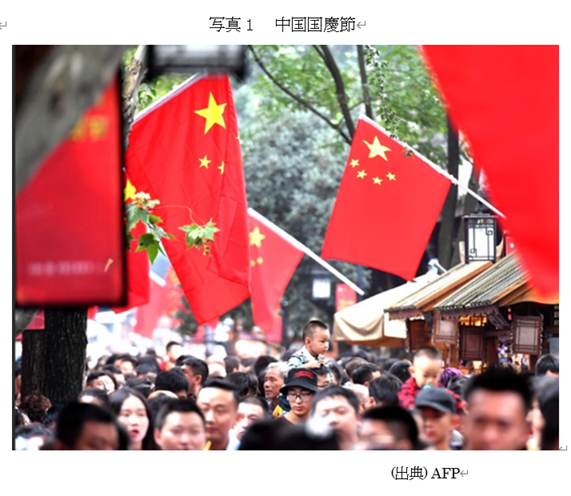
2.渡航先は日本が人気
一方、同国国家移民管理局は9日、連休中の出入国者数は延べ1634万3人であったと発表。1日あたりの平均出入国者数は例年より+11.5%。同国のコロナウィルス流終息後、欧州やアジアなどを対象として短期滞在ビザの免除措置を拡大。訪中した外国人は延べ75万千人と、昨年比+19.8%。
同国旅行大手の携程集団の9月下旬発表によると、連休中の海外旅行先の人気トップは日本で、都市別渡航先の主因は万博開催地の大阪。
令和7年10月8日 ベトナム7-9月期GDP
おはようございます。ベトナムの7-9月期GDPは、堅調でした。
1. インフレ率は減速
まず、インフレ率を見ておきましょう。ベトナム統計局が10月6日に発表した7月の消費者物価指数(CPI)上昇率は+3.38前月の+3.24%から加速(図表1参照)。

2. 7-9月のGDP成長率は+7.96%に減速
一方、ベトナム統計総局は10月6日に、7-9月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+7.96%になったと発表(図表2参照)。4-6月期の+6.93%から加速。16四半期連続の増加。
7-9月期には予想外の加速。製造業と輸出に支えられました。但し、9月二」超大型台風が上陸した影響で広範囲な被害が齎され、年末にかけては厳しいものになるとの警告が相次いでいます。

同国経済は今年に入って、底堅さを示していました。同国の陳首相が物流コストの削減やインフラの改善を公約する中、投資資金が流入。スマートフォンなどの電子機器や半導体の生産において、中国に代わる現実的な選択肢として同国が浮上。
令和7年10月7日 中国のアリババの株価上昇
おはようございます。中国のアリババの株価が上昇しています。
1. 時価総額増加率の上位を独占
まず、中国の人口知能関連株に世界の投資家の資金が集中。世界の主要500社の2025年7−9月期の時価総額増加の上位では、上位20社の半数を中国勢が占めました。海外投資家は、中国のAI企業への傾斜を強めています。
中国本土企業の関連株で構成するCSIのAIインデックスは、4-9月期に6割弱の上昇。米ナスダック総合指数の同1割上昇を上回りました。
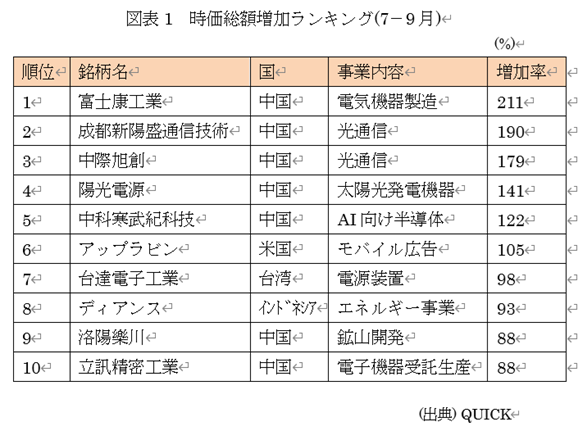
2.アリババの株価上昇
一方、AI関連で注目されている銘柄の1つがアリババ(BABA)。今年に入って2500億ドルきぼの株価上昇であり、この値上がりが更に続く可能性があります。
米株式市場では同社のADR(米国預託証券)が年初から倍以上となっています。中国政府が新たなテクノロジー環境における自立路線を取っており、投資家がこれに注目。

同国のAIを象徴する銘柄となったアリババの株価は猶、上場来高値を▲65%あまり下回っています。米国では、大手IT銘柄がこのところ高値を更新。
中国経済への慎重姿勢や激しい市場競争を背景として、先月にはアリババの空売りも急増。只、株価は依然として割安感があり、海外ファンドの投資比率が低水準にとどまっており、上値余地があるとの見方があります。
令和7年10月6日 EV大手BYDの販売台数が減速
おはようございます。EV大手BYDの販売台数が減速しました。
1. BDYが世界の販売台数首位へ
中国の電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)が、2025年のEV販売台数で、米テスラを抜いて初の世界首位となる見通し。車載電池の自社生産を背景とする低価格を武器として、ここ数年で急成長しており、ついに王座に就くこととなりました。
BYDが1日発表した1-9月期のEV阪大台数は前年同期比+37%の約161万台。これに対してテスラは、イーロン・マスクCEOの政治活動への反発などにより122万台にとどまっています。残り3カ月でBYDを抜くのは困難な状況。
2. 9月の販売台数は減少
一方、BYDの玄関販売台数が1年半強ぶりに減少。中国市場ではEV監視過酷な競争が繰り広げられており、同社のライバル企業は大幅な販売増加を記録。

同社の9月の出荷台数は前値脳月比▲5.5%の39万6270台と、同社にとって2024年2月以来の減少。旧正月による変動を除くと、出荷台数の減少は20年以来初。当時は新型コロナウィルス禍の影響でサプライチェーンと日常生活が混乱していました。
令和7年10月4日 中国AI企業に注目集まる
おはようございます。中国のAI企業に投資家の注目が集まっています。
1. 時価総額増加率の上位を独占
中国の人口知能関連株に世界の投資家の資金が集中。世界の主要500社の2025年7−9月期の時価総額増加の上位では、上位20社の半数を中国勢が占めました。海外投資家は、中国のAI企業への傾斜を強めています。
中国本土企業の関連株で構成するCSIのAIインデックスは、4-9月期に6割弱の上昇。米ナスダック総合指数の同1割上昇を上回りました。
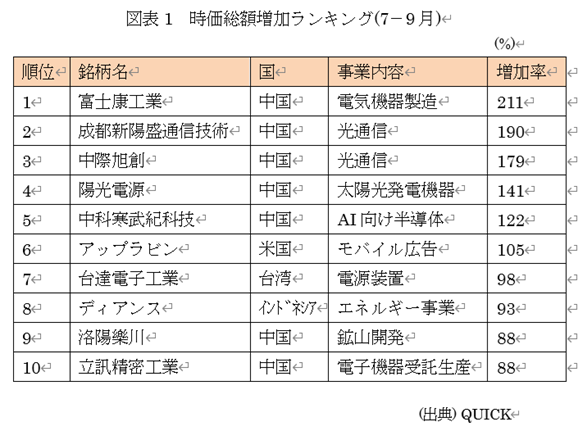
2. 中国で半導体後工程企業の大規模投資相次ぐ
一方、中国で半導体製造の後国定をになる天水華科技は9月22日、江蘇省南京市で集積回路のパッケージング・テスト吉建設プロジェクトの第2期着工式を行いました。先端設備を導入。国際的に先進レベルに達する生産ラインを構築することで、ストーレージ、高周波、コンピューティング、人口知能などに広く応用されるICチップの制作を目指しています。
中国の半導体分野の調査・研究を手掛ける緊急機関である芯思想研究院が纏めた2023年の半導体パッケージング・テスト工程企業の世界売上高ランキングでは、通富微電子が4位、天水華天科技が6位。両者が相次いで大規模投資を実施する背景として、中国で急速に進む自動車のスマート化などに伴う半導体の国内需要の高まりがあります。
令和7年10月2日 中国国慶節8連休開始
おはようございます。中国では、国慶節(建国記念日)と中秋節に伴う8連休が始まりました。
1. 延べ23億人が移動
中国では1日、国慶節と中秋節に伴8連休が開始。中国交通省は連休中に延べ23憶6000万人が好況交通や自家用車で出かけると予想。慮国会社によると、海外旅行目的地では日本が首位。
上海市の玄関口である鉄道の上海虹橋駅では、1日の午前中から、旅行鞄を持った人で混雑。今年は1日あたり平均2憶9500万人が移動すると予想されています。2024年の国慶節休暇と比較して+3%。連休中に移動する人のうち8割が自家用車で出かけると予想されています。

2. 海外渡航先にでは日本が人気
一方、旅行会社によると、海外の人気旅行先では1位日本。以下、韓国、タイ、マレーシア、シンガポールの順
中国人旅行客を呼び込もうと、優遇策を打ち出す国もあります。韓国政府は、中国人団体旅行客を対象としてビザ(査証)の免除措置を期間限定で再会しました。
令和7年10月1日 中国9月PMI
おはようございます。9月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 9月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が30日発表した9月の製造業購買担当者指数(PMI)49.8と、前月の49.4
から上昇。市場予想は49.6。
同指数は景況感の分かれ目となる50を6か月連増で下回りました。製造業者が内需押し上げに向けた追加刺激策を待って、米国との貿易摩擦を見極めようとする様子見をしていることを示唆。
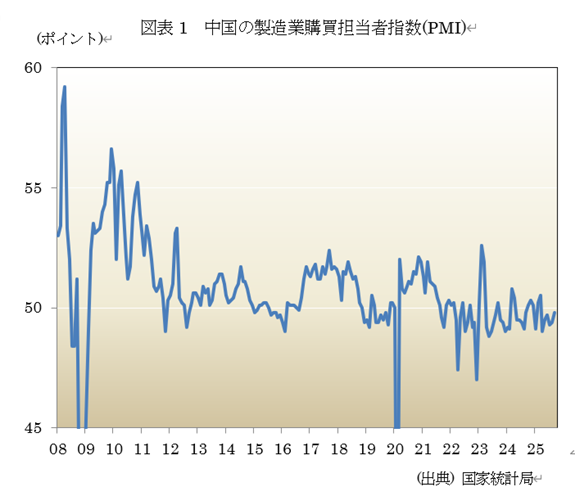
2. 非製造業PMIは低下
一方、同日に発表した9月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.0と、前月より50.3から低下。市場予想は50.2。デフレへの懸念が広がり、販売価格が下落。
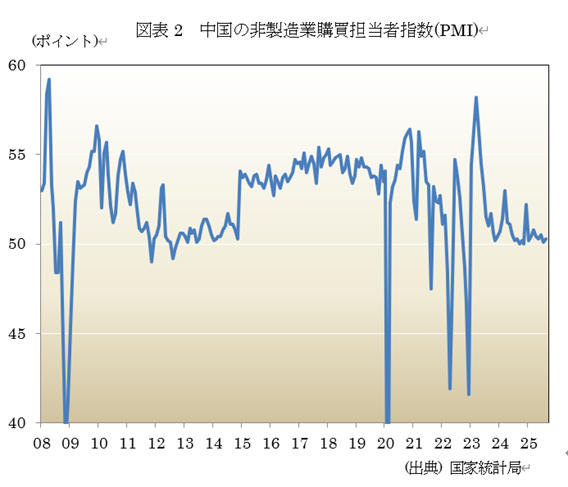
米国と中国は、今年11月を期限として間税措置などを巡る協議を継続。その行方が企業の景況感を左右することとなりそう。
令和7年9月30日 ブラジルで前大統領の恩赦求める動き
おはようございます。ブラジル中銀が政策金利を据え置きました。
1. 政策金利を据え置き
ブラジル中央銀行9月17日の金融政策委員会で、政策金利を15.00%に据え置くことを決定据え置きは市場予想通り。
同委員会は声明で、「外部環境は米国の経済政策の影響により深くジス性が高まっている。国内経済は活動の鈍化が予想通り進む一方、労働市場は堅調さを維持。インフレ率を目標に収束させるには、長期的な金融引き締め政策が必要ン」としました。
9月12日付中銀習字レポート「フォーカス」によると、2025年の拡大消費者物価指数(IPCA)上昇率読雄は4.83%で、中銀のインフレ目標値である+1.5〜4.5%を上回っています。
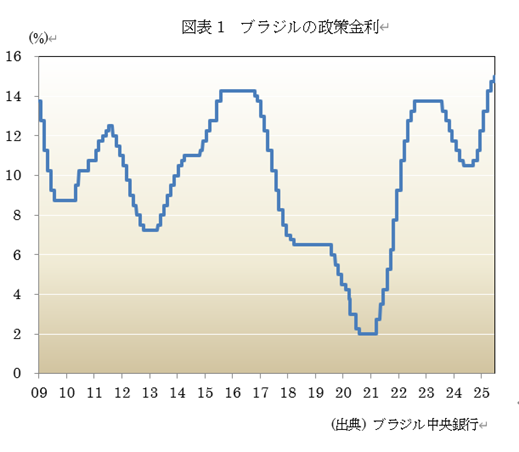
2. インフレ率が減速
一方、ブラジル地理統計院は9月10日に、8月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+5.13%と、前月の同+5.23%から伸び率はわずかに減速(図表2参照)。市場予想の+5.1%とほぼ一致。5.33%とほぼ一致。
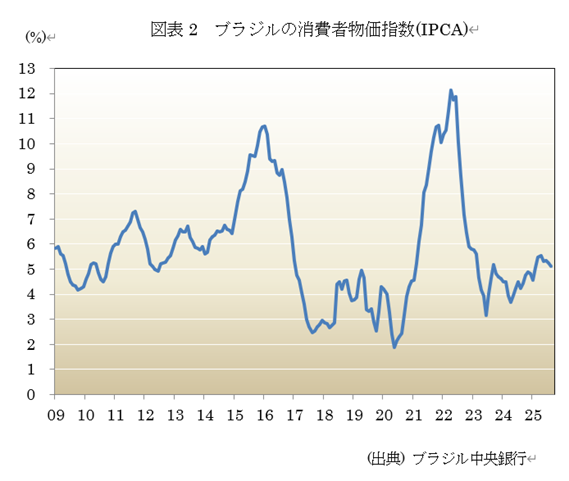
3. 4-6月期GDPは+2.2%に減速
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は9月2に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.2%であったと発表(図表3参照)。前期の同+2.9%から減速。高金利の影響により、投資の減速が目立っています。
18四半期連続のプラス成長となったものの、経済成長は減速傾向にあります。前期比は+0.4%。
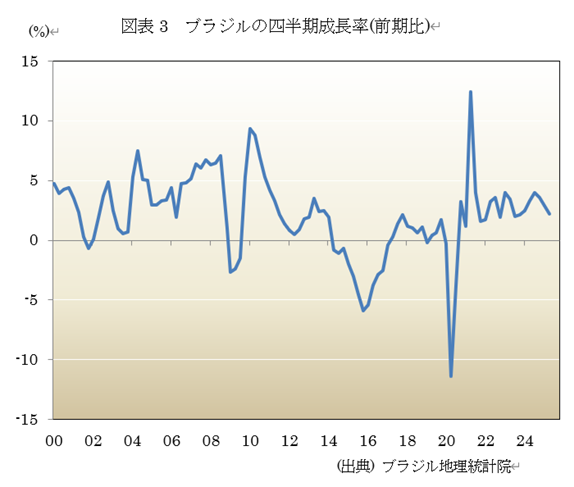
農牧畜業が前年同期比+10.1%。主力のトウモロコシが+19.9%、大豆が+14.2%。気候に恵まれ、収穫量は過去最高水準に達しました。
他の分野では、国内経済の過半を占めるサービス業が+2%、製造業は+1.1%。設備投資を中心とする固定資本形成は同+4.11%と堅調。前期比では▲2.2%。
4. 前大統領に有罪判決
一方、ブラジルの催告裁判所は9月11日、大統領選挙の結果を覆そうとして」クーデターを企てた罪などに問われていたジャイル・ボルソナロ前大統領(70)に有罪判決を下して、禁固27年3カ月の刑を言い渡しました。
最高裁の判事5人は、有罪判決からわずか数時間後に量刑を告げました。
5. ボルソナロ前大統領恩赦に反対する動き
他方、ブラジルでは21日、議員の面積特権を強化する議会の動きに反発して、国内各地で大規模な抗議デモが行われました。デモでは、クーデターを試みた罪で有罪判決を受けたジャイル・ボルソナロ前大統領らの恩赦に反対する声が上がりました。
11日に前大統領に禁固27年3カ月の有罪判決が言い渡された同国では、恩赦の是非を巡って国内の世論が二分。保守派が多数を占める議会に対しては、社会・経済的課題よりもみずからの利益を優先しているとの批判が上がっています。
抗議デモでは、リオデジャネイロを含む十数都市で行われました。デモ隊は、「恩赦はない」と叫び、街頭を行進。リオデジャネイロでは、カエターノ・ベローゾさんらが抗議集計に登場すると伝えられました。
令和7年9月28日 ロシア成長率予想下方修正
おはようございます。ロシア財務相は25年成長率予想を下方修正しました。
1. 4-6月期GDP成長率
ロシア連邦統計局は9月12日、4-6月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+1.1%になったと発表(速報値)。市場予想通り。1-3月期の+1.4%から減速。伸び率は9四半期連続でプラス成長。
ロシアの成長率は1996年から2025年で、1999年10-12月期に市場最高の+12.1%となり、2009年4-6月期には史上最低の▲11.2%とつけています。

2. インフレ率減速
国家統計局から9月10日発表された8月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+8.1%と、伸び率は前月の+8.8%から減速(図表2参照)。

3. 政策金利を据え置き
一方、ロシア中央銀行は9月12日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲1.0%ポイント引き下げ17.0%にすることを決定。引き下げは3会合連続。引き下げ幅は市場予想の▲2.0%を下回りました。
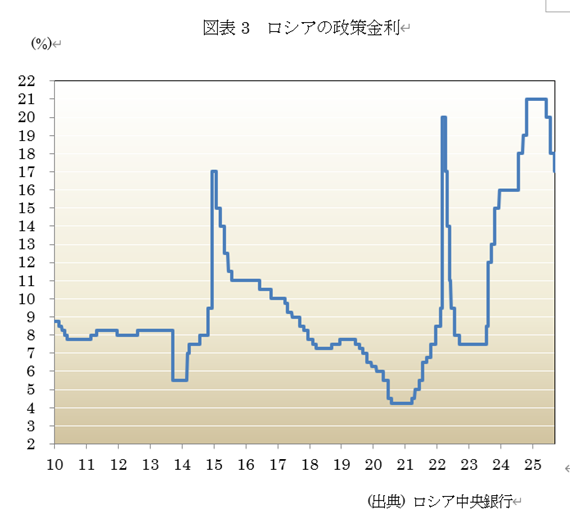
4. 25年成長率予想を+1.5%に下方修正
一方、ロシアのシルアノフ財務相は27日、2025年の国内総生産(GDP)の成長率について「少なくとも+1.5%以上」の見込みであると、プーチン大統領に政府会合で報告。政策金利の高止まりが経済活動の足枷となる中、ロシア政府による従来予想の+2.5%から下方修正。
ロシア経済は、202年のウクライナ侵攻により欧米から制裁を受けるものの、軍需が牽引してGDP成長率は23年が前年比+4.1%、24年は同+4.3%。先進7か国(G7)と比較して高い成長率を維持してきたものの、戦時下の疲弊が進んで、今年には減速する見通し。
ロシア中銀は高インフレ率対策で、昨年政策金利を史上最高の21%に引き上げ。今年6月に20%、7月には18%に引き下げたものの、高水準の金利が企業などの借り入れ、活動を阻害。戦争による労働力不足も相俟って、ロシア経済を圧迫。
令和7年9月27日 メキシコ中銀利下げ
おはようございます。メキシコの中銀が利下げしました。
1. CPI上昇率は加速
メキシコ国立地理情報研究所は9月9日に、メキシコの8月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.57%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+3.51%から加速。市場予想に一致。
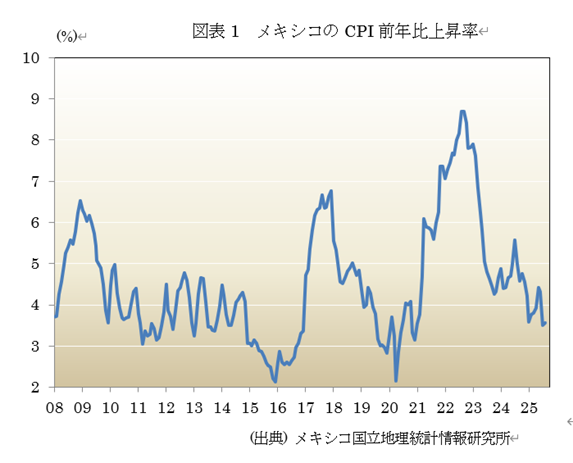
2. 4-6月期GDPは減速
メキシコ統計局は8月2日に、4-6月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前四半期比+0.6%になったとしました。速報値の+0.4%から小幅下方修正。2四半期連続のプラスは維持。猶、図表2は前年同期比速報値。
農畜産業などの第1次産業が▲2.4%と、下げ幅を拡大。製造業など第2次産業も+0.7%(速報値は+0.8%)に留まりました。金融サービス業など第3次産業は+0.8%(同+0.7%)と小幅上振れ。
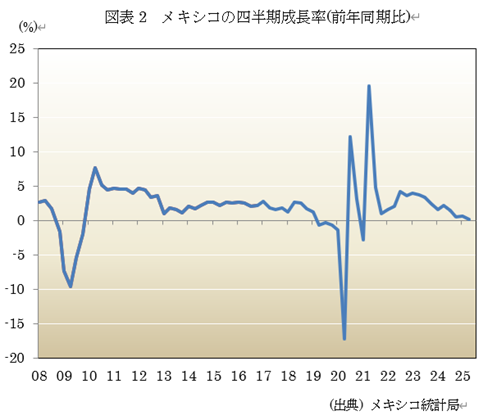
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は9月25の金融政策決定会合で、政策金利を▲02.5%ポイント引き下げて7.5%にすることを決定(図表3参照)。利下げは10回連続。足下で通貨ペソが1ドル=18ペソ台中盤と、年前半の安値から+10%近い水準で安定。インフレ率が安定したとみて緩和サイクルを継続。
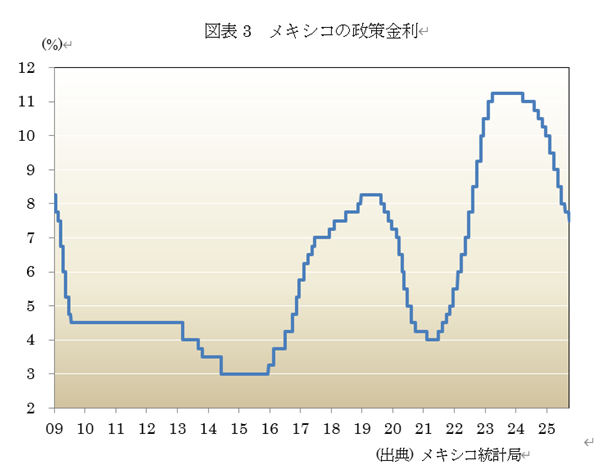
同行は同日の声明で、同行が「弱い成長力」と世界の変動する貿易政策を勘案して、今後の会合における更なる緩和の余地を残しました。水曜日のデータでは、コア・インフレ率は年率で9月までの半年で+4.26%であることを示唆。
令和7年9月25日 OECD世界経済見通し上方修正
おはようございます。OECDが世界経済見通しを上方修正しました。
1. 25年の世界経済見通しを+0.3%上方修正
経済協力開発機構(OECD)は23日、2025年の世界経済見通しが+3.2%になるとしました。前回6月の予測から+0.3%ポイントの上方修正。米国のAI(人口知能)開発関連投資や中国の財政出動が寄与。米関税措置に対しては、発動前に貿易、生産で駆け込み需要があったものの、負の影響はまだ完全には表れていないとしました。
今後は、トランプ関税がリスク要因として残るとしています。米国お実効関税率は8月末時点で19.5%と、1933年以来の水準。政策の不確実性も高く、投資や貿易を弱まる効果が見込まれます。世界の成長率は24年+3.3%に対して、25年+3.2%、26年2.9%に鈍化すると予想。
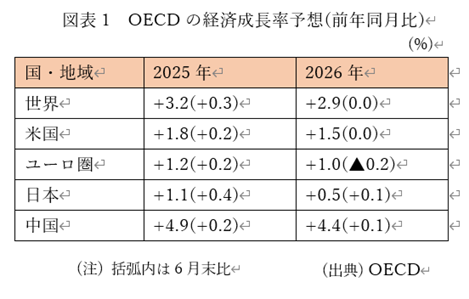
2. 国・地域別見通し
25年の成長率予想を国・地域別に見ると、米国は+1.8%で+0.2%ポイントの上方修正。24年の+2.8%からは鈍化。高関税や移民の減少が要因。失業率上昇など、景気減速の兆しが既にあります。
ユーロ圏は+0.2%ポインとの+1.2%。足下の政策金利は+2%と、23-24年のピークから半減。利下げを継続したことにより、貿易摩擦の影響が幾分和らいでいます。
新興国経済も6月時点での想定以上の堅調さを維持。中国派+0.2%ポイントの上方修正で+4.9%と、24年の+5%からほぼ横這い。26年には米国の関税引き上げ前の輸出の駆け込み需要の反動や財政支出縮小で+4.4%に減速するとしました。
令和7年9月22日 アルゼンチン4-6月期GDP
おはようございます。アルゼンチンの4-6月期GDP成長率は、前年同月比でプラスを維持しました。
1. 8月CPI上昇率が鈍化
アルゼンチン統計局の9月10日発表によると、8月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+33.6%(図表1参照)。前月の+36.6%から減速。市場予想の+33.6%にほぼ一致。
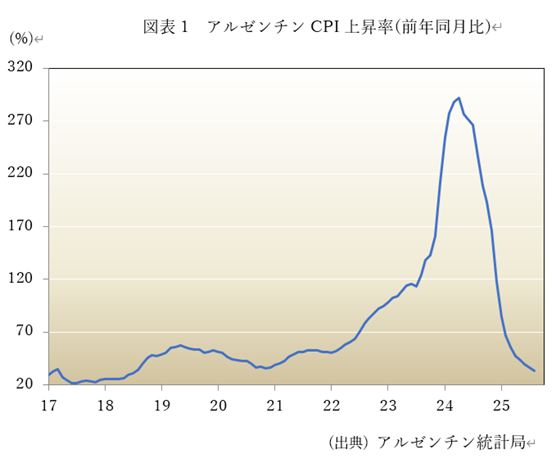
2. 政策金利を引き下げ
アルゼンチンの中央銀行は1月31日、インフレ率の低下を受けて、政策金利を▲3%引き下げて29%にすると発表。これは、ミレイ大統領の2023年12月の就任以来9回目の利下げ。これにより、借入コストは2020年10月以来最低の水準となりました。
2024年12月には、インフレ率は8カ月連続で低下して+117.8%となり、2023年7月以来の水準となり、11月の+166%から鈍化。
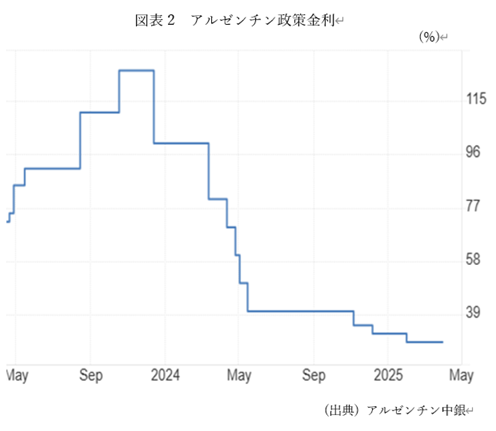
前月比上昇率は+2.7%と、3カ月連続で+3%を下回りました。利下げは、政府の2月1日開始の月次通貨低下率の▲2%から▲1%への圧縮と重なりました。
3. 4-6月期GDP
アルゼンチン統計局の9月10日発表によると、4-6月期のGDP成長率は前年同月比+6.3%。前期の+5.8%から加速。市場予想の+6.5%からは下振れ。
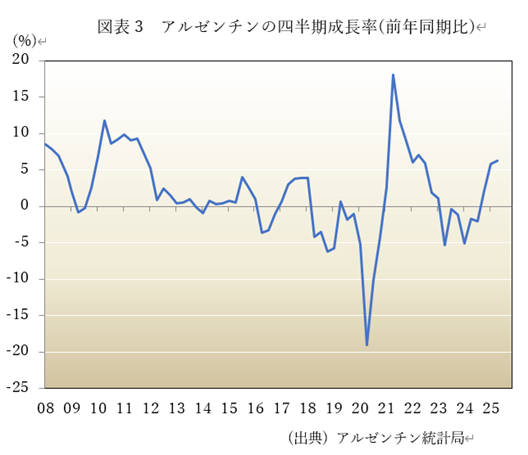
前年同月比では2022年4-6月期以来の高い成長率であり、農業部門(+4.8%、前期は+3.7%)が牽引。製造業が+6.9%(前期は+0.7%)、卸・小売りは+10.3%(同+2.5%)、輸送・通信は+1.4%(同+2%)、金融仲介は+26.7%(同+8.4%)など。好況事業は▲1.1%(同▲1%)。
同国では2023年12月に発足したミレイ政権下で、急進的な緊縮策を進めてきました。国内経済は一時大幅に冷え込んだものの、24年10-12月期には前年同期比でプラス成長に転じていました。
令和7年9月21日 ブラジル中銀金利据え置き
おはようございます。ブラジル中銀が政策金利を据え置きました。
1. 政策金利を据え置き
ブラジル中央銀行9月17日の金融政策委員会で、政策金利を15.00%に据え置くことを決定据え置きは市場予想通り。
同委員会は声明で、「外部環境は米国の経済政策の影響により深くジス性が高まっている。国内経済は活動の鈍化が予想通り進む一方、労働市場は堅調さを維持。インフレ率を目標に収束させるには、長期的な金融引き締め政策が必要ン」としました。
9月12日付中銀習字レポート「フォーカス」によると、2025年の拡大消費者物価指数(IPCA)上昇率読雄は4.83%で、中銀のインフレ目標値である+1.5〜4.5%を上回っています。
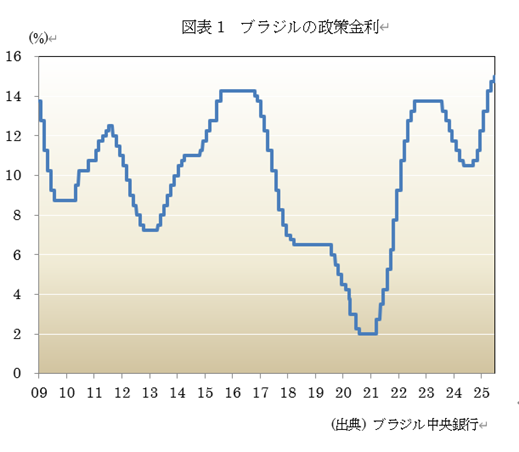
2. インフレ率が減速
一方、ブラジル地理統計院は9月10日に、8月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+5.13%と、前月の同+5.23%から伸び率はわずかに減速(図表2参照)。市場予想の+5.1%とほぼ一致。5.33%とほぼ一致。
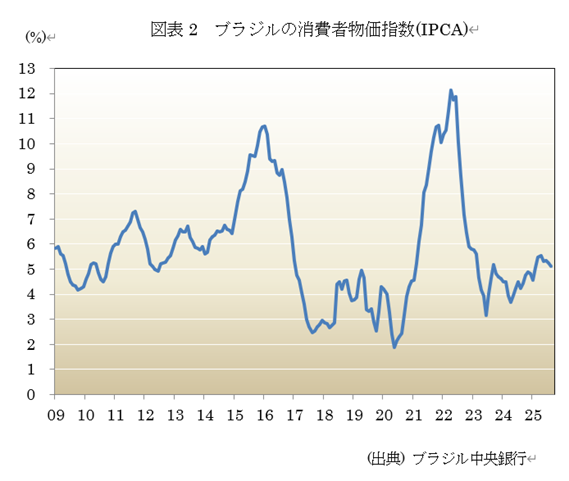
3. 4-6月期GDPは+2.2%に減速
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は9月2に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.2%であったと発表(図表3参照)。前期の同+2.9%から減速。高金利の影響により、投資の減速が目立っています。
18四半期連続のプラス成長となったものの、経済成長は減速傾向にあります。前期比は+0.4%。
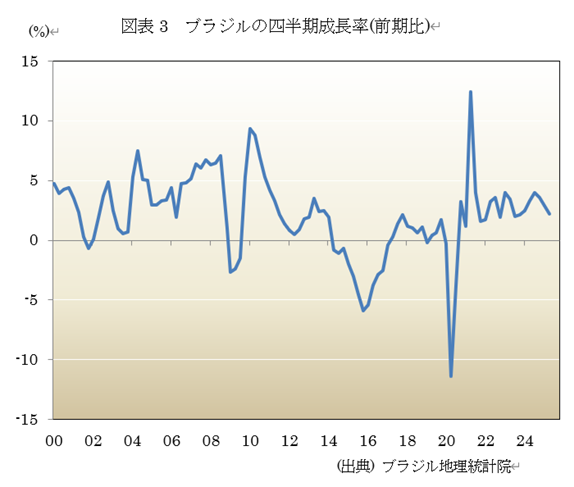
農牧畜業が前年同期比+10.1%。主力のトウモロコシが+19.9%、大豆が+14.2%。気候に恵まれ、収穫量は過去最高水準に達しました。
他の分野では、国内経済の過半を占めるサービス業が+2%、製造業は+1.1%。設備投資を中心とする固定資本形成は同+4.11%と堅調。前期比では▲2.2%。
令和7年9月20日 インドネシア中銀利下げ
おはようございます。インドネシア中銀は利下げしました。
1. 8月CPI上昇率は減速
インドネシア中央統計局は9月1日に、8月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.31%になったと発表(図表1参照)。前月の+2.37%から減速。
致。

2. 4政策金利を引下げ
一方、インドネシア中央銀行は9月17日の理事会で、政策金利であるBIレートを▲0.25%ポイント引き下げて4.75%にすることを決定。利下げは市場の予想外。利下げは昨年9月に金融緩和サイクルと開始して以来6回目。
同行総裁は、緩和サイクルでルピアの安定維持と成長支援の必要性のバランスを取らなければならなかったとしました。
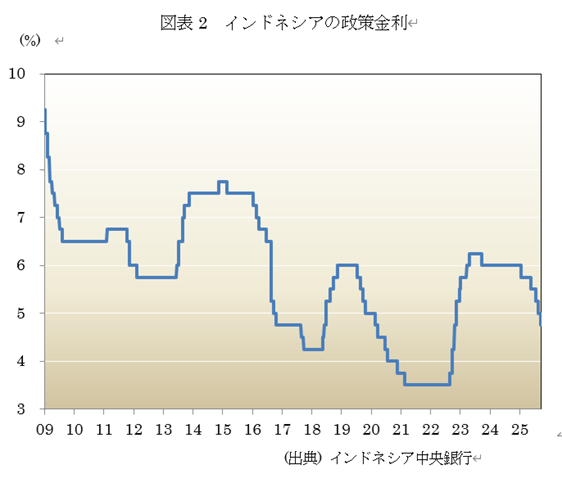
3. 4-6期GDP加速
インドネシア中央統計局(BPS)は8月5日に、同国の4-6月期GDP成長率が、前年同期比+5.12%になったと発表。前期の同+4.87%から減速。市場予想の4.8%から上振れ。前期比では+4.04%。市場予想は+3.69%。
今回の結果は、個人消費の半分以上を占める個人消費の減速を見込んでいた市場予想に反するもの。最近の利下げや政府による景気刺激策、安定した食品価格に加えて、イスラム教のラマダン(断食月)明け大祭や休暇シーズン中の支出増加が国内需要を下支えした可能性があります。
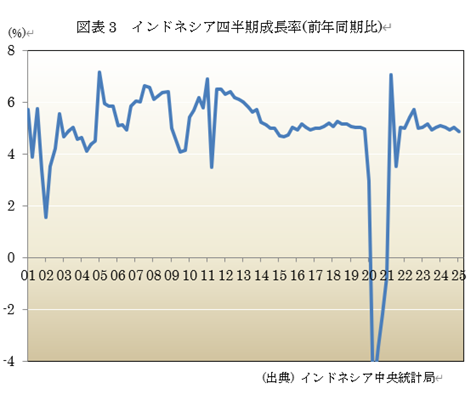
個人消費は+4.97%、総固定資本形成は+6.99%。輸出は+10.67%と、米国の関税発動んを前に前倒し出荷が引き続き寄与。米国はインドネシアに対する関税率を当初の32%から19%に引下げ。
只、貿易戦争の激化や世界経済の減速により、今後は内需や貿易の勢いが鈍化するリスクもあります。対米輸出にかかる関税の引き上げは週内に発効予定。
令和7年9月16日 ブラジル・ボルソラノ前大統領有罪
おはようございます。ブラジル最高裁は11日、ボルソラノ大統領に対して有罪判決を下しました。
禁固27年3月の有罪判決
ブラジス最高裁は11日、2022年の大統領選後にクーデターを計画したとして有罪となったボルソラノ前大統領(70)に、金庫27年3月の刑を言い渡しました。
民主主義と攻撃した罪で有罪判決を受けるのは、ブラジル大統領経験者として初。
判事5人のうち4人が武装犯罪組織への参加、民主主義を暴力的に破壊しようとしたこと、クーデターを組織したこと、政府の財産や保護された文化財を損壊したこととの5つの罪で同氏に有罪判決を下しました。

2. 8月新築住宅価格
一方、中国の8月の主要70都市の住宅価格が発表されました。前年比で9年余りぶりの大幅な落ち込み。政府は一連の支援策を導入しているもの、不動産部門の実質的な回復を促すにはいったっていません。
国家統計局のデータに基づく計算では、新築住宅価格は前年同月比▲5.3%下落。下落幅は7月の▲4.9%から拡大。2015年5月以来の大きさ。
前月比では▲0.7%。下落幅は7月と同じ。14か月連続の下落。
不動産仲介を手掛ける中原地産のアナリスト、張氏は、住宅購入者の情や所得、信頼感が回復するには暫く時間がかかるため、不動産市場は依然として底入れの課程にあると指摘。「市場はより強力な政策を期待している」としました。
令和7年9月14日 中国8月CPI
おはようございます。中国の8月CPIは、前年同月比下落に転じました。
1. 8月CPIが下落
中国国家統計局が10日発表した8月消費者物価指数(CPI)は、前年同月比▲0.4%。市場予想は▲0.2%。7月は横這いでした。
食品価格は前年同月比▲4.3%。7月は▲1.6%。変動の激しい食品と燃料価格を除くコアインフレ率は同+0.9%と、7月の同+0.8%から加速。2年半ぶりの伸び率。

2. PPIはマイナス幅縮小
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、87月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.9%と、前月の▲3.6%からマイナス幅が縮小。市場予想に一致。

当局はこのところ、主要産業に対して過当競争の縮小を求めています。自動車産業では長年の価格競争が大手自動車メーカーの財務諸表に悪営業を及ぼしています。
同国では生産者物価のデフレが3年近く継続。消費者信頼感指数の低迷や米国の関税政策による不透明感の増大なども、製造業者の収益を圧迫。
令和7年9月13日 トルコ中銀が利下げ
おはようございます。トルコ中銀が利下げしました。
1. 7月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が8月4日に発表した7月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+33.52%と、前月の+35.05%から減速。市場予想の+34.05%から下振れ。

2. 政策金利を引下げ
一方、トルコ中央銀行は8月1日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を▲2.5%ポイント引き下げ、40.5%にすることを決定(図表2参照)。利下げは市場の予想通り。利下げは市場の予想通り。只、利下げペースの減速を見込んでいた市場予想に反して、中銀は積極的な利下げ姿勢を維持。
カラハン総裁は総合インフレ率だけでなく、データの詳細な分析にも目を向ける必要があると指摘。需要主導による価格圧力は依然として出るれ傾向み一致しているとしました。
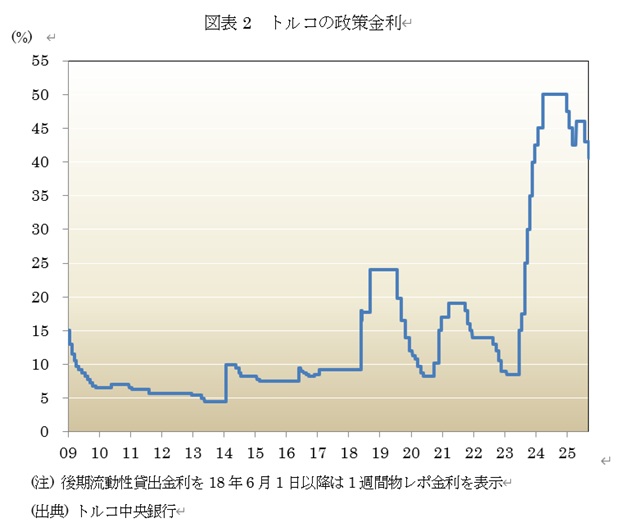
3. 4-6月期成長率+4.8%
他方、トルコ統計局が9月1日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.8%と、前期の+2.3%(改定値)から加速。市場予想の+4.1%から上振れ。
景気拡大は予想を上回る家計消費+5.1%(前期は+1.6%)、投資の加速+8.8%(同+1.8%)、輸出の増加+1.7%(同+0.1%)、輸入+8.8%(同+2.7%)を反映。一方、政府支出は▲5.2%(同+1.9%)と急落。
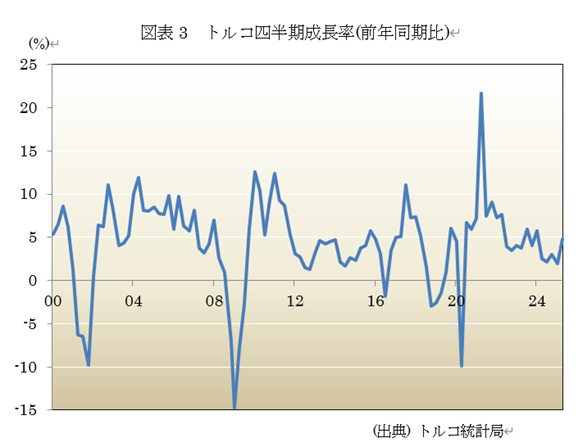
生産面では、建設+10.9%(同+8.6%)、情報・通信+7.1%(+5.7%)、不動産+2.6%(同+2.0%)、製造業+6.1%(▲1.7%)など。
令和7年9月11日 アルゼンチン地方選で与党惨敗
おはようございます。アルゼンチンの地方選で与党が惨敗しました。
1. 7月CPI上昇率が鈍化
アルゼンチン統計局の8月13日発表によると、7月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+36.6%(図表1参照)。前月の+39.4%から減速。
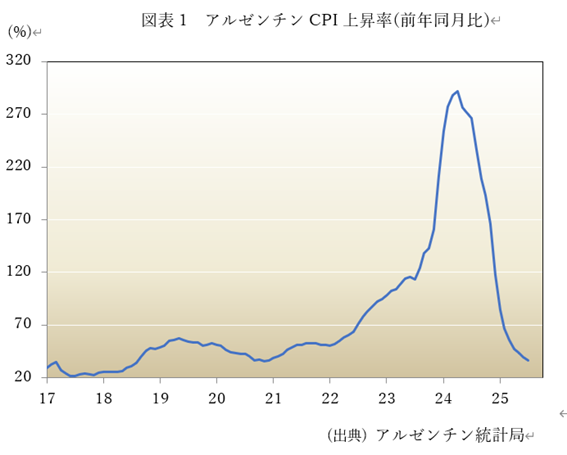
2. 政策金利を引き下げ
アルゼンチンの中央銀行は1月31日、インフレ率の低下を受けて、政策金利を▲3%引き下げて29%にすると発表。これは、ミレイ大統領の2023年12月の就任以来9回目の利下げ。これにより、借入コストは2020年10月以来最低の水準となりました。
2024年12月には、インフレ率は8カ月連続で低下して+117.8%となり、2023年7月以来の水準となり、11月の+166%から鈍化。
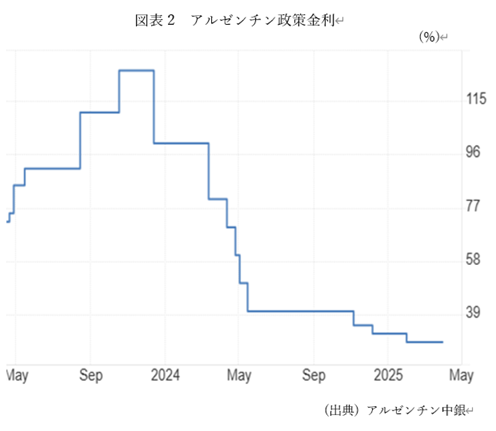
2. 政策金利を引き下げ
アルゼンチンの中央銀行は1月31日、インフレ率の低下を受けて、政策金利を▲3%引き下げて29%にすると発表。これは、ミレイ大統領の2023年12月の就任以来9回目の利下げ。これにより、借入コストは2020年10月以来最低の水準となりました。
2024年12月には、インフレ率は8カ月連続で低下して+117.8%となり、2023年7月以来の水準となり、11月の+166%から鈍化。
3. 地方選で与党が惨敗
7日に実施された同国のブエノスアイレス州議会選挙で、与党「自由の前進」は最大野党「正義党」に惨敗。10月の中間選挙を前に、与党の苦戦が一段と鮮明となり、金融市場ではミレイ改革の行方に対する懸念が広がり、混乱が生じています。
同政権は発足以来、財政健全化やインフレ抑制で成果を上げました。貧困率が低下し、景気も持ち直しの傾向。経済の立て直しは進展。只、
政権が主導する公的部門縮小は貧困層に打撃を与えるなど、正義党の支持基盤を刺激。更に、足下ではミレイ氏の妹カリーナ氏の汚職疑惑が噴出。政権党にとって逆風となる中、苦戦を強いられました。
ブエノスアイレス州は伝統的に正義党の牙城とされる土地ではありますが、最大の票田である同州での敗北は、今後の改革実現の障害となる可能性があります。政府と議会は対立の様相を強めており、民主主義国家において「破綻国」の立て直しが極めて困難であることを示唆しています。
令和7年9月10日 中国8月貿易統計
おはようございます。7月の中国貿易統計で、輸出は増加しました。
1. 8月輸出は減速
中国税関総署が8日発表した8月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+4.4%と、前月の+7.2%から減速。市場予想の+5.0%から下振れ。輸入は+1.3%と、前月の+4.1%から減速。市場予想の+4.1%から下振れ。
米国との関税を巡る休戦による一時的な押し上げ効果が薄れました。只、米国以外からの需要は安心材料となりました。
エコにミスと・インテリジェンス・ユニットのシニアエコノミストのティエンチェン氏は「数字は依然としてまずまずで、輸出の底堅さは我々の予想より確実に長く続いて」としました。
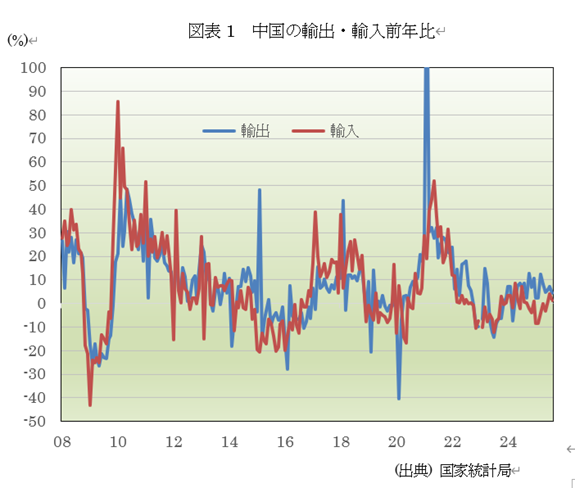
2. 米中は一時休戦状態
米中両国は8月11日、関税を巡る休戦を更に90日間延長することで合意。米国が中国製品に課す関税率は30%、中国が米国に課す関税は10%で維持。只、両国は現在の九千機関後の道筋を描くのに苦労している模様。
ユーラシア・グループの中国担当ディレクター、ダン・ワン氏は「輸出は今のところ順調に持ちこたえている」としました。
令和7年9月8日 文京区に中国人が移住
おはようございます。文京区に中国人が多数移住しています。
1. 文京区で外国籍の子供が増加
東京文京区では、「3S1K」と呼ばれる小学校をはじめとして、外国籍の小学生が増加しています。これらの地区は中学受験をする子供の割合が高いことで知られています。中でも目立つのが中国籍の子供。
文京区では中国からの移住者が増加しており、「インターネットで教育の雰囲気が良いと聞いて、子供のために引っ越しました」といった中国人の両親が増加。「3S1K」と呼ばれる区立小学校では、このようなケースが増加。千駄木、窪町、お茶の水などで増加。
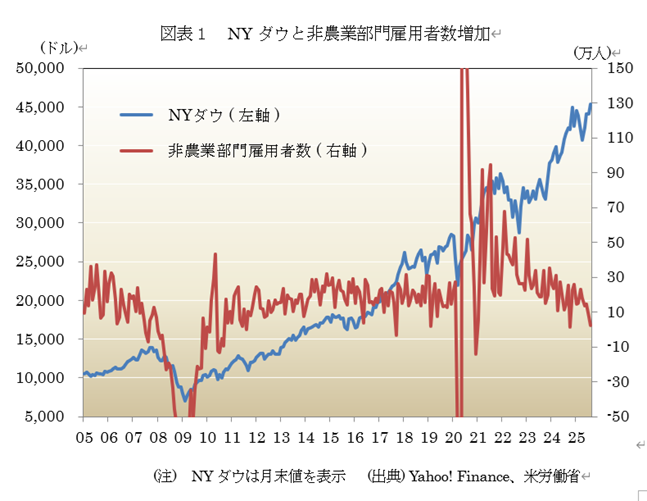
2. 晴海フラッグに中国人集結
一方、東京都の一大プロジェクトとして、東京2020オリンピック選手村を改修して売り出されたマンション群「晴美フラッグ」。2024年1月に入居が開始されました。一帯には中国人が多く集まり近隣との間で軋轢が生じています。
付近では違法の民泊が横行。それを阻止しようとする地元住民が「禁止」の張り紙を張るなどの事態になっています。
違法民泊の運営は、中国人が行っている模様。並び立つマンションの玄関には高級車が止まり、中国人が荷物を積んだり卸したりする様子が見られます。
完全に中国人のコミュニティを形成。周辺との摩擦が高まっており、池袋などでも、同様のケースが見られます。
令和7年9月8日 米8月雇用統計
おはようございます。米国の8月の雇用統計で、雇用者数が+13.9万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が8月の雇用統計を5日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+2.2万人。市場予想の+7.5万人にから下振れ。失業率は4.3%と、前月の4.2%から上昇して、約4年振りの高水準。雇用の減速が鮮明となり、米連邦準備理事会(FRB)による月内の利下げはほぼ確実とみられます。
又、6月の公用車数は▲1.3万人と、当初の+1.4万人から下方収支絵され、2020年12月以来の減少。
7月分は+7.3万人から+7.9万人に上方修正されました。
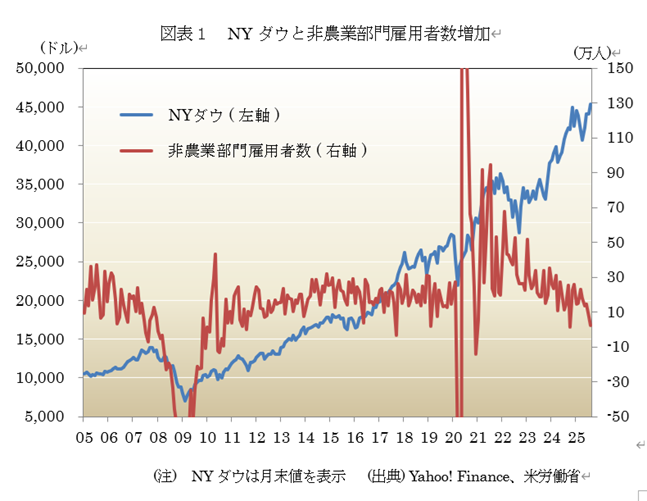
2. FRBは9月に利下げへ
一方、FRBのパウエル議長は22日の「ジャクソンホール会議」での講演で、雇用への「下振れリスクの高まり」に言及。9月の公開市場委員会(FOMC)で利下げに着手する可能性に言及。
8月の効用統計で、非農業部門雇用者数の伸びが大幅に鈍化し、失業率も上昇。この結果を受けて、次回FOMCでの利下げはほぼ確実とみられます。
令和7年9月6日 ブラジル4-6月期GDP
おはようございます。ブラジル4-6月期GDP成長率は鈍化しました。
1. 政策金利を引き上げ
ブラジル中央銀行6月18日の金融政策委員会で、政策金利を+0.25%ポイント引き上げて、15.00%にすることを決定。決定は全会一致。利上げは7会合連続で、金利は2006年7月以来の高水準に達しました。
市場予想は概ね金利据え置きでした。他方、金利先物では据え置きと利上げの確率はほぼ語五分五別でした。
中銀は声明で、現在の金利を維持する方針を示唆。「委員会は利上げサイクルの中断を見込んでおり、その累積的な影響を検証して、現在の金利水準が非常に長期にわたって安定すると仮定した場合、インフレ率が目標に収束するのに十分かどうかを評価する」としました。
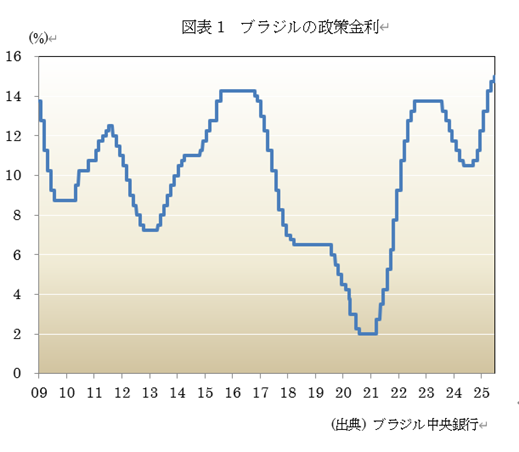
2. インフレ率が減速
一方、ブラジル地理統計院は8月12日に、7月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+5.23%と、前月の同+5.35%から伸び率はわずかに減速(図表2参照)。市場予想の+5.33%とほぼ一致。
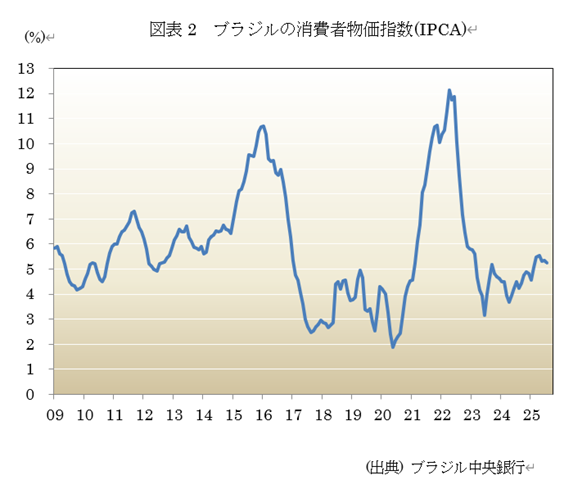
3. 4-6月期GDPは+2.2%に減速
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は9月2に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.2%であったと発表(図表3参照)。前期の同+2.9%から減速。高金利の影響により、投資の減速が目立っています。
18四半期連続のプラス成長となったものの、経済成長は減速傾向にあります。前期比は+0.4%。
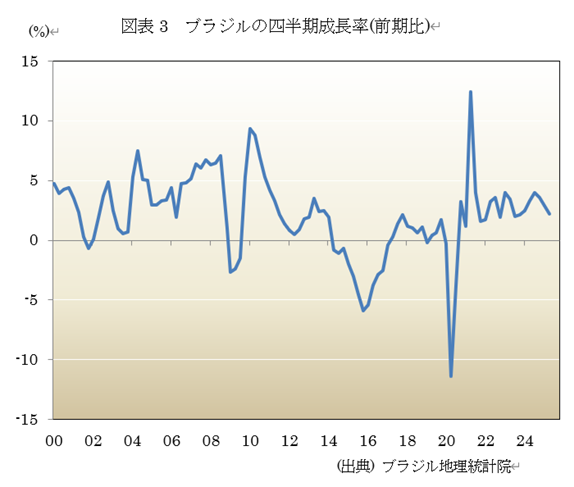
農牧畜業が前年同期比+10.1%。主力のトウモロコシが+19.9%、大豆が+14.2%。気候に恵まれ、収穫量は過去最高水準に達しました。
他の分野では、国内経済の過半を占めるサービス業が+2%、製造業は+1.1%。設備投資を中心とする固定資本形成は同+4.11%と堅調。前期比では▲2.2%。
令和7年9月3日 トルコ4-6月期GDP加速
おはようございます。トルコ4-6月期GDPは加速しました。
1. 7月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が8月4日に発表した7月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+33.52%と、前月の+35.05%から減速。市場予想の+34.05%から下振れ。

2. 政策金利を引下げ
一方、トルコ中央銀行は7月24日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を▲3.0%ポイント引き下げ、43.0%にすることを決定(図表2参照)。利下げは市場の予想通り。利下げは市場の予想通り。利下げ幅は、市場予想の▲2.5%を上回りました。
地政学的リスクによりリラが急落した、4月における+3.5%の大幅利上げをほぼ帳消しとしました。
同行は又、基調となるインフレ率の鈍化傾向は変わらないとしました。只、借入コストの高さは、需要へのディスインフレ効果となっているとしました。
同行は更に、景気の不透明感の高まり、世界貿易における保護主義の高まりは成長へのダウンサイドリスクとなっており、借入コストの低下に繋がっているとしました。
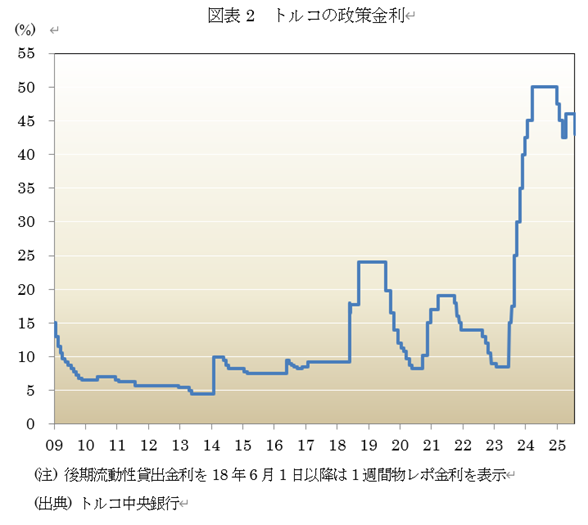
3. 4-6月期成長率+4.8%
他方、トルコ統計局が9月1日に発表した4-6月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+4.8%と、前期の+2.3%(改定値)から加速。市場予想の+4.1%から上振れ。
景気拡大は予想を上回る家計消費+5.1%(前期は+1.6%)、投資の加速+8.8%(同+1.8%)、輸出の増加+1.7%(同+0.1%)、輸入+8.8%(同+2.7%)を反映。一方、政府支出は▲5.2%(同+1.9%)と急落。
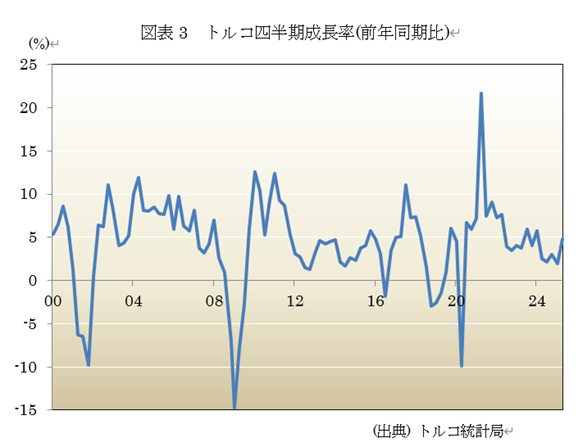
生産面では、建設+10.9%(同+8.6%)、情報・通信+7.1%(+5.7%)、不動産+2.6%(同+2.0%)、製造業+6.1%(▲1.7%)など。
令和7年9月2日 中国8月PMI
おはようございます。8月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 8月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が31日発表した8月の製造業購買担当者指数(PMI)49.4と、前月の49.3からわずかに上昇。市場予想は49.5。景気の拡大の分かれ目となる50を引き続き割り込みました。
同国経済は、米関税措置を受けた輸出の先細り、不動産セクターの低迷、雇用不安の高まり、地方政府の巨額債務、以上気象といった問題に直面。エコノミストは、約+5%という野心的な今年の成長目標が、このような圧力で達成できない恐れがあると指摘。
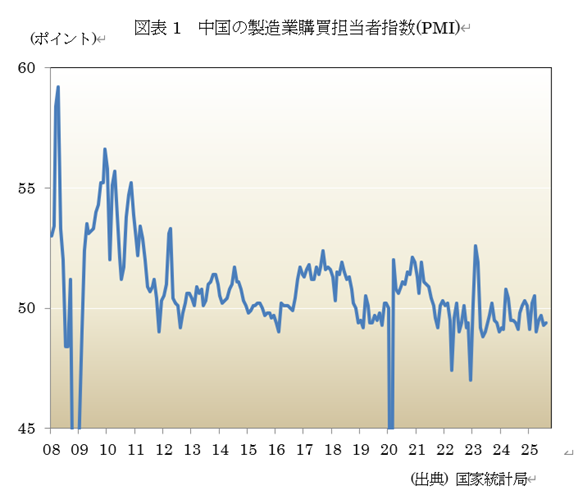
2. 非製造業PMIは上昇
一方、同日に発表した8月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.3と、前月より50.1から上昇。市場予想は50.2。
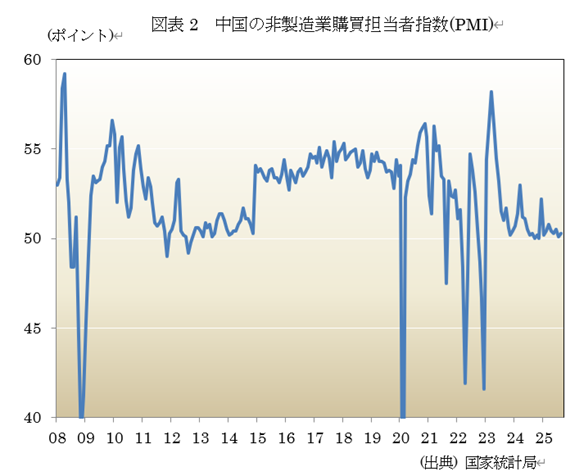
保銀投資のチーフエコノミスト、張智威氏は、同国経済の勢いは内需の持続的な弱さと不動産市場の冷え込みによって、第3四半期に鈍化したと指摘。「年内のマクロ見通しは、輸出がどれだけ好調を維持できるか、それと財政政策による支援が第4四半期に拡大するかどうかに左右される」としました。
令和7年9月1日 インド4-6月期成長率
おはようございます。イインド4-6月期GDP成長率は、加速しました。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が8月12日発表した7月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+1.55%(図表1参照)。前月の+2.1%から減速。市場予想の+1.76%から下振れ。
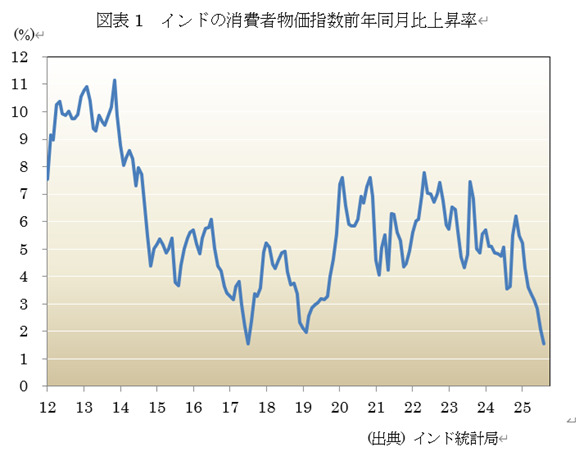
2. 4-6月期成長率+7.8%に加速
続いて、インド統計局が29日に発表した4-6月期成長率は、前年同期比+7.8%(図表2参照)。前期の同+7.4%から伸び率が加速。5四半期ぶりの高さ。市場予想の+6.7%から上振れ。只、エコノミストからは、米国による追加関税の引き上げがインド経済を圧迫することになるとの懸念が出ています。
同国のGDPの57程度を占める個人消費は25年4-6月期には+7.0%と、前期の同+6%から加速。前期▲1.8%であった政府消費支出は+7.4%、資本支出も+7.8%。只、4月以降の米関税引き上げによる不透明感で、民間企業に投資を控える動きの出ている模様。製造は+7.7%、建設は+7.6%の伸び。
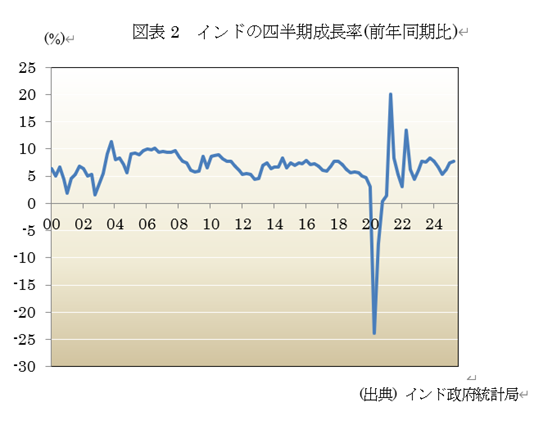
3. 政策金利を維持
他方、インド準備銀行(中央銀行)は8月4-6日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを5.5%に据え置くことを決定。金融姿勢は「中立」を維持。据え置きは2025年で初めてで、直前の6月会合では、市場予想を上回る▲0.5%ポイントの大幅利下げを実施。
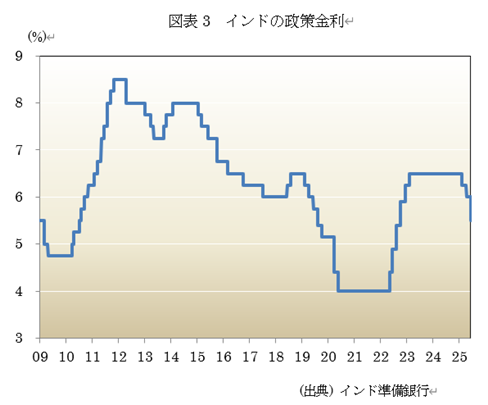
中銀は声明で、6月のCPI上昇率が、前年同月比+2.1%と、77箇月振りの低水準を記録したことを指摘。食品価格の下落が全体の物価を押し下げたものの、コアインフレ率は+4%前後で推移。2025年度第4四半期以降は再び+4%超に上昇する見通しとしました。
令和7年8月31日 フィリピン中銀利下げ
おはようございます。フィリピン中銀は利下げしました。
1. 7月CPIが減速
フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は8月5日に、7月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+0.9%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+1.4%から減速。
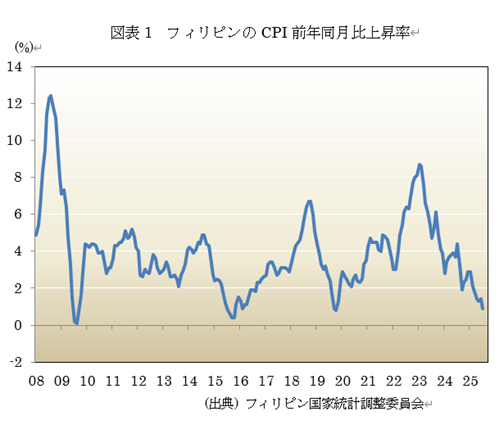
2. 政策金利を引き下げ
一方、フィリピン中央銀行は8月28日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を▲0.25%ポイント引き下げて、5.00%にすると決定(図表2参照、上限を表示)。引き下げは市場の予想通り。利下げは3会合連続。
レモロナ中銀総裁は今月、利下げが2026年迄続く可能性を示唆。政策当局は世界的な貿易摩擦への備えとして、経済の下支えを図っています。
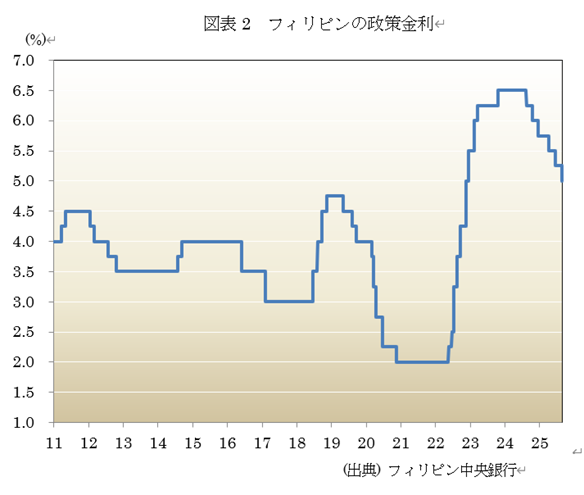
3. 4-6月GDPは伸び率加速
一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は8月7日に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.5%の伸びになったと発表(図表3参照)。市場予想の+5.4%から上ぶれ。前期の同+5.4%から加速。
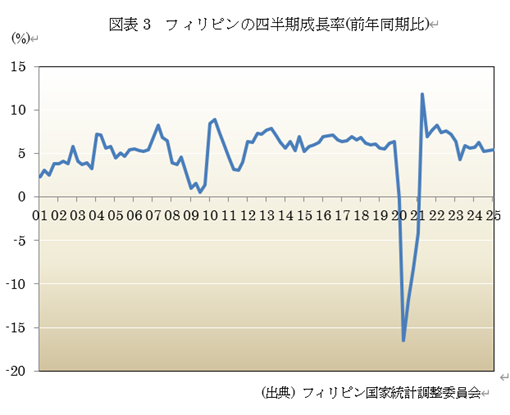
東南アジアの中でも比較的高い成長率を維持した背景には、インフレの鈍化と雇用の安定があります。昨年から始まった一連の利下げ、景気拡大を後押し。中銀のレモロナ総裁は、今後、数課月以内に追加の金融緩和を行う可能性があるとの考えを示唆。
令和7年8月28日 中国7月貿易統計
おはようございます。7月の中国貿易統計で、輸出は増加しました。
1. 7月輸出は増加
中国税関総署が7日発表した7月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+7.2%と、前月の+5.8%から加速。市場予想の+5.4%から上振れ。今月12日に迫る米関税の一時停止期限を控えて、輸出業者が出荷を急ぎました。特に東南アジアへの輸出が増加。
輸入は+4.1%と、6月の+1.1%から加速。市場予想の▲1.0%から上振れ。政策当局が家計主出増加促進に向けて取り組みを強化。国内需要が改善していることを示唆。
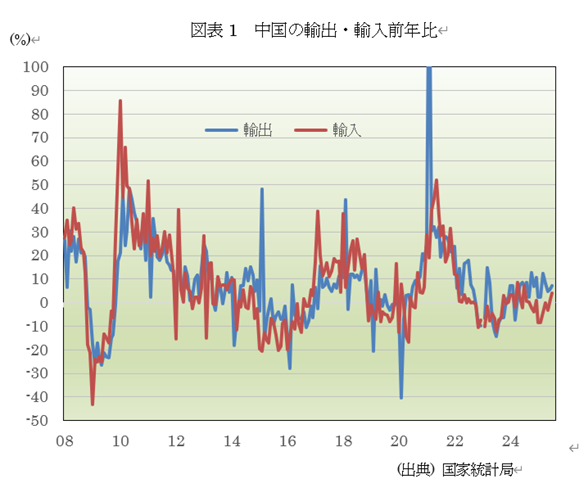
2. 貿易黒字は減少
一方、貿易黒字額は982億4000万ドル。6月の1147億7000万ドルから縮小。
エコノミスト・インテリジェンス・ユニットのシニア・エコノミスト、シー・タンチェン氏は、「貿易データは、米中貿易において東南アジア市場がこれまで以上に重要な役割を果たしている今年示唆している」と指摘。
令和7年8月27日 中国7月新築住宅価格
おはようございます。中国7月新築住宅価格は前月比で66の都市で下落しました。
1. 4-6月期GDP
中国国家統計局が5月15日発表した4-6月期実質GDPは+5.2%。市場予想の+5.1%から上振れ。前期の+5.4%から伸び率は鈍化。同統計局によると、1-6月期は前年同期比+5.3%。
同国は米国との貿易戦争が強まっているものの、米国以外への市場への多角化が奏功。
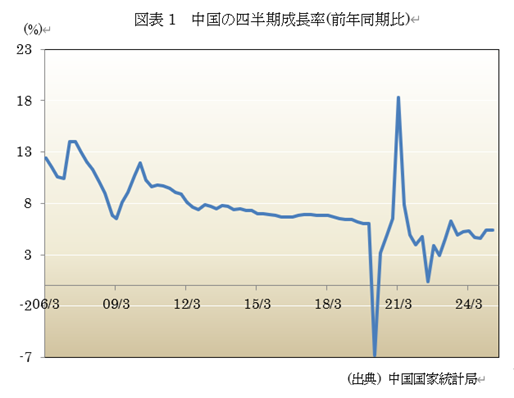
2. 7月新築住宅価格
一方、中国の7月の主要70都市の住宅価格が発表されました。新築・中古住宅ともの9割以上の都市で下落。国家統計局によると、7月の新築住宅価格は、前月比66都市で下落。50都市以上で下落するのは、昨年の8月以来12か月連続。
更に、中古受託価格も北京市、上海市、雲南省の昆明を除く67都市で下落。
低迷する不動産市場を梃入れするため、中国政府は不動産の「買い替え政策」を進め、買い替えに補助金を出したり、手数料を割引いたりしています。
令和7年8月26日 中7月鉱工業生産
おはようございます。中国7月鉱工業生産は減速しました。
1. 鉱工業生産は減速
中国国家統計局が15日発表した7月の鉱工業生産は、前年同月比+5.7%と、全月の+6.8%から伸び率が減速。市場予想の+5.9%から下振れ。

2. 7月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、7月の小売売上高は前年同期比+3.7%と、前月の+4.8%から伸び率が減速。市場予想の4.6%から下ぶれ。

3. 1-7月固定資産投は伸び率減速
他方、国家統計局による同日発表の1-7月期の固定資産投資は、前年同期比+1.6%。伸び率は1-6月期の+2.8%から減速。
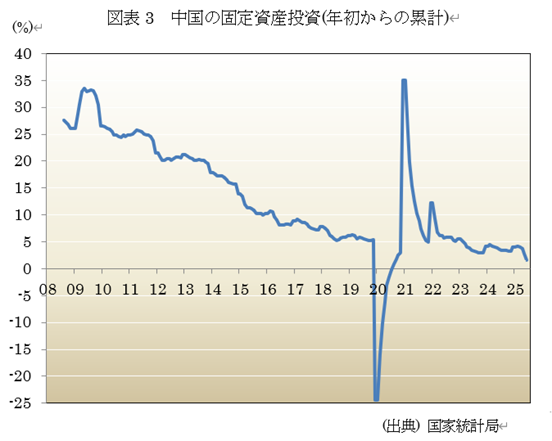
鉱工業生産の伸び率は2024年11月以来の低水準。小売売上高も24年12月以来の低い伸び率。
米中貿易摩擦が一時休戦となっているものの、行内需要の低迷やデフレ圧力、過当競争が企業収益を圧迫。
記録的な猛暑や洪水などの以上企業も、工場の生産や事業への支障となっており、経済に悪影響を及ぼしています。
令和7年8月24日 メキシコ4-6月期GDP確報値
おはようございます。メキシコの4-6月期GDPは減速しました。
1. CPI上昇率は減速
メキシコ国立地理情報研究所は7月9日に、メキシコの6月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.32%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.42%から減速。市場予想の+4.31%とほぼ一致。
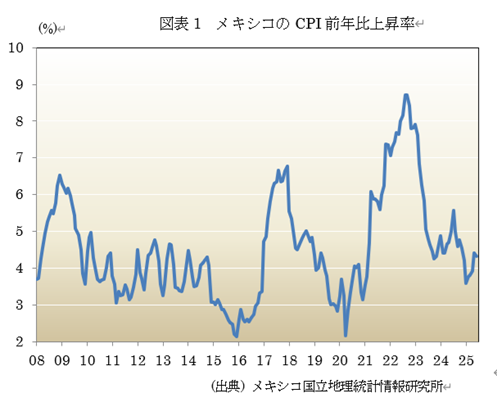
2. 4-6月期GDPは減速
メキシコ統計局は8月2日に、4-6月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前四半期比+0.6%になったとしました。速報値の+0.4%から小幅下方修正。2四半期連続のプラスは維持。猶、図表2は前年同期比速報値。
農畜産業などの第1次産業が▲2.4%と、下げ幅を拡大。製造業など第2次産業も+0.7%(速報値は+0.8%)に留まりました。金融サービス業など第3次産業は+0.8%(同+0.7%)と小幅上振れ。
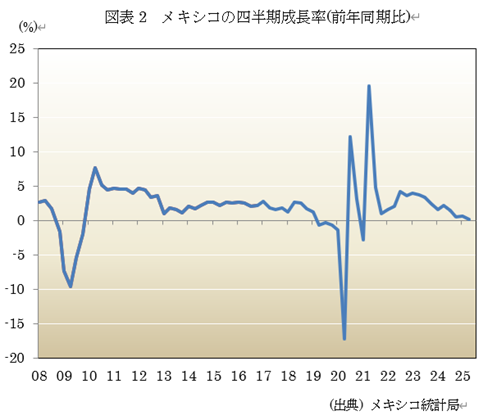
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は6月26日の融政策決定会合で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて8.0%にすることを決定(図表3参照)。4回連続で▲0.50%の利下げ。
声明では、政策委員会は▲0.5%ポイントの利下げを継続する可能性があるとし、ディスインフレ・プロセスが緩和期間持続を可能にするとしています。
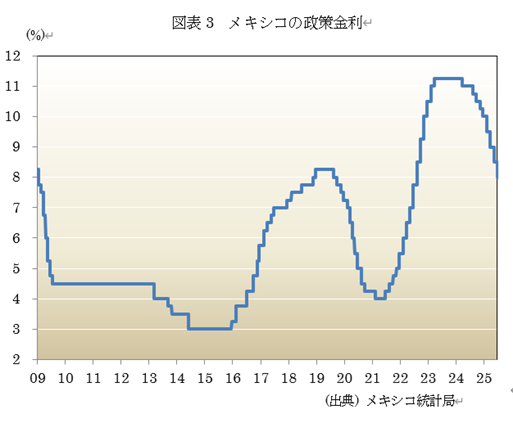
只、中銀は貿易摩擦、地政学的リスクの高まりなど、世界経済の不透明感を指摘。それらの要素がペソ下落を通じてインフレを再燃させ、景気を減速させるリスクがあるとしています。
令和7年8月236日 インドネシア中銀利下げ
おはようございます。ンドネシア中銀は利下げしました。
1. 7月CPI上昇率は加速
インドネシア中央統計局は8月1日に、7月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.37%になったと発表(図表1参照)。前月の+1.87%から加速。
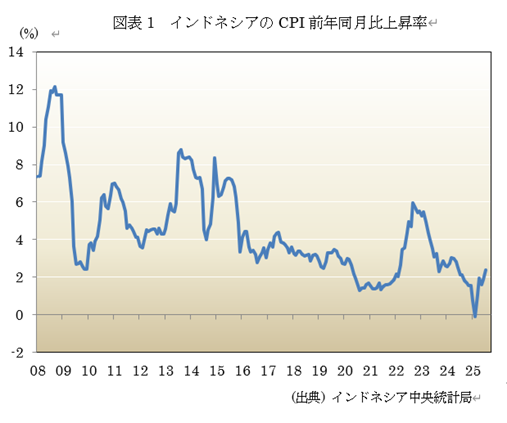
2. 政策金利を引下げ
一方、インドネシア中央銀行は8月20日の理事会で、政策金利であるBIレートを▲0.25%ポイント引き下げて5.0%にすることを決定。利下げは市場の予想外で、金融政策の軸足を景気刺激に一段と移行。
4-6月期GDP成長率が予想を上回る結果となったことを考慮すると、2カ月連続利下げには意外感があります。
只、貸出や製造業の伸びが鈍く、今年+5%の成長率維持は困難になったことから、内需を支えるには、金融緩和の継続が必要であるとの味方もあります。
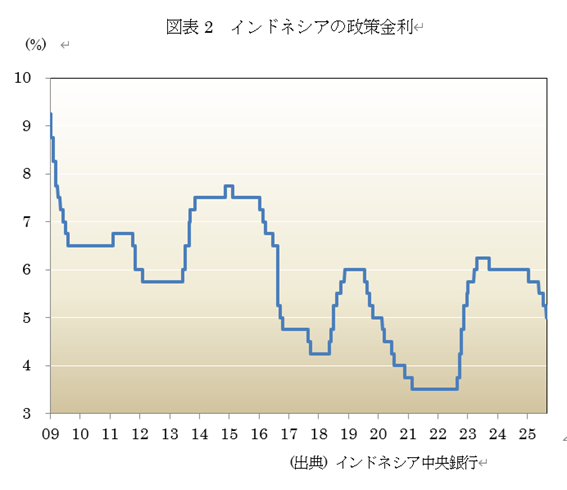
3. 4-6期GDP加速
インドネシア中央統計局(BPS)は8月5日に、同国の4-6月期GDP成長率が、前年同期比+5.12%になったと発表。前期の同+4.87%から減速。市場予想の4.8%から上振れ。前期比では+4.04%。市場予想は+3.69%。
今回の結果は、個人消費の半分以上を占める個人消費の減速を見込んでいた市場予想に反するもの。最近の利下げや政府による景気刺激策、安定した食品価格に加えて、イスラム教のラマダン(断食月)明け大祭や休暇シーズン中の支出増加が国内需要を下支えした可能性があります。
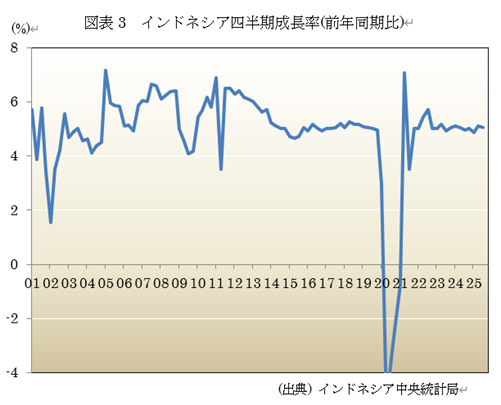
個人消費は+4.97%、総固定資本形成は+6.99%。輸出は+10.67%と、米国の関税発動んを前に前倒し出荷が引き続き寄与。米国はインドネシアに対する関税率を当初の32%から19%に引下げ。
只、貿易戦争の激化や世界経済の減速により、今後は内需や貿易の勢いが鈍化するリスクもあります。対米輸出にかかる関税の引き上げは州内に発効予定。
令和7年8月20日 タイ4-6月期GDP
おはようございます。タイ4-6月期GDPは減速しました。
1. 4-6月期成長率+2.8%に減速
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は8月18日に、4-6月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+2.8%になったと発表(図表1参照)。前期の+3.1%から減速。市場予想の+2.0%からは上振れ。前期比(季節調整済み)の成長率や+0.6%。
項目別では、主に純輸出の鈍化が成長率減速に繋がったことがわかります。
まず、民間消費は前年同期比+2.1%(前期:同+2.52%)と低下。政府消費は同+2.2%(同+3.4%)と鈍化。政府消費支出は同+2.2%(同+3.4%)と鈍化。総固7定資本形成は同+5.8%(+4.7%)と加速。純輸出の成長率寄与度は+1.6%と、前期の+7.0%ポイントから縮小。

2. 消費者物価指数(CPI)上昇率マイナス
タイ商業省は6日、7月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.7%であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.25%からマイナス幅が拡大。
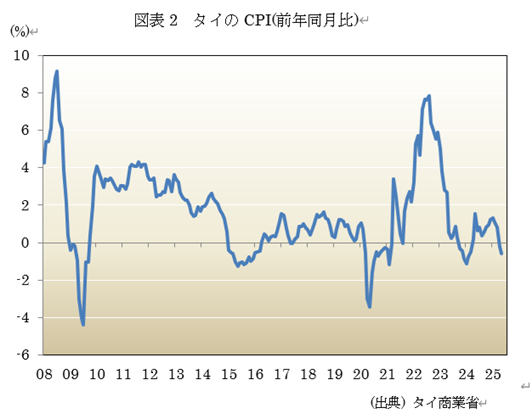
3. 政策金利を維持
一方、タイ中央銀行は6月25日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.0%で維持。国内政治の不確実性に加えて、米国の関税措置や中東情勢などの世界的リスクが重なる中、政策余地を温存。
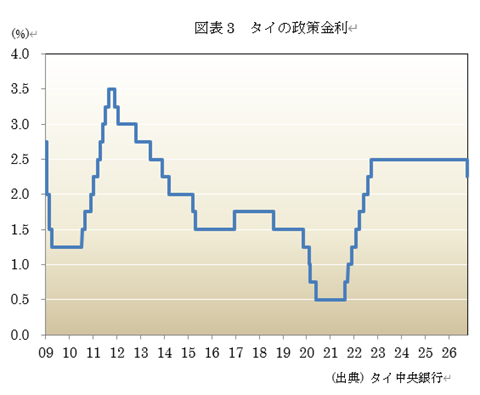
中銀の政策決定員会(MPC)では、7人中6人が据え置きを指示。市場では概ね政策金利維持を予想していました。
令和7年8月19日 パキスタンで大規模洪水
おはようございます。パキスタンでは大雨により大規模な洪水が発生しましたした。
1. 300人以上が死亡
雨期を迎えているパ紀成譚で、大雨に影響により、洪水や土砂崩れが相次いでおり、これまでにカイバル・プクトゥンク州などで300人以上が死亡。
現地からの映像では、川が増水して勢いよく流れている様子や、多くの人や車が行きかう道路にも水が流れ込む様子が移されています。住宅や学校が倒壊する被害が出ているほか、多くの人が避難を余儀なくされている模様。
更に、隣国のインドでは、インドが直角地とする北部のジャム・カシミール地方の山間の村で豪雨による洪水が発生。ロイター通信によると、これまでに60人以上が死亡し、200人以上が行方不明。

2. インドとパキスタン水で対立
一方、2025年5月、インドとパキスタンの間では、無人機やミサイルと用いた武力衝突が発生。両国の係争地であるカシミール地方を巡って再び緊張が高まり、報復の欧州が続いています。どちらも核兵器を保有する国であり、国際社会は事態の行方を注視。
この衝突を巡っては、宗教や領土を巡る対立と共に、水を巡る争いがあります。
インダス川は、中国・治部十自治区の高地を源に、インドのラダック地方を通ってパキスタンに流れ、アラビア海に注ぎます。流域全体の国別割合には諸説ありますが、パキスタンが約半分以上、インドが3-4割、中国が源流部を含んでいます。
令和7年8月17日 インド国債18年振り格上げ
おはようございます。S&Pはインド国債を格上げしました。
1. 18年振り格上げ
大手格付け会社のS&Pグローバル・レーティング(以下、S&P)が8月14日、インド国債(長期ソブリン)の信用格付けを「BBB-」から「BBB」へと、18年ぶりに引き上げ。
インド経済の構造的な成長力、金融政策の信頼性、財政健全化の進展が国際的に評価されたものと言えます。
引き上げの要因としては、財政再建の進展、米国関税リスクへの耐性、つまり、貿易依存度が低いこと、などがあります。
2. インド国債市場
外国投資家が、インド現地通貨建て債券市場に投資する場合、投資枠による規制があり、資金流入が制限されています。そのため、インドでは債券市場全体に占める外国投資家の比率が低く、世界的なリスク回避局面でも、資金流出による影響が相対的に小さいとみられます。
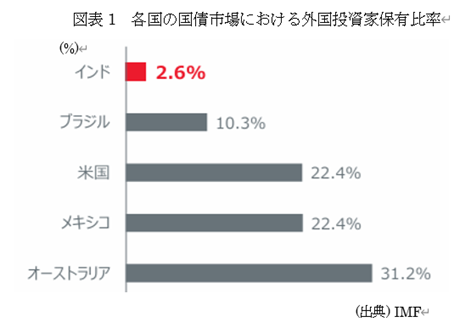
各国10年債国債利回りの推移を比較すると、インド国債利回りの変動は相対的に小さく、過去10年間の利回り変動幅は、米国債よりも小さくなっています。
投資適格で、相対的に高利回りでありながら、変動制の低いインド国債は、ポートフォリオにおいて投資ファンドの分散投資効果と利回り確保観点から、今後一層注目される可能性があります。
令和7年8月16日 タイ中銀利下げ
おはようございます。タイ中銀は利下げしました。
1. 1-3月期成長率+3.1%に減速
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は5月19日に、1-3月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+3.1%になったと発表(図表1参照)。前期の+3.2%から減速。市場予想の+2.9%からは上振れ。
只、NESDCは、米国の関税により輸出が打撃を受ける恐れがあり、今年のGDP成長率予想を+2.3〜3.3%から+1.3〜2.3%に下方修正。第1四半期GDPは季節調整済み前期比では+0.7%。市場予想の+0.6%、昨年10-12月期の+0.4%30上回りました。
NEDSCは第1四半期について、個人消費と政府支出が下支え要因となったものの、消費者と企業の高水準の債務負担や世界的な貿易戦争が、年内の経済活動の重荷になるとの見方を示唆。
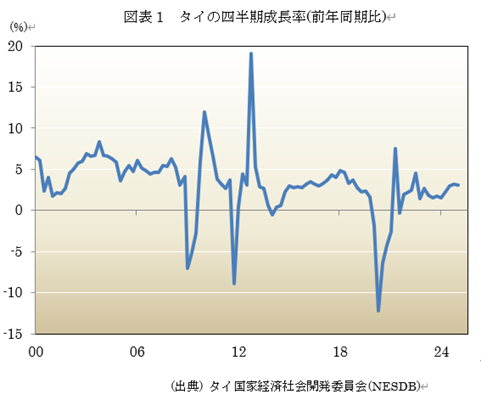
2. 7月CPIマイナス幅拡大
一方、タイ商業省は8月6日に、7月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.7%であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.25%からマイナス幅が拡大。
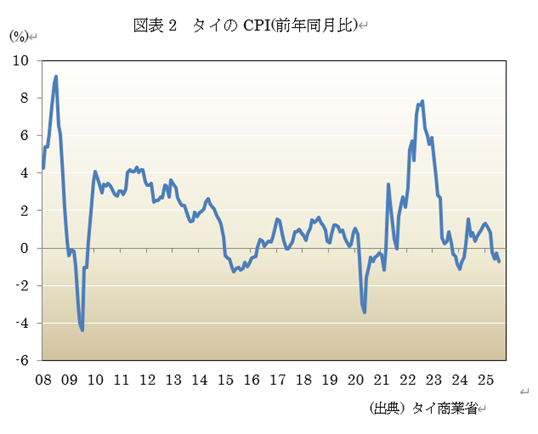
3.政策金利を引下げ
一方、タイ中央銀行は8月13日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を▲0.25%ポイント引き下げて、1.5%としました。利下げは2会合振り。米関税政策による景気悪化を織り込みました。
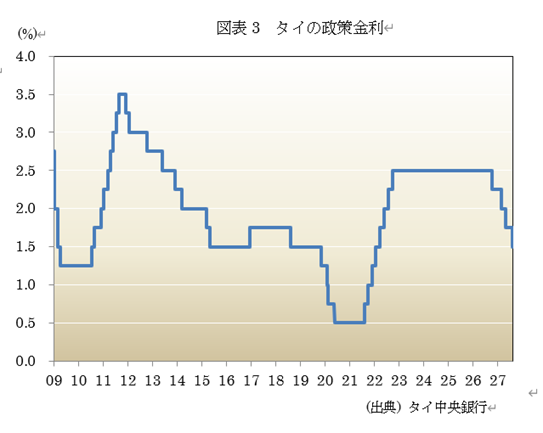
中銀の政策決定員会(MPC)では、7人中6人が据え置きを指示。市場では概ね政策金利維持を予想していました。
令和7年8月14日 中国7月新車販売
おはようございます。中国7月新築住宅価格は下落率が加速しました。
1. 4-6月期GDP
中国国家統計局が7月15日発表した4-6月期実質GDPは+5.2%。市場予想の+5.1%から上振れ。前期の+5.4%から伸び率は鈍化。同統計局によると、1-6月期は前年同期比+5.3%。
同国は米国との貿易戦争が強まっているものの、米国以外への市場への多角化が奏功。
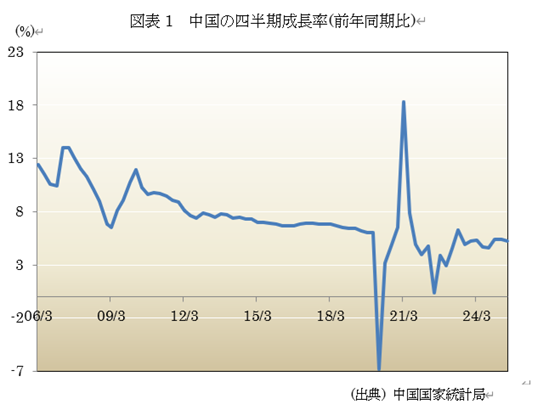
同国経済は今年、政府が掲げる「約5%」という成長目標の達成に向けて国内外から圧力を受けています。多くのエコノミストは、更なる政策支援がなければ、目標達成は困難であるとみています。
2. 7月新車販売
一方、中国汽車工業会は11日、7月の新車販売台数(輸出を含む)が、前年同月比+14.7%の259万3000代であったと発表。新型車への買い替えを促進する補助金政策や、新型車の投入効果で、電気自動車(EV)が5割近い伸び。
EVなど新エネルギー車の販売は、+24.4%の45満1000台。新車販売に占める新エネルギー車比率は+4.9%ポイントの48.7%。
7月は一般に自動車の購入意欲が弱くなります。只、旧型車から新型車に買い換える際の補助金と共に、中国メーカーを中心として新型車が多く販売されたことが全体を押し上げました。自動車メーカー別では、民営大手の浙江吉利控股集団などが伸びました。
令和7年8月13日 マレーシア4−6月期成長率加速
おはようございます。マレーシアの4−6月期成長率鈍化は加速しました。
1. CPI上昇率は横這い
マレーシア統計庁は7月22日に、6月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.1%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月から減速。市場予想の+1.2%から下振れ。
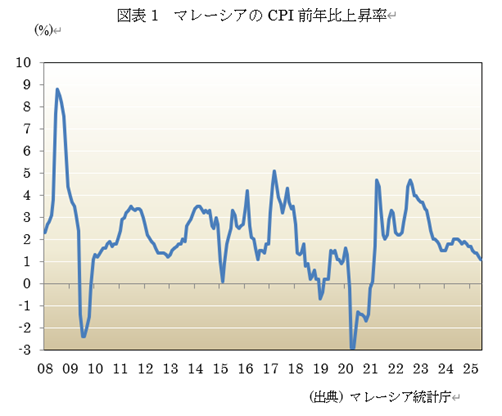
2. 2. 4-6期成長率は+4.5%に加速
マレーシア統計局は7月18日に、4-6月期の実質GDP成長率が+4.5%になったと発表(図表2参照、速報値)。前期の+4.4%からは加速。市場予想の+4.2%をも上回りました。サービス業が牽引。
当局が2025年の成長率見通し(+4.5〜+5.5%)の見直しを検討する中、一定の安心材料となる可能性もあります。
マレーシアは米国から25%の輸入関税を課される可能性があり、当局は8月1日の発効前に引下げ交渉を行っています。
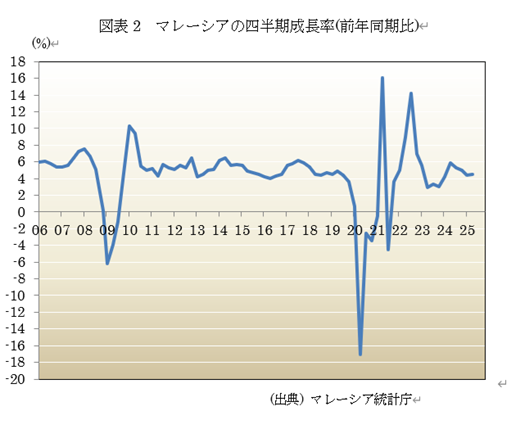
3. 政策金利を引下げ
一方、マレーシア中央銀行7月9日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を▲0.25%ポイント引き下げて2.75%にすることを決定。利下げは5年振り。成長見通しの弱さと世界貿易を巡る不確実性の高まりを背景に、景気を下支えする狙いがあります。
市場予想は、据え置きと▲0.25%引下げに分かれていました。
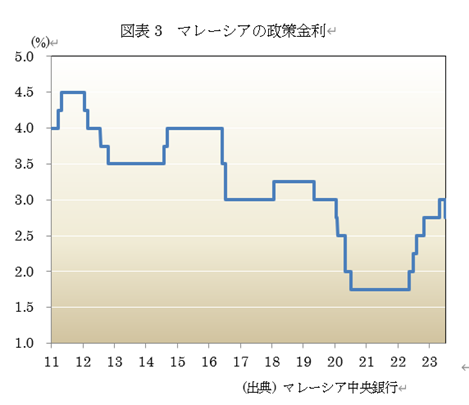
同行は、関税を巡る不確実性や地政学的緊張によって、世界経済の成長に通しが圧迫されており、世界の金融市場や商品価格の変動が大きくなる可能性があるとの見解を示唆。
令和7年8月10日 中国7月CPI
おはようございます。中国の7月CPIは、前年同月比横這いとなりました。
1. 7月CPIが横這い
中国国家統計局が9日発表した7月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が+0.1%と、前月の▲0.1%からプラスに転じました。予想は横這い。
食品価格は▲1.6%と、6月の▲0.3%から下げ幅が拡大。変動の激しい食品と燃料を除くコアインフレ率は前年同月比+0.8%と、1年5カ月ぶりの高い伸び。
中国経済については、先月に同国の東海岸を襲った熱波や、今月の豪雨被害といった以上気象も負荷を齎しています。
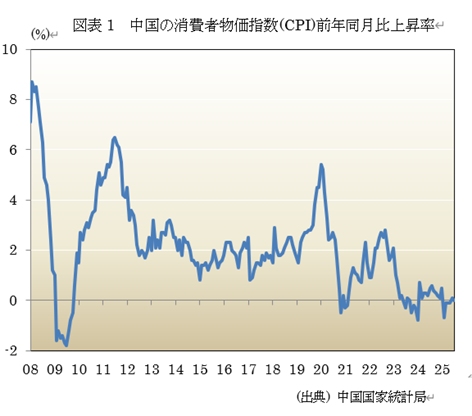
中銀は同日の声明で「不確実性と貿易摩擦から(国内景気は)下振れリスクがある」とも言及した。利下げ判断は5人の理事による4対1の多数決で、ジョナタン・ヒース副総裁のみ現状維持を主張した。6月の前回会合までは4会合連続で0.5%ずつ下げてきたが、今回の利下げ幅は25年に入って初めてとなる0.25%にとどめた。
同日午前に発表していた7月の消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率)は前年同月比3.51%と、3カ月ぶりに政策目標の上限とする4%を下回った。中銀の声明でも物価の先行きについて「21年から24年にかけて直面したリスクよりも鈍化している」としており、22年に8%を超えていた過度なインフレは落ち着いてきた。
米国系大手銀行のシティメキシコが7月末に発表していたリポートでは、37の金融機関に所属するアナリスト、エコノミストによる25年末の政策金利予想(中央値)は7.5%だった。24年3月から1年半足らずで3.5%下げた金融緩和サイクルを経て、さらなる利下げ余地は小さいとの見方が多い。
メキシコの通貨ペソは6月下旬以降、1ドル=18ペソ台中盤から後半のドル安・ペソ高水準で安定している。輸入物価の上昇からインフレの再燃につながる過度なペソ安のリスクも一時期に比べれば遠ざかっている。
ペソはトランプ米大統領の相次ぐ関税による脅しを受け、年前半には21ペソ台に迫る局面も見られた。3月以降は相次ぐ自由貿易協定、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)適合品への課税猶予などもあり、一定の耐性を身につけつつある。
トランプ氏は8月1日からメキシコに課すと宣言していた30%の追加関税も、直前で90日間先送りした。メキシコには自動車大手をはじめ、米資本の製造業も多く進出している。トランプ関税の発動ラッシュが落ち着けば従来通り、ペソ相場は米国との金利差が注目される展開に戻るとみる金融関係者は多い。
2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、7月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲3.6%と、下落幅は前月と同じ。市場予想は▲3.3%。34か月連続でマイナス。長引く不動産不況や米国との貿易問題を巡る不透明感が、消費や企業活動の重石となっています。

PPIは2年以上に亘り下落。主要産業の過剰生産能力への対応で、当局はまだ成果を上げていないことを示唆。2023年7月以来大幅マイナスでった6月を同じ下げ幅となりました。
令和7年8月9日 フィリピン4-6月期GDP
おはようございます。フィリピン4-6月期GDP成長率が加速しました。
1. 7月CPIが減速
フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は8月5日に、7月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+0.9%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+1.4%から減速。
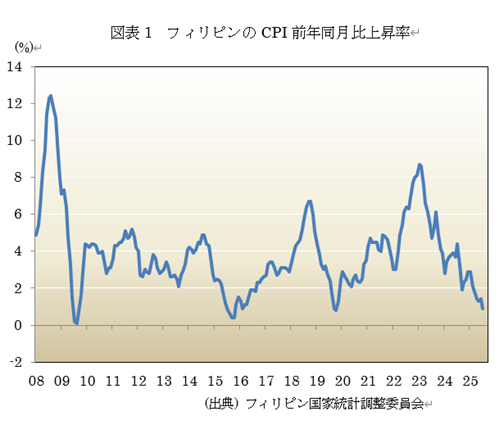
2. 政策金利を引き下げ
一方、フィリピン中央銀行は6月19日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を▲0.25%ポイント引き下げて、5.25%にすると決定(図表2参照、上限を表示)。引き下げは市場の予想通り。2会合連続。
インフレリスクの中止が必要としながらも、景気支援のために、追加緩和を実施する可能性を示唆。
レモロナ総裁は会見で、あと1回の▲0.25%ポイント利下げが可能と発言。時期は
明示しませんでした。今年はあと3回の政策決定会合が予定されています。
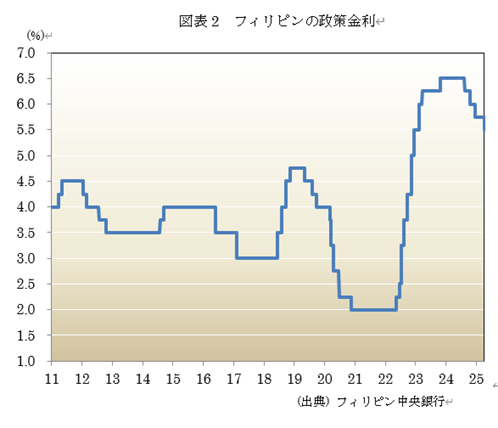
3. 4-6月GDPは伸び率加速
一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は8月7日に、4-6月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.5%の伸びになったと発表(図表3参照)。市場予想の+5.4%から上ぶれ。前期の同+5.4%から加速。
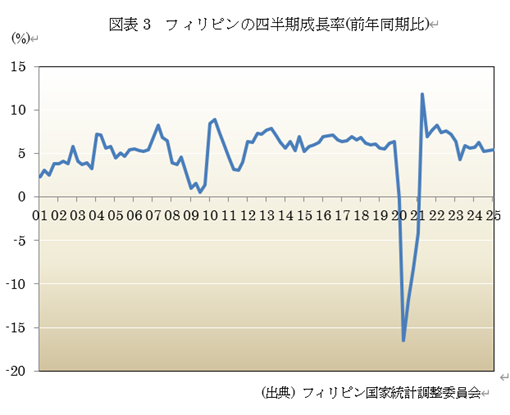
東南アジアの中でも比較的高い成長率を維持した背景には、インフレの鈍化と雇用の安定があります。昨年から始まった一連の利下げ、景気拡大を後押し。中銀のレモロナ総裁は、今後、数課月以内に追加の金融緩和を行う可能性があるとの考えを示唆。
令和7年8月7日 インドネシア4-6月期GDP
おはようございます。インドネシアの4-6月期GDPは加速しました。
1. 7月CPI上昇率は加速
インドネシア中央統計局は8月1日に、7月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+2.37%になったと発表(図表1参照)。前月の+1.87%から加速。
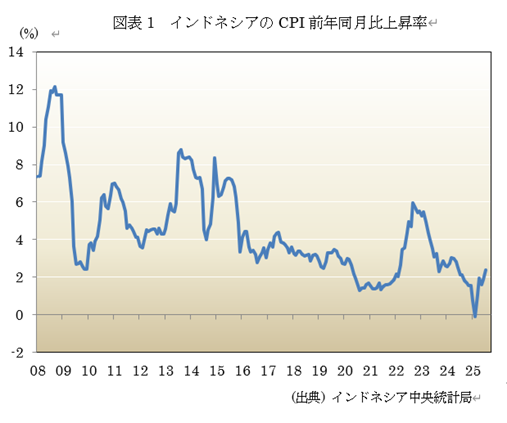
2. 政策金利を引下げ
一方、インドネシア中央銀行は7月16日の事会で、政策金利であるBIレートを▲0.25%ポイント引き下げて5.25%にすることを決定。米国との関税合意が経済にプラスになるとの見解も示唆。
昨年9月に開始した金融緩和サイクルで4回目の利下げ。国際貿易の鈍化や内需低迷を受けて景気を支援。
市場では、利下げ、据え置きの予想がほぼ半々でした。
ペリー・ワルジョ中銀総裁は会見で、今回の利下げは国内の経済成長を支えるn必要性と整合性が取れていると発表。
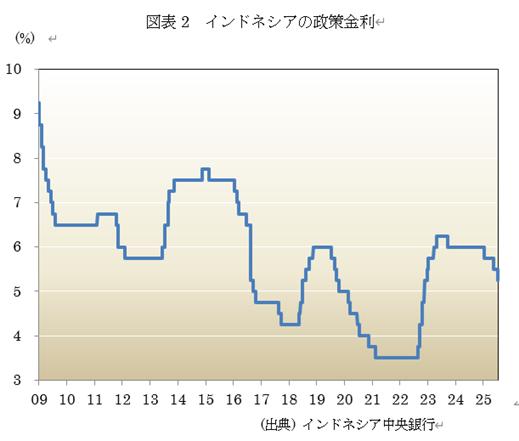
3. 4-6期GDP加速
インドネシア中央統計局(BPS)は8月5日に、同国の4-6月期GDP成長率が、前年同期比+5.12%になったと発表。前期の同+4.87%から減速。市場予想の4.8%から上振れ。前期比では+4.04%。市場予想は+3.69%。
今回の結果は、個人消費の半分以上を占める個人消費の減速を見込んでいた市場予想に反するもの。最近の利下げや政府による景気刺激策、安定した食品価格に加えて、イスラム教のラマダン(断食月)明け大祭や休暇シーズン中の支出増加が国内需要を下支えした可能性があります。
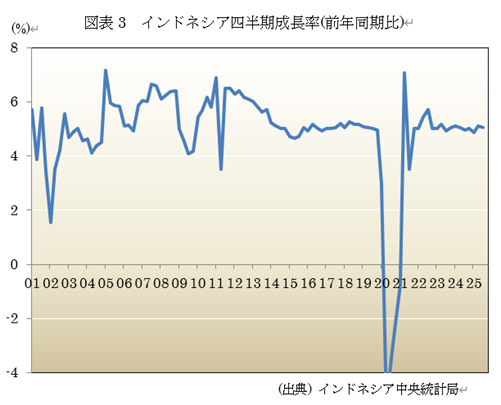
個人消費は+4.97%、総固定資本形成は+6.99%。輸出は+10.67%と、米国の関税発動んを前に前倒し出荷が引き続き寄与。米国はインドネシアに対する関税率を当初の32%から19%に引下げ。
只、貿易戦争の激化や世界経済の減速により、今後は内需や貿易の勢いが鈍化するリスクもあります。対米輸出にかかる関税の引き上げは州内に発効予定。
令和7年8月6日 米インド関税交渉進展せず
おはようございます。米国とインド関税交渉進展していません。
1. 米とインド、ロシア産原油巡り対立
トランプ大統領が7日からの「相互関税」のは発動を発表する中、世界第5位の経済規模のインドは、関税交渉で米国と合意できていません。インドがウクライナ侵攻を続けるロシアから原油購入を続けることも問題となっています。交渉は難航することも予想されます。
7月30日の米国の発表によると、インドは主要貿易相手国の中での高水準の25%の関税を課せられます。
ベッセント米財務長官は4月、米メディアのインタビューで、「私たちが最初に署名する貿易相手の取引の1つはインドになるだろう」としていました。
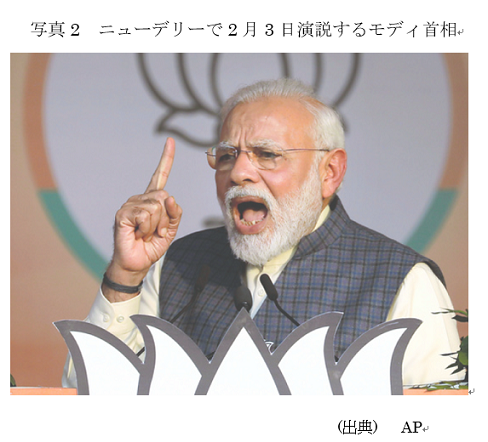
2. 米とブラジル関税で対立
他方、ブラジル政府は、トランプ政権が今週発動する「相互関税」について、直接的な報復対策を講じるのを当面控え、打撃を受ける輸出業界を救済する政策に注力。
ブラジルに適用される「相互関税」は累計で50%。トランプ大統領は自身と関係が深いブラジルのボルソナロ前大統領がクーデター計画の罪で起訴されたことを「政治的な迫害」として、こうした関税を課す理由としています。
令和7年8月4日 米7月雇用統計
おはようございます。米国の7月の雇用統計で、雇用者数が+13.9万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が7月の雇用統計を1日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+7.3万人。市場予想の+11万人にから下振れ。伸びが予想以上に鈍化したほか、過去2カ月分の雇用者数も▲25万8000人下方修正。労働市場の急激な悪化を示唆しており、米連邦準備時理解(FRB)に、9月での利下げ再開を催促する可能性があります。
6月分は当初発表の+14.7万人から+1.4万人に下方修正。5月分も+12.5万人から+1.9万人に下方修正。米労働統計局(BLS)は、5、6月分の「通常よりも大きい」下方修正の理由を明らかにしなかったものの、「月次の修正は推定値発表以降に企業や政府機関から受け取った追加報告と季節要因の再計算によるもの」としました。
失業率は4.2%で、6月の4.1%から上昇。市場予想は4.2%。
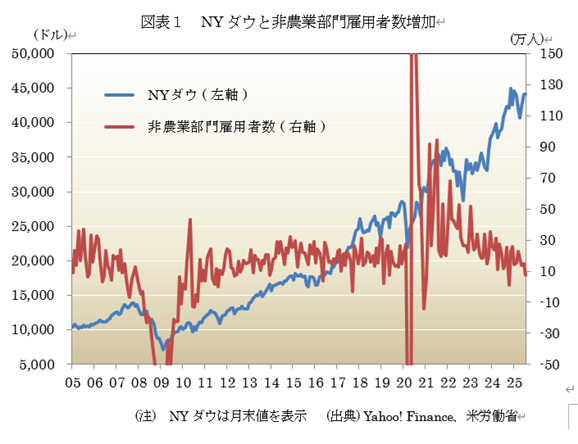
2.FRBは9月に利下げも
FWDBONDSのチーフエコノミスト、クリストファー・ラプキー氏は「FRBの9月利下げへの可能性が高まった」としました。「労働市場が崩壊の瀬戸際にあるわけではないが、深刻な打撃を受けており、米経済の運命を反転させる可能性もある」としました。
過去3カ月の雇用者数の伸びは月平均+3.5万人と、前年同期の+12.3万人から大きく減少。エコノミストは、関税措置を巡る不確実性によって、企業の長期計画策定が困難になっていると指摘。
令和7年8月3日 メキシコ4-6月期GDP
おはようございます。メキシコの4-6月期GDPは減速しました。
1. CPI上昇率は減速
メキシコ国立地理情報研究所は7月9日に、メキシコの6月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.32%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+4.42%から減速。市場予想の+4.31%とほぼ一致。
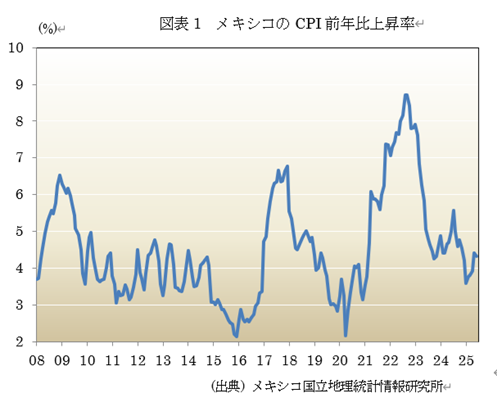
2. 4-6月期GDPは減速
メキシコ統計局は7月30日に、4-6月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+0.1 %になったと発表(速報値、図表2参照)。前期の確報値+0.8%から減速。
同国経済は、輸出の8割が米国向け、米トランプ政権による関税政策に翻弄されています。米国はメキシコに追加関税の発動と延期を繰り返しており、メキシコとの協議を継続。
足下では、輸出の駆け込みも追い風となり、4-6月期GDP成長率は前期比年率+2.72%。
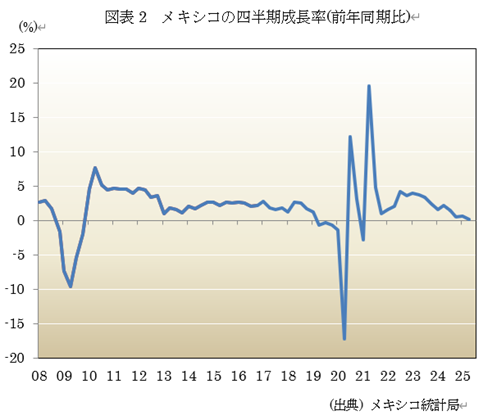
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は6月26日の融政策決定会合で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて8.0%にすることを決定(図表3参照)。4回連続で▲0.50%の利下げ。
声明では、政策委員会は▲0.5%ポイントの利下げを継続する可能性があるとし、ディスインフレ・プロセスが緩和期間持続を可能にするとしています。
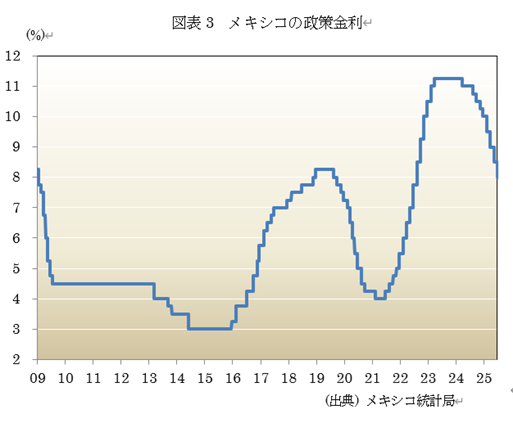
只、中銀は貿易摩擦、地政学的リスクの高まりなど、世界経済の不透明感を指摘。それらの要素がペソ下落を通じてインフレを再燃させ、景気を減速させるリスクがあるとしています。
令和7年8月2日 中国7月PMI
おはようございます。7月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。
1. 7月製造業PMIは前月から低下
中国国家統計局が31日発表した7月の製造業購買担当者指数(PMI)49.3と、前月の49.7
から低下。市場予想は49.7。景気の拡大の分かれ目となる50を引き続き割り込みました。
米国とは関税協定に至ったものの、輸出が減速。内需も低迷が継続。
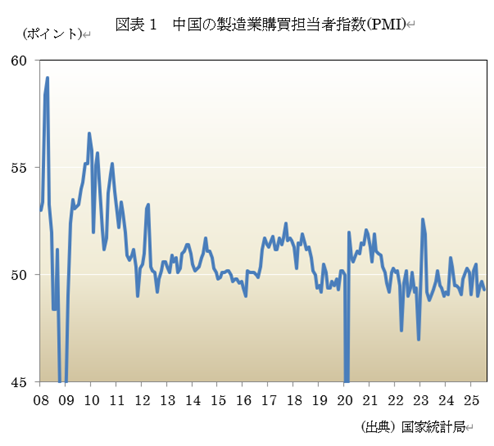
2. 非製造業PMIは低下
一方、同日に発表した7月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.1と、前月より50.5から低下。市場予想は50.2。
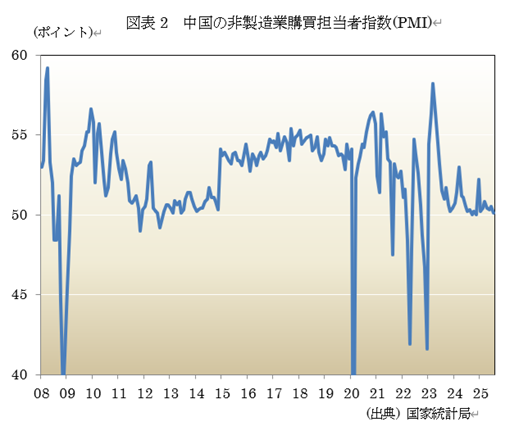
統計局は声明で、「一部地域での高温や豪雨、水害などが製造業に影響した」と指摘。7月は例年、製造業が閑散期に入る時期だとも説明。
共産党指導部は30日開催の中央政治局会議で、経済の底堅さを指摘。東南アジア向け出荷の急増や、対米輸出の安定化により、上期の貿易収支は過去最大の黒字を計上。
令和7年7月31日 IMF世界経済見通し引き上げ
おはようございます。IMFが世界経済見通しを引き上げました。
1. 世界経済見通しを▲0.5%引き下げました
国際通貨基金(IMF)は29日、世界の経済成長見通しを前回4月の時点から+0.2%ポイント引き上げ。トランプ米政権の高関税政策で景気が後退するリスクは後退しているものの、成長率は24年の+3.3%から減速すると予想。
IMFは経済見通しを四半期毎に見直しています。米国による相互関税の発表後に示唆した4月見通しでは、▲0.5%ポイントの大幅下方修正を行いました。
米中間で激化した100%を超える報復県税の欧州が5月の合意で収束。4月に24.4%と想定していた米国の実行関税率は17.3%に低下。輸入の前倒しなど企業の関税対応も進みました。
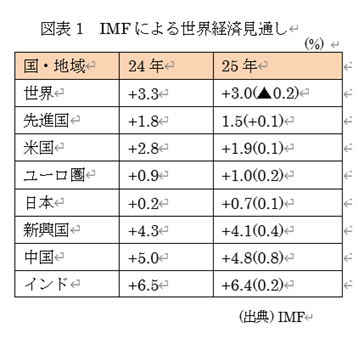
2. 米国を上方修正
国別では、米国を+1.9%と、+0.1%ポイント上方修正。7月の減税・歳出法の成立を受けて、26年も+0.3%ポイント引き上げて+2.0%としました。IMFは同法によって26年に米国の財政赤字が国内総生産(GDP)比で+1.5%ポイント拡大して、関税収入でも半分しか相殺できないとしました。
日本は1-3月期実績などを踏まえて、+0.1%ポイント上昇修正して+0.7%としました。ユーロ圏も小幅上方修正。7月下旬に公表された米政府と日本・欧州連合(EU)との関税合意は今回の試算には反映されていません。
IMFは世界経済の現状について、「不確実性が継続する中での脆弱な回復」との見解を示唆。米政府は8月1日に新たな関税率を発表。ここにきて、一部で関税交渉の進展が見られるものの、保護主義の高まりや見通しの悪さは、企業活動を下押しする恐れがあります。
令和7年7月30日 ロシア中銀利下げ
おはようございます。ロシア中銀が利下げしました。
1. 1-3月期成長率は+1.4%
ロシア連邦統計局は5月16日、1-3月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+1.4%になったと発表(速報値)。10-12月期の+4.5%から減速。伸び率は8四半期連続でプラス成長。2025年1-3月期の+5.4%からは大幅減速。
1-3月期GDP成長率、2023年第2四半期にプラス成長に転じて以来、最も低い成長率となりました。以前に、同統計局はやや高い+1.7%になる見込であると報じていました。同統計局では今後、2025年の成長率が+2.5%と予想。一方、中銀はもっと慎重な予想であり、+1-2%程度の成長率になると予想しています。
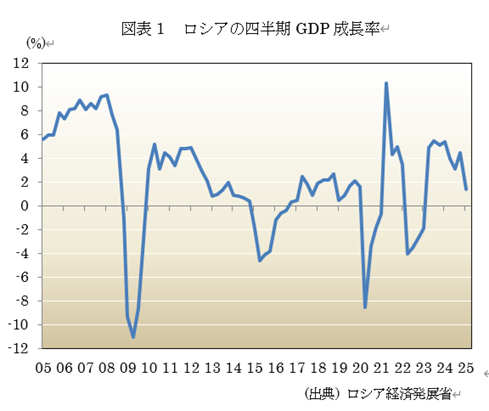
2. インフレ率減速
国家統計局から7月11日発表された6月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+9.4%と、伸び率は前月の+9.9%から減速(図表2参照)。

3. 政策金利を据え置き
一方、ロシア中央銀行は7月25日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を▲2.0%ポイント引き下げ18.0%にすることを決定。引き下げは2会合連続。引き下げ幅は▲1%から▲2%ポイントに拡大。ウクライナ侵攻に伴う戦時経済が停滞して、大幅な利下げを求める声が強まっていました。
同行声明で、「インフレ圧力が予想されたよりも早く低下している」と説明。国内の需要の伸びが鈍化している点にも触れて、戦時下で加熱した経済について「バランスのとれた成長軌道に戻りつつある」としました
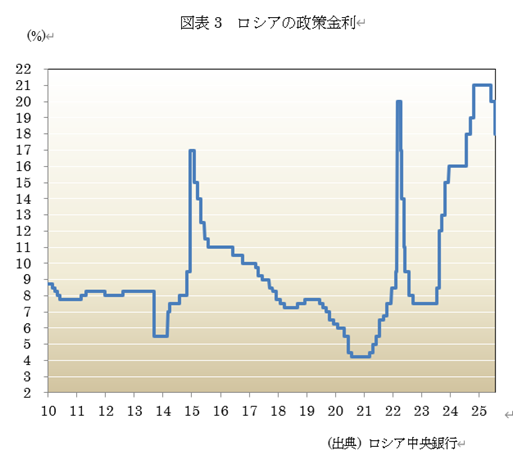
インフレ率は6月に+9.4%と、3箇月連続で低下。7月の21日時点で+9.2%に留まる。中銀はインフレ率が2025年末に+6〜7%に低下して、26年目標の+4%になると予想。インフレ目標達成への必要な金融引き締めを継続する構えも示唆。
令和7年7月28日 中国6月貿易統計
おはようございます。6月の中国貿易統計で、輸出が鈍化しました。
1. 6月輸出は加速
中国税関総署が14日発表した6月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+5.8%と、前月の+4.8%から加速。市場予想の+5.0%を上回りました。米中の関税一時停止が8月に期限を迎えるのを前に企業が出荷を急ぎました。5月は+4.8%。
特に東南アジアの中継拠点向け輸出が好調。
6月の輸入は+1.1%と、プラスに転じたものの、市場予想の+1.3%から下振れ。5月は▲3.4%。
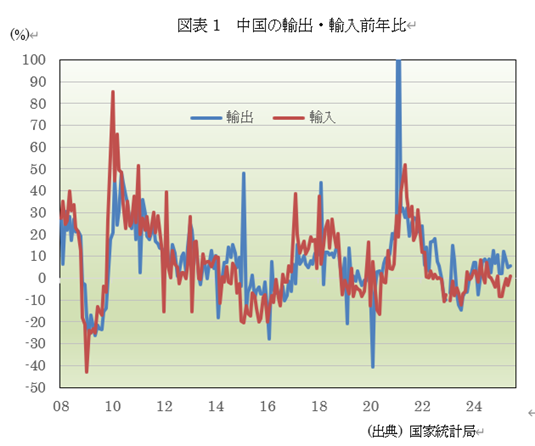
2. 対米輸出が増加
一方、対米輸出は前月比+32.4%。米国の関税引き下げの音階を受けました。前年比では依然としてマイナス。
東南アジア諸国連合(ASEAN)向け輸出は+16.8%。
中国の貿易黒字は1147億ドル。5月の1032億2000万ドルから増加。
令和7年7月27日 アジア開銀アジア成長率見通し下方修正
おはようございます。アジア開銀は、アジア成長率見通し下方修正しました。
1. アジア・太平洋地域成長率見通し下方修正
アジア開発銀行(ADB)は、今年及び来年のアジア・太平洋地域の開発途上国における経済成長率を下方修正。今回の修正は、米国による関税引き上げや世界的な貿易の不確実性による輸出減と共に、内需の低下が主な要因であるとしています。
同行が発表した「アジア経済見通し2025年7月版」によると、同地域の今年の経済成長率は+4.7%と予想され、4月時点の前回予想から▲0.2%ポイント下方修正。更に、来年の成長率見通しも+4.7%から+4.6%へと下方修正。
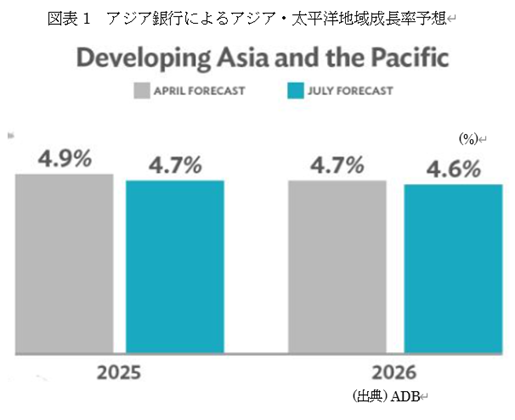
2. トランプ関税交渉妥結
一方、米トランプ大統領は22日、フィリピンと貿易交渉で妥結したと発表。フィリピンから米国への輸入品に19%の関税を課す一方、米国はフィリピンに無関税で輸出できます。軍事面でも協力。トランプ氏は合意を発表するのは、英国、ベトナム、インドネシアに続いて4か国。
自らのソーシャルメディで、「貿易協定を結んだ。フィリピンは米国に市場を開放し、関税をゼロにする。フィリピンは19%の関税を支払う。加えて、我々は軍事的にも協力する」としました。
令和7年7月24日 TSMC決算
おはようございます。台湾の半導体受託大手TSMCが4-6月期決算を発表しました。
1. 売り上げ、利益とも最高
台湾の半導体受託生産の世界最大手のTSMCが46月期決算を7月17日に発表。AI(人口知能)向けなどの半導体の販売が好調で、売り上げ、最終利益ともに四半期として過去最高を記録しました。
同社が17日発表したところでは、4-6月期で売り上げは前年同期比+38.6%の9337憶台湾元(約4兆7000億円)。最終利益は前年同月比+60.7%の3982億台湾元(約2兆円)。
売り上げ、最終利益ともに四半期としては過去最高で、6四半期連続で増収増益。

2. エヌビディアの決算も好調
一方、米半導体大手エヌビデイアが26日発表した2024年11月から25年1月決算は、売上高が前年同期比約1.8倍の393億3100万ドル、最終利益も1.8倍の220国9100万ドル。生成AI向け半導体の需要が引き続き好調で、売上高、最終利益共に四半期として過去最高。
売り上げと利益は市場予想も上回りました。ジェンスン・ファン最高経営責任者は「新型半導体ブラックウェルの需要は驚異的だ。AIは光の速さでシンポしている」との声明を発表。
令和7年7月23日 中国人民銀行優遇金利据え置き
おはようございます。中国人民銀行は、優遇金利据きました。
1. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が15日発表した6月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、全月の+5.8%から伸び率が加速。市場予想の+5.7%から上振れ。
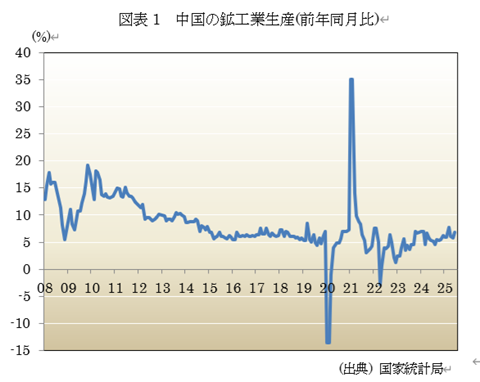
2. 2. 6月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、6月の小売売上高は前年同期比+4.8%と、前月の++6.4%から伸び率が減速。市場予想の5.4%から下ぶれ。
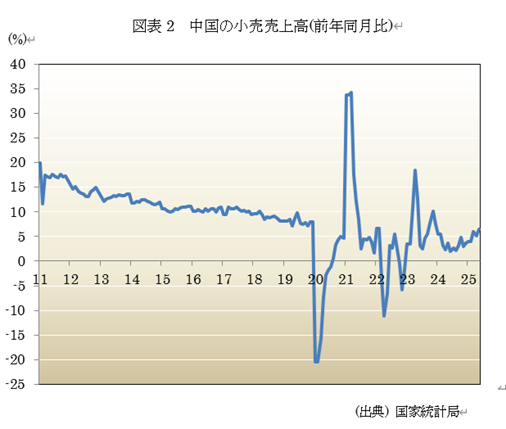
3. 1-6月固定資産投は伸び率減速
他方、国家統計局による同日発表の1-6月期の固定資産投資は、前年同期比+2.8%。伸び率は1-5月期の+3.7%から減速。
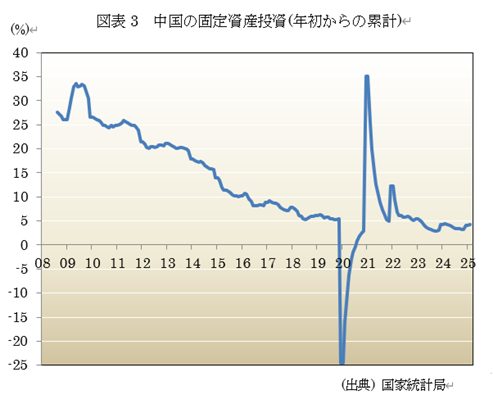
一方、同日発表の同国4-6月期国内総生産(GDP)は、実質で前年同期比+5.2%。成長率は1-3月期の+5.4%から減速。
4. 4-7月期GDP
中国国家統計局が15日発表した4-7月期実質GDPは+5.2%。市場予想の+5.1%から上振れ。前期の+5.4%から伸び率は鈍化。同統計局によると、1-6月期は前年同期比+5.3%。
同国は米国との貿易戦争が強まっているものの、米国以外への市場への多角化が奏功。
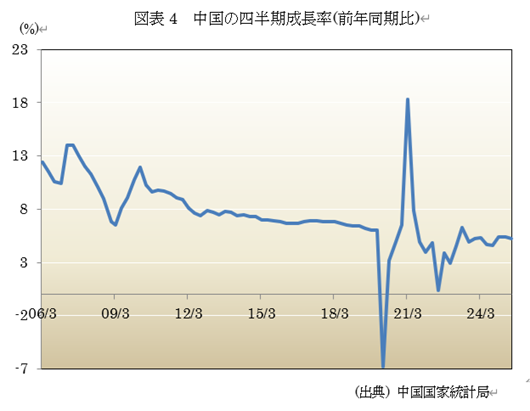
同国経済は今年、政府が掲げる「約5%」という成長目標の達成に向けて国内外から圧力を受けています。多くのエコノミストは、更なる政策支援がなければ、目標達成は困難であるとみています。
5. 優遇金利を据え置き
一方、中国人民銀行(中銀)は。21日発表した7月の最優遇貸出金利(LPR、ローンプライムレート)を期間1年で年3.0%、同5年超で3.5%にすると発表。
いずれも6月と同じ水準に据え置き。5月の引き下げ効果を見極めるためとみられます。
令和7年7月22日 中国6月新築住宅価格
おはようございます。中国5月新築住宅価格は下落率が加速しました。
1. 4-6月期GDP
中国国家統計局が5月15日発表した4-6月期実質GDPは+5.2%。市場予想の+5.1%から上振れ。前期の+5.4%から伸び率は鈍化。同統計局によると、1-6月期は前年同期比+5.3%。
同国は米国との貿易戦争が強まっているものの、米国以外への市場への多角化が奏功。
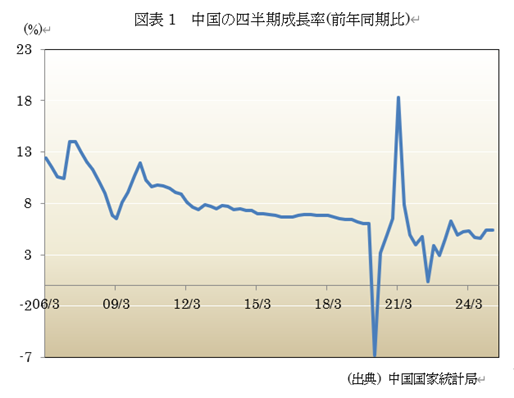
2. 5月新築住宅価格
一方、中国の新築住宅価格は5月には7か月振りの大幅下落。中国政府は不動産市場の立て直しに向けた取り組みを改めて強調。
国家統計局が16日発表したデータによると、70都市の新築住宅価格は5月には前月比▲0.22%の下落。4月の値下がり率は▲0.12%。5月の中古住宅価格は前月比▲0.5%と、8か月振りの大きな下げ。
こうしたデータは、昨年9月に打ち出された大規模な景気刺激策の効果が薄れつつあることを示唆。米国との関税合戦を巡る休戦が実現したものの、物価下落が企業利益や働き手の所得を圧迫。同国経済にはあまり恩恵が及んでいません。こうした状況が住宅購入需要の低迷に繋がっており、政策当局は需要喚起を図っています。
令和7年7月19日 インドネシア中銀利下げ
おはようございます。インドネシアの中銀は、利下げしました。
1. 6月CPI上昇率は加速
インドネシア中央統計局は7月1日に、6月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.87%になったと発表(図表1参照)。前月の+1.6%から加速。
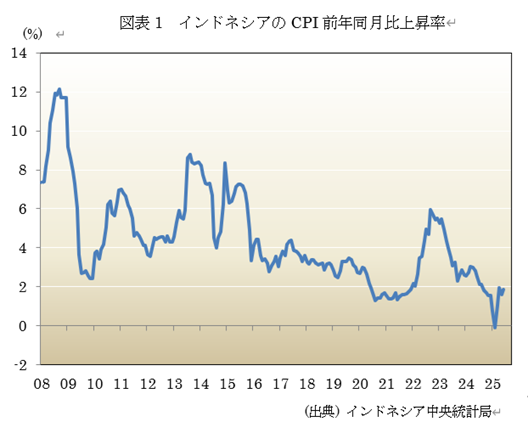
2. 政策金利を引下げ
一方、インドネシア中央銀行は7月16日の事会で、政策金利であるBIレートを▲0.25%ポイント引き下げて5.25%にすることを決定。米国との関税合意が経済にプラスになるとの見解も示唆。
昨年9月に開始した金融緩和サイクルで4回目の利下げ。国際貿易の鈍化や内需低迷を受けて景気を支援。
市場では、利下げ、据え置きの予想がほぼ半々でした。
ペリー・ワルジョ中銀総裁は会見で、今回の利下げは国内の経済成長を支えるn必要性と整合性が取れていると発表。
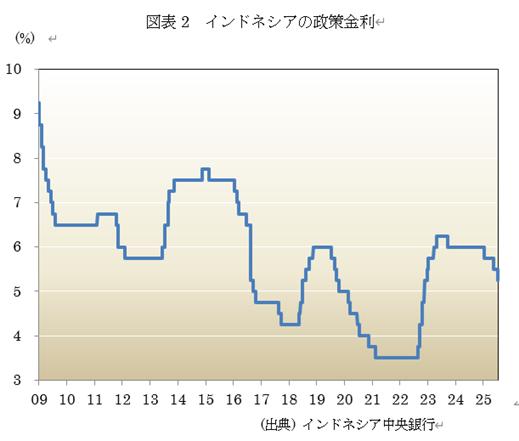
3. 1-3期GDP+4.87%に減速
インドネシア中央統計局(BPS)は5月5日に、同国の1-3月期GDP成長率が、前年同期比+4.87%になったと発表。前期の同+5.02%から減速。市場予想の4.91%から下振れ。
需要項目別に見ると、個人消費は+4.98%(前期は+4.91%)とやや加速。政府支出は+417%(同+4.62%)、固定資産投資は+5.03%(同+5.16%)と、いずれもやや減速。
の伸び悩みが成長率を下押し。
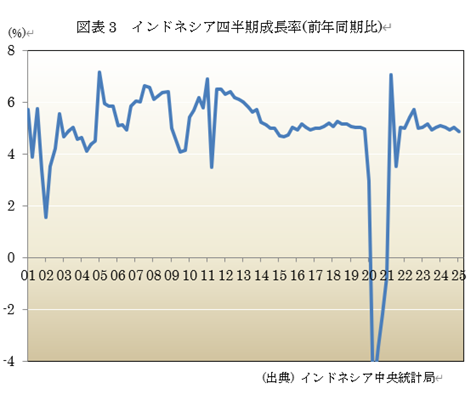
これは2021年第3四半期以来の低い伸び率であり、緊縮予算により政府支出が減少(▲1.38%、前期は+4.17%)、また、個人消費が+4.89%(前期は+4.98%)、固定資産投資が+2.12%(同+5.03%)に鈍化してことも影響しました。
貿易については、世界需要の減退により輸出が+6.78%(同+7.63%)と鈍化。国内の購買力の減少により、輸入は+3.98%(同+10.63%)と大幅鈍化。
生産面では、製造業は+4.55%(同+4.89%)とやや鈍化して、卸及び小売は+5.03%(同+5.19%)に、不動産は+2.94%(同+2.97%)とやや鈍化。鉱業は▲1.23%(同+3.95%)と、マイナスに転じました。
令和7年7月17日 中国4-7月期GDP成長率
おはようございます。中国4-7月期GDP成長率は鈍化しました。
1. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が15日発表した6月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、全月の+5.8%から伸び率が加速。市場予想の+5.7%から上振れ。
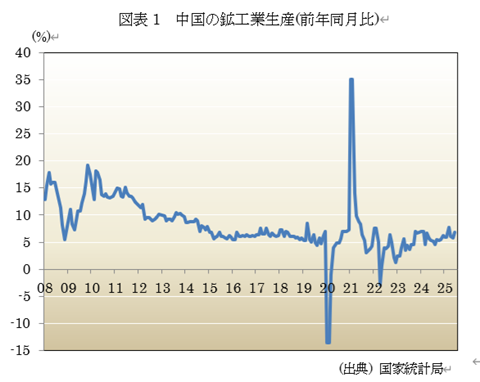
2. 2. 6月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、6月の小売売上高は前年同期比+4.8%と、前月の++6.4%から伸び率が減速。市場予想の5.4%から下ぶれ。
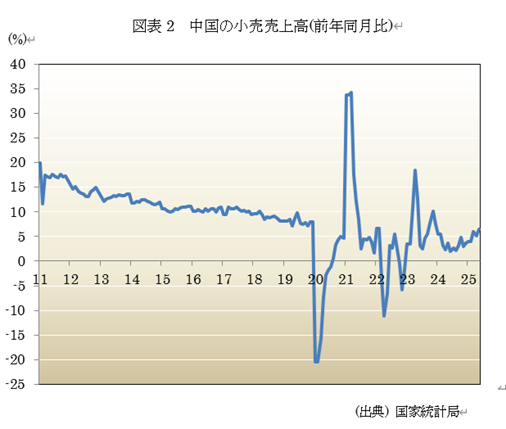
3. 1-6月固定資産投は伸び率減速
他方、国家統計局による同日発表の1-6月期の固定資産投資は、前年同期比+2.8%。伸び率は1-5月期の+3.7%から減速。
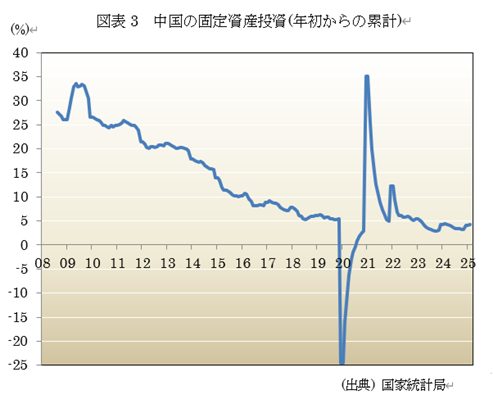
一方、同日発表の同国4-6月期国内総生産(GDP)は、実質で前年同期比+5.2%。成長率は1-3月期の+5.4%から減速。
4. 4-7月期GDP
中国国家統計局が15日発表した4-7月期実質GDPは+5.2%。市場予想の+5.1%から上振れ。前期の+5.4%から伸び率は鈍化。同統計局によると、1-6月期は前年同期比+5.3%。
同国は米国との貿易戦争が強まっているものの、米国以外への市場への多角化が奏功。
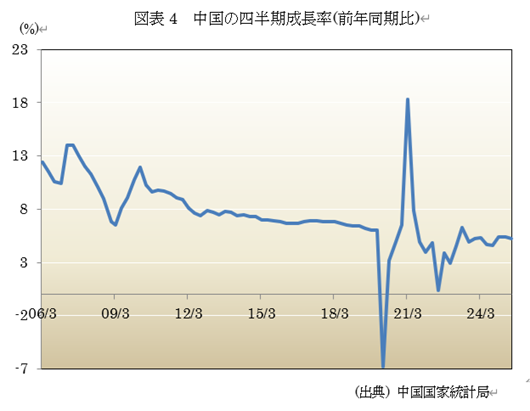
同国経済は今年、政府が掲げる「約5%」という成長目標の達成に向けて国内外から圧力を受けています。多くのエコノミストは、更なる政策支援がなければ、目標達成は困難であるとみています。
令和7年7月16日 中国6月鉱工業生産
おはようございます。中国5月鉱工業生産は加速しました。
1. 鉱工業生産は加速
中国国家統計局が15日発表した6月の鉱工業生産は、前年同月比+6.8%と、全月の+5.8%から伸び率が加速。市場予想の+5.7%から上振れ。
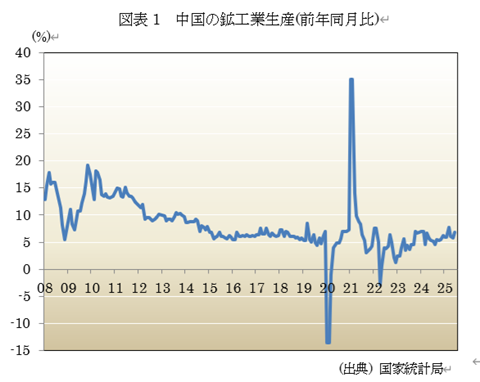
2. 2. 6月小売売上高は減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、6月の小売売上高は前年同期比+4.8%と、前月の++6.4%から伸び率が減速。市場予想の5.4%から下ぶれ。
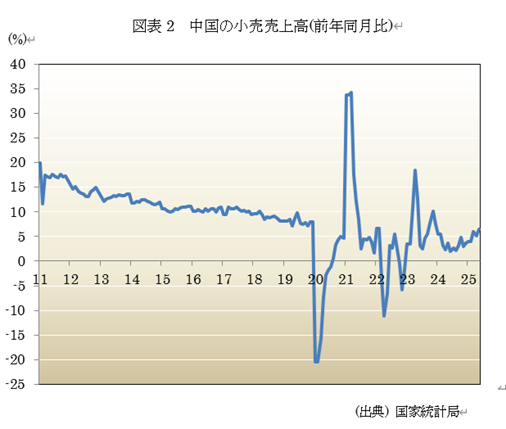
3. 1-6月固定資産投は伸び率減速
他方、国家統計局による同日発表の1-6月期の固定資産投資は、前年同期比+2.8%。伸び率は1-5月期の+3.7%から減速。
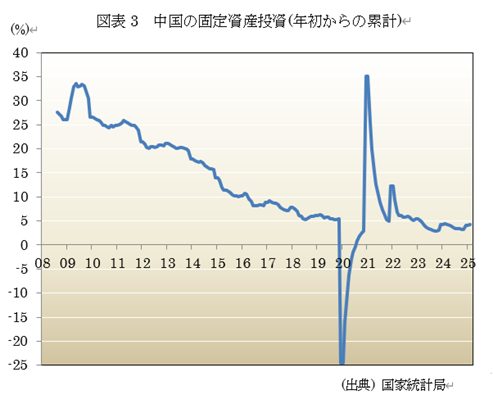
一方、同日発表の同国4-6月期国内総生産(GDP)は、実質で前年同期比+5.2%。成長率は1-3月期の+5.4%から減速。
令和7年7月15日 ブラジルの資産急落
おはようございます。トランプ政権がブラジルに50%の関税を通告。ブラジルの資産が10日には大幅に下落しました。
1. ブラジルの通貨、株式が大幅下落
ブラジルの通貨、株式が10日早朝に大幅下落。トランプ大統領が、ブラジルからの輸入品い50%の関税を課すと発表。同氏とルラ大統領の確執が高まっています。
トランプ氏はブラジルあての書簡で、ルラ氏の政敵であり、2022年の大統領瀬敗北後にクーデターを企画したとして起訴されたボルソロナ前大統領に言及。今回の関税措置について「一部hが、ブラジルによる自由選挙、米国人の基本的言論の自由への陰湿が攻撃が理由だ」として、政治と関係があることを示唆。
ボルソロナ氏は大統領在任中に、トランプ氏の政治的スタイルを模倣。同氏は法的問題に直面するたびに、度々トランプ氏に支援を求めてきました。
関税発表を受けてブラジル・レアルは対ドルで▲%近く下落。ブラジル株に連動する上場投資信託(ETF)「iシェアーズMSCIブラジルETF」も、通常取引終了後に約▲2%下落。
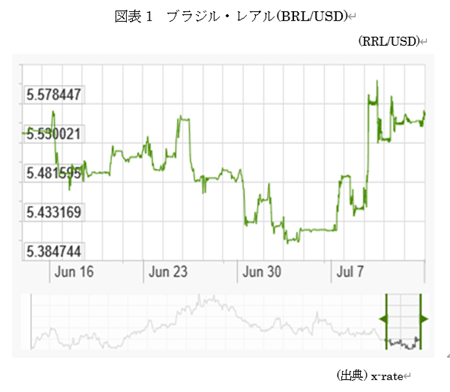
2. メキシコ、EUには30%を通告
一方、トランプ大統領は、メキシコとEU(欧州連合)に対して、30%の関税を課すと表明。自身の貿易アジェンダで、同盟国をほんろうし、世界お金融市場に不確実性を齎しています。
同氏は12日、新たな税率を通告する2通の書簡をソーシャルメディに公開。交渉で条件が改善されなければ、8月1日から適用すると通告。
同氏は各国に書簡を送り、4月に提案していた関税水準を微調整しつつ、更なる交渉を呼びかけていました。
メキシコはトランプ米大統領が12日警告した新たな30%の関税について、これを回避できる自信を示唆。最悪の事態を避けるための協議を既に開始しているとしています。
令和7年7月13日 マレーシア中銀利下げ
おはようございます。マレーシアの中銀が利下げしました。
1. CPI上昇率は鈍化
マレーシア統計庁は6月24日に、5月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.2%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月から鈍化。市場予想の+1.4%から下振れ。

2. 1-3期成長率は+4.8%に減速
マレーシア統計局は4月18日に、1-3月期の実質GDP成長率が+4.4%になったと発表(図表2参照、速報値)。前期の+5.0%からは減速。市場予想の+4.5%をも下回りました。
統計局は声明で、国内経済活動と安定した需要が第1四半期の成長を支えたと説明。統計局股間は「世界的な逆風が吹くものの、GDP成長率は国内の堅調なファンダメンタルズに支えられ、堅調に推移した」としました。
サービス部門は+5.2%と、昨年第4四半期の+5.5%から減速したものの、引き続き経済成長の主な牽引役であったとしました。小売・販売業の誇張、良好な雇用市場に加えて、主要輸出品の需要回復が世界的な課題に対する緩衝材になったと分析。
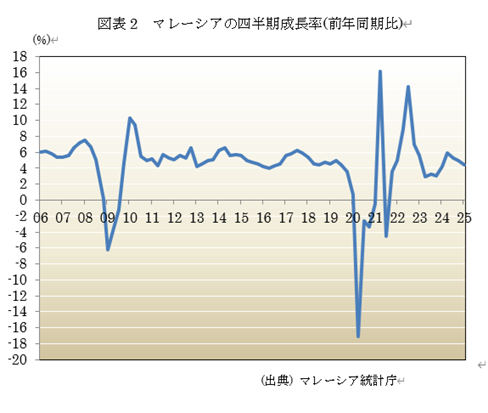
3. 政策金利を引下げ
一方、マレーシア中央銀行7月9日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を▲0.25%ポイント引き下げて2.75%にすることを決定。利下げは5年振り。成長見通しの弱さと世界貿易を巡る不確実性の高まりを背景に、景気を下支えする狙いがあります。
市場予想は、据え置きと▲0.25%引下げに分かれていました。
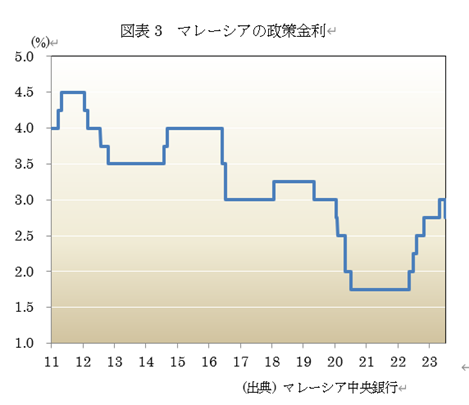
同行は、関税を巡る不確実性や地政学的緊張によって、世界経済の成長に通しが圧迫されており、世界の金融市場や商品価格の変動が大きくなる可能性があるとの見解を示唆。
令和7年7月12日 中国6月CPI
おはようございます。中国の5月CPIは、前年同月比+0.1%上昇しました。
1. 6月CPIが上昇
中国国家統計局が9日発表した6月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が+0.1%と、前月の▲0.1%からプラスに転じました。予想は横這い。
前月比では▲0.1%で、市場予想と一致。5月は▲0.2%。
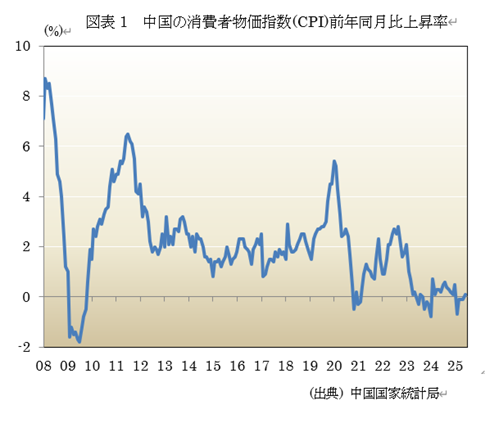
2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、6月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲3.6%と、下落幅は前月の▲3.3%から拡大。市場予想は▲3.2%。33か月連続でマイナス。
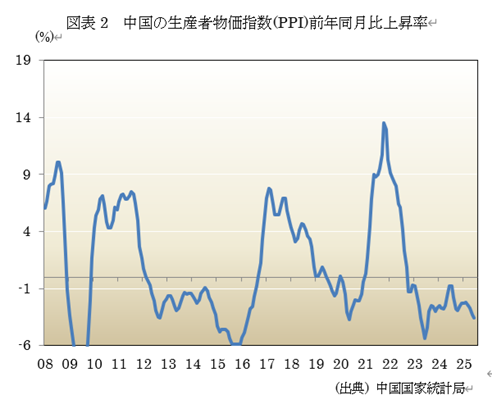
中国では内需の低迷が継続しており、企業は値下げ競争を展開。
ING銀行の中国担当エコノミストは、人民元が最近、相対的に堅調で、インフレ率も低迷しているため、中国人民銀行(中銀)は、年内の追加利下げ余地があると予想。
令和7年7月10日 BRCS首脳会議閉幕
おはようございますBRCS首脳会議が閉幕しました。
1. 「反米」色を薄める
ブラジル・リオデジャネイロ開催のBRICS首脳会議が7日、閉幕。「反米」色を薄めて加盟国を拡大。今回は米国と中国に中立を保つインドネシアも初めて参加。高関税政策をとる米トランプ政権に対して、自由貿易を標榜。グローバルサウス(新興・途上国)を取り組む考え。
「BRICSは世界の他国主義を存続させるための枠組みにねれる」と、議長国のルラ大統領は、7日、閉幕後の記者会見で強調。米国の政策などを念頭として、主権の尊重を無視する行為があるとして「時代遅れ」の国際的な枠組みを変えるよう訴えました。
ルラ氏の言葉からは、反米色を払拭しようとの意図も見えました。「BRICSはだれかと敵対するために誕生したのではない」都市、議長国を引き継ぐインドのモディ首相も「議長国としてBRICSの再定義に取り組む」との声明を発表。

2.加盟国が拡大
一方、BIRCSの歴史を振り返ると、ブラジル、ロシア、インド、中国の4か国が2009年、それぞれの頭文字を取って「BRICs」という新興国の枠組みを立ち上げ。アンナが11年に加わり「BRICS」に変更。
ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国は2009年、それぞれの国名の頭文字をとって「BRIC」という新興国の枠組みを立ち上げた。南アフリカが加わった11年に呼称を「BRICS」に変えた。
24年にはイラン、エジプト、エチオピア、アラブ首長国連邦(UAE)が加わり、インドネシアも25年に加わって10か国体制となりました。
令和7年7月6日 BYD売り上げ堅調
おはようございます。中国電気自動車(EV)大手BYDの売り上げが堅調です。
1. 5月の売上好調
中国の電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド車(PHEV)大手、比亜迪(BYD)は、2025年5月に過去最高となる38万2476台の新車販売台数と記録。今年に入って最も好調な(月)となりました。
5月に発表した大幅な値引きキャンペーンが奏功。BYDの市場戦略が引き続き中国国内外で成功を収めている今年示唆。値下げによる価格競争力の強化が、消費者の購買意欲を大きく刺戟しており、ショールームへの来客数を増加させました。

2.テスラの販売不振
一方、米電気自動車大手テスラが2日に発表した25年4-6月期の世界販売台数は前年同期比▲13%の38万4122第。イーロン・マスク氏による政治的発言などに対して消費者が反発し、不買運動も起こっていました。2四半期連続で2桁減少となり、不振が鮮明となっています。
同社の上半期のEV販売台数は72万803台。他方、中国のBYDのEV販売台数は102万33811台と、テスラを上回りました。このままで推移すると、年間でもBYDがテスラを上回る可能性が高くなっています。
令和7年7月5日 米6月雇用統計
おはようございます。米国の6月の雇用統計で、雇用者数が+13.9万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想上回る
米労働省が6月の雇用統計を3日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+14.4万人。市場予想の+11万にから上振れ。5月は14.4、万人に上方修正されました。労働市場の安定を示唆しており、米連邦準備理事会(FRB)は利下げ開始を9月以降に先延ばしするとみられます。
失業率は4.2%と、市場の予想通り。62.5万人が労働市場から離脱したことが背景にあります。
大半のエコノミストは、失業率は今年後半にかけて上昇し、FRBが9月の公開市場委員会(FOMC)で利下げを再開する可能性が高いとみています。
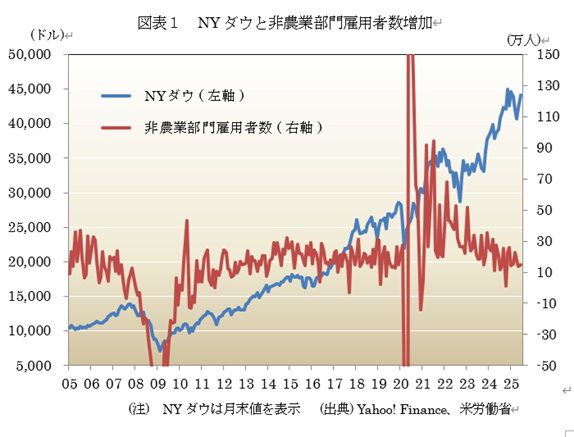
2.FRBは利下げ急がず
一方、トランプ大統領はインフレが抑制されているとして、FRBが利下げを進めるべきであると主張。只、FRB内でこの考えに賛同する向きは殆どありません。次回7月のFOMCで、利下げする可能性に言及しているのは今のところ2人に留まっています。
他の政策当局者は慎重。ボストン連銀のコリンズ総裁は26日、FRBが7月に利下げを検討するのは時期尚早であると示唆。ブルームバーグとのインタビューで、「7月の会合迄に得られるデータはあと1か月分しかない。綿澤岻はそれ以上の情報を見たいと考えている」としました。
令和7年7月3日 新興国株式投資信託年初来リターン
おはようございます。新NISA成長枠投資向けの投資信託で、年初来リターンを見ましょう。
1. 中欧株式ファンドがトップ
QUICKによると、トップは「中欧株式ファンド」の+31.47%。ポーランドなど中欧諸国は欧州連合(EU)への域内輸出が多く、トランプ関税の影響を受けにくいことなどを理由として、株価が上昇。現地通貨に対する円安もプラスの材料。
2位は「ダイワ・ブラジル株式ファンド」で、上昇率は+17.62%。3位以下もブラジル株式への投信が目立ちました。米国による関税が10%に収まったのも、ブラジル株式にとって上昇要因。
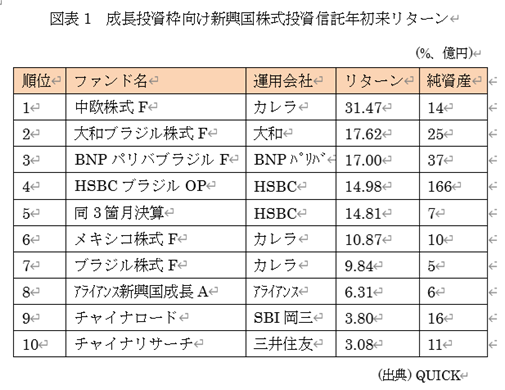
2. なぜ純資産が少ないのか
一方、ファンドの純資産総額を見ると、4位のHSBCブラジルOPを除くと、純資産は100国にも満たない少なさ。これでは運用会社にとって採算がとらず、ファンドの効率も非常に悪くなります。
嘗て、2000年代にはブラジル、中国、インドなどの株式ファンドが日本国内では大変売れていました。私自身も一時、HSBC投信に所属して、新興国株式などのファンドの組成を行っていました。
日本人は一般に、喉元過ぎれば熱さを忘れる、或いは日本人とアラブ人が相場に入ってくれば、そこで相場は終わりだ、などと言われます。
嘗て日本で注目されたグローバル・ソブリン・オープンなども、最近は全く話題に上りません。
短期的な売り買いでなく、中長期的な運用が、今こそ求められていると言えます。NISAの成長枠も、正に長期的な資産形成を目指す制度であるといえるでしょう。
令和7年7月2日 中国6月PMI
おはようございます。6月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 6月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が30日発表した6月の製造業購買担当者指数(PMI)49.7と、前月の49.5
から小幅上昇。市場予想と一致。景気判断の分かれ目となる50を3箇月連続で下回りました。
米関税の圧力や内需低迷に直面する中、経済下支えに一般の刺激策が必要であるとの見方が強まっています。
新規受注指数は5月の49.85から50.2に上昇。新規輸出受注指数は47.5から47.7に改善。
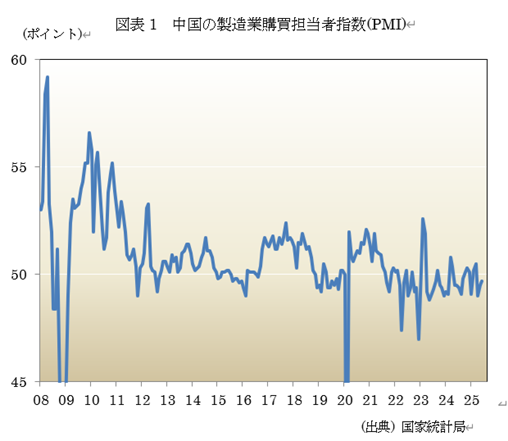
2. 非製造業PMIは上昇
一方、同日に発表した6月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.5と、前月より50.3から上昇。
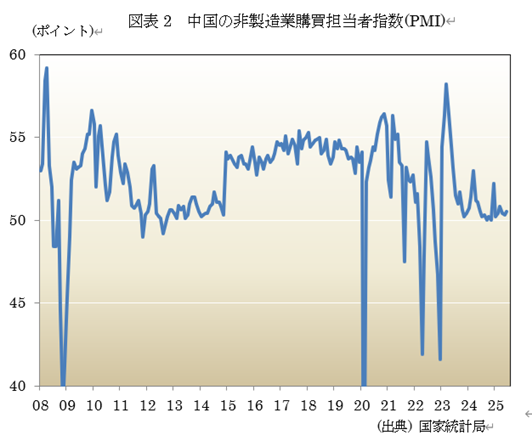
中国では引き続き不動産市況が低迷。米関税などに対する警戒感もあり、サービス業の景況感も停滞気味。
令和7年6月30日 メキシコ中銀利下げ
おはようございます。メキシコ中銀は、政策金利を引き下げました。
1. CPI上昇率は加速
メキシコ国立地理情報研究所は5月8日に、メキシコの4月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.93%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+3.8%からやや加速。市場予想の+3.9%とほぼ一致。
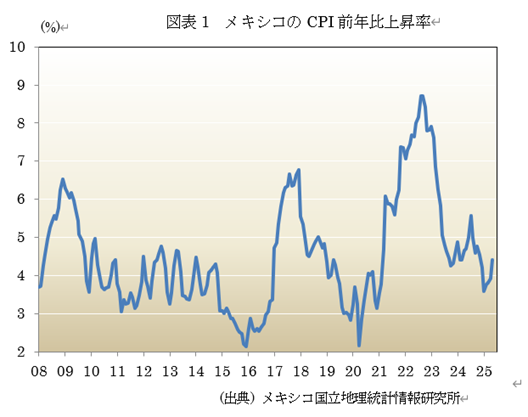
2. 1-3月期GDPは加速
メキシコ国立地理情報研究所は6月9日に、メキシコの5月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+4.42%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+3.93%から加速。

前期比では+0.2%。プラスは2四半期ぶりで、旱魃で大きく落ち込んでいた農業の復調が製造業の不振を補いました。
農畜産業などの第1次産業が+8.1%(前期は▲8.9%)と、プラスに転じました。一方、米トランプ政権による相次ぐ関税の発動の義侠に直接さらされた製造業など第2次産業は回復したものの、▲0.3%と(同▲1.2%)と、マイナス水準を継続。サービス業など第3次産業は横這い(+0.2%)でした。
同国のシェインバウム大統領は同日の記者会見で、「失業率は最低水準で、インフレも安定している。メキシコ経済は順調だ」としました。只、トランプ米大統領が発動させた鉄・アルミニウム関税は国内産業への影響が避けられず、メキシコを狙い撃ちにする25関税も大部分の課税が猶予されているに過ぎない状況です。
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は6月26日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて8.0%にすることを決定(図表3参照)。4回連続で▲0.50%の利下げ。政策金利は2022年8月以来の低水準。決定は全会一致ではなかったものの、大方の予想通り。
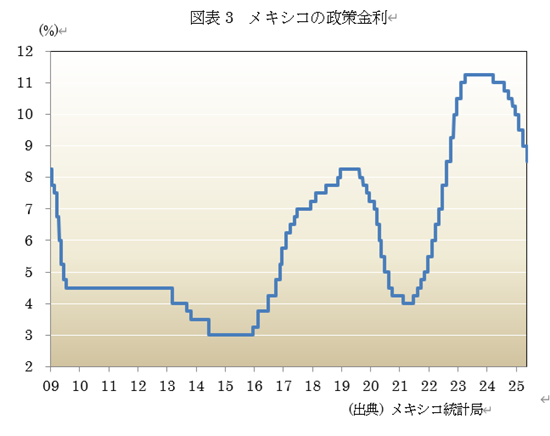
中銀は26日の声明で、年末の平均総合インフレ率見通し5月の+3.3%から+3.7%に引き上げ。2026年第3四半期に+3%に収束するとの予想を据え置き。
中銀は景気が低迷して、貿易摩擦や地政学的情勢に伴う不確実性に直面する中、インフレ抑制と景気支援という2つの課題のバランスと取ろうとしています。
令和7年6月29日 タイ中銀政策金利維持
おはようございます。タイ1-3月期GDPは減速しました。
1. 1-3月期成長率+3.1%に減速
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は5月19日に、1-3月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+3.1%になったと発表(図表1参照)。前期の+3.2%から減速。市場予想の+2.9%からは上振れ。
只、NESDCは、米国の関税により輸出が打撃を受ける恐れがあり、今年のGDP成長率予想を+2.3〜3.3%から+1.3〜2.3%に下方修正。第1四半期GDPは季節調整済み前期比では+0.7%。市場予想の+0.6%、昨年10-12月期の+0.4%30上回りました。
NEDSCは第1四半期について、個人消費と政府支出が下支え要因となったものの、消費者と企業の高水準の債務負担や世界的な貿易戦争が、年内の経済活動の重荷になるとの見方を示唆。
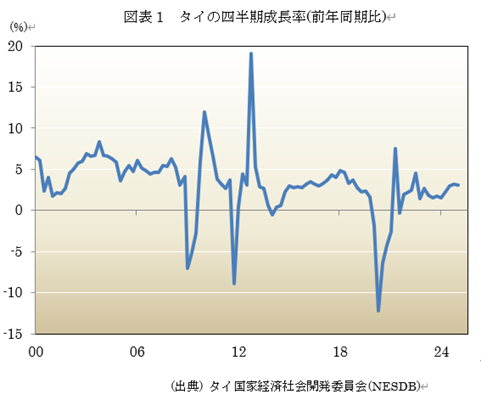
2. 5月CPIマイナスに
一方、タイ商業省は6月6日に、5月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.57%であったと発表(図表2参照)。前月の▲0.11%からマイナス幅が拡大。
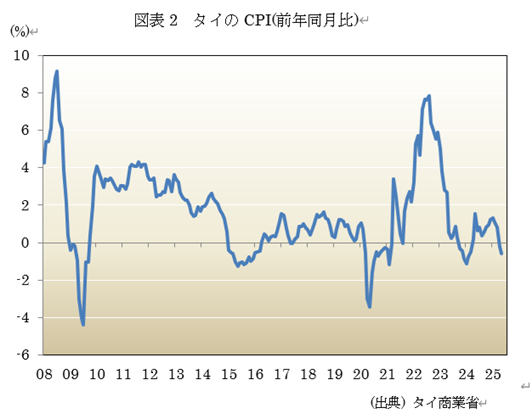
3. 政策金利を維持
一方、タイ中央銀行は6月25日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.0%で維持。国内政治の不確実性に加えて、米国の関税措置や中東情勢などの世界的リスクが重なる中、政策余地を温存。
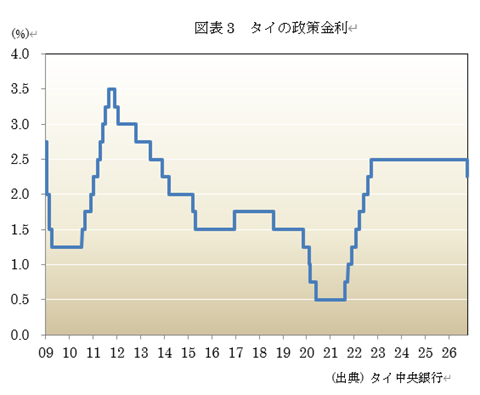
中銀の政策決定員会(MPC)では、7人中6人が据え置きを指示。市場では概ね政策金利維持を予想していました。
令和7年6月28日 中国5月新築住宅価格
おはようございます。中国5月新築住宅価格は下落率が加速しました。
1. 1-3月期GDPは+5.4%
まず、景気動向を見ておきましょう。中国国家統計局が16日発表した1-3月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。10-12月期の+5.4%から伸び率は横這い。
生産が堅調に推移したほか、米トランプ関税を警戒した駆け込み需要も見られました。只、不動産関連は引き続き低迷。
前期比伸び率は+1.2%と、前期の+16%から減速。
先進国のように前期比伸び率を年率換算した成長率は+4.9%程度。生活実感に近い名目成長率は前年同期比+4.6%。24年10-12月には+4.6%。
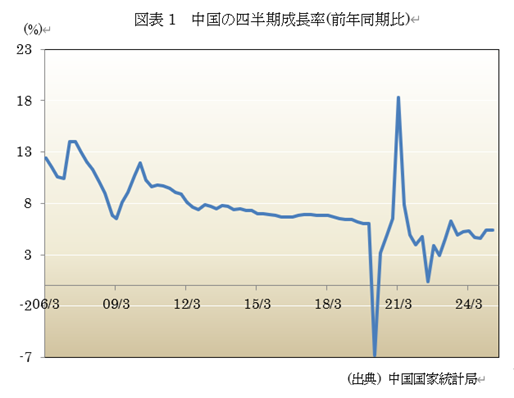
2. 5月新築住宅価格
一方、中国の新築住宅価格は5月には7か月振りの大幅下落。中国政府は不動産市場の立て直しに向けた取り組みを改めて強調。
国家統計局が16日発表したデータによると、70都市の新築住宅価格は5月には前月比▲0.22%の下落。4月の値下がり率は▲0.12%。5月の中古住宅価格は前月比▲0.5%と、8か月振りの大きな下げ。
こうしたデータは、昨年9月に打ち出された大規模な景気刺激策の効果が薄れつつあることを示唆。米国との関税合戦を巡る休戦が実現したものの、物価下落が企業利益や働き手の所得を圧迫。同国経済にはあまり恩恵が及んでいません。こうした状況が住宅購入需要の低迷に繋がっており、政策当局は需要喚起を図っています。
令和7年6月26日 世界の富裕層が大量に移住
おはようございます。世界の富裕層が大量に移住しています。
1. 中国などから大量に移住
富裕層の移住先は、単なるライフスタイルの選択に留まらず、世界経済や政治の変動を反映しています。移民と言えば、経済的に困窮した人や政治的迫害からの脱出が注目されていますが、資産100万ドル以上を持つ「ミリオネア」もまた、嘗てない程の速度で国を変わりつつあります。
2024年の予測では、12.8万人以上の富裕層が新たな国へと移住。これは一国の経済状況また政治環境のバロメーターともなり、特定の国から富裕層が大量に流出することは、その国の経済政策や社会環境への疑念を反映。
2.富裕層移住の動向
2024年に最も多くの富裕層が流出すると予想されている国のトップ10は以下の通り。
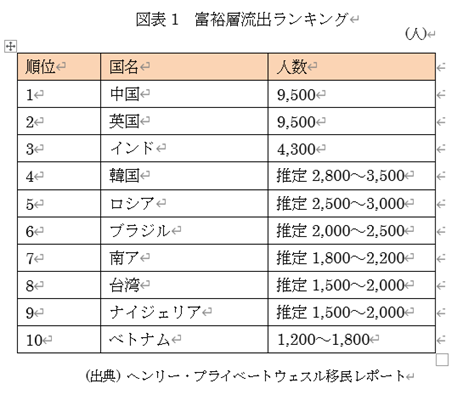
国別では、中国では長年に亘り世界で最も多くの富裕層が流出している国であり、2024年もその傾向が海賊。経済成長率の鈍化、不動産市場の低迷、政府の資本規制などが影響。
英国については、流出数が9,500人に達して、中国とならぶトップ。EU離脱後の経済不安や、高関税率などが要因。
インドについては、経済成長は続いているものの、税制の複雑さやビジネス環境の不安定さから、富裕層が海外移住を選択するケースが増加。
令和7年6月25日 米国がイランの核施設攻撃
おはようございます。米国トランプ大統領は、イランとイスラエルが停戦したと発表しました。
1. 停戦したと発表
米トランプ大統領は24日午前1時、交戦が続いていたイスラエルとイランについて「今停戦が発効した。どうか違反しないでくれ」とSNSに投稿。イスラエル首相府も同日、停戦に同意したと明らかにしました。
首相府の声明は、イスラエルはイランの核や弾道ミサイルの脅威の排除という目的を達成した、としたうえで、「いかなる停戦違反に対しても協力に対応する」としました。

2. 最大の勝者はイスラエルか
米トランプ大統領が停戦合意を発表した対イラン軍事衝突で、最大の勝者はイスラエルであると言えます。イスラエルのネタニヤフ首相は、トランプ大統領にイラン攻撃を決断させ、イランの核開発を大幅に後退させることに成功。イスラエルはイスラも玄理主義ハマスの奇襲を受けた2023年10月以降、自国に対する敵対勢力を次々に弱体化させてきました。
ネタニヤフ首相は22日、米軍によるイラン空爆のビデオ声明で、「トランプ氏の指導力は歴史の転換点を作った」と称賛。米軍参戦に導いた自身への賞さんでもあるといえます。
3. 原油価格は乱高下
一方、イランとイスラエルとの衝突により、原油価格先物のWTI先物価格はアジア時間23日午前の取引で、一時1バレル=78台を付けました。チャート上は、1月につけた80ドルが視野に入ります。ここを抜けると、23年9月につけた95ドルが節目となります。
ところが、トランプ大統領が23日夕方イスラエルとイランが「完全な停戦で合意対」とSNSに投稿。原油先物価格は急落。指標であるWTI8月ものは米伊藤ブ時間の午後6時過ぎに1バレル=65ドル代迄下落しました。
令和7年6月24日 米国がイランの核施設攻撃
おはようございます。米国がイランの核施設を攻撃しました。
1. 3つの核施設を攻撃
米トランプ大統領は22日午前11時過ぎからホワイトハウスで演説して「アメリカ軍はイランの3つの主要な核施設を標的としてダイキ後那精密攻撃を行った。われわれの目的はイランの核濃縮能力の破壊と、世界最大のテロ新国家が齎す核の脅威を阻止すること。私は世界に対して、今攻撃が軍事的に見事な成功を収めたことを報告できる」としました。又、イランの対応次第で、更に攻撃を続けると警告。
米国がイラン本土を攻撃するのは初めてで、イランが中東に展開する米軍などに報復する可能性もあり、中東の更なる軍事衝突の懸念が高まっています。

2. 国連安保理が緊急会合
一方、コクラン安全保障理事会は22日、米軍によるイラン核施設への空爆を受けて、緊急会合を開催。各国が米軍の攻撃に強い懸念を表明。アントニオ・グテレス事務総長は「戦争か対話の岐路に立っている。平和を諦めてはいけない」としました。イランは報復を示唆。米国は報復があった場合、壊滅的な反撃を警告しており、更に事態が悪化する恐れがあります。
グテレス氏は「報復の連鎖に陥る危機に直面している。これを回避するには、外交が優先去らなくてはならない」としました。国連加盟国に対して「戦闘停止に向けた断固たる行動が必要だ」としました。
令和7年5月26日 フィリピン1-3月期GDP
おはようございます。フィリピン経済が好調を持続しています。
1. 4月CPIが減速
フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は6月5日に、5月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+1.3%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+1.4%から減速。市場予想に一致。
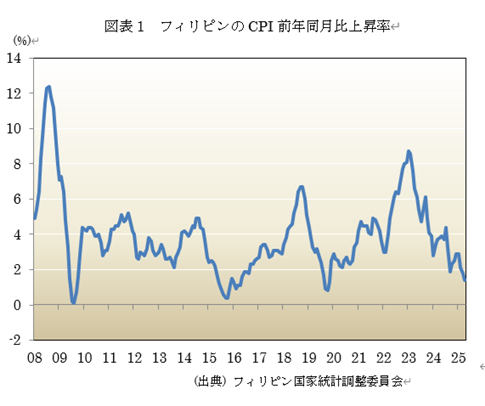
2. 政策金利を引き下げ
一方、フィリピン中央銀行は6月19日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を▲0.25%ポイント引き下げて、5.25%にすると決定(図表2参照、上限を表示)。引き下げは市場の予想通り。2会合連続。
インフレリスクの中止が必要としながらも、景気支援のために、追加緩和を実施する可能性を示唆。
レモロナ総裁は会見で、あと1回の▲0.25%ポイント利下げが可能と発言。次期は
明示しませんでした。今年はあと3回の政策決定会合が予定されています。
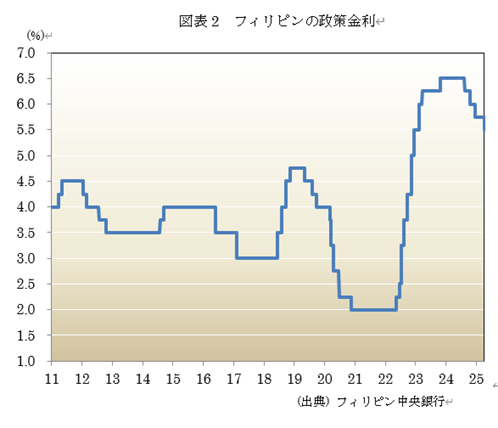
3. 1-3月GDPは伸び率加速
一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は5月8日に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.4%の伸びになったと発表(図表3参照)。市場予想の+5.7%から下ぶれ。前期の同+5.3%(確定値)から加速。
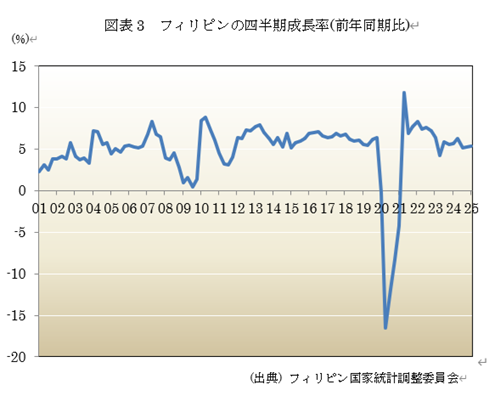
需要項目別では、消費と投資が改善。まず、民間消費は前年同期比+5.3%となり、前期の同+4.7%から加速。政府支出は同+18.7%と、前期の同+9.0%から大幅加速。総固定資本形成は+5.9%。純輸出は実質GPDへの寄与度が▲2.1%となり、前期の▲0.1%からマイナスの寄与度が拡大。
令和7年6月21日 ブラジル中銀利上げ
おはようございます。ブラジル中銀が利上げしました。
1. 政策金利を引き上げ
ブラジル中央銀行6月18日の金融政策委員会で、政策金利を+0.25%ポイント引き上げて、15.00%にすることを決定。決定は全会一致。利上げは7会合連続で、金利は2006年7月以来の高水準に達しました。
市場予想は概ね金利据え置きでした。他方、金利先物では据え置きと利上げの確率はほぼ語五分五別でした。
中銀は声明で、現在の金利を維持する方針を示唆。「委員会は利上げサイクルの中断を見込んでおり、その累積的な影響を検証して、現在の金利水準が非常に長期にわたって安定すると仮定した場合、インフレ率が目標に収束するのに十分かどうかを評価する」としました。
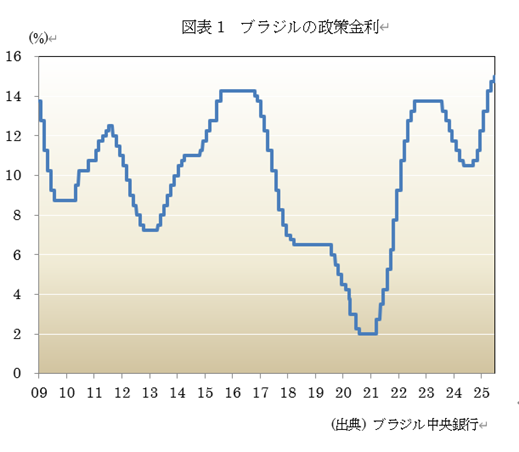
2. インフレ率が減速
一方、ブラジル地理統計院は6月10日に、5月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+5.32%と、前月の同+5.53%から伸び率は減速(図表2参照)。
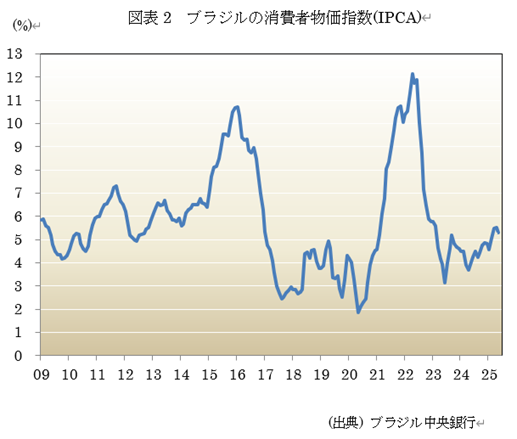
3. 1-3月期GDPは+2.9%
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は5月30に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.9%であったと発表(図表3参照)。8四半期連続でプラス成長。市場予想(+3.2%)を下回り、前期の+3.6%から減速。
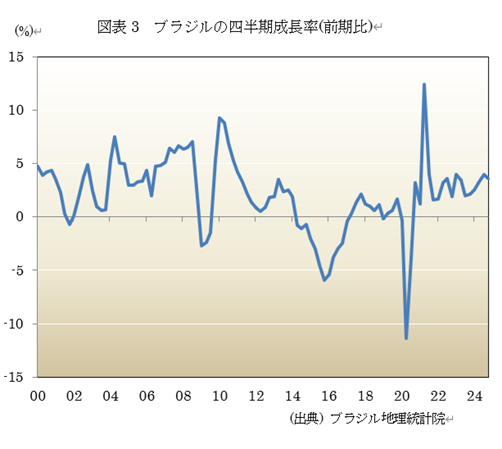
建設は+3.4%(前期は+5.1%)と鈍化し、サービス+2.1%(同+4.7%)、公的セクター+0.5%(同+1.7%)、製造業+2.4%(同+2.5%)と鈍化。一方、農業は+10.2%(同▲1.5%)と急激に回復し、公益事業+1.6%(同▲3.5%)と回復。
需要面では、個人消費は+2.6%(同+3.7%)と鈍化し、政府支出は+1.1%(同+1.2%)、固定資産投資+9.1%(同+9.4%)と鈍化。
貿易面では、輸出は+1.1%(同▲0.7%)と加速し、輸入は+14%(同+16%)と減速。
令和7年6月19日 中国5月貿易統計
おはようございます。5月の中国貿易統計で、輸出が鈍化しました。
1. 5月輸出は鈍化
中国税関総署が9日発表した5月の貿易統計によると、ドル建て輸出は前年同月比+4.8%と、前月の+8.1%から大きく鈍化。米国の関税に影響により、3箇月振りに低水準。予想の+5.0%からも下振れ。輸入は▲3.4%と、前月の▲0.2%からマイナス幅が拡大。市場予想の▲0.9%から下振れ。5月貿易黒字は1032億2000万ドルで、前月の961億8000万ドルから拡大。
世界的な貿易戦争と米中貿易関係の悪化により、中国輸出業者はこの2箇月、大幅な環境の悪化に見舞われており、世界経済の成長も阻害されています。
米中は5月半ばに、相互に発動した関税率を▲115%引き下げることで合意。上乗せ分の90日間の停止、経済・貿易関係に関する協議のメカニズムの構築も打ち出しました。
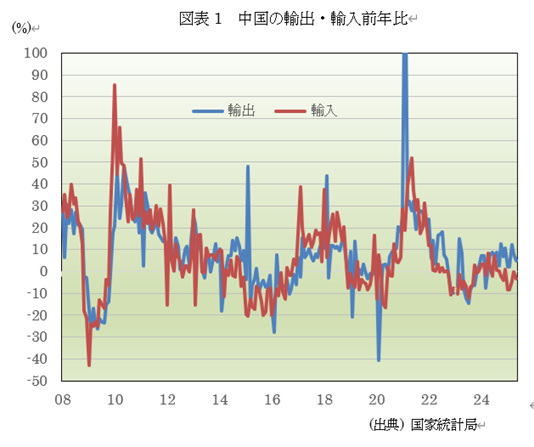
2. 中国はレアアースで対抗
一方、中国はレアアースの輸出管理を強化。同国は4月、米トランプ政権が打ち出した関税措置への対抗として、レアアース7種の輸出規制を実施して、影響が世界に広がっています。レアアースを使用した部品の供給が停滞して影響により、米国の自動車メーカーが生産停止を余儀なくされただけでなく、欧州、日本においても自動車メーカーが生産の一時停止に押し入っています。
自動車などに使うレアアースは大半が中国で算出されており、精錬のシェアは更に高くなっています。米国としては、中国に貿易面で譲歩せざるを得ない状況となっています。中国は?小平氏の時代からレアアースを戦略物資と位置付けており、長年の戦略が実ったかたちとなりました。
令和7年6月16日 イランがイスラエルに報復
おはようございます。イランはイスラエルに対して報復攻撃を行いました。
1. 核関連施設などを空爆
まず、イスラエル軍が13日、イランを攻撃。中東の二大軍事大国の対立が先鋭化しており、地域全体を巻き込んだ緊張が高まる可能性があります。
イスラエル軍は13日未明の声明で、「イランの核プログラムに対する先制攻撃を実施した」と発表。数十期の空軍機が、イランの複数地域にある各関連施設を含む数十の目標を空爆。
声明は「今、イランは核兵器の取得に嘗てない程近づいている。イランの耐性が大量破壊兵器を保有することは、イスラエルと世界にとって脅威だ。イスラエルは、イスラエルの破壊を目的とする体制が大量破壊兵器を保有することを許さない」としました。

2. イランが反撃
一方、イランは日本時間の14日未明、イスラエルに対する報復攻撃を開始。軍事精鋭部隊の革命防衛軍は弾道ミサイルや無人機で、イスラエルの軍事拠点や空軍基地などを標的にしたとしています。
イランの国営テレビは、革命防衛部隊がイスラエルに対する報復で、これまでに150の標的を攻撃したとして、「作戦は必要なだけ続く」としました。
イスラエルでは、イランによる攻撃で中部にある最大の商業都市テルアビブやその近郊などで被害が出ており、複数の地元メディアによると、これまでに3人が死亡、70人以上が怪我をしたとしています。
イスラエルでは14日午前中も、一部の地域で防空警報が出て、イスラエル軍はイランが発射した無人機などを迎撃したと発表。
令和7年6月15日 中国5月CPI
おはようございます。中国の5月CPIは、前年同月比▲0.1%下落しました。
1. 5月CPIが下落
中国国家統計局が9日発表した5月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が▲0.1%と、前月からマイナス幅が横這い。市場予想の▲0.2%からは上振れ。
4箇月連続でCPIは前年比マイナスとなっており、米国との関税の懸念、国内の需要の弱さ、失業の懸念を反映。
非食品価格は2箇月連続で横這い。住居費+0.1%(4月には+0.1%)、衣料+1.5%(同+1.3%)、ヘルスケア+0.3%(同+0.2%)、教育+0.9%(同+0.7%)に対して、輸送▲4.3%(同▲3.9)が相殺。

2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、5月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲3.3%と、下落幅は前月の▲2.7%から拡大。市場予想は▲3.2%。32か月連続でマイナス。
トランプ政権の関税により外部要因の不透明感が増大し、生産のための材料費、原材料が下落。耐久消費財、食品なども下落。
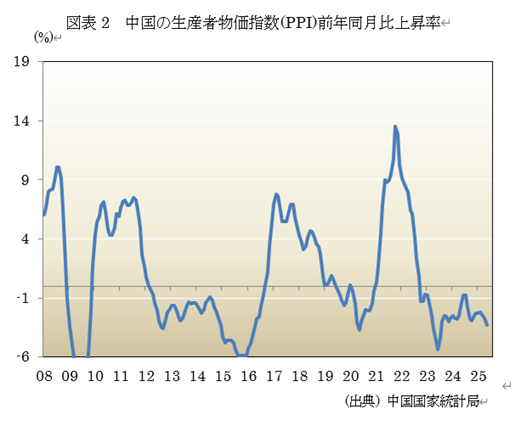
保銀投資のチーフエコノミスト、張智威氏は「中国派引き続きデフレ圧力に直面している。自動車セクターの価格競争は激しく、価格下落を齎している。又、一時安定していた不動産価格がここ数か月で再び下落都連祖を示唆している」としました。
令和7年6月14日 イスラエルがイランを攻撃
おはようございます。イスラエルがイランを先生攻撃しました。
1. 核関連施設などを空爆
イスラエル軍が13日、イランを攻撃。中東の二大軍事大国の対立が先鋭化しており、地域全体を巻き込んだ緊張が高まる可能性があります。
イスラエル軍は13日未明の声明で、「イランの核プログラムに対する先制攻撃を実施した」と発表。数十期の空軍機が、イランの複数地域にある各関連施設を含む数十の目標を空爆。
声明は「今、イランは核兵器の取得に嘗てない程近づいている。イランの耐性が大量破壊兵器を保有することは、イスラエルと世界にとって脅威だ。イスラエルは、イスラエルの破壊を目的とする体制が大量破壊兵器を保有することを許さない」としました。

2. 原油価格上昇
一方、原油価格がアジア時間13日に急騰。イスラエルがイランの首都テヘランで複数の地点を空爆。世界の原油生産の3分の1を占める中東地域での新た場衝突に対する懸念が露がっています。
北海ブレント原油は一時+5.7%上昇。1バレル=73ドルを上回りました。ウェストテキサス・インタミーディエート(WTI)も一時+6.2%上昇。
イスラエルのカッツ国防相は、「イランへの先制攻撃」が行われたとし、報復の備えて非常事態を宣言。これに先立ち、トランプ大統領はイスラエルがテヘランを攻撃する可能性が「十分ある」としていました。
オランダのINGグループで商品戦略責任者を務めるウォーレン・パターソン氏は、「地政学的リスクが高まる環境に再び戻った。原油市場は神経質な状況にあり、供給混乱の可能性を織り込んで、より大きなリスクプレミアムを反映し始めている」としました。
令和7年6月11日 インド中銀利下げ
おはようございます。インド中銀が利下げしました。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が5月13日発表した4月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+3.16%(図表1参照)。前月の+3.34%から減速。市場予想の+3.27から下振れ。
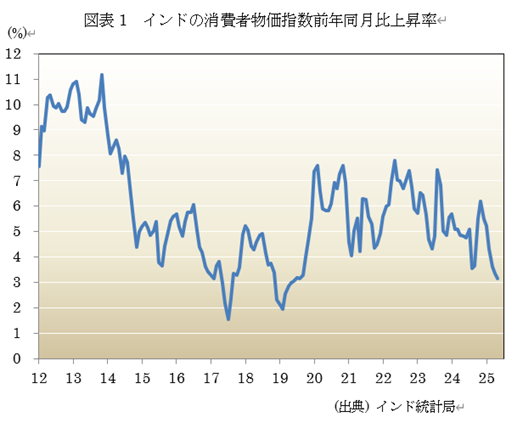
2. 1-3月期成長率+5.4%に減速
続いて、インド統計局が28日に発表した1-3月期成長率は、前年同期比+7.4%(図表2参照)。前期の同+6.4%から伸び率が加速。24年1-3月期以来となる高成長。中国を上回る成長率となってものの、米政権による関税を巡る不透明感も見られます。
25年1-3月期には建設が+10.8%、製造は+4.8%。いずれも24年10-12月期から伸びが加速。一方、同国のGDPの57%を占める個人消費は+6.0%。都市部での消費の低迷などで、10-12月期の+8.1%から減速。
10-12月期に+9.3%だった政府支出は▲1.8%。資本支出hが+9.4%。只、関税などの不確実性から、民間企業は投資を先送りする傾向にあるとみられます。
25会計年度(25年4月から26年3月)の成長率は+6.5%と予想。インド準備銀行(RBI)の予想と同じ。国際通貨基金(IMF)の推計によると、このペースで推移すると、同国は主要経済国の中で最も高い成長率を維持することとなり、25年度に4兆1800億ドルと、日本と経済規模で並ぶ可能性があります。
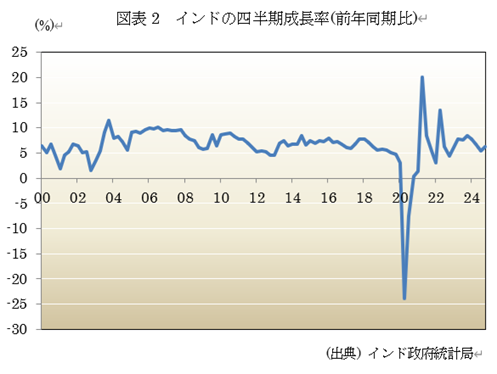
3. 政策金利を引下げ
他方、インド準備銀行(中央銀行)は6月6日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを▲0.5%ポイント引き下げて5.5%としました。3会合連続で引下げ。利下げ幅は市場の予想を上回りました。貿易摩擦により成長率見通しに不透明感が増しており、中銀は景気下支え他のために利下げ。
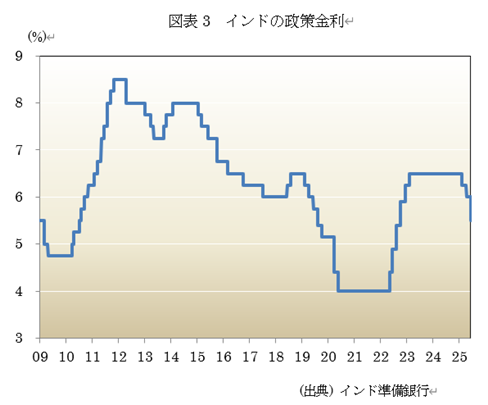
マルホトラ総裁はムンバイでのスピーチで、インフレ率が予想を大きく下回る水準に「軟化し」短期見通しも物価が持続的に目標水準に収斂するとの確信を中銀に与えていると述べました。「インド経済の構図は力強さと安定性、機会だ」と指摘。インドは現在も急ペースで成長しており、「更に高い成長率を目指している」としました。
令和7年6月10日 ブラジル1-3月期GDP
おはようございます。ブラジル1-3月期GDP成長率は、予想を下回りました。
1. 政策金利を引き上げ
ブラジル中央銀行5月30日の金融政策委員会で、政策金利を+0.5%ポイント引き上げて、14.75%にすること決定。インフレ率を政策目標レンジに近づけることが目的。又、景気変動と完全雇用を実現することも狙っています。
成長率は鈍化しつつあり、インフレ率が政策目標レンジを超えています。2025年及び2026年のインフレ率予想はそれぞれ+5.5%、+4.5%となっています。
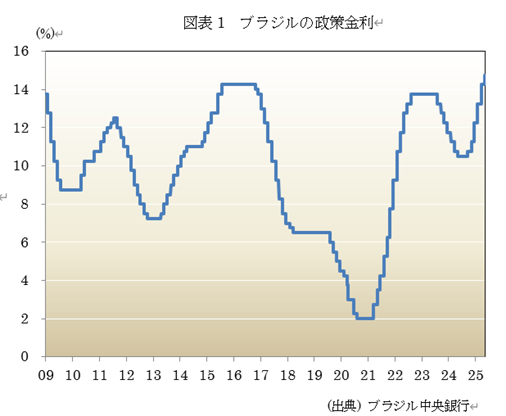
2. イインフレ率が加速
一方、ブラジル地理統計院は5月9日に、4月の拡大消費者物価指数(IPCA-15)を発表。同月のIPCAは前年同月比+5.53%と、前月の同+5.48%から伸び率はやや加速(図表2参照)。
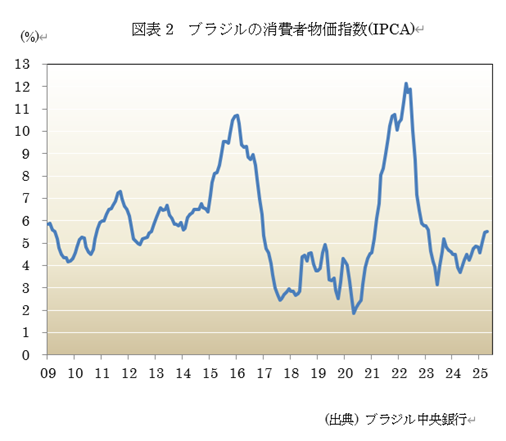
3. 1-3月期GDPは+2.9%
他方、ブラジル地理統計院(IBGE)は5月30に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+2.9%であったと発表(図表3参照)。8四半期連続でプラス成長。市場予想(+3.2%)を下回り、前期の+3.6%から減速。
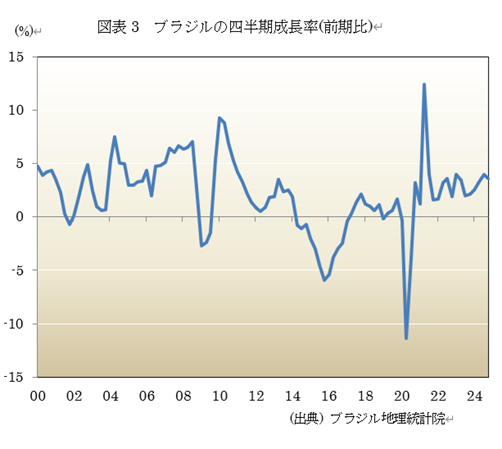
建設は+3.4%(前期は+5.1%)と鈍化し、サービス+2.1%(同+4.7%)、公的セクター+0.5%(同+1.7%)、製造業+2.4%(同+2.5%)と鈍化。一方、農業は+10.2%(同▲1.5%)と急激に回復し、公益事業+1.6%(同▲3.5%)と回復。
需要面では、個人消費は+2.6%(同+3.7%)と鈍化し、政府支出は+1.1%(同+1.2%)、固定資産投資+9.1%(同+9.4%)と鈍化。
貿易面では、輸出は+1.1%(同▲0.7%)と加速し、輸入は+14%(同+16%)と減速。
令和7年6月8日 米5月雇用統計
おはようございます。米国の4月の雇用統計で、雇用者数が+17.7万人増加しました。
1. 米国の4月の雇用統計で、雇用者数が+17.7万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が5月の雇用統計を6日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+13.9万人。前月からは減速しましたが、市場予想の+13万人を上回りました。関税措置の不確実性を背景に鈍化したものの、堅調な賃金上昇で経済が当面拡大するとの見方から、連邦準備理事会(FRB)が利下げ開始を遅らせる可能性があります。
失業率は3箇月連続で4.2%と、市場の予想通り。62.5万人が労働力から離脱したことが背景にあります。
4月の非農業部門雇用者数は+17.7万人から+14.7万人に下方修正。3月分も当初発表から+6.5万人に下方修正。労働市場の勢いの衰えが浮き彫りとなりました。
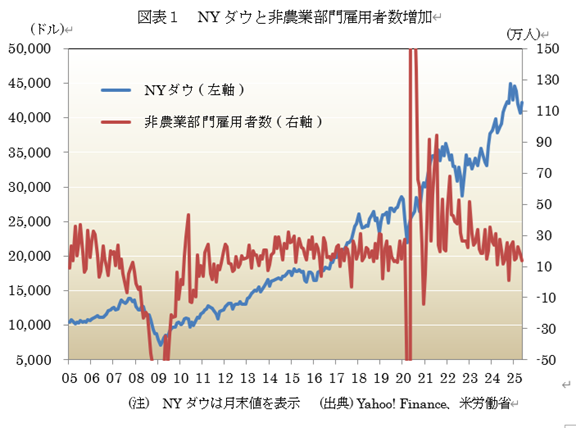
2.FRBは利下げ見送りか
一方、5月の雇用統計で、トランプ政権が掲げる関税措置による混乱が見られるものの、労働市場が堅調に推移していることが確認され、FRBは利下げを急がないとの見方が強まりました。
金融市場はこれまでも、FRBは利下げ開始を9月迄待って、12月迄に2回目の利下げを実施するとの見方がでていました。今回の雇用統計を受けて、年内の3回目の利上げが実施されるとの見方が後退。
グローバルXの投資戦略家スコット・ヘルフスタイン氏は「雇用者数が底堅く推移していることで、FRBが示唆している、忍耐強く、対応する姿勢が裏付けられた」とし、「関税交渉の進展を見守ると同時に、物価が安定していると確認するため、FRBは夏の終わりまで金利据え置く可能性が高い」としました。
令和7年6月5日 OECDが世界経済見通しを下方修正
おはようございます。OECDが世界経済見通しを下方修正しました。
1. 米関税負担重く
経済協力開発機構(OECD)は3日発表した経済見通しでは、2025年の世界の成長率を+2.9%と予想。3月時点から▲0.2%ポイント引き下げ。トランプ政権による関税引き上げを受けた貿易や投資の伸び悩みが深刻。米国では成長鈍化とインフレが同時進行すると予想。
3月には関税の影響を一部見込んで世界の経済成長率見通しを▲0.2%ポイント引き下げ。2回連続で下方修正。今回は5月時点での関税の水準を反映しており、今後の関税交渉次第では、再び下方修正される可能性もあります。
間税が経済に与える影響は米国が一番深刻。24年には平均で2%だった輸入品への税率は足下で15%と、1938年以来の高水準。米国内の物価を押し上げ。
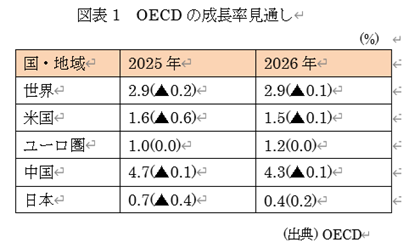
2. 米国のインフレ率予想を引き上げ
一方、OECDは世界のインフレ率予想を引き下げたのに対して、米国は逆に25年について+0.4%ポイント引き上げ。26年も+0.2%の引き上げ。
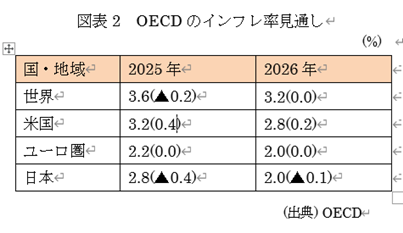
関税引き上げにより、消費者の購買力が低下。政策の不確実性が消費や投資への意欲を後退させると予想。
カナダ、メキシコ、日本など米経済と深くかかわっている国の経済も下振れすると予想。中国の見通しは、米国に比べて小幅の修正。米国の関税引き上げの他、消費の鈍化、国内の不動産市場の停滞も成長の阻害要因であるものの、政府による景気刺激差が下支えすると予想。
令和7年6月4日 トルコ1-3月期GDP
おはようございます。トルコ中銀が利下げしました。
1. 4月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が5月5日に発表した4月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+37.86%と、前月の+38.1%からわずかに減速。市場予想の+38%にほぼ一致。

2. 政策金利を引下げ
一方、トルコ中央銀行は3月6日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を▲2.5%ポイント引き下げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。利下げは市場の予想通り。利下げは市場の予想通り。
2月の消費者物価指数上昇率が鈍化。一方、食品やエネルギーなど価格変動の激しい項目を除くコアインフレは猶高止まりしており、サービス価格のインフレも根強くなっています。
政策決定と合わせた声明では、MPCは「インフレの基調的な趨勢は2月には後退。1月に特異な上昇を示唆したサービスのインフレも鈍化した」としました。
「昨年10-12月に内需は予測を上回ったものの、引き続きデフレの水準だった」として、インフレ見通しに注目しつつ「会合毎に政策金利を決定してく」としました。
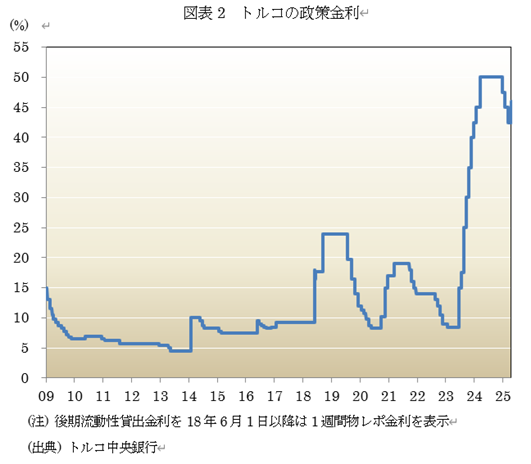
3. 1-3月期成長率+3.0%
他方、トルコ統計局が5月30日に発表した1-3月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+2.0%と、前期の+3.0%から減速。市場予想の+2.3%から下振れ。国内金融引き締め政策やイスタンブール市長逮捕に端を発した国内市場の混乱などが影響。季節調整済み前期比では+1.0%。
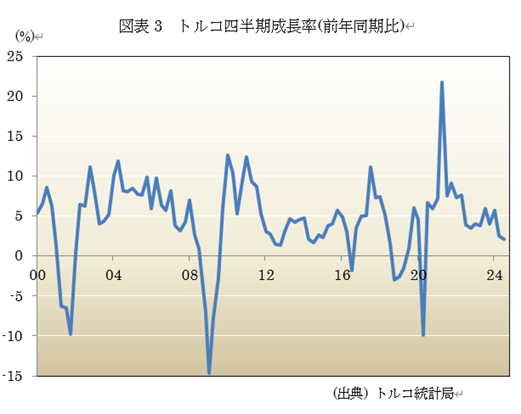
シムシェキ財務相はXへの投稿で、ディスインフレは順調に進んでおり、経済は緩やかに成長性して、消費と投資の見直しは均衡がとれているとの認識を示唆。「第2四半期の書記指標は、経済活動が緩やかなペースで継続していることを示唆している」と指摘。
その後の声明で、「成長、雇用、輸出を支援しながらディスインフレの課程で想定される悪影響を軽減するための包括的な対策を迅速に講じている」としました。
令和7年6月3日 インド1-3月期成長率加速
おはようございます。インド1-3月期GDP成長率は、加速しました。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が5月13日発表した4月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+3.16%(図表1参照)。前月の+3.34%から減速。市場予想の+3.27から下振れ。
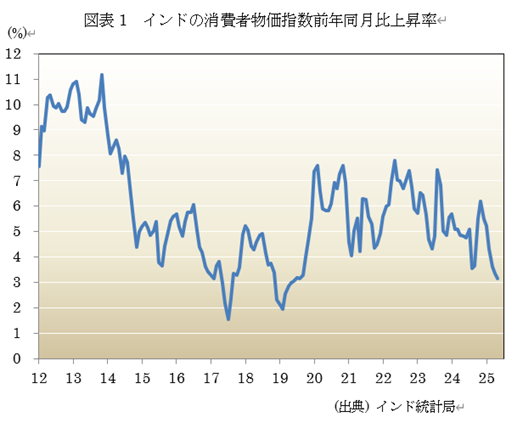
2. 1-3月期成長率+5.4%に減速
続いて、インド統計局が28日に発表した1-3月期成長率は、前年同期比+7.4%(図表2参照)。前期の同+6.4%から伸び率が加速。24年1-3月期以来となる高成長。中国を上回る成長率となってものの、米政権による関税を巡る不透明感も見られます。
25年1-3月期には建設が+10.8%、製造は+4.8%。いずれも24年10-12月期から伸びが加速。一方、同国のGDPの57%を占める個人消費は+6.0%。都市部での消費の低迷などで、10-12月期の+8.1%から減速。
10-12月期に+9.3%だった政府支出は▲1.8%。資本支出hが+9.4%。只、関税などの不確実性から、民間企業は投資を先送りする傾向にあるとみられます。
25会計年度(25年4月から26年3月)の成長率は+6.5%と予想。インド準備銀行(RBI)の予想と同じ。国際通貨基金(IMF)の推計によると、このペースで推移すると、同国は主要経済国の中で最も高い成長率を維持することとなり、25年度に4兆1800億ドルと、日本と経済規模で並ぶ可能性があります。
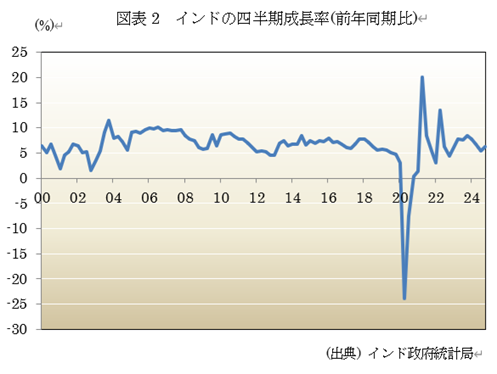
3. 政策金利を引下げ
他方、インド準備銀行(中央銀行)は4月9日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを▲0.25%ポイント引き下げて6.0%としました。利下げは市場の予想通り。インフレ率の低下、生産の鈍化、世界的な貿易に対する懸念を反映して、2022年11月以来の低い水準としました。
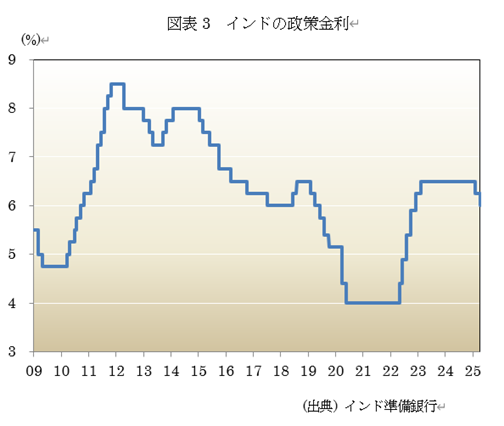
今後の見通しについては、RBIは2025-26年度GDPの予想を+6.7%から+6.5%へと引下げ。4-6月期GDPの予想は+6.5%に据え置き、7-9月期は+6.6%、10-12月期は+6.6%、1-3月期は+6.3%としました。
インフレ率の予想は+4.2%から+4.0%へと引下げ、引き続きRBIの目標レンジである+2〜6%に留まるとしました。四半期の予想ではインフレ率は4-6月期が+3.6%、7-9月期+3.6%、10-12月期+3.8%、1-3月期+4.4%としました。
令和7年6月2日 中国5月PMI
おはようございます。5月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 5月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が31日発表した5月の製造業購買担当者指数(PMI)49.5と、前月の49から上昇。市場予想と一致。景気判断の分かれ目となる50を下回り、市場予想と一致。
同PMIは前月から上昇したものの、景気判断の分かれ目となる50を2箇月連続で下回りました。米国との間で問題となっていた追加関税を引き下げることで米国と合意し、企業の間では以前ほど悲観的な見方が後退したものの、依然として景気の先行きへの懸念が強いことが窺えます。
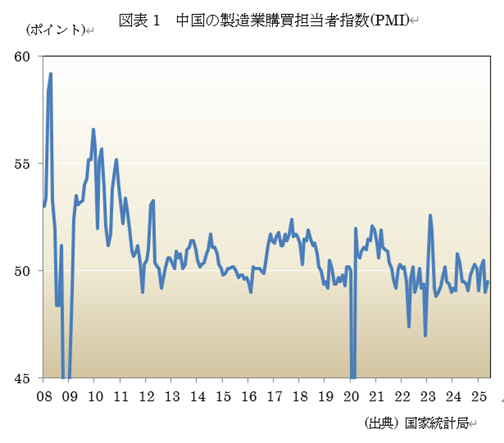
2. 非製造業PMIは低下
一方、同日に発表した5月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.3と、前月より50.8から低下。景気判断の分かれ目となる50は上回りました。
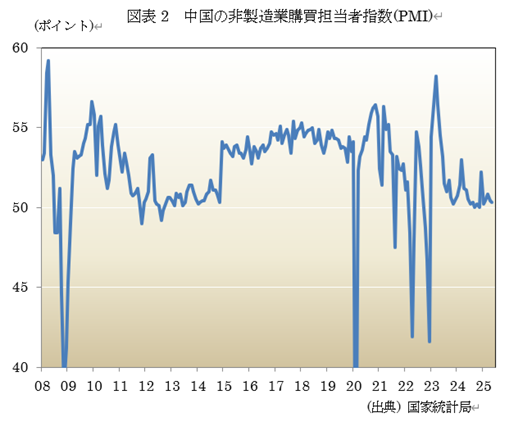
アナリストは、中国当局が更に今後金融緩和を行い、経済成長を下支えするものと予想。政策金利の引き下げ及び流動性の供給を中銀が行うものと予想しています。
令和7年4月31日 米国が中国人留学生ビザを積極的取り消し
おはようございます。インドネシアの1-3月期GDPは、減速しました。
1. 米国務長官が表明
米国のマルコ・ルビオ国務長官は28日、「中国人留学生のビザを積極的に取り消す」と表明。同長官は、国務省と国土安産保障省が連携して同留学生ビザの取り消しを進めると表明。対象には「中国共産党との繋がりのある学生や、重要分野で学ぶ学生」が含まれる」としました。
更に、」ビザの基準も改定して、中華人民共和国と香港からの全てのビザ申請に対して今後の審査を強化する」としました。
米政権は海外からの米国への留学を様が下かねない措置を打ち出しています。各国の大使館に対して、SNS審査の強化に向けて学生ビザ申請面接の新規予約を停止するよう指示。先週には、ハーバード大学の留学生受け入れ資格を取り消すと発表。その後、この措置は連邦裁判所に差し止められています。

2. 米国の科学者が流出
一方、トランプ政権の政府効率化政策や科学技術政策により、米国からの頭脳流出が顕在化。欧州や中国、新興国は失業した米科学者のスカウトを開始。4年間の窮地を救えば、米国と自国の生態系を繋ぐ橋渡し役になるとの期待もあります。
只、研究環境の違い、教授クラスの高い給与などもあり、選択肢としては欧州、カナダなどが有力。円安の効果もあり、日本は相対的の魅力が低いと見做されています。
英科学誌ネイチャーの調査によると、トランプ政権による研究環境の悪化により、米国在籍の役1600人の研究者の75%が出国の意思があるとしています。日本学術会議の三石会長は「日本よりもカナダや欧州に向いている。為替や言葉の壁は小さくない」としました。
令和7年4月29日 中国4月鉱工業生産
おはようございます。中国4月鉱工業生産は鈍化しました。
1. 鉱工業生産は鈍化
中国国家統計局が同日発表した4月の鉱工業生産は、前年同月比++6.1%と、前月の+7.7%から鈍化。市場予想の+5.5%から上振れ。
米国との貿易戦争で、世界第2位の経済大国の勢いが減速する中、米関税による痛みはまだ大きくは現れてはいません。政府の支援策が寄与した可能性があります。

2. 4月小売売上高は加減速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、4月の小売売上高は前年同期比+5.1%と、前月の+5.9%から伸び率が減速。市場予想の5.2%から下振れ。
今年の消費は、消費財の下取り策や地方自治体による商品券など、家計支出を支援する政府の取り組みによって支えられています。家電製品の売上高は+38.8%。
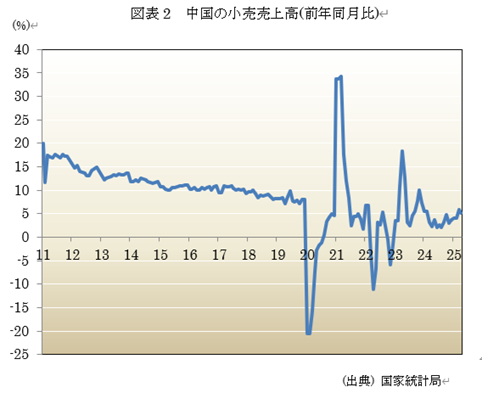
3. 1-4固定資産投は伸び率減速
他方、国家統計局による同日発表の1-4月期の固定資産投資は、前年同期比+4.0%。伸び率は1-3月期の+4.2%から減速。
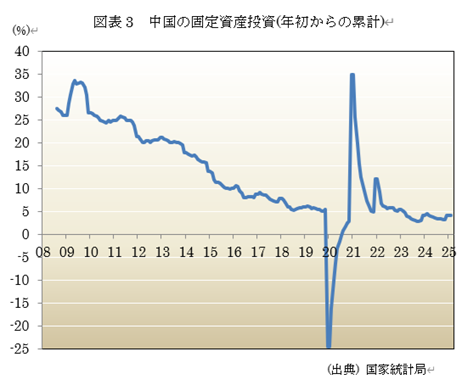
4月の新築住宅価格は前月比横這い。住宅セクターを安定化させる当局の取り組みにもかかわらず、下落圧力が継続。1-4月期の不動産投資は前年同期比▲10.3%。不動産販売は前年比▲2.8%。
更に、同統計局は4月の失業率が5.1%と、前月比▲0.1%の改善だと発表。只、米市場に大きく依存している一部工場では、従業員を一時帰休させているとしています。
令和7年5月26日 フィリピン1-3月期GDP
おはようございます。フィリピン1-3月期GDP成長率が加速しました。
1. 4月CPIが減速
フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は5月6日に、4月の消費者物価指数(CPI)上昇率が前年同月比+1.4%になったと発表(図表1参照)。伸び率は前月の+1.8%から減速。
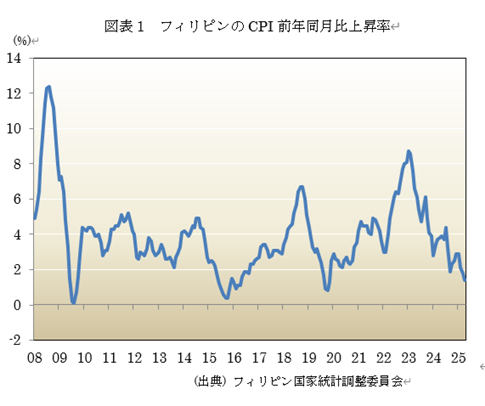
2. 政策金利を引き下げ
一方、フィリピン中央銀行は4月10日の金融政策決定会合で、主要政策金利である翌日物借入金利を▲0.25%ポイント引き下げて、5.5%にすると決定(図表2参照、上限を表示)。引き下げは市場の予想通り。
政策金利引き下げはインフレ率鈍化に伴うものであり、3月にはインフレ率は+1.8%に減速し、2020年5月以来の低水準。中銀の政策目標である+2〜4%のレンジを下回りました。又、利下げは世界的な貿易摩擦の高まりによる景気減速を下支えすることを狙っています。
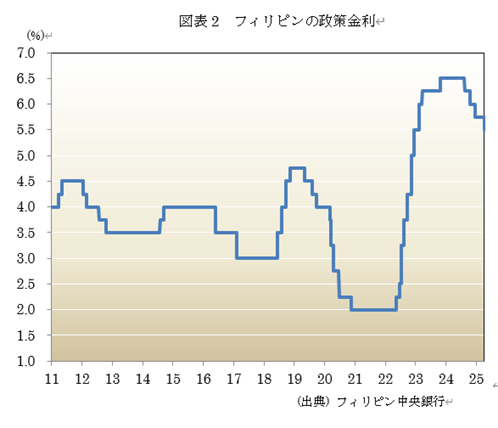
3. 1-3月GDPは伸び率加速
一方、フィリピンの国家統計調整委員会(NSCB)は5月8日に、1-3月期の実質国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比で+5.4%の伸びになったと発表(図表3参照)。市場予想の+5.7%から下ぶれ。前期の同+5.3%(確定値)から加速。
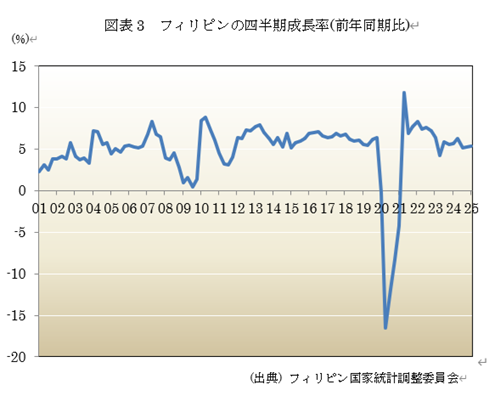
需要項目別では、消費と投資が改善。まず、民間消費は前年同期比+5.3%となり、前期の同+4.7%から加速。政府支出は同+18.7%と、前期の同+9.0%から大幅加速。総固定資本形成は+5.9%。純輸出は実質GPDへの寄与度が▲2.1%となり、前期の▲0.1%からマイナスの寄与度が拡大。
令和7年4月25日 マレーシア1−3月期成長率鈍化
おはようございます。マレーシアの1−3月期成長率鈍化は鈍化しました。
1. CPI上昇率は横這い
マレーシア統計庁は5月22日に、4月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.4%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月から横這い。市場予想に一致。
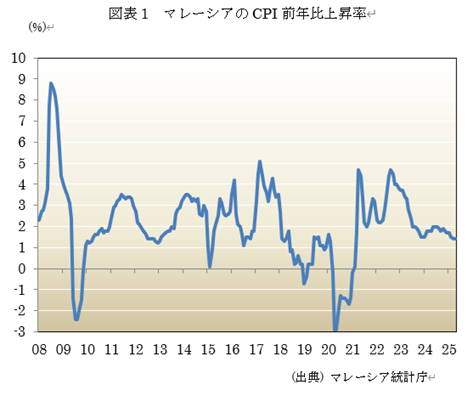
2. 1-3期成長率は+4.8%に減速
マレーシア統計局は4月18日に、1-3月期の実質GDP成長率が+4.4%になったと発表(図表2参照、速報値)。前期の+5.0%からは減速。市場予想の+4.5%をも下回りました。
統計局は声明で、国内経済活動と安定した需要が第1四半期の成長を支えたと説明。統計局股間は「世界的な逆風が吹くものの、GDP成長率は国内の堅調なファンダメンタルズに支えられ、堅調に推移した」としました。
サービス部門は+5.2%と、昨年第4四半期の+5.5%から減速したものの、引き続き経済成長の主な牽引役であったとしました。小売・販売業の誇張、良好な雇用市場に加えて、主要輸出品の需要回復が世界的な課題に対する緩衝材になったと分析。
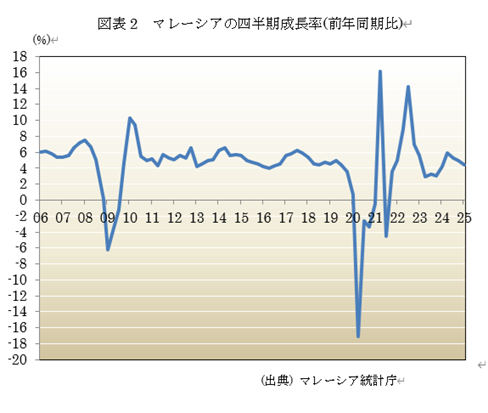
3. 政策金利を据え置き
一方、マレーシア中央銀行5月8日の金融政策決定会合で、政策金利である翌日物政策金利(OPO)を3.00%に据え置くことを決定。据え置きは市場予想通り。金利据え置きは11会合連続。
当局は、今年には、経済成長の勢いを維持しながらインフレを抑制できると予想。エコノミストは、今年いっぱいは中銀が政策金利を維持するものと予想。
中銀は成長を下支えするとして、現在の政策金利の維持は最近のインフレ及び成長見通しを整合的であるとしました。
1-3月期の総合インフレ率は+1.5%となり、世界的な穏やかなコストと抑制的な国内需要を考慮すると、今年の今後のインフレ見通しは管理可能であるとしました。
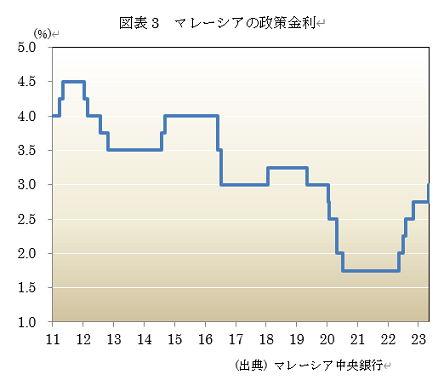
今後の見通しについては、堅調な国内需要に下支えられて成長率は底堅いと予想されるものの、貿易における緊張の高まりと世界における政策の不確実性により、外需に不透明感が高まっているとしています。
令和7年5月24日 インドネシア中銀利下げ
おはようございます。インドネシアの中銀は、利下げしました。
1. 4月CPI上昇率は加速
インドネシア中央統計局は5月3日に、4月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+1.95%になったと発表(図表1参照)。前月の+1.03%から加速。
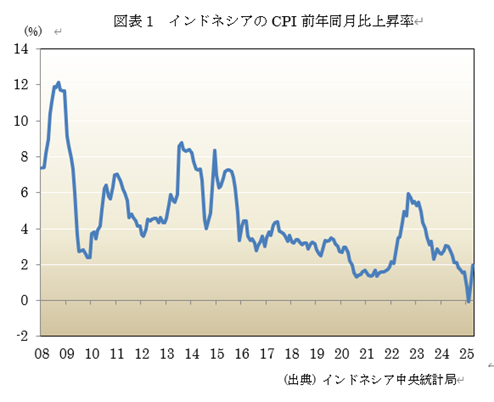
2. 政策金利を引下げ
一方、インドネシア中央銀行は5月21日の理事会で、政策金利であるBIレートを▲0.25%ポイント引き下げて5.75%にすることを決定。利下げは市場の予想通り。
利下げは、同行が2025-26年におけるインフレ率を目標レンジである+2.5%±1%ポイント以内に収めるということについての自信を反映。また、通貨ルピアを景気の下支えを狙ったものでもあります。
インフレ率は3月の+1.03%から4月には+1.95%へと加速したものの、同行の目標レンジに留まっています。
一方、ルピアは4月末から5月20日には対ドルで+1.13%し、主要な新興国に対して、またドル以外の通貨に対しても上昇。
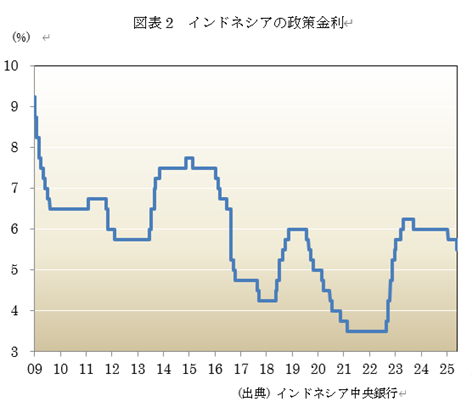
3. 1-3期GDP+4.87%に減速
インドネシア中央統計局(BPS)は5月5日に、同国の1-3月期GDP成長率が、前年同期比+4.87%になったと発表。前期の同+5.02%から減速。市場予想の4.91%から下振れ。
需要項目別に見ると、個人消費は+4.98%(前期は+4.91%)とやや加速。政府支出は+417%(同+4.62%)、固定資産投資は+5.03%(同+5.16%)と、いずれもやや減速。
の伸び悩みが成長率を下押し。
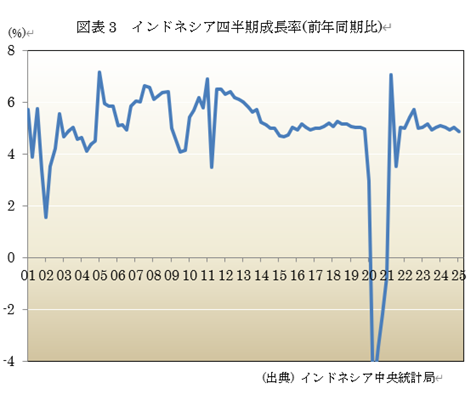
これは2021年第3四半期以来の低い伸び率であり、緊縮予算により政府支出が減少(▲1.38%、前期は+4.17%)、また、個人消費が+4.89%(前期は+4.98%)、固定資産投資が+2.12%(同+5.03%)に鈍化してことも影響しました。
貿易については、世界需要の減退により輸出が+6.78%(同+7.63%)と鈍化。国内の購買力の減少により、輸入は+3.98%(同+10.63%)と大幅鈍化。
生産面では、製造業は+4.55%(同+4.89%)とやや鈍化して、卸及び小売は+5.03%(同+5.19%)に、不動産は+2.94%(同+2.97%)とやや鈍化。鉱業は▲1.23%(同+3.95%)と、マイナスに転じました。
令和7年5月22日 メキシコペソ堅調
おはようございます。メキシコペソが堅調に推移しています。
1. メキシコペソ堅調
メキシコペソは、対ドルで堅調に推移。4月初めには1ドル=20.5ペソ程度の取引でしたが、5月20日には同19.4ペソ程度まで上昇。
メキシコは米国からの25%関税を免れる見通しとなりそれを好感した買いが入って、ペソが上昇する展開。

2. トランプ大統領が相互関税の対象から除外
メキシコのシェインバウム大統領は4月3日「他の国よりも優先的な地位が得られた」として、トランプ大統領が3日に発表した相互関税の対象からメキシコが除外された意義を強調。トランプ政権との良好な関係を構築した成果であると自賛。相互関税を多くの国が課される中、多くの国が米国への批判を売り広げる姿勢とは一線を画しました。
メキシコはカナダと共に、米国への合成麻薬フェンタニルの流入阻止対策が不十分であるなどとして、トランプ氏に間税の標的とされていました。1月のトランプ政権発足を受けて、エブラルド経済相をワシントンに派遣。ラトニック米商務長官、グリア米通商(USTR)代表らと共に協議を重ねて、信頼を醸成。
メキシコは貿易面で大きな影響を受けない見込となり、メキシコペソも上昇。カナダとは好対照な交渉結果となっています。
令和7年5月21日 タイ1-3月期GDP
おはようございます。タイ1-3月期GDPは減速しました。
1. 1-3月期成長率+3.1%に減速
タイ国家経済社会開発庁(NESDB)は5月19日に、1-3月期の国民総生産(GDP)成長率が前年同期比+3.1%になったと発表(図表1参照)。前期の+3.2%から減速。市場予想の+2.9%からは上振れ。
只、NESDCは、米国の関税により輸出が打撃を受ける恐れがあり、今年のGDP成長率予想を+2.3〜3.3%から+1.3〜2.3%に下方修正。第1四半期GDPは季節調整済み前期比では+0.7%。市場予想の+0.6%、昨年10-12月期の+0.4%30上回りました。
NEDSCは第1四半期について、個人消費と政府支出が下支え要因となったものの、消費者と企業の高水準の債務負担や世界的な貿易戦争が、年内の経済活動の重荷になるとの見方を示唆。
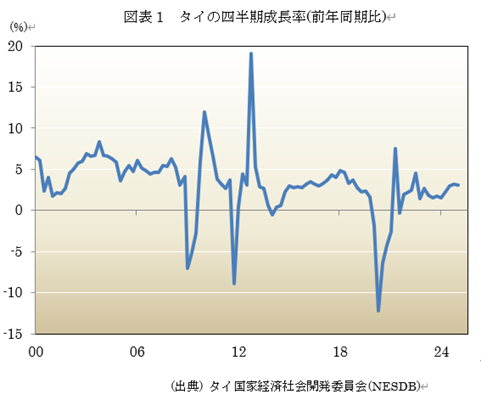
2. 4月CPIマイナスに
一方、タイ商業省は5月6日に、4月の消費者物価指数(CPI)上昇率が、前年同月比▲0.22%であったと発表(図表2参照)。前月の+0.84%からマイナスに転じました。

3. 政策金利を引下げ
一方、タイ中央銀行は2月26日の金融政策委員会で、政策金利である翌日物レポ金利を2.0%に引下げ。
引下げはMPC(金融政策委員会)において6対1で可決。市場予想は概ね金利引き下げと予想。
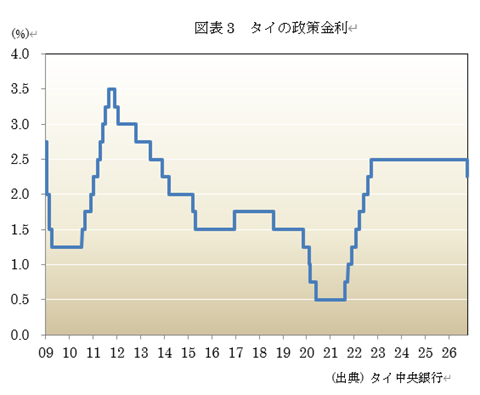
会合では、6人が経済に対する下振れリスク増大により、適切に対処するため政策金利を▲0.25%ポイント引き下げることに賛成。他方、1名は、先行きの不確実性の高まりに対応すべく、今後に金融政策の余地を残すことが重要であるとして、政策金利維持を主張。
令和7年5月20日 中国1月新築住宅価格
おはようございます。中国4月新築住宅価格は下落率が加速しました。
1. 1-3月期GDPは+5.4%
まず、景気動向を見ておきましょう。中国国家統計局が16日発表した1-3月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。10-12月期の+5.4%から伸び率は横這い。
生産が堅調に推移したほか、米トランプ関税を警戒した駆け込み需要も見られました。只、不動産関連は引き続き低迷。
前期比伸び率は+1.2%と、前期の+16%から減速。
先進国のように前期比伸び率を年率換算した成長率は+4.9%程度。生活実感に近い名目成長率は前年同期比+4.6%。24年10-12月には+4.6%。
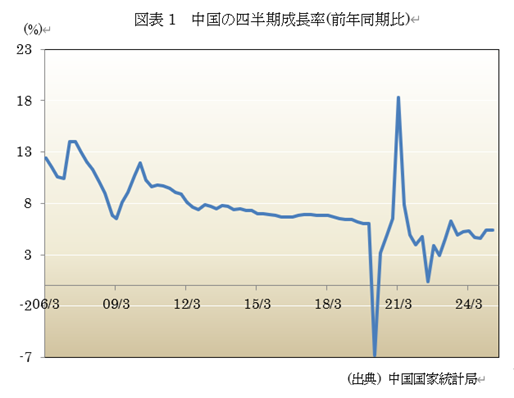
2. 4月新築住宅価格
一方、中国の住宅価格は4月に下落ペースが加速。政府は長期化している不動産不況への取り組みを強化しようとしています。
国家統計局が17日発表したデータによると、70都市の新築住宅価格は4月には前月比▲0.58%の下落。中古住宅価格は同▲0.94%。いずれもここ10年間で最大の下落率。
4月の新築住宅価格は前年比では▲3.51%。3月には▲2.7%。4月の中古住宅価格は同▲6.79%。新築も中古も2011年に現在のデータを収集し始めて以来、記録的な値下がり。
3. 中国政府、不動産支援策を巡り国有銀行や規制当局と17日協議
中国政府は住宅の過剰在庫解消に向けた提案を含め、不動産市場に関して協議するため、17日午前に主要当局者と会合を開催。
国務院はビデオ会議形式で会合を開催して、住宅都市農村建設相と金融規制当局、地方政府、国有銀行の交換や幹部が参加。
政府や金融セクターの出席予定者は幅広く、中国の指導部が自国経済を圧迫している不動産市場の低迷を終わらせる取り組みを優先しつつあることを示唆。
令和7年5月19日 ロシア1-3月期GDP
おはようございます。ロシアの1-3月期GDPは減速しました。
1. 1-3月期成長率は+1.4%
ロシア連邦統計局は5月16日、1-3月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+1.4%になったと発表(速報値)。10-12月期の+4.5%から減速。伸び率は8四半期連続でプラス成長。2025年1-3月期の+5.4%からは大幅減速。
1-3月期GDP成長率、2023年第2四半期にプラス成長に転じて以来、最も低い成長率となりました。以前に、同統計局はやや高い+1.7%になる見込であると報じていました。同統計局では今後、2025年の成長率が+2.5%と予想。一方、中銀はもっと慎重な予想であり、+1-2%程度の成長率になると予想しています。
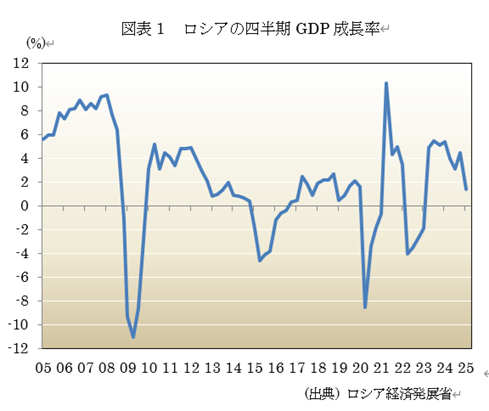
2. インフレ率減速
国家統計局から5月16日発表された4月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+10.2%と、伸び率は前月の10.3%から減速(図表2参照)。
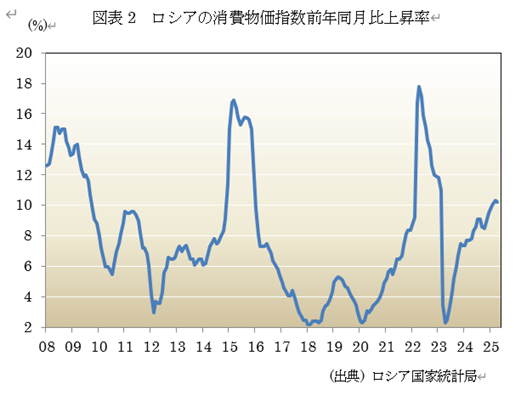
3. 政策金利を据え置き
一方、ロシア中央銀行は4月25日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を予想外に21.0%に据え置き。据え置きは4会合連続。
中銀は声明で、現在のインフレの状況について、「全体として低下傾向にあるものの、依然として高い水準にある」と指摘。今後も緊縮的な金融政策をとると説明。
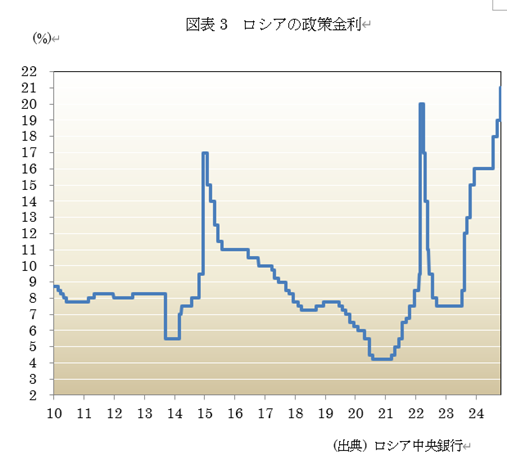
ウクライナへの侵略が長期化する中、戦時経済下による人手不足などでインフレが継続。4月のインフレ率は+10.2%と高水準で推移。中銀は今後のインフレ率の推移について、2025年末には+7-8%に低下して、26年末には目標とする+4%になるとの見通しを示唆。
令和7年5月17日 メキシコ中銀利下げ
おはようございます。メキシコ中銀は、政策金利を引き下げました。
1. CPI上昇率は加速
メキシコ国立地理情報研究所は5月8日に、メキシコの4月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.93%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+3.8%からやや加速。市場予想の+3.9%とほぼ一致。
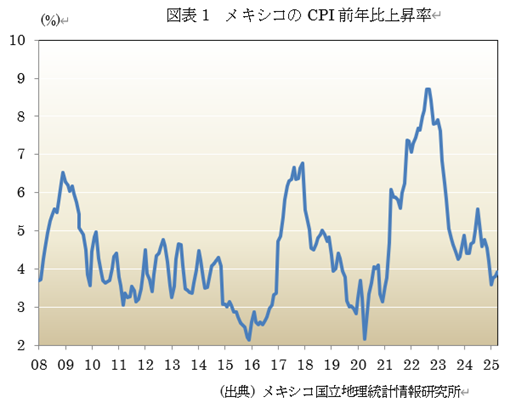
2. 1-3月期GDPは加速
メキシコ統計局は4月30日に、1-3月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+0.6%になったと発表(速報値、図表2参照)。市場予想に一致。前期の同+0.5%からわずかに加速。

前期比では+0.2%。プラスは2四半期ぶりで、旱魃で大きく落ち込んでいた農業の復調が製造業の不振を補いました。
農畜産業などの第1次産業が+8.1%(前期は▲8.9%)と、プラスに転じました。一方、米トランプ政権による相次ぐ関税の発動の義侠に直接さらされた製造業など第2次産業は回復したものの、▲0.3%と(同▲1.2%)と、マイナス水準を継続。サービス業など第3次産業は横這い(+0.2%)でした。
同国のシェインバウム大統領は同日の記者会見で、「失業率は最低水準で、インフレも安定している。メキシコ経済は順調だ」としました。只、トランプ米大統領が発動させた鉄・アルミニウム関税は国内産業への影響が避けられず、メキシコを狙い撃ちにする25関税も大部分の課税が猶予されているに過ぎない状況です。
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は5月15日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて8.5%にすることを決定(図表3参照)。3回連続で▲0.50%の利下げ。政策金利は2022年8月以来の低水準。
中銀は声明で、今後の会合でも同程度の利下げを検討する可能性があるとしました。
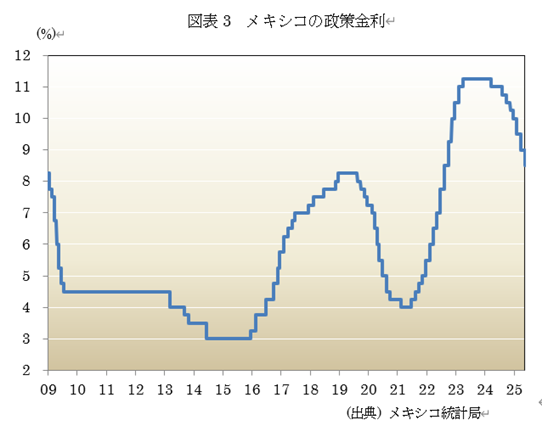
決定は全会一致で、市場予想通り。インフレ率は中銀目標内に留まっているものの、貿易を巡る不確実性が続いており、景気が軟調になっていることに対応したとみられます。
令和7年5月15日 中国4月CPI
おはようございます。中国の4月CPIは、前年同月比▲0.1%下落しました。
1. 4月CPIが下落
中国国家統計局が10日発表した4月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が▲0.1%と、前月からマイナス幅が横這い。市場予想と一致。前月比では+0.1%で、3月の▲0.4%からプラスに転じました。変動の激しい食品と燃料価格を除いたコアインフレ率は3月と同じ+0.5%。
住宅市場や雇用不安を背景とする個人消費の減速と共に、米国との貿易戦争も影響。
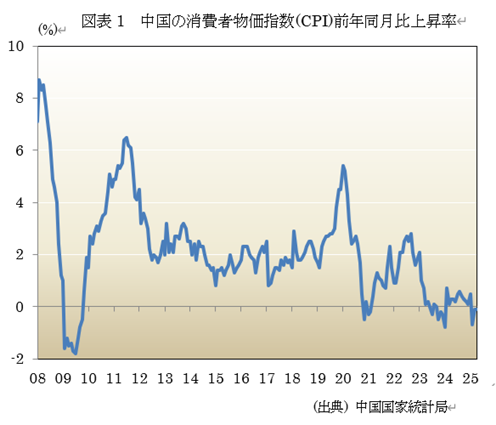
2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、4月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.7%と、下落幅は前月の▲2.5%から拡大。市場予想は▲2.8%。

上海保銀投資管理のチーフ・エコのミスト、張智威氏は「以前、デフレ圧力が継続。輸出の減速が予想され、デフレ圧力は古語数か月継続する可能性がある」としました。
令和7年5月14日 米中が関税引き下げで合意
おはようございます。米中が関税引き下げで合意しました。
1. 関税大幅引き下げで合意
米中両国が、互いの関税を▲115%引き下げることで合意。
米ベッセント財務長官と中国の何立峰副首相は、今月10日からスイスで関税を巡る協議を行に、両国が共同声明を発表。
共同声明では「2国間の経済・貿易関係の重要性を認識する」として、追加関税を相互に▲11.5%引き下げることで合意したとしました。
これにより、米国の中国への関税は145%から30%に、中国の米国への関税は、125%から10%に低下。只、引き下げた関税のうち24%については、90日間の停止で、協議を継続するとしています。
これによりアメリカの中国への関税は145%から30%に、中国のアメリカへの関税は、125%から10%に下がります。しかし引き下げた関税のうち24%については90日間の停止で、協議を継続するという事です。
両国をめぐっては、実質的に貿易がストップする事態となっていましたが、経済への悪影響が広がる中、双方が大幅に譲歩する形となりました。

2. 米中の対立継続か
一方、米トランプ大統領は、台湾に対する政策については、明示せず。台湾を巡って、今後米中両国が争う可能性があります。
米トランプ政権は、今回中国との関税引き下げで中国と合意したものの、自動車、半導体などでは、引き続き中国に対して高い関税を課す可能性があります。
中国は引き続き「一帯一路」を推進して、米国に対抗する外剛政策などを推進する構え。米中は、今後様々な場面で、引き続き対立するものを予想されます。
令和7年5月12日 中国4月貿易統計
おはようございます。4月の中国貿易統計で、輸出が増加しました。
1. 4月輸出は増加
中国税関総署が9日発表した4月の貿易統計によると、輸出は予想を大きく上回るペースで増加。米トランプ政権による90日間の上乗せ関税停止期間に対米輸出を急いだ海外メーカーからの需要が寄与。一方、輸入は予想よりもかなり小幅な減少に留まりました。
輸出は前年同月比+8.1%。市場予想は+1.9%。米国が中国への関税を145%に引き上げる前のかけこみ需要があった3月の+12.4%からは鈍化。
輸入は同▲0.2%と、3月の▲4.3%から大幅に改善。市場予想は▲5.9%。政府の景気下支えにより内需が回復しつつあることを示唆。

2. トランプ大統領対中関税引き下げを示唆
一方、米トランプ大統領は9日、中国との貿易協議を控えて、対中関税の引き下げを示唆。
同氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「中国への関税は80%が妥当だと思う」と投稿。現在の145%(一部製品は最大245%)から引き下げる考えを示唆。
さらに「スコット・ゲンセント財務長官に言及し、「スコット・Bの判断次第だ」としました。ベンセント氏はスイス・ジュネーブで中国の何立峰副首相と会談して、国際市場を揺るがしている対立の鎮静化を図る予定。
令和7年5月10日 印パ両国の衝突が拡大
おはようございます。印パ両国のカシミール地方などでの衝突が拡大しています。
1. 国連安保理事会で協議
国連安全保障理事会は、軽装地域カシミール地方で4月に発生した観光客襲撃事件を巡って、関係が悪化しているインドをパキスタンに対して、緊張を緩和して軍事衝突を避けるよう促しました。
パキスタン外務省によると、安保理は5日に会合を開催。インド、パキスタン情勢、インドの行動による「差し迫った脅威」を示す情報について説明がありました。「彼ら(安保理メンバー)は、緊張を緩和して、軍事対立を避けるために、対話と外交を求めた」としました。
パキスタンは現在安保理の非常任理事国。5日の会合前に、理事国と協議を行いました。多くの理事国が、パキスタンによる最近のミサイル発射実験と核を巡る発言が事態をエスカレートさせる要因として懸念を示唆したとしました。

2.印パ双方が攻撃
パキスタン政府は、インド側から新たに無人機による攻撃を受けたと発表。インド側は逆に、パキスタン側からミサイル攻撃を仕掛けられたなどとして、双方の軍事的緊張が高まっています。
パキスタン軍の報道官は、7日夜から8日にかけて、パキスタン国内の各地でインド軍の無人機による攻撃を受けたと発表。無人機25機を撃ち落としたとしました。
一方、インド政府は逆に、パキスタン側から、7-8日にかけてインド北部や西部の軍事施設にミサイルや無人機による攻撃を仕掛けられたとしています。これを受けて、軍がパキスタン各地の防空レーダーを攻撃し、東部ラホールでは防空システムを破壊したとしました。
令和7年5月8日 中国太陽光パネル価格下落
おはようございます。中国の太陽光パネルの価格が大幅に下落しています。
1. 太陽光パネルが生産過剰
太陽光パネルが大幅下落。世界市場をほぼ独占している中国の生産過剰が主な原因。ここ1年で半値に落ち込みました。今後も過剰生産が続く可能性が 高く、更に価格が下落すると予想されます。安価な中国製品が世界中に流布。エネルギーの安全保障上からは一国に頼るのは、リスクがあるといます。
日本総合研究所の調査によると、中国の太陽光パネルの平均輸出単価は今年5月時点
54.1ドルと、昨年5月の102.3ドルから半減。中国の生産過剰が原因で、日本総合研究所の野木稔研究員は「多くの国の関連企業が激しい価格競争に陥っている」としました。
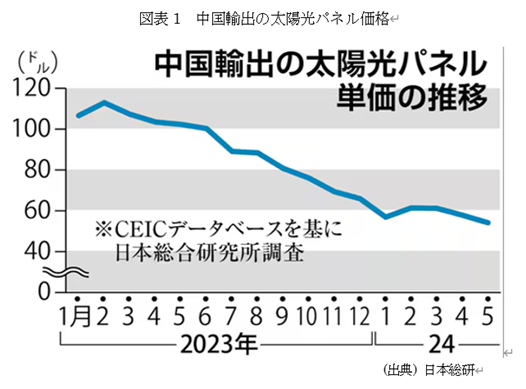
2.中国がデフレ輸出へ
中国では供給サイドの景気が底入れする一方、需要サイドは内需が弱く力強さを欠いています。需給ギャップ拡大の懸念があり、外需は堅調である者の、いわゆる「デフレの輸出」が顕在化。世界経済は中国の景気動向に振り回さる展開となりつつあります。
製造業PMIなどの指標で見ても、内需の弱さが目立っています。受注が弱含んでおり、非製造業PMIも弱含み。幅広い業種でデフレ傾向が強まっており、デフレ輸出が加速する可能性があります。中国政府は成長率の回復を目指しており、デフレ輸出が加速することとなりそうです。
令和7年5月6日 印パ両国が衝突
おはようございます。印パ両国がカシミール地方で衝突しました。
1. 両国がカシミール地方で衝突
インドとパキスタンが領有権を争っているカシミール地方で先週、武装勢力の襲撃により多数の死者が出た事件を巡って、米国は両国に対して、緊張の緩和と衝突の回避に向けて努力するよう要請。
ルビオ米国務長官が4月30日に両国の高官と協議して、「南アジアの平和と安全の維持を要請。国務省の声明によると、ルビオ氏はパキスタンのシャリフ首相に対して、今回の襲撃を非難したうえで、直接的な対話を再開すべきであるとしました。ルビオ氏はインドのシンシャルカル外相とも協議。
インドとパキスタンは長年に亘り対立してきましたが、襲撃事件を契機に関係が急速に悪化。インドと米国はこの事件を「テロ行為」と断定。インドのモディ政権はパキスタンの関与を主張。責任を追及する構え。パキスタンは関与を全面的に否定して、インドが軍事行動を取れば報復すると警告。

2.4月22日にテロ発生
今回の対立のきっかけは、4月22日にカシミール地方で発生したテロ事件。年間数万人と訪れる風向名義那観光地バハルガムで26人の観光客が武装勢力に銃殺されました。このうち25人はインド人。
声明を発表したのはイスラーム組織「抵抗戦線」。同戦線は2020年以来、カシミール地方で賃部隊、ジャーナリスト、民間人などへの襲撃を頻繁に行っており、昨年6月にはインド人巡礼者を含む10人を殺害。
同戦線はパキスタンの支援を受けているとされており、両国の対立が一気に高まりました。
令和7年5月4日 米4月雇用統計
おはようございます。米国の4月の雇用統計で、雇用者数が+17.7万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が4月の雇用統計を2日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+17.7万人。市場予想の+13万人を上回りました。
雇用者数の伸びは、4月には小幅に鈍化。雇用主は雇用者の確保を進めているものの、トランプ大統領の保護主義的な貿易政策が不確実性と高めており、労働市場の見通しは悪化しつつあります。
3月は+22.8万人から+18.5万人に下方修正。2月も▲1.5万人下方修正されて10.2万人となりました。
失業率は4.2%で前月から横這い。予想も4.2%。第1四半期GDPが縮小したことを受けて浮上した景気後退懸念は和らぎました。只、他ランプ大統領の次々に変化する関税政策の影響が労働市場の現れるには時期尚早と見られます。
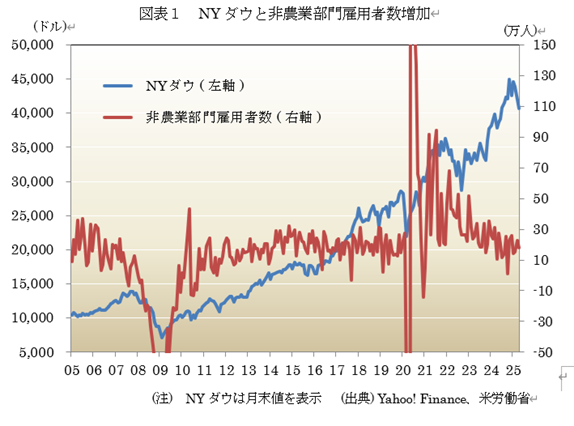
2.FRBは利上げ見送りか
一方、米連邦準備理事会(FRB)は6−7日、金融政策を協議する連邦公開市場委員会(FOMC)を開催します。トランプ政権の「相互関税」など高関税政策による物価、雇用への影響を見極めるため、主要政策金利を維持する見通し。
金利を据え置けば、3会合連続。原稿は、短期金利のFFレート誘導目標を4.25〜4.5%としています。
トランプ大統領は、インフレは解消した、などとして、景気を刺激する利下げを自身の交流サイトなどで求めています。一方、パウエルFRB議長は、利下げに慎重な姿勢を取っており、4月16日の講演では、高関税政策を「予想をはるかに上回るものだ」とし、インフレ加速や成長鈍化に対する警戒感を示唆。
令和7年3月3日 メキシコ1-3月期GDP
おはようございます。メキシコ1-3月期GDPは、加速しました。
1. CPI上昇率は減速
メキシコ国立地理情報研究所は4月9日に、メキシコの3月の消費者物価指数(CPI)が、前年同月比+3.8%になったと発表(図表1参照)。上昇率は前月の同+3.77%からわずかに加速。市場予想と一致。
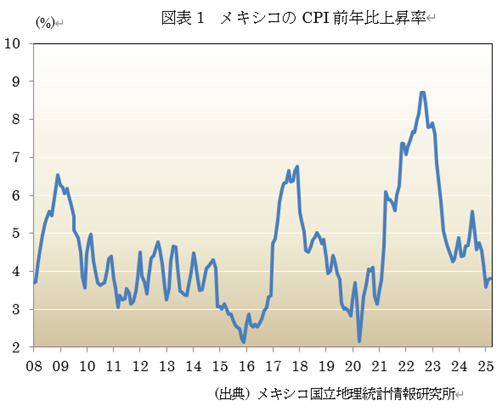
2. 1-3月期GDPは加速
メキシコ統計局は4月30日に、1-3月期季節調整済み国内総生産(GDP)成長率は、前年同期比+0.6%になったと発表(速報値、図表2参照)。市場予想に一致。前期の同+0.5%からわずかに加速。

前期比では+0.2%。プラスは2四半期ぶりで、旱魃で大きく落ち込んでいた農業の復調が製造業の不振を補いました。
農畜産業などの第1次産業が+8.1%(前期は▲8.9%)と、プラスに転じました。一方、米トランプ政権による相次ぐ関税の発動の義侠に直接さらされた製造業など第2次産業は回復したものの、▲0.3%と(同▲1.2%)と、マイナス水準を継続。サービス業など第3次産業は横這い(+0.2%)でした。
同国のシェインバウム大統領は同日の記者会見で、「失業率は最低水準で、インフレも安定している。メキシコ経済は順調だ」としました。只、トランプ米大統領が発動させた鉄・アルミニウム関税は国内産業への影響が避けられず、メキシコを狙い撃ちにする25関税も大部分の課税が猶予されているに過ぎない状況です。
3. 政策金利を引き下げ
メキシコ銀行(中央銀行)は3月27日の金融政策決定会合で、政策金利を▲0.5%ポイント引き下げて9.5%にすることを決定(図表3参照)。2回連続で▲0.50%の利下げ。決定は全会一致で、市場の予想通り。中銀は声明で、今後の会合でも、▲0.5%利下げを検討する可能性があるとしました。
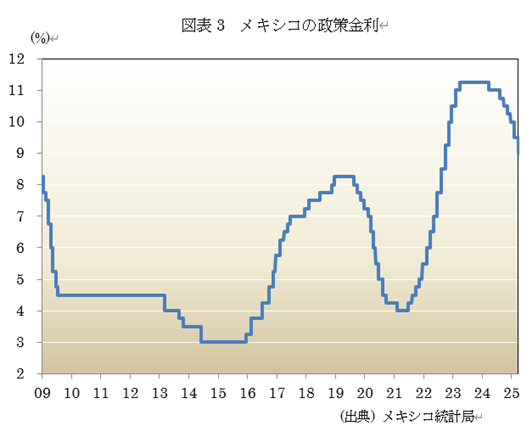
同国ではインフレが鎮静化しており、4月のインフレ率は+3.8%と、依然として呈す順。中銀の政策目標である+3%±1%ポイントの範囲に収まっています。只、中銀は米国の経済政策の変更により、中銀の経済予測に不確実性が生じているとして「インフレ圧力が両方向に動く可能性がある」と指摘。
令和7年5月1日 中国4月PMI
おはようございます。4月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から低下しました。
1. 4月製造業PMIは前月から低下
中国国家統計局が30日発表した4月の製造業購買担当者指数(PMI)49.0と、前月の50.5から低下。市場予想と一致。景気判断の分かれ目となる50を下回り、市場予想の49.8から下振れ。
生産者は米国の関税を見越して出荷を前倒ししてきたものの、関税導入により、そうした戦略は終了して、政策当局者に景気刺激策を求める声が高まっています。
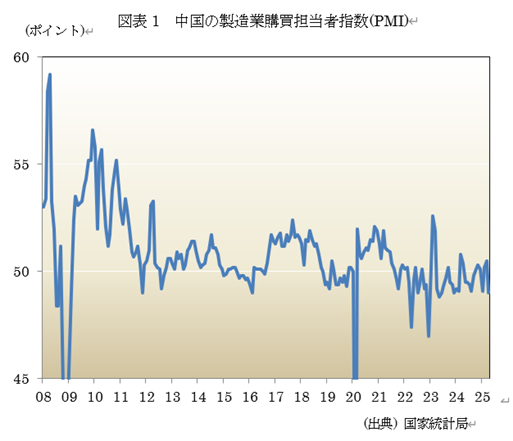
2. 非製造業PMIも低下
一方、同日に発表した4月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.4と、前月の50.8から低下。製造業とサービス業の両方を含む総合PMIは50.2と、3月の51.4から低下。
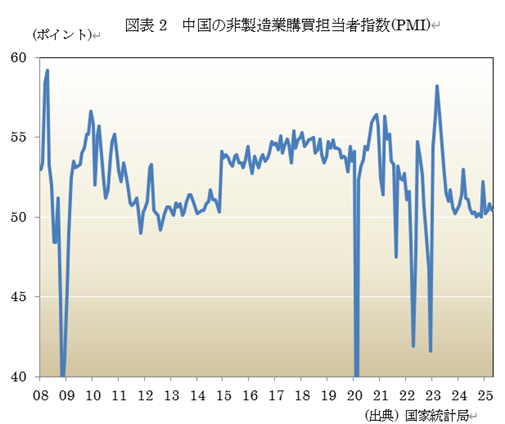
キャピタル・エコノミックスの中国担当エコノミスト、ファング氏は「PMIの大幅低下は、ネガティブな感情により関税の影響を無視している可能性が高いが、それでも外需の冷え込みに伴い、中国経済が圧迫されていることを示唆している」としました。
令和7年4月30日 米中がチキンレース
おはようございます。米中が関税を巡りチキンレースを展開しています。
1. 米ベッセント財務長官が顕在を巡り緊張緩和が必要と
ベッセント米財務長官は23日、中国との貿易を巡る交渉を進展させるには緊張緩和が必要であるとして、米中が互いに表明している関税率を現在のかどに高い水準から引き下げる必要があるとの見解を示唆。
同氏は国際数か基金(IMF)・世界銀行の春季会合に出席した際に記者団に対して、世界に大経済国が貿易関係を再調整するためには緊張緩和が必要との考えを示唆。
このことは、米国の対中関税率145%、中国の対米関税率125%の引き下げを意味するのかとの質問に対して、「そうあるべきだと考える」として、「米国も中国もこれが持続可能が水準とは考えていない。禁輸措置に相当する水準だ。両国間の貿易の断絶は誰の利益にもならない」としました。
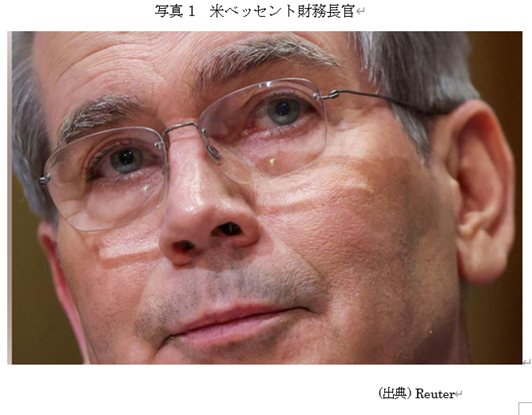
2. 国は米国離れを画策
一方、中国の習近平政権は、第1次トランプ政権における経験などに基づいて、脱米国をこれまで推進してきました。
まず、通貨における対米依存脱却の試み。現在、世界の基軸通貨は米ドルとなっていますが、中国は人民元の決済のおける拡大を意図して、ドルへの依存度を低下させてきました。又、BRICS共通の通貨設立を探るなど、ドル依存度の低下に努めてきました。
更に、貿易面でも米国への依存度を低下。大豆、牛肉などの農産物については、米国への依存度を低下させ、豪州、ブラジルなどに輸入先を分散。半導体についても、米国への依存度を低下させる政策を取っています。
このように、米中は関税を巡ってチキンレースを展開。中国がこれまで、周到に準備してきたこともあり、米側の焦りが今後表面化する可能性もあります。
令和7年4月28日 G20で関税について議論
おはようございます。G20財務省・中央銀行総裁会議が開幕。関税についての議論がなされました。
1. 米国の関税に対して懸念
日米欧に中国、ロシア、新興国を加えた主要20カ国(G20)税務相・中央銀行総裁会議が23日、米首都ワシントンで開幕。
出席した国からは、米トランプ政権の発動した大規模な関税の撤回を求めたり、世界経済への悪影響を懸念したりする声が相次ぎました。関税などを巡る立場の違いは大きく、議長国の南アフリカによる共同声明発表は見送られる見通し。
会合には、別撰と米財務長官も出席し、関税引き上げン関するトランプ政権の立場を説明。1月に第2次トランプ政権が発足して以来、経済閣僚のトップであるベッセント氏がG20に主席するのは初めて。
日本からは加藤勝信財務相と、植田和夫日銀総裁が出席。加藤財務相は会合とに記者会見して、日本政府としての発言内容を公表。
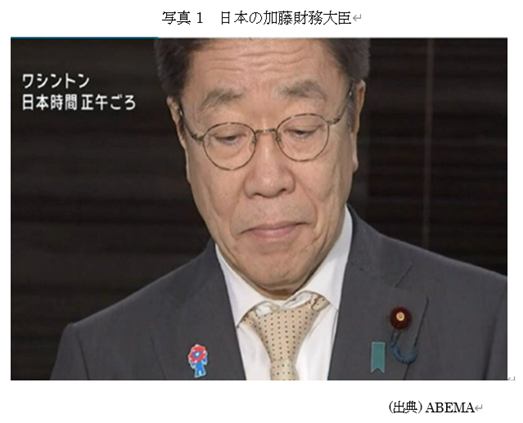
2. トランプ関税が米成長率を下押し
一方、経済教旅行開発機構(OECD)は17日、米トランプ政権による関税引き上げは、カナダ、メキシコ、米国の経済成長率を押し下げ、インフレ率を押し上げると予想。世界経済の見通しを下方修正して、より広範な貿易戦争が成長をさらに低下させると警告。
全編的な貿易ショックの場合、米国では家計が直接的な高い代償を志原氏、景気が減速し、関税が生み出すのは追加収入以上のコストを負うことになると予想。
世界成長率は2024年の+3.2%から25年が+3.1%に、26年には+3.0%に減速するとを予想。昨年12月の予想(ともに+3.3%)から下方修正。
令和7年4月27日 ロシア中銀政策金利維持
おはようございます。ロシアの中銀は政策金利を維持しました。
1. 7-9月期成長率は+4.0%
ロシア連邦統計局は11月13日、7-9月期GDP(国内総生産、速報値)が前年同期比+3.1%になったと発表(速報値)。4-6月期の+4.1%から減速。伸び率は6四半期連続でプラス成長。
7-9月期GDP成長率について経済発展省は2.9%、ロシア中央銀行は+3.2%と予想していました。
ウクライナとの戦争継続に伴う多額の予算投入と、軍需産業の拡大を背景として、ロシア政府は24年のGDP成長率予想を+3.9%としています。23年の+3.6%を上回ると予想。

2. インフレ率加速
国家統計局から4月11日発表された3月の消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率は+10.3%と、伸び率は前月の10.1%から加速(図表2参照)。
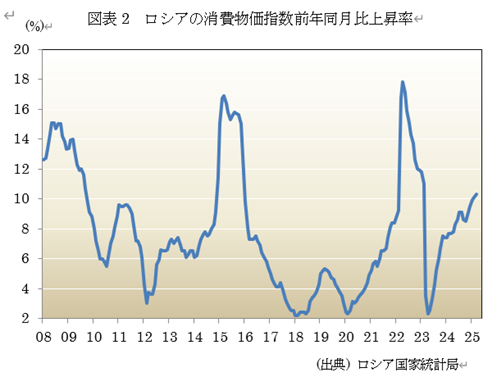
3. 政策金利を据え置き
一方、ロシア中央銀行は4月25日の理事会で、主要政策金利である資金供給のための1週間物入札レポ金利と資金吸収のための1週間物入札金利を予想外に21.0%に据え置き。据え置きは4会合連続。
中銀は声明で、現在のインフレの状況について、「全体として低下傾向にあるものの、依然として高い水準にある」と指摘。今後も緊縮的な金融政策をとると説明。
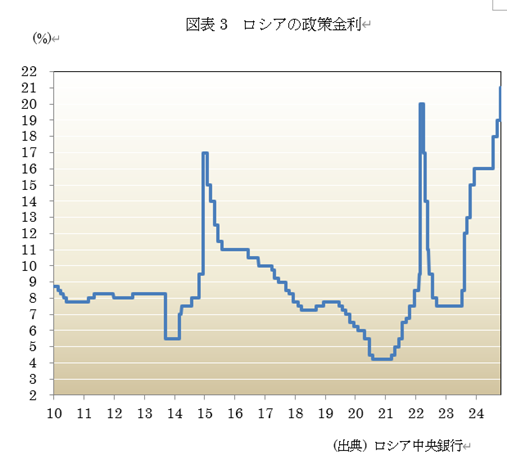
ウクライナへの侵略が長期化する中、戦時経済下による人手不足などでインフレが継続。3月のインフレ率は+10.3%と高水準で推移。中銀は今後のインフレ率の推移について、2025年末には+7-8%に退化して、26年末には目標とする+4%になるとの見通しを示唆。
令和7年4月26日 上海モーターショー開幕
おはようございます。上海モーターショーが開幕しました。
1. 1000社近くが出展
中国上海でモーターショーが開幕。主催者発表で国内外の1000社近くが出展。只、前回2023年には1000社を超えていました。米中の関税摩擦の激化を反映。トランプ政権が145%の対中関税を課すとしており、自動車消費が冷えこめば、中国の景気に影響することも考えられます。
上海モーターショーは北京と核燃で開催される世界最大級の自動車展示会。今回もトヨタ、独フォルクスワーゲンなど各国の主要メーカーが揃って参加。
只、韓国の現代自動車と起亜自動車は今回いずれも20年ぶりに参加を見送り。中国国有大手、広州汽車集団展示の近くでは、動画配信のビリビリが専用ブースを設けました。ある日系メーカーは主催者が「何とか空間を埋めようとした」としました。

2. ハイブリッド、EVなど好調
一方、中国ではEV(電気自動車)の他、ハイブリッド車の販売が好調。
2024年通年の中国市場の新車販売台数は+4.5%の3,143.6万代で、SUVモデルが全体の47%を占めました。グループ別の販売台数はBYDが大幅増加。上汽団を抜いてトップとなりました。
乗用車における中国系メーカーは好調で、前年比+22.2%の1,807.9万代と、シェアは65%以上。特にBYDは+41.1%の425.0万台と独走。ドイツ系メーカーは▲10.8%の401.3万台。日系メーカーは▲18.7%の315.8万台。シェアは11.5%&。米系メーカーは▲23.7%の177.4万台。
令和7年4月24日 IMF世界経済見通し引下げ
おはようございます。IMFが世界経済見通しを引下げました。
1. 世界経済見通しを▲0.5%引き下げました
国際通貨基金(IMF)は22日、世界の経済成長見通しを前回1月の時点から▲0.5%引き下げて+2.8%としました。トランプ政権の関税引き上げの影響により、全ての地域を下方修正。米国自身も打撃を受けるとして、「世界景気悪化」の目安となる+2%割れの可能性も3割あるとしました。
米政権の関税に関する政策が頻繁に変更されるため、IMFは基本シナリオの予測を4月4日の時点とし、途中段階で見込んでいた予測値も公表しました。
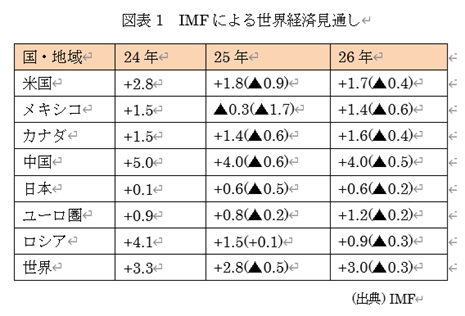
2. 米国自身も下方修正
国別では、震源地となっている米国は25年成長率が▲0.9%ポイントの大幅引き下げ24年から急減速。37%の確率で年内に景気後退に陥るとしました。トランプ政権は景気減速を「短い移行期間」としていますが、IMFは26年も▲0.4%ポイント引き下げて+1.7%としました。
中国は25年を▲0.6%ポイント引き下げて+4.0%と予想。中国では財政刺激策が景気を下支えする見通し。米中とも試算には4日以降に激化した報復措置を含んでおらず、下げ幅は更に拡大する可能性もあります。
また、米国からの高関税を告げられたメキシコは25年には▲1.7%ポイントの大幅下方修正で▲0.3%。カナダも同様に大幅引き下げとなっており、北米の2箇国は大きな影響を受ける見通し。
。レアアースは電気自動車などハイテク製品に必要なものが多く、海外でレアアース不足のリスクが高まっています。
令和7年4月22日 ディープシークの衝撃
おはようございます。ディープシークが、AIなどハイテク業界に波紋を広げています。
1. ディープシークが話題に
1月27日から始まる週で、中国のAI(人口知能)のスタートアップの1つであるDeepSeek(ディープシーク)が、1月20日に独自に低コストで開発した生成AIを発表したことにより、株式市場に衝撃を与えました。これを受けて、米エヌビディアなどAI関連銘柄のハイテク株は急落することとなりました。
ディープシークについて、専門家は、多様なデータ処理能力、リアルタイム処理に特徴があるとしています。従来、生成AIなどの開発には膨大な資金と半導体が必要であるとされてきました。同社の技術は一部他社の模倣であるとして、著作権の問題を指摘する向きもあります。ともあれ、低コストのライバルが現れたことにより、米IT大手は戦略の見直しを迫られることとなりました。
2. 中国政府がAI開発に注力
一方、中国政府は米国への対抗上もあり、AI開発に注力。同国のAI開発は、汎用人口知能(AGI)、実用的なAIエージェント、先進的な大規模言語モデル(LLM)の研究開発、そして政府主導による戦略的支援と規制迄、あらゆる角度で発展しています。
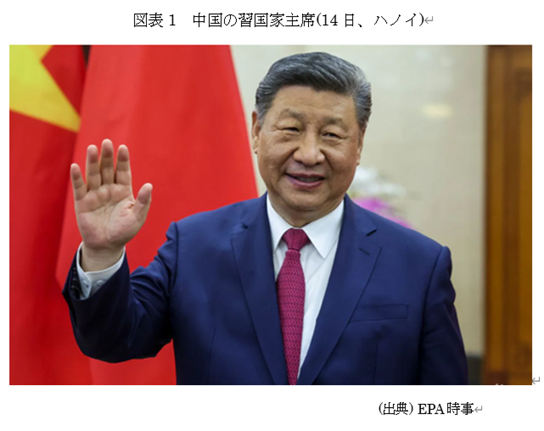
そのスピードを規模は、欧米のIT企業にも引けを取らないほど。虫を政府と産業界の一体感、スピード感により、2030年迄に世界トップレベルとのAI先進国になる可能性があります。
3. 中国がレアアース輸出を規制
他方、中国政府はハイテク製品の生産に欠かせないレアアース(希土類)の統制を強化。4月上旬に7種類のレアアースを輸出規制の対象に入れ、14日迄に輸出が凍結状態になった模様。対中圧力を増す米トランプ政権への報復措置の一環と見られます。
中国の輸出業者が同国政府からいつ輸出許可が得られるかは不透明。レアアースは電気自動車などハイテク製品に必要なものが多く、海外でレアアース不足のリスクが高まっています。
令和7年4月21日 中国がカンボジアに接近
おはようございます。中国がカンボジアなどASEAN諸国に接近しています。
1. 習近平国家主席がカンボジア訪問
中国の習近平国家主席が17日、東南アジア3カ国歴訪の最終訪問国であるカンボジアの首都プノンペンに到着。フン・マネット首相と会談。インフラ整備や安産保証面での関係強化を図ったとみられます。
中国派かねてから、同国に巨額に資金を投じて影響力を強化。州政権は両国関係を「鉄の友情」と表現。トランプら政権は今月、カンボジアに対して東南アジアの中で最も高い49%の相互関税を課すと発表。カンボジアが中国製品の迂回輸出先になる事を防ぐ狙いとみられます。
カンボジアの米国に対する不満を利用して、習政権は今回の訪問により関係強化を目指しています。同主席は地元紙に寄稿して「覇権主義や保護主義に対抗して、途上国の利益を守る」ために協力すべきだと首相。合同軍事演習や治安維持分野での連携に意欲を示唆。
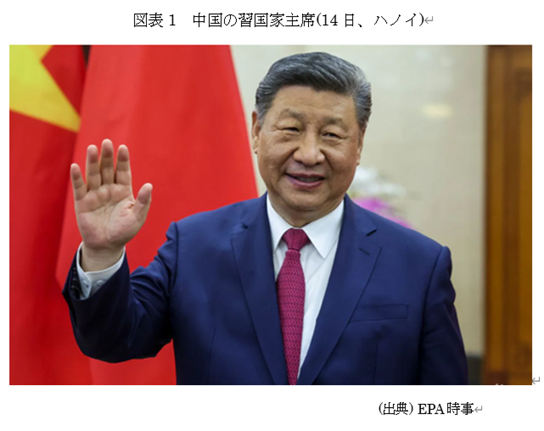
2. ベトナムも訪問
中国の習近平国家主席は14日、ベトナムを訪問、両国は供給(らプライチェーン)や鉄道をはじめとする多くの分野での協力協定に調印。
同主席はベトナム共産党のトー・ラム書記長と会談。書記長は国営メディアで14日、防衛、安全保障、鉄道を中心とするインフラ分野での協力拡大を望むと表明。
両国の商工省、国防省、商業会議所の間でも協定を締結。中国とベトナムの国営メディアは同日遅く、45件の協定が締結されたと報じました。
令和7年4月19日 トルコ中銀利上げ
おはようございます。トルコ中銀が利上げしました。
1. 3月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が4月3日に発表した3月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+38.1%と、前月の+39.05%から伸び率が鈍化。市場予想の+38.9%からは下振れ。
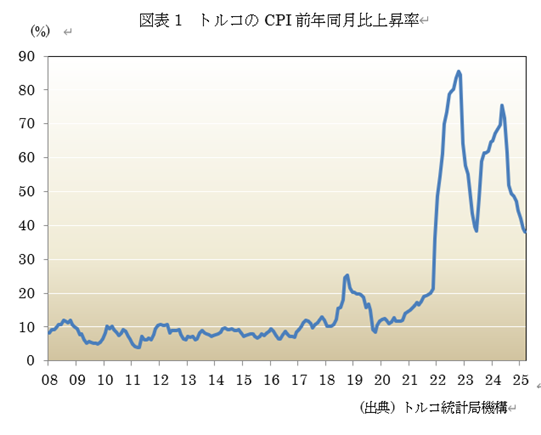
2. 政策金利を引上げ
一方、トルコ中央銀行は4月17日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を+3.5%ポイント引き下げ、46.0%にすることを決定(図表2参照)。昨年12月かの利下げ開始からわずか4箇月での政策転換は、市場では予想外と受け止められました。
市場関係者によると、利上げの狙いは数週間にわたって続いた通貨リラの下落圧量を和らげることと、予想物価の上昇。
3月にはエルドアン大統領最大の政敵とみなされたイスタンブール市長が汚職の容疑で逮捕されました。リラの対ドル相場は一時安値を更新トルコの株式と債券が急激に下落しました。
中銀は「金融市場における最近の情勢」が4月のコアエースの物の物価上昇率をややう押し上げると見込まれることに加えて、内需が想定か上振れている点を踏まえると、ディスインフレの力が弱まっている様子が伺えるとしました。
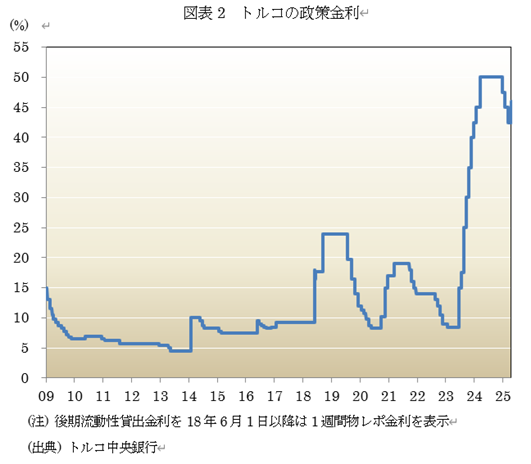
3. 10-12月期成長率+3.0%
他方、トルコ統計局が2月28日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.0%と、前期の+2.1%から加速。市場予想の+2.6%から上振れ。前期比では季節調整済みで+1.7%。
24年通期のGDP成長率は+3.2%、市場予想は+3.0%。
シムシェキ財務相は、24年の成長率は内需が+2.1%ポイント、外需が+1.1%寄与したと指摘。バランスの取れた成長を達成したとしました。
経済見通しについて、「ディスインフレに伴う良好な金融情勢、政策に対する予測可能性の向上、信頼感の改善が経済活動に好影響を与える」との見方を示唆。
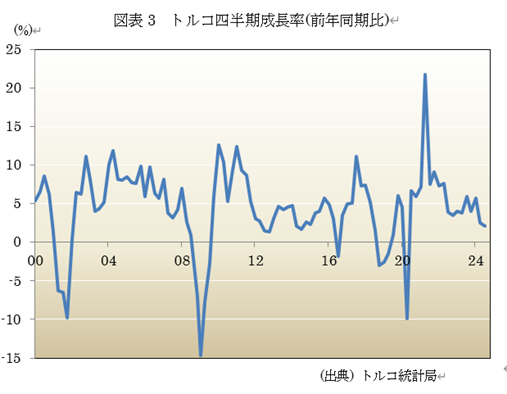
トルコの貿易相手国の成長加速、世界的な金融情勢の追い風、穏やかな商品価格の見通しは、25年の成長にプラスの影響を与えると述べました。その一方、世界貿易における保護主義的な政策の増加や地政学的同行をリスク要因として挙げました。
令和7年4月17日 原油価格が低迷
おはようございます。原油価格が低迷しています。
1. WTI先物60ドル前後まで低迷
トランプ関税ショックなどにより、原油価格が乱高下。需給の状況を見ると、米WTI原油先物価格は60ドル前後で推移する可能性が強くなっています。原油価格の低下は、産油国、特に中東諸国の経済的打撃をなりそうです。
米WTI原油先物価格はこのところ55〜63ドル程度で推移。米中関税戦争の激化により、中国などの需要が低迷。トランプ大統領の言動に振り回される展開。
トランプ政権の相互関税の発動により、4月9日の原油価格は一時1バレル=55.12ドルと。2021年2月以来、4年2箇月振りの安値。その後、同氏が「米国側に交渉を持ち掛けている75以上の国・地域の相互関税を90日間に限って10%の引き下げる」と発表し、移転して上昇して62.35ドルを付けました。

2. 米中関税戦争が原油市場に打撃
これまで原油価格の下支えを行ってきたOPECプラス(原油輸出国機構とロシアなどの大産油国で攻勢)にとて、好ましくない展開。
OPECプラスは5日に合同閣僚会議を開催して、各国に割り当てた原油の生産枠について「完全な適合と保証を達成することが極めて重要出ることを再認識した」との声明を発表。生産量が記録的な水準に達しているカザフスタンなどに対して、過剰資産文を抑制するとともに、保証のための減産枠を上積みするよう、重ねて要請。
OPECプラスは3日、5月から日量41万1000バレルを増産することを決定。増産領が4月の約3倍であったため、原油価格に下落圧力がかかり、その後の米中関税競争も重なって、市場には弱気が広がりしました。
令和7年4月16日 中国3月貿易統計
おはようございます。3月の中国貿易統計で、輸出加速しました。
1. 3月輸出は伸び率加速
中国税関総署が14日発表した3月の貿易統計によると、輸出は前年同月比+12.4%、輸入は▲4.3%。市場予想は輸出が+4.4%、輸入が▲8.4%。
1-2月には輸出+2.3%、輸入▲8.4%。
3月の輸出増加は、トランプ米大統領による4月2日の大規模な関税引き上げを前に、中国の工場が出荷を急いだため。
キャピタル・エコノミストの中国経済担当責任者、ジュリアン・エバンスプリチャード氏は、「しかし、出荷は今後数か月、数四半期に亘って減少するだろう。中国の輸出が現在のレベルと取り戻すには数年かからと我々は考えている」としました。
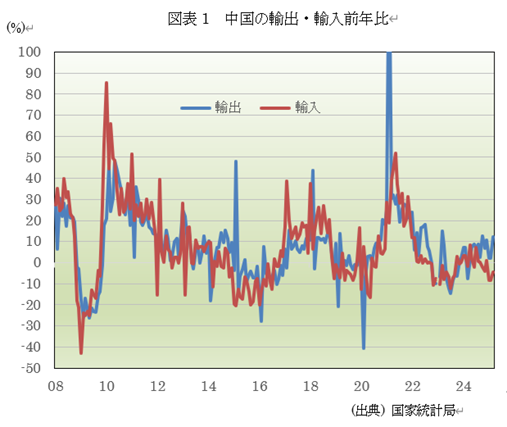
2. 第1四半期の対米黒字額が増加
中国の3月の貿易黒字は1026億4000万ドル。直近の比較対象である昨年12月の1048億ドルからわずかに減少したものの、前年同月とほぼ同水準。
第1四半期の対米黒字は766億ドルと、前年同比の702億ドルから増加。
大豆輸入が3月には▲36.8%減少するなど、コモディティー(商品)貿易は、米国からの輸入が既に貿易摩擦の影響を受けている可能性を示唆。
令和7年4月15日 アルゼンチンのインフレ率低下
おはようございます。アルゼンチンのインフレ率が低下しました。
1. 3月CPI上昇率が鈍化
アルゼンチン統計局の4月11日発表によると、3月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+55.9%(図表1参照)。前月の+66.9%から減速。2022年3月以来、約3年振りに低い伸び率。
ミレイ政権は最大の課題であるインフレ率を抑え込み、経済再建に向けた改革を進めるとしています。24年4月の前年同月比+289%を頂点として、11箇月連続でインフレ率が鈍化。

2. 政策金利を引き下げ
アルゼンチンの中央銀行は1月31日、インフレ率の低下を受けて、政策金利を▲3%引き下げて29%にすると発表。これは、ミレイ大統領の2023年12月の就任以来9回目の利下げ。これにより、借入コストは2020年10月以来最低の水準となりました。
2024年12月には、インフレ率は8カ月連続で低下して+117.8%となり、2023年7月以来の水準となり、11月の+166%から鈍化。
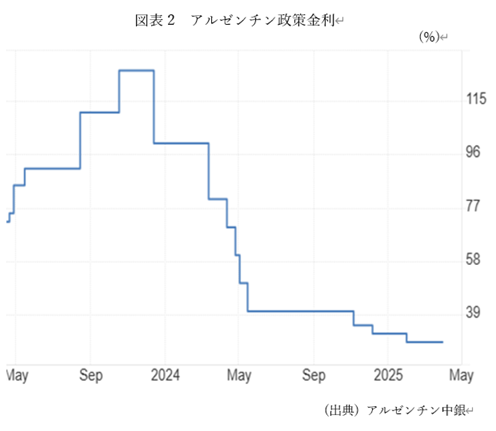
前月比上昇率は+2.7%と、3カ月連続で+3%を下回りました。利下げは、政府の2月1日開始の月次通貨低下率の▲2%から▲1%への圧縮と重なりました。
令和7年4月14日 中国が米国への関税引き上げ
おはようございます。中国は米国に対する125%報復関税を示唆しました。
1. これ以上は無視と
中国政府は11日、米国からの全輸入品に対する関税を12日から最大125%に引き上げると発表。一方今後米国から更なる関税を課されても、「無視する」と表明。
これについて中国商務省は「原稿の関税水準で米国からの輸入品が中国市場に受け入れられる余地は既にない」とし、もはや経済合理性が失われたとして、今後の追加関税に対しては実質的な対応を取らない方針を示唆。
中国商務省の報道官は、トランプ政権が導入した「以上に高い」対中関税について「米国の横暴かつ威圧的な態度を一層際立たせるものであり、いずれ国際的な嘲笑の的となるだろう」としました。
2.米トランプ政権、相互関税の対象からスマホなど除外
一方、米トランプ政権は、相互関税などの対象からスマートフォンなどの電子機器を除外すると発表。中国からの輸入に大きく依存している商品を除外することにより、米国内の価格高騰を抑制する狙いがあるとみられます。米国の税関・国境系戯曲が11日夜発表。
それによると、スマートフォン、コンピュータといった電子機器が、相互関税の対象から外されるとのこと。又、ハンド対製造装置やハードディスクも相互関税の対象外。

トランプ政権は、中国からの輸入品に対する追加関税を繰り返し引き上げ、10日には合わせて145%に達したとしているほか、相互関税については、問題解決に向けて協議を要請している日本などの国々に対して、90日間措置を停止。この間、関税率を10%に引き下げるとしていています。
令和7年4月12日 中国3月CPI
おはようございます。中国の3月CPIは、前年同月比▲0.1%下落しました。
1. 3月CPIが下落
中国国家統計局が10日発表した3月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が▲0.1%と、前月の同▲0.7%からマイナス幅が縮小。2箇月連続で下落。市場予想の横這いから下振れ。
前月比では▲0.4%の下落。市場予想は▲0.3%、2月には▲0.2%。
変動の大きい食品と燃料価格を除くコアインフレ率は+0.5%。前月は▲0.1%。

2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、3月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.5%と、下落幅は前月の▲2.2%から拡大。市場予想の▲2.3%から下振れ。4箇月ぶりの大きさ。30か月連続の下落。
変動の激しい食費と燃料価格を除くコアインフレ率は+0.52%と、前月の▲0.1%から反転。

国家統計局の担当者は、PPIの下落ペース加速の原因は国際原油価格の下落の他、暖房期が終了したことによるエネルギー需要の季節的な減少によるものと述べました。
令和7年4月8日 ベトナム1-3月期GDP堅調
おはようございます。ベトナムの1-3月期GDPは、堅調でした。
1. 1. インフレ率は加速
まず、インフレ率を見ておきましょう。ベトナム統計局が4月6日に発表した3月の消費者物価指数(CPI)上昇率は+3.13%、前月の+2.91%から加速(図表1参照)。
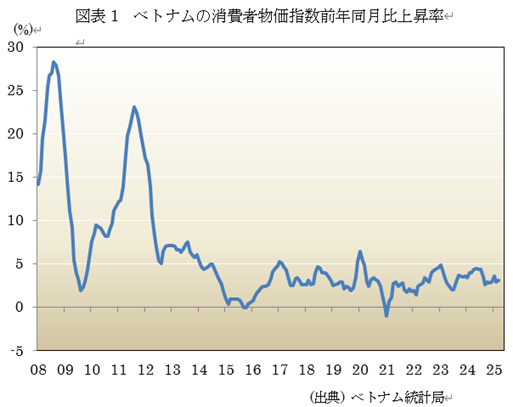
2. 1-3月のGDP成長率は+6.93%に減速
一方、ベトナム統計総局は4月6日に、1-3月期の国内総生産(GDP)成長率が、前年同期比+6.93%になったと発表(図表2参照)。10-12期の+7.55%から減速。14四半期連続の増加。第1四半期としては、2020年以来の高い成長率。
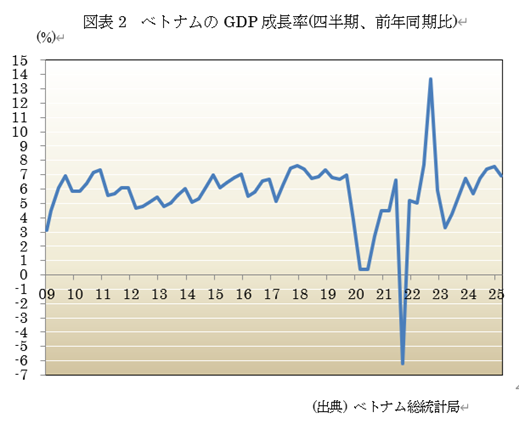
1-3月期実質GDPを産業別に見ると、サービスは前年同期比+7.70%(前期は同+8.21%)と減速し、製造・建設は+7.42%(同+8.35%)とやはり鈍化。農業は+3.74%(同+2.99%と加速。
支出面では、GDPの約60%を占める最終消費は、旧正月にも下支えられて+7.45%と堅調。
貿易面では、輸出は+9.71%と伸びたものの、輸入は+12.45%をそれを上回る加速。
同国首相は、トランプ大統領の関税にもかかわらず、同国の成長目標+8%は維持するとしました。只、関税により輸出が▲10%減少するとすれば、GDP成長率に対して▲0.84%ポイントの下押し要因になるとしました。
令和7年4月7日 中国が報復関税を発表
おはようございます。中国が米国に対する報復関税を発表しました。
1. 米国からの輸入品に報復関税を発表
中国は4日、トランプ政権による関税への対抗措置として、米国からの全輸入品に34%の追加関税を10日から課すと発表。これを受けて欧米の株式市場の混乱が深まっています。一連の関税により、長期的な貿易戦争と世界経済への悪影響の可能性が高まっています。
中国は報復関税に加えて、主要鉱物の輸出を制限し、複数の米国企業をブラックリストに追加。トランプ大統領の行動は強圧的な「いじめ」だと非難し、世界貿易機構(WTO)の規則に「深刻に違反するものだ」としました。

2. 米農業に打撃
一方、中国系短編動画透谷アプリTikTokの米事業売却計画も火種となっています。トランプ大統領は4日、米事業の売却期限を75日間延長すると発表。相互関税の引き下げをちらつかせて、売却に必要とされる中国政府の承認を引き出す考えとみられます。
中国は、相互関税を受けて、米事業売却を承認しない可能性を示唆。売却計画は一旦棚上げされた模様。オランダ金融大手INGのエコノミストは、トランプ第1次政権時の米中貿易戦争を受けて、中国派対米輸出依存度が下がっているとし「報復への自信を深めている」と示唆。
米国にとって中国は穀物などの主要輸出先。前回の貿易戦争では、農産物輸出が急減し、大きな打撃を受けました。業界団体の米国大豆協会は「農家はシェア喪失やイメージ悪化、強豪国の生産拡大など、その悪影響に今も苦しんでいる」とし、貿易戦争の回避を求めています。
令和7年4月6日 米3月雇用統計
おはようございます。米国の3月の雇用統計で、雇用者数が+15.1万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が3月の雇用統計を4日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+22.8万人。市場予想の+13-14万人を上回りました。失業率はやや上昇。関税引き上げで、景気悪化懸念が深まる中、雇用の勢いが今後どれくらい減速するかが焦点となっています。
伸びは、1月が12.5万人から11.1万人に、2月は15.1万人から11.7万人にそれぞれ下方修正。3カ月平均では15万人ていどとなっており、雇用の勢いはまだ維持されています。
失業率は4.2%。市場では2月の4.1%から横這いか、4.2%への小幅上昇との予想が多くなっていました。平均時給は前月比で予想通り+0.3%となりましたが、前年同月比の伸びは+3.8%と、予想をやや下回りました。
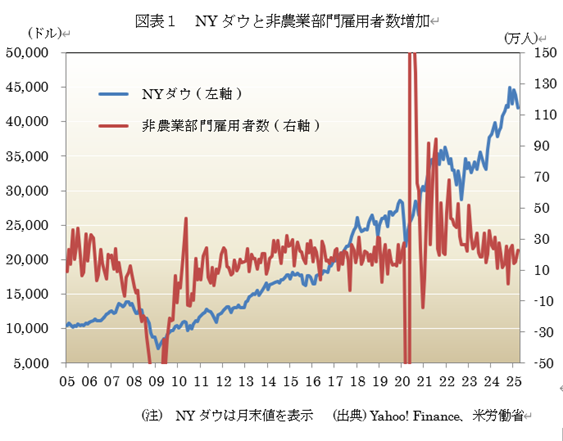
2.政府リストラが焦点
今後の最大の焦点は、2月から本格化した米政府効率化省(DOGE)による政府のリストラ。連邦政府職員の減少幅は2月の1.1万人から3月には4000人に縮小。有給休暇の状態になっている職員などはまだ今日状態とみなされています。
米民間調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスによると、米企業や政府機関が3月に公表した人員削減計画は計27万5240人と、21-24年平均の6倍に跳ね上がりました。8割が政府部門。
「DOGEに馘首された。あなたは私たちが採用します」。3月、首都和信とのユニオン駅では、ニューヨーク州政府が出した求人広告が並びました。
令和7年4月5日 トランプ大統領が相互関税を発表
おはようございます。米トランプ大統領は2日、全世界を対象とする相互関税を発表しました。
1. 中国34%
トランプ大統領は2日、全世界を対象とする相互関税を発表。各国に一律10%の関税を課した上で、国・地域毎に異なる税率を上乗せ。米国は第二次大戦後、率先して関税を下げて、世界の貿易と経済を牽引。米国が主導してきた自由貿易体制は崩壊して、世界の分断化が進むこととなりました。
国毎の上乗せ税率は9日に発動。日本は24%、EU(欧州連合)は20%。中国には34%を科すとしており、既に発動している20%と合わせて計57%となります。
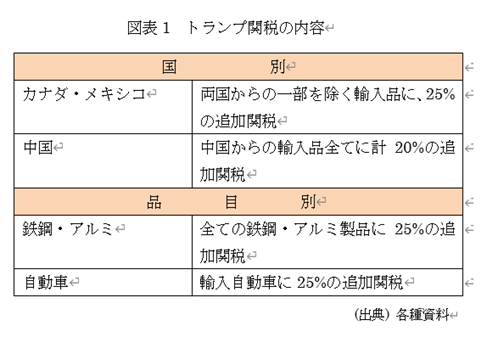
2. 2. 東南アジア諸国にも打撃
一方、同日に「相互関税」では、東南アジアで高い税率が適用される国が目立ちました。各国は米国に対して、税率の減免などを求める取り組みを続ける見込。ディール(取引)を掲げるトランプ氏に訴えるような提案ができるかどうか注目されます。
東南アジアの主要国では、ベトナム46%、タイ37%、インドネシア32%、マレーシアの24%などとなっています。最低はシンガポールの10%。
ベトナムのファミ・ミン・チン首相は3日、閣僚が参加する会議で、「(米国には)長年の戦争による深刻で長期の影響を受けているベトナムにあった政策を期待している」として、緊急チームの立ち上げを指示しました。
令和7年4月3日 中国株と他の新興国株との連動性低下
おはようございます。中国株と他の新興国株との相関が低下しています。
1. 中国株が堅調
中国株の値上がりは、一般に他の新興国株も押し上げるものの、今回は様相が異なっています。
中国本土の株式は、ここ半年で大きく上昇し、数年に亘る低迷から脱出。一方、他の新興国株式は全般に依然として低調。現在の中国株式の上昇は、外国との広範な貿易による中国経済の改善が主な要因ではなく、AIなどテクノロジーによる熱狂が齎したものであると考えられます。
UBSグループで新興国市場戦略調査を担当するマニク・ナレイン氏(ロンドン在勤)は、「中国株の好調は、投資よりも消費に重点を置いた特定のハイテク主導の支出増加によるものだ。他の新興国に大きな波及効果を齎す可能性は非常に低い」としました。
MSCI中国指数は昨年8月末から+30%あまり上昇。中国を除く新興国市場の株式指標はほぼ▲7%の下落。0-10年に中国株は+63%上昇し、広範な新興国市場指数は+103%。16-17年は中国株が+50%上昇し、新興国市場全体の指数は+46%。
中国株は昨年9月に大きく上昇。追加的な景気刺激策を巡り、楽観的な見方が広がったものの、その後の政策発表が来たい外れであったため、その値上がり分はほぼ帳消しとなりました。今年1月に中国の新興企業ディープ・シーク(DeepSeek)が新しい人口知能(AI)モデルを発表。AIを中心に注目が集まりました。

2. トランプ関税に注目
只、今後懸念されている大きな材料の1つに、トランプ大統領が4月2日に発表するいわゆる「報復関税」があります。同氏は、自動車輸入に25%の関税を課すとしており、世界の投資家は固唾を飲んで見守っています。
中国は対米貿易に大きく依存しており、特に脆弱であると見られています。一部のファンドは、既に中国株の比率を引き下げています。
ラザード・アセット・マネジメントのポートフォリオマネージャー、ロヒト・チョプラ氏は(NY在勤)は自社について「24年中に中国株を買いました後、多くのファンドが今年値上がりした保有資産の一部を売却している。我々のファンドは、対中エクスポージャーを若干減らした」としました。
令和7年4月2日 中国3月PMI
おはようございます。3月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 3月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が31日発表した3月の製造業購買担当者指数(PMI)50.5と、前月の50.2
から上昇。市場予想と一致。2箇月連続で景気判断の分かれ目となる50を上回り、政府による景気刺激策が景気を下支えしていることを示唆。

2. 非製造業PMIも上昇
一方、同日に発表した3月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.8と、前月の50.4から+0.4ポイントの上昇。
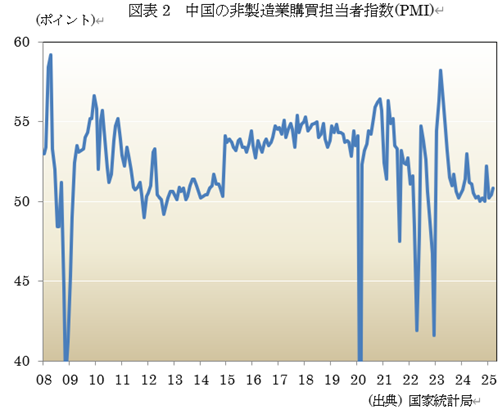
中国では、不動産不況の長期化の伴い、内需が停滞。米トランプ政権との間で貿易摩擦も激化しており、景気の先行きの不透明感が強くなっています。
同国政府は、消費の押し上げや内需の拡大に力を入れる方針。効果的な対策を今後出せるかどうかが今後の焦点となります。
令和7年3月29日 中国ディープシーク創業者が富裕層の一員に
おはようございます。中国ディープシーク創業者が富裕層の一員になりました。
1. ディープシークの梁文鋒氏が胡潤グローバル富豪リストに初登場
中国メディアの快科技などによると、中国の民間シンクタンク胡潤研究院が27日公表した「胡潤グローバル富豪リスト20252」に、中国の人口知能(AI)開発新興企業、深度求索(ディープシーク)の創業者で、今年40歳の梁文鋒(リアン・ウェンファン)最古経営責任者(CEO)と、米オープンAI創業者のサム・アルトマン(39)が、共に初めて名を連ねました。米換算での資産は梁氏が40憶ドル、アルトマン氏が18億ドル。
1月15日時点で、米ドル換算で10億ドル以上の試算を持つ富豪は、前年より163人増えて過去最多の3442人。
トップは米テスラのイーロン・マスク氏で+82%の4200億ドル、2位は米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏で+44%の2660億ドル、3以はメタのザッカーバーグ氏で+53%の2420憶ドル。
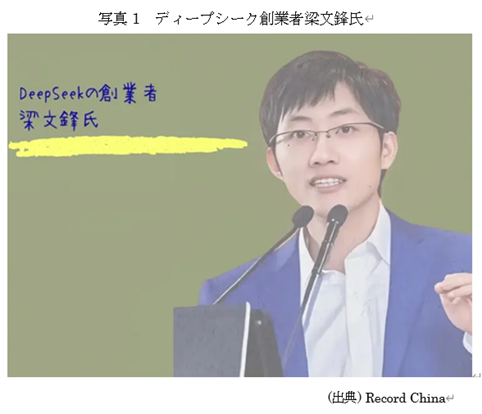
2. 中国半導体販売+17%
一方、中国半導体行業協会の帳立副理事長は27日、2024年の国内半導体販売が前年比+17%の1兆4300億元(約30兆円)になったと発表。米国都の対立が続いているものの、25年についても、「良好な立ち上がりとなった」との見方を示唆。
上海市で26日開幕した半導体分野の国際展示会「セミコン・チャイナ」のフォーラムで示唆。
中国政府は半導体の国産化を急いでおり、中国の自動車や家電メーカーに国内半導体を積極的に採用するよう求めたほか、国内の増力増が寄与しました。
令和7年3月27日 トルコ大統領の「政敵」を逮捕
おはようございます。トルコ大統領の「政敵」が逮捕されました。
1. トルコ大統領の「政敵」を逮捕、野党への取り締まり強化
トルコの裁判所は23日、最大都市イスタンブールのイマモール市長を汚職の容疑で収監。権威主義的なエルドアン大統領に対しる野党の取り締まりが教化されています。
同大統領にとって最大の「政敵」とされる今モース氏は、19日に自宅で拘束されました。同紙は2028年の大統領選で、最大野党である共和人民党(CHP)の候補者として登録されると見られていました。
同氏は容疑を否認。批評家からは、今回の逮捕について、権威主義的な傾向を強めていたトルコにとって、完全な独裁体制に陥る危険となる転換点となり得るのとの指摘があります。

2. クルド勢力指導者が獄中から武装解除を呼びかけ
一方、トルコからの分離独立を目指して武装闘争を続け、トルコ財布などからテロ組織に認定されているPKK(クルド労働者党)の指導者が、2月27日に、獄中から武装解除と組織の解散を呼びかけました。
40年以上続いている武装闘争が転換点を向かるかどうか、注目されています。
PKKは、トルコからの分離独立を目指して、1984年から40年以上に亘ってブドウ逃走を継続。トルコ政府などからテロ組織に指定されています。
昨年首都アンカラ郊外でテロ事件を起こしたとして、トルコ軍は報復としてシリア北部やイラク北部にあるクルド人武装組織の拠点などへの攻撃を行いました。
令和7年3月26日 トルコ中銀利下げ
おはようございます。トルコ中銀は利下げしました。
1. 2月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が3月3日に発表した2月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+39.05%と、前月の+42.12%から伸び率が鈍化。市場予想の+39.9%からは下振れ。

2. 政策金利を引下げ
一方、トルコ中央銀行は3月6日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を▲2.5%ポイント引き下げ、42.5%にすることを決定(図表2参照)。利下げは市場の予想通り。利下げは市場の予想通り。
2月の消費者物価指数上昇率が鈍化。一方、食品やエネルギーなど価格変動の激しい項目を除くコアインフレは猶高止まりしており、サービス価格のインフレも根強くなっています。
政策決定と合わせた声明では、MPCは「インフレの基調的な趨勢は2月には後退。1月に特異な上昇を示唆したサービスのインフレも鈍化した」としました。
「昨年10-12月に内需は予測を上回ったものの、引き続きデフレの水準だった」として、インフレ見通しに注目しつつ「会合毎に政策金利を決定してく」としました。
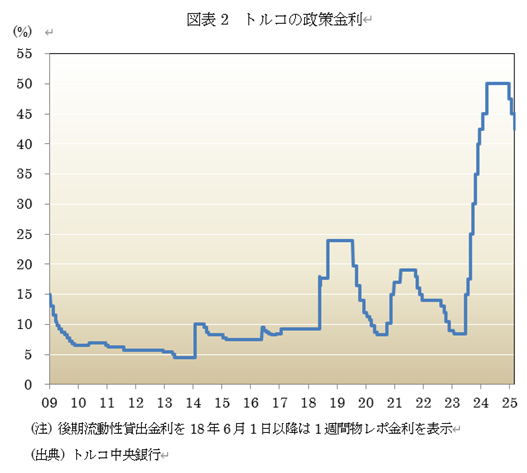
3. 10-12月期成長率+3.0%
他方、トルコ統計局が2月28日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.0%と、前期の+2.1%から加速。市場予想の+2.6%から上振れ。前期比では季節調整済みで+1.7%。
24年通期のGDP成長率は+3.2%、市場予想は+3.0%。
シムシェキ財務相は、24年の成長率は内需が+2.1%ポイント、外需が+1.1%寄与したと指摘。バランスの取れた成長を達成したとしました。
経済見通しについて、「ディスインフレに伴う良好な金融情勢、政策に対する予測可能性の向上、信頼感の改善が経済活動に好影響を与える」との見方を示唆。
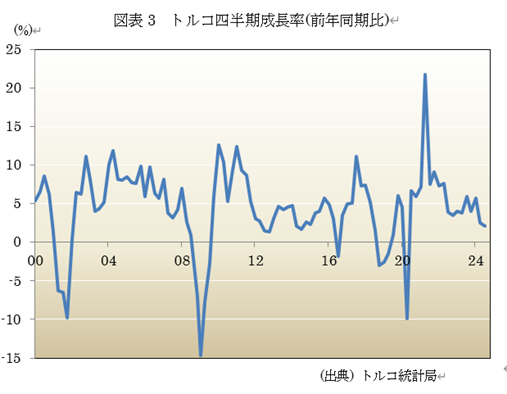
トルコの貿易相手国の成長加速、世界的な金融情勢の追い風、穏やかな商品価格の見通しは、25年の成長にプラスの影響を与えると述べました。その一方、世界貿易における保護主義的な政策の増加や地政学的同行をリスク要因として挙げました。
令和7年3月25日 中国2月新築住宅価格
おはようございます。中国2月新築住宅価格は主要45都市で下落しました。
1. 10-12月期GDPは+5.4%
中国国家統計局が1月17日発表した10-12月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。7-9月期の+4.6%からも加速。
加速の背景には、同国指導部が9月の最終週に景気刺激策の前倒しを決断したことが背景としてあります。この刺激策は、大半が金融面の刺激策となっています。
それ以降、政策当局者は成長に繋がる他の一連の施策も行いました。その中には、地方政府支援を念頭に置いた10兆人民元(約210兆円)規模の債務救済策、金利の引き下げ、家電製品の買い替え促進補助プログラムの拡大などが含まれています。
24年通年のGDP成長率は+5.0%。23年の+5.2%から減速。不動産不況による内需不振が継続しており、GDPの伸び率は名目成長率の4.2%を下回りました。実質が名目を下回るのは9年振り。
名目が生活実感に近いといわれており、15年以来の「名実逆転」。15年には人民元切り下げを契機に金融市場が「人民元ショック」に見舞われました。GDPの名実逆転は、デフレ圧力の強さを示唆。
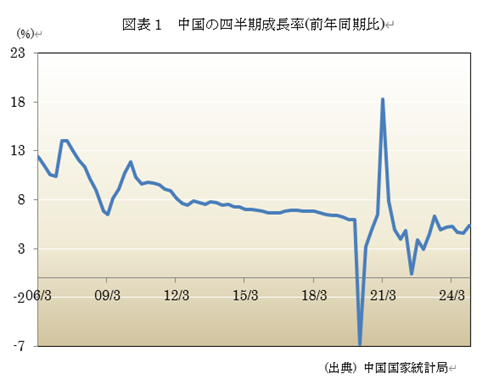
2. 2. 2月新築住宅価格
一方、2月の中国新築住宅価格は、6割以上に当たる45都市で前月比下落。同国政府は対策を打ち出しているものの、効果は限定的。
2カ月連続で前月比横這い。政府の支援策にもかかわらず、不動産セクターが依然として低迷していることを示唆。
中国国家統計局が3月17日発表したデータに基づくと、2月の新築住宅価格は主要70都市のうち45都市で前月比下落。前の月から下がった年3都市増加して、全体の6割余り。上昇したのは北京や上海など18都市、7都市は横這い。
同国政府は住宅ローン規制緩和などで、不動産市場活性化策と打ち出していますが、効果は限定的で再び下落傾向が強まっています。
又、1-2月の消費動向を示唆する小売売上高は8兆3730億元(薬172兆円)となり、昨年比で+4.0%。
令和7年3月24日 中国1-2月貿易統計
おはようございます。1-2月の中国貿易統計で、輸出は減速しました。
1. 1-2月輸出は伸び率減速
中国税関総署が7日発表した1-2月の貿易統計によると、輸出は前月から伸び率が減速。米中の貿易摩擦の影響を受けました。輸出に大きく依存している中国の景気回復に打撃を与えることも考えられます。一方、輸入は予想に反して減少。
1-2月輸出は前年同気比+2.3%と、市場予想の+5%から下振れ。昨年12月には+10.7%。
輸入は▲8.4%。市場予想は+1%、昨年12月には+1.0%。
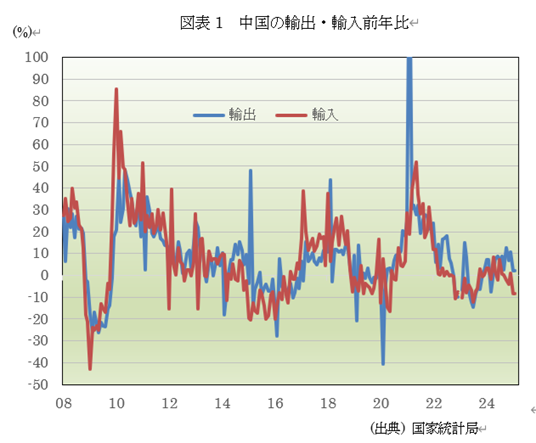
2. 今後も貿易が低迷か
保銀投資(ピンポイント・アセットマネジメント)のチーフエコノミストの張智威氏は「(輸出の鈍化は)貿易戦争を避けるために昨年末活発であった前倒し輸出が鈍化したことが一因かもしれない。輸入の急減は、内需の低迷と加工貿易向け輸入の減少が両方を反映している可能性がある」と指摘。米関税引き上げのダメージは、来月に現れるとの見方を示唆。
米トランプ政権は対中関税を降下する姿勢を強めています。中国国内では不動産市況の継続、消費の弱さが継続。今後も中国の貿易が低迷する可能性があります。
令和7年3月19日 中国1-2月鉱工業生産
おはようございます。中国1-2月鉱工業生産は減速しました。
1. 鉱工業生産は減速
中国国家統計局が17日発表した1-2月の主張経済指標は、小売売上高の伸びが加速し、政策当局の国内消費喚起に向けた取り組みが奏功している可能性を示唆。一方、鉱工業生産は伸び率が鈍化して、米国の新たな関税により経済に圧力がかかっていることを示唆。
旧正月に伴う連休で工場が閉鎖されたことにより、1-2月の鉱工業生産は前年同月比+5.9%。伸び率は前月の同+6.2%から減速。市場予想の+5.3%から上振れ。
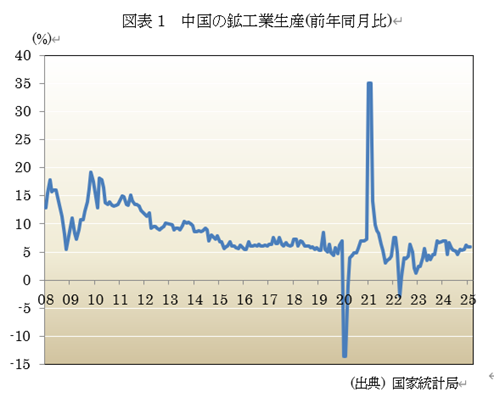
2. 1-2月小売売上高は加速
中国の国家統計局が同日に発表した統計によると、1-2月の小売売上高は前年同期比+4.0%と、前月の+3.7%から伸び率が加速。市場予想の4.0%に一致。
アニメ映画「ナタ2」の記録的ヒットで春節(旧正月)の連休中の支出が増加。家計消費を押し上げました。
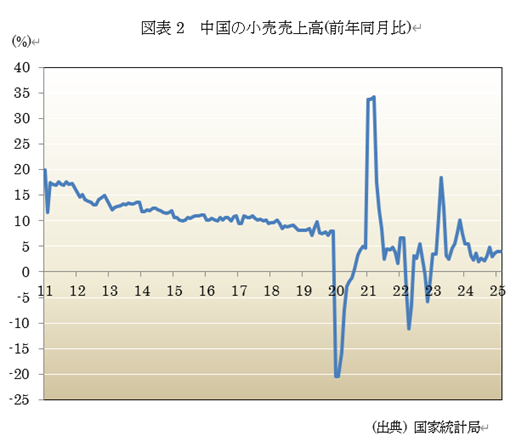
3. 1-2月固定資産投は伸び率加速
他方、国家統計局による同日発表の1-2月の固定資産投資は、前年同期比+4.1%。伸び率は1-12月期の+3.2%から加速。市場予想+3.6%から上振れ。
不動産投資は▲9.8%。昨年の不動産投資は▲10.6%。国家統計局報道は、住宅市場は安定化の兆しが見られるものの、依然として一定の圧力に直面していると示唆。
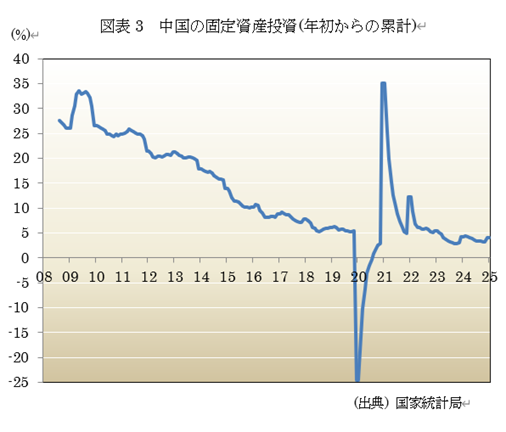
中国では人口減少と少子高齢化が加速。24年末の総人口は14億828万人と、3年連続で減少。不動産市場の不況も継続。今後、景気減速感が強まる可能性があります。br />
4. 第1四半期GDPは減速か
ゴールドマンサックスの亜也リストは顧客向けノートで、昨年末の輸出前倒しによる押し上げ効果が一巡して、米国の関税引き上げによる悪影響が出始めた可能性があると指摘。「1-2月の活動データ及び3月初めの高頻度トラッカー、第1四半期のGDP成長モメンタムが、昨年第4四半期で緩やかに減速することを示唆」としました。
キャピタル・エコにミスとの中国担当アナリスト、ツーチュン氏は、「中国経済は、財政刺激策に後押しされたとみられ、まずまずのスタートを切った。今後数カ月は回復続くを予想されるが、逆風が大きくなっていることにより、目先の改善が長く続くとは考えていない」としました。
令和7年3月18日 中国2月CPI
おはようございます。中国の2月CPIは、前年同月比▲0.7%下落しました。
1. 2月CPIが下落
中国国家統計局が9日発表した2月消費者物価指数(CPI)は、前月比上昇率が▲0.7%と、前月の同+0.5%から反落。マイナス圏に入るのは昨年1月以来、1年1か月振り。春節(旧小学)の大型連休の時期がずれたこともあり、食品や旅行など関連する物価が押し上げられました。
2月CPIを品目別に見ると、中国人の食卓に欠かせない豚肉が前年同月比で+4.1%で、上昇率は1月の+13.8%から大幅に縮小。食品価格は▲3.3%。旅行関連は▲9.6%と、それぞれマイナス圏に転じました。
春節(旧正月)の時期は毎年変化しており、今年は1月、昨年は2月。春節の前後には大型連休があり、その効果から今年1月のCPIは+0.5%と、伸び率が先月から+0.4%ポイント拡大。統計局は2月のCPIに関して、「物価が緩やかに回復している傾向に変わりはない」との見解を示唆。

2. PPIはマイナス継続
一方、中国の国家統計局の同日の発表によると、2月の生産者物価指数(PPI)は、前年同月比▲2.2%と、下落幅は前月の▲2.3%から縮小。市場予想の▲2.1%から上振れ。29か月連続の下落。2024年8月以来の小幅の落ち込み。1月後半の旧正月の影響を受けたものとみられます。
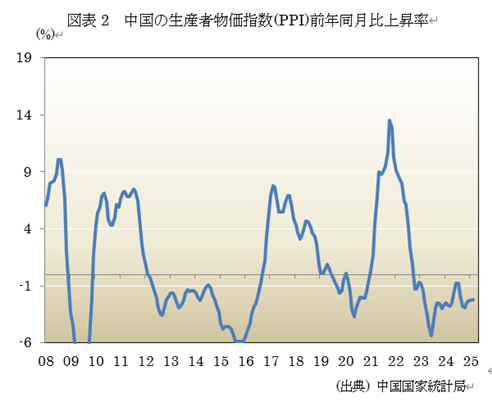
資本財は▲2.5%(前月は▲2.6)と引き続き下落し、鉱業は▲6.3%(同▲4.9%)と落ち込みが拡大。素材▲1.5%(同▲1.9%)、製造▲2.7%(同▲2.7%)。消費財は▲1.2%(同▲1.2%)を引き続き弱含み、食品▲1.6%(同▲1.4%)、衣料▲0.2%(▲0.1%&)なども低迷。
令和7年1月8日 インドネシアがBRICSに正式加入
おはようございます。インドネシアがBRICSに正式加入しました。
1. インドネシアがBRICSに正式加入
BRICS (ブラジル、ロシア、インド、中国、南ア)は、東南アジアのインドネシアの正式加盟を承認。
BRICSは当初、上記5カ国で構成されていたものの、その後、エジプト、イランなど中東の国やエチオピアなどアフリカの国などに拡大。最近では、東南アジアでも加盟を希望する国が出ていました。
こうした中、BRICSで今年議長国を務めるブラジルは6日、インドネシアが正式に加盟したと発表。
東南アジアの加盟は初。ブラジル外務相は「インドネシアは、グローバル・サウスにおける協力の深化に積極的に貢献している」としました。

2. OECD入り目指す
一方、OECD(経済協力開発機構)の閣僚理事会では5月、インドネシアの加盟に向けた審査を開始。加盟が実現すれば、東南アジアでは初。いわゆるグローバル・サウスの経済提携今日が期待されます。
日本、欧米など38か国衙構成するOECDの閣僚理事会が2日からパリで開始。開会式でインドネシアの加盟に向けた本格的な審査が開始されたことを発表。
この中で、インドネシアのアイルランガ経済担当調整相は「2045年迄に先進国になるという国家目標を達成するための第一歩だ」としました。
令和7年3月16日 中国レアメタル規制強化
おはようございます。中国がレアメタル規制を強化しました。
1. 2月製造業PMIは前月から上昇
まず、同国の景気動向を見ましょう。中国国家統計局が1日発表した2月の製造業購買担当者指数(PMI)50.2と、前月の49.7
から+1.1ポイント上昇。
企業別では、大企業のPMIは52.5と、前月比+2.6ポイント。中小企業のPMIは▲0.3の49.2と、景気判断の分かれ目となる50をしたまわりました。
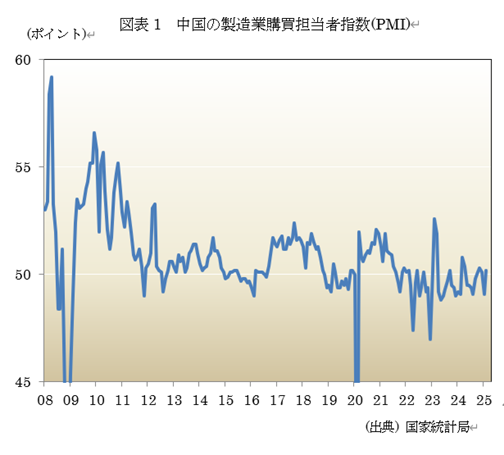
2. 非製造業PMIも上昇
一方、同日に発表した2月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.4と、前月の50.2から+0.2ポイントの上昇。
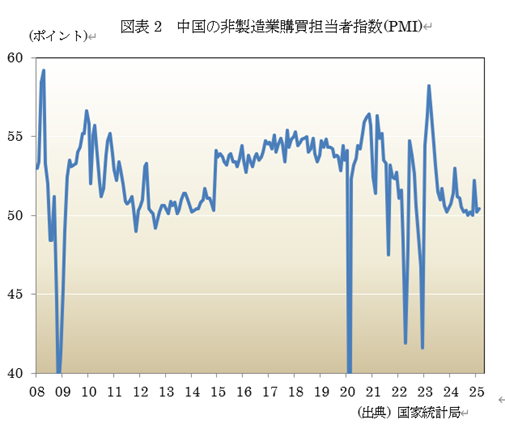
中国では、不動産不況の長期化の伴い、内需が停滞。米トランプ政権の発足により、米週刊の貿易摩擦が激化数と予想されます。
景気の先行きに不透明感が強まる中、中国政府が今後、不動産市況の改善や内需拡大に繋がる対策を打ち出すかどうかが焦点となります。
3. レアメタル規制を強化
一方、中国商務省と税関当局は2月4日、国家安全保障上の利益保護を理由として、タングステン、テルル、モリブデン、ビスマス、インジウムという5種のレアメタルに対する輸出規制強化を即日実施。
今回の発表は、トランプ政権が同日中に中国からの輸入品全てに10%の追加関税を課すと発表した直後に行い、対米報復の意味合いが濃くなっています。
同国は2023年以降、ガリウム、ゲルマニウム、黒鉛、アンチモンといったレアメタルの輸出規制を徐々に強化。今回は規制発表から実施までの猶予期間がなく、即日実施された点が過去とは大きく異なっています。
企業が駆け込みで輸入して備蓄する時間的猶予がなかったことにより、市場の混乱と価格上昇圧量が一層高まっています。
令和7年3月15日 インドCPI減速
おはようございます。インドの消費者物価指数が減速しました。
1. 消費者物価指数上昇率が減速
インド統計局が3月12日発表した2月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+3.61%(図表1参照)。半年ぶりに+4%の大台を割り込み、昨年7月以来の低い伸び率。
市場予想の+3.98%を下回り、1月の前年同月比上昇率は+4.31%から+4.226%に下方修正されたため、準備銀行(RBI、中銀)の追加利下げの余地が拡大。
CPIの前年同月比上昇率がRBIの目標レンジである+2〜6%の範囲に収まるのは4箇月連続。
2月のCPIの減速は、好天により供給状況が改善した野菜価格下落が小野な要因。1月にも前年比+11.35%と上昇した野菜や、2月には▲1.07%と下落に転じ、食品価格全体も+3.75%と、23年5月以来の低い伸び。
野菜価格は、過去1年に亘り、物価押し上げを主導していました。
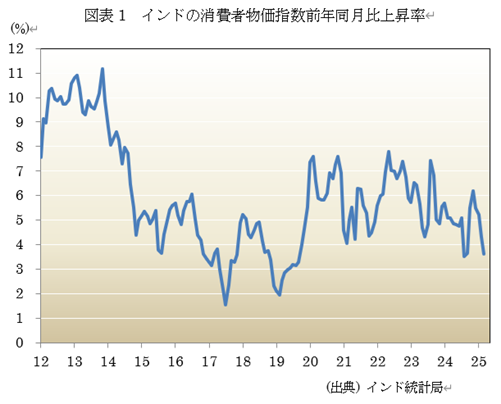
2. 10-12月期成長率+5.4%に減速
続いて、インド統計局が28日に発表した10-12月期成長率は、前年同期比+6.2%(図表2参照)。前期の同+5.6%から伸び率が加速。政府支出と個人消費が寄与。市場予想は+6.3%、インド純魏銀行の予想は+6.8%。
好調な農村部経済もGDPに押し上げに起用。製造業は依然として低迷。GDPはコロナかごに見られたピークを下回りました。
経済活動の指標である祖付加価値(GVA)は+6.2%で、前期の+5.63%から加速。
政府は通年のGDP伸び率見通しを+5.6%としています。その達成には、今年1-3月期に+7.6%の成長が必要となります。
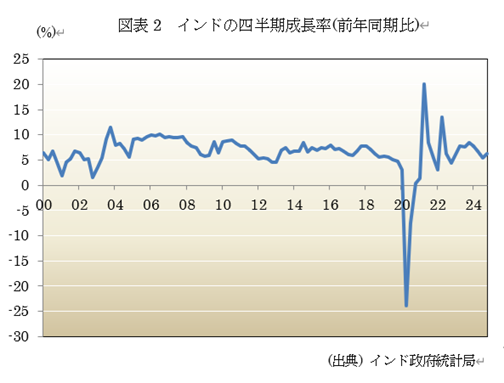
3. 政策金利を引下げ
他方、インド準備銀行(中央銀行)は2月6日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを訳5年振りに引き下げると発表。世界的に景気リスクが高まる中、鈍化しつつある景気をてこ入れする狙い。
マルホトラ新総裁率いる金融政策委員会(MPC)は、政策金利のレポレートを▲0.25%ポイント引き下げて6.25%にすることを全員一致で決定。利下げは2020年5月以来。利下げは概ね市場の予想通り。
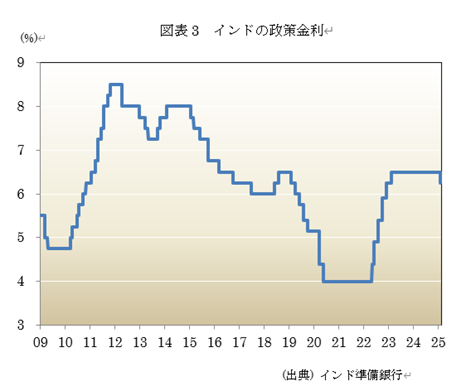
更に、MPCメンバーの6人全員が金融政策姿勢を中立に維持すると決定。これにより、同行は今後、柔軟に対応できると同氏は説明。
マルホトラ氏は、テレビ中継されたムンバイとの演説で、インフレ率を巡る動向について「成長に照準を定める余地を開く」ものであると指摘。中銀は「成長を支援し乍ら、インフレを目標に持続的に一致させることに明確に焦点を絞り続ける」としました。
令和7年3月13日 中国全人代閉幕
おはようございます。中国の全人代が閉幕しました。
1. 10-12月期GDPは+5.4%
中国国家統計局が1月17日発表した10-12月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。7-9月期の+4.6%からも加速。
加速の背景には、同国指導部が9月の最終週に景気刺激策の前倒しを決断したことが背景としてあります。この刺激策は、大半が金融面の刺激策となっています。
それ以降、政策当局者は成長に繋がる他の一連の施策も行いました。その中には、地方政府支援を念頭に置いた10兆人民元(約210兆円)規模の債務救済策、金利の引き下げ、家電製品の買い替え促進補助プログラムの拡大などが含まれています。
24年通年のGDP成長率は+5.0%。23年の+5.2%から減速。不動産不況による内需不振が継続しており、GDPの伸び率は名目成長率の4.2%を下回りました。実質が名目を下回るのは9年振り。
名目が生活実感に近いといわれており、15年以来の「名実逆転」。15年には人民元切り下げを契機に金融市場が「人民元ショック」に見舞われました。GDPの名実逆転は、デフレ圧力の強さを示唆。
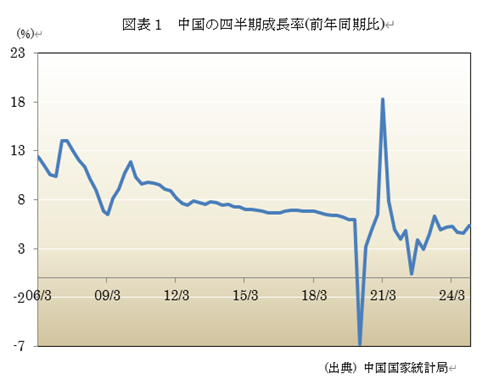
2. 全人代が閉幕
同国は、国会に相当する全国人民代表会議(全人代)を5日から、北京で開催し、11日に閉幕。今年の経済成長率目標を「+5%前後」とする政府活動報告書や、前年比+7.2%の国防予算(1兆7846億円、約36兆2000億円)を含む2025年予算案などを承認。今年mの成長率目標を上回る国防予算の伸びを確保し、習近平主席が主導する軍拡路線の継続を明らかにしました。
へいまくしきでは、党序列3位の趙楽際・全人代常務委員長(国会議長)が「呼吸器の県戦勝」を理由として欠席。全人代委員長の閉幕式欠席は異例。
政府活動報告では、成長率目標を3年連続で「+5%前後」に設定。景気低迷が続く中、トランプ米政権が発動した対中追加関税の影響により、外需の落ち込みが懸念されます。州政権は内需拡大で景気の下支えを図る意向。
令和7年3月10日 グリーンランドへの注目高まる
おはようございます。グリーンランドへの注目が高まっています。
1. トランプ氏が購入に意欲
トランプ米大統領は4日の施政方針演説で、デンマーク自治領グリーンランドの取得に改めて意欲を表明。同氏は「グリーンランドの素晴らしい人々に向けたメッセージがある」と切り出し、「あなた方が選択するのであれば、私たちはあなた方を米国の一員として歓迎する」としました。
グリーンランドは、非常に広大な土地であり、軍事、安全保障にとって非常に重要な場所であると強調。「我々はグリーンランドを手に入れることができると思う」として、「我々はあなた方の安全を守る。そして、共にグリーンランドをこれまで想像もしなかったような高みへと導いていく」と呼びかけました。
同氏はグリーランドの購入に度々意欲を表明。デンマーク政府やグリーンランド自治政府は応じられないとの見解を示唆しています。

2. 中露なども注目
一方、中国、ロシアなども北極圏に注目。地球の温暖化により、北極海を航路として使用できる期間が伸びつつあります。グリーンランドは戦略的要衝として注目されつつあります。
又、グリーンランドにあるレアアースにも関心が高まっています。氷河が溶解することにより、採掘が可能な地域が拡大しています。
世界銀行によると、グリーンランドの域内総生産はデンマークの1%を下回っており、デンマークからの早期の自立は無地かしいと考えられます。国防などもデンマークに頼っており、当面は自治権の拡大が焦点となると予想されます。
住民は、米国への帰属を85%が望んでいないとの調査もあり、トランプ氏によるデンマークの購入は、少なくとも当面は現実的な選択ではないと言えます。只、北極圏におけるグリーンランドの重要性を改めて浮き彫りにするという効果はあったとも言えます。
令和7年3月9日 米2月雇用統計
おはようございます。米国の2月の雇用統計で、雇用者数が+15.1万人増加しました。
1. 雇用者数は市場予想下回る
米労働省が2月の雇用統計を7日に発表し、非農業部門の雇用者数増加は前月比+15.1万人。市場予想の+16万人を下回りました。失業率は4.1%と前月の4.0%から上昇。
貿易政策を巡る不透明感の高まりや、連邦政府の大幅な支出削減により、堅調に推移してきた労働市場に陰りが出始めています。
1月の非農業部門雇用者数は+12.5万人に下方修正。当初発表は+14.3万人。
年初来の雇用者数の伸びは平均で月間+13.8万人。昨年第4半期の月刊平均は+20.9万人。
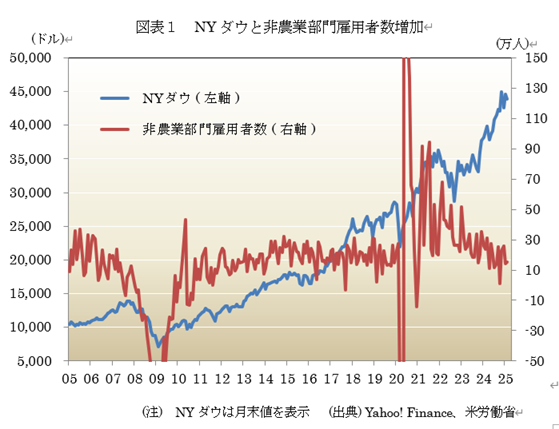
2.パウエル議長利下げ急がず
一方、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は7日、NYで開催された経済イベントで演説。今後の利下げの判断について「急ぐ必要はない」としました。トランプ政権の高関税政策などを巡り、景気や物価に与える影響が明確になるまで、政策金利を維持すると示唆。
同氏は、米国経済は堅調に成長しており、良好な状態にあるとの見方を示唆。他方、「最近の経済指標は、2024年後半の急速な成長率と比較して、個人消費がやや減速する可能性祖を示している」としました。
令和7年3月8日 中国1月新築住宅価格
おはようございます。中国は全人代にで、中国1月新築住宅価格は横這いとなりました。
1. 10-12月期GDPは+5.4%
中国国家統計局が1月17日発表した10-12月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。7-9月期の+4.6%からも加速。
加速の背景には、同国指導部が9月の最終週に景気刺激策の前倒しを決断したことが背景としてあります。この刺激策は、大半が金融面の刺激策となっています。
それ以降、政策当局者は成長に繋がる他の一連の施策も行いました。その中には、地方政府支援を念頭に置いた10兆人民元(約210兆円)規模の債務救済策、金利の引き下げ、家電製品の買い替え促進補助プログラムの拡大などが含まれています。
24年通年のGDP成長率は+5.0%。23年の+5.2%から減速。不動産不況による内需不振が継続しており、GDPの伸び率は名目成長率の4.2%を下回りました。実質が名目を下回るのは9年振り。
名目が生活実感に近いといわれており、15年以来の「名実逆転」。15年には人民元切り下げを契機に金融市場が「人民元ショック」に見舞われました。GDPの名実逆転は、デフレ圧力の強さを示唆。
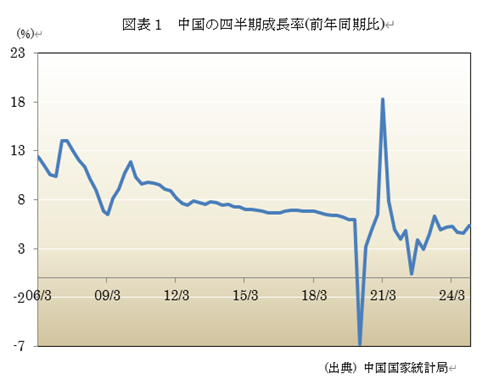
2. 1月新築住宅価格は横這い
一方、1月の中国新築住宅価格は、2カ月連続で前月比横這い。政府の支援策にもかかわらず、不動産セクターが依然として低迷していることを示唆。
中国国家統計局が2月19日発表したデータに基づくと、1月の新築住宅価格は前月比横這い、前年同月比▲5.0%。前年比の下落率は12月の同▲5.3%からマイナス幅がやや縮小。
野村はリサーチノートで、「2025年の価格が下落の長期化は、中国の不動産メルトダウンがまだ終わっておらず、財政システムの見直しが必要という我々の長年の見解を更に裏付けている」としました。
ムーディーズ・レーティングスは調査ノートで、主要指標は不動産市場の持続的な回復が依然として不確実であることを示唆しているとしました。「もし好ましい収益見通しが出て、不動産価格が安定又は上昇して、在庫水準が低下して、規律ある供給管理を示唆すれば、不動産価格のより持続的な回復が期待できる」としました。
令和7年3月6日 中国成長率目標据え置きへ
おはようございます。中国は全人代にで、成長率目標を据え置くことになるとみられます。
1. 10-12月期GDPは+5.4%
中国国家統計局が1月17日発表した10-12月期実質GDPは+5.4%。市場予想の+5.0%から上振れ。7-9月期の+4.6%からも加速。
加速の背景には、同国指導部が9月の最終週に景気刺激策の前倒しを決断したことが背景としてあります。この刺激策は、大半が金融面の刺激策となっています。
それ以降、政策当局者は成長に繋がる他の一連の施策も行いました。その中には、地方政府支援を念頭に置いた10兆人民元(約210兆円)規模の債務救済策、金利の引き下げ、家電製品の買い替え促進補助プログラムの拡大などが含まれています。
24年通年のGDP成長率は+5.0%。23年の+5.2%から減速。不動産不況による内需不振が継続しており、GDPの伸び率は名目成長率の4.2%を下回りました。実質が名目を下回るのは9年振り。
名目が生活実感に近いといわれており、15年以来の「名実逆転」。15年には人民元切り下げを契機に金融市場が「人民元ショック」に見舞われました。GDPの名実逆転は、デフレ圧力の強さを示唆。
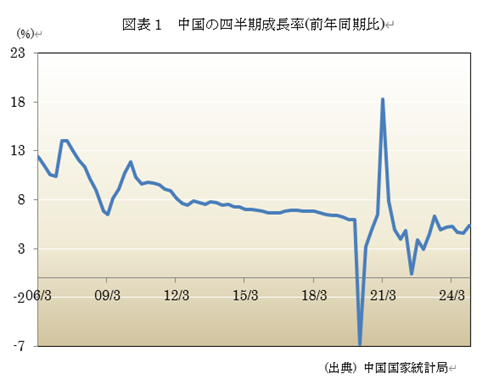
2. 成長率目標据え置きへ
同国は、国会に相当する全国人民代表会議(全人代)を5日から、北京で開催します。2025年の実質経済成長率の目標値は24年と同じ「+5%前後」に据え置くと予想されます。国内総生産(GDP)に対する財政赤字の比率引き上げ幅も注目されます。
全人代の報道官は4日の記者会見で、会期は11日午後迄の7日間であると発表。20年以降は会期を7-9間に短縮しています。
5日には李強首相が所信表明演説にあたる政府活動報告を読み上げます。25年の実質経済成長率目標似ついても説明します。
市場関係者の多くは、24年目標を据え置くと予想しています。全人代に先立ち、北京市、上海市、広東省などは25年目標を+5%前途と決めました。国際通貨基金(IMF)は、25年の成長率目標を+4.6%と予想。このように、+4%台に留まるとの予想もあります。
令和7年3月4日 中国1月PMI
おはようございます。12月の中国製造業購買担当者指数(PMI)は、前月から上昇しました。
1. 2月製造業PMIは前月から上昇
中国国家統計局が1日発表した2月の製造業購買担当者指数(PMI)50.2と、前月の49.7
から+1.1ポイント上昇。
企業別では、大企業のPMIは52.5と、前月比+2.6ポイント。中小企業のPMIは▲0.3の49.2と、景気判断の分かれ目となる50をしたまわりました。
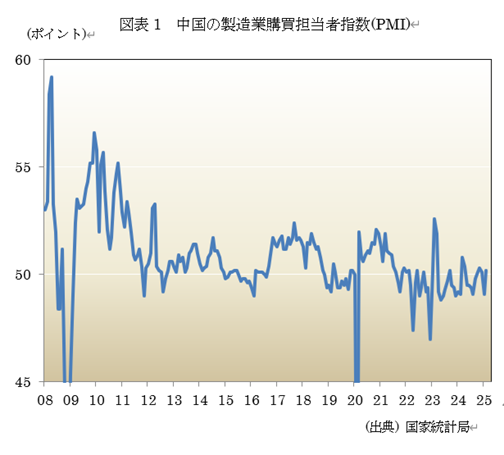
2. 非製造業PMIも上昇
一方、同日に発表した2月のサービス業と建設業を含む非製製造業PMIは50.4と、前月の50.2から+0.2ポイントの上昇。
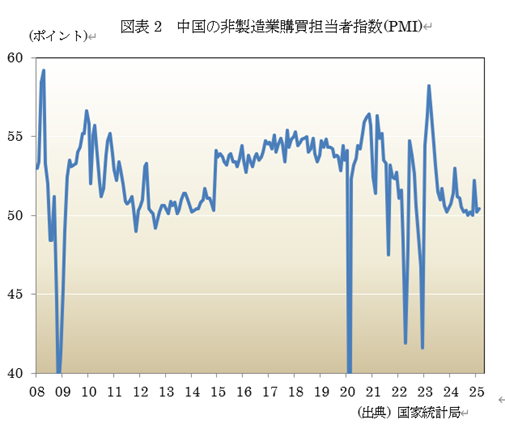
中国では、不動産不況の長期化の伴い、内需が停滞。米トランプ政権の発足により、米週刊の貿易摩擦が激化数と予想されます。
景気の先行きに不透明感が強まる中、中国政府が今後、不動産市況の改善や内需拡大に繋がる対策を打ち出すかどうかが焦点となります。
令和7年3月3日 トルコ10-12月期GDP+3.0%
おはようございます。3月3日ひな祭りですね。トルコの10-12月期GDPは+3.0%に加速しました。
1. 1月CPI上昇率鈍化
トルコ統計局が2月3日に発表した1月消費者物価指数(CPI)上昇率は、前年同月比+42.12%と、前月の+44.38%から伸び率が鈍化。市場予想の+41.25%からは上振れ。

2. 政策金利を引下げ
一方、トルコ中央銀行は1月23日の金融政策決定会合で、主要政策金利である1週間物レポ金利を▲2.5%ポイント引き下げ、45.0%にすることを決定(図表2参照)。利下げは市場の予想通り。
中銀の課題は、経済成長を支えるために金利を引き下げつつ、徳に企業や家計のインフレ期待が再び高まらぬようにすること。インフレ期待は既に中銀の予想を上回っており、当局那ディスインフレに対するリスク要因であると指摘。
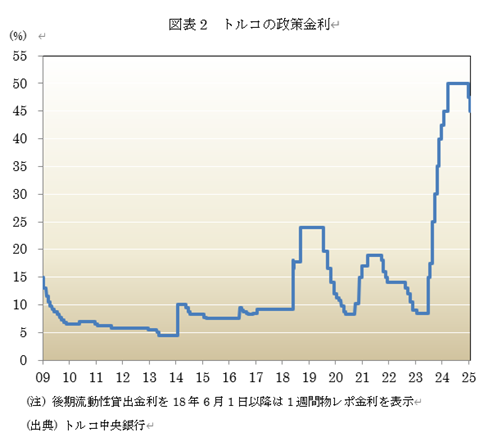
3. 10-12月期成長率+3.0%
他方、トルコ統計局が2月28日に発表した10-12月期GDP(国内総生産)は、前年同期比+3.0%と、前期の+2.1%から加速。市場予想の+2.6%から上振れ。前期比では季節調整済みで+1.7%。
24年通期のGDP成長率は+3.2%、市場予想は+3.0%。
シムシェキ財務相は、24年の成長率は内需が+2.1%ポイント、外需が+1.1%寄与したと指摘。バランスの取れた成長を達成したとしました。
経済見通しについて、「ディスインフレに伴う良好な金融情勢、政策に対する予測可能性の向上、信頼感の改善が経済活動に好影響を与える」との見方を示唆。
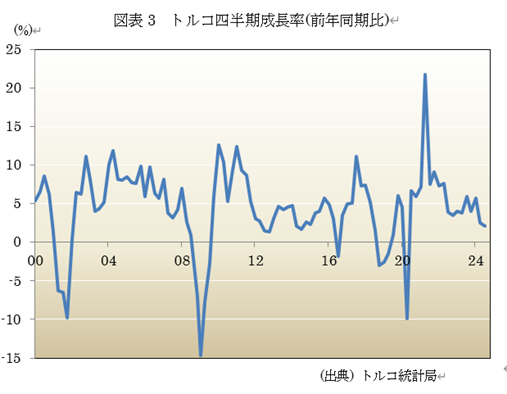
トルコの貿易相手国の成長加速、世界的な金融情勢の追い風、穏やかな商品価格の見通しは、25年の成長にプラスの影響を与えると述べました。その一方、世界貿易における保護主義的な政策の増加や地政学的同行をリスク要因として挙げました。
令和7年3月2日 インド10-12月期成長率加速
おはようございます。インド10-12月期GDP成長率は、加速しました。
1. 消費者物価指数上昇率が加速
まず、消費者物価指数(CPI)を見ましょう。インド統計局が2月12日発表した1月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月比+4.31%(図表1参照)。前月の+5.22%から減速。市場予想の+4.60から上振れ。
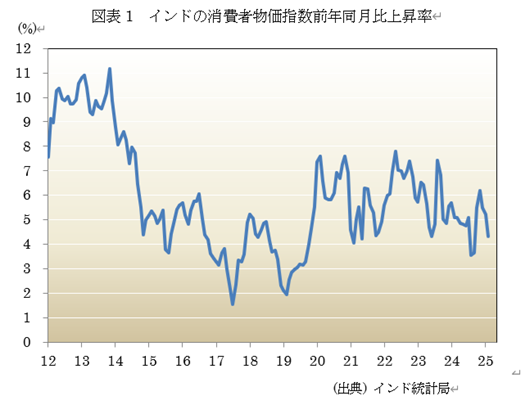
2. 10-12月期成長率+5.4%に減速
続いて、インド統計局が28日に発表した10-12月期成長率は、前年同期比+6.2%(図表2参照)。前期の同+5.6%から伸び率が加速。政府支出と個人消費が寄与。市場予想は+6.3%、インド純魏銀行の予想は+6.8%。
好調な農村部経済もGDPに押し上げに起用。製造業は依然として低迷。GDPはコロナかごに見られたピークを下回りました。
経済活動の指標である祖付加価値(GVA)は+6.2%で、前期の+5.63%から加速。
政府は通年のGDP伸び率見通しを+5.6%としています。その達成には、今年1-3月期に+7.6%の成長が必要となります。
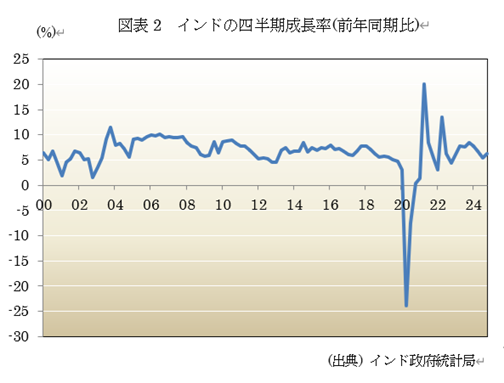
3. 政策金利を引下げ
他方、インド準備銀行(中央銀行)は2月6日開催の金融政策決定会合で、政策金利のレポレートを訳5年振りに引き下げると発表。世界的に景気リスクが高まる中、鈍化しつつある景気をてこ入れする狙い。
マルホトラ新総裁率いる金融政策委員会(MPC)は、政策金利のレポレートを▲0.25%ポイント引き下げて6.25%にすることを全員一致で決定。利下げは2020年5月以来。利下げは概ね市場の予想通り。
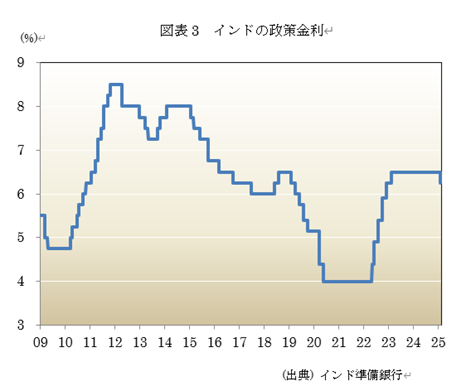
更に、MPCメンバーの6人全員が金融政策姿勢を中立に維持すると決定。これにより、同行は今後、柔軟に対応できると同氏は説明。
マルホトラ氏は、テレビ中継されたムンバイとの演説で、インフレ率を巡る動向について「成長に照準を定める余地を開く」ものであると指摘。中銀は「成長を支援し乍ら、インフレを目標に持続的に一致させることに明確に焦点を絞り続ける」としました。
令和7年3月1日 G20機能不全
おはようございます。G20が機能不全に陥っています。
1. 共同声明採択できず
日米欧や中国、ロシアなどが参加する20か国・地域(G20)の財務相・中央銀行総裁会議は273日、南ア・ケープ単で2日間の日程を終了。トランプ米大統領が保護主義的な政策を打ち出し、世界経済を取り巻く不確実性や分断への懸念が表明されました。米国をはじめとする複数のくにが閣僚の出席を見合わせ、先に行われたG20外相会合に続いて、共同声明を採択できませんでした。
議長国の南アは「議長総括」を発表。紛争や戦争、地政学的緊張、経済の分断、保護主義の擡頭などを経済の下振れリスクとしました。「経済成長を妨げる可能性がある」と指摘。更に「保護主義に抵抗することに対する関与を再認識した」としました。
共同声明のん見送りは、2024年2月以来3会議ぶり。南アのゴドングワーナ財務相は、閉会後の記者会見で「様々な問題で(加盟国間の)相違があった」として、拓環境庁の難しさを示唆。一方、斎藤洋明財務副大臣は「連携の重要性を指摘して、日本の存在感を示唆できた」としました。

2. G7も纏まらず
一方、ロシアによるウクライナ侵攻が始まって3年となるのに合わせて24日、G7(主要7か国)のオンラインによる首脳会合が開催され、参加してウクライナのゼレンスキー大統領は、米国のトランプ大統領に対して、支援を継続するよう要請しました。
又、首都キーウでは欧州やカナダなど10カ国以上の首脳が集まって対面とオンラインによる首脳会合を開き、侵攻の終結に向けて、各国が結束していくことを確認。
首脳会合の共同声明は、文言を巡って調整が続き、発表されませんでした。「ロシアによる侵攻」など、ロシアに批判的な文言に米国が反対。